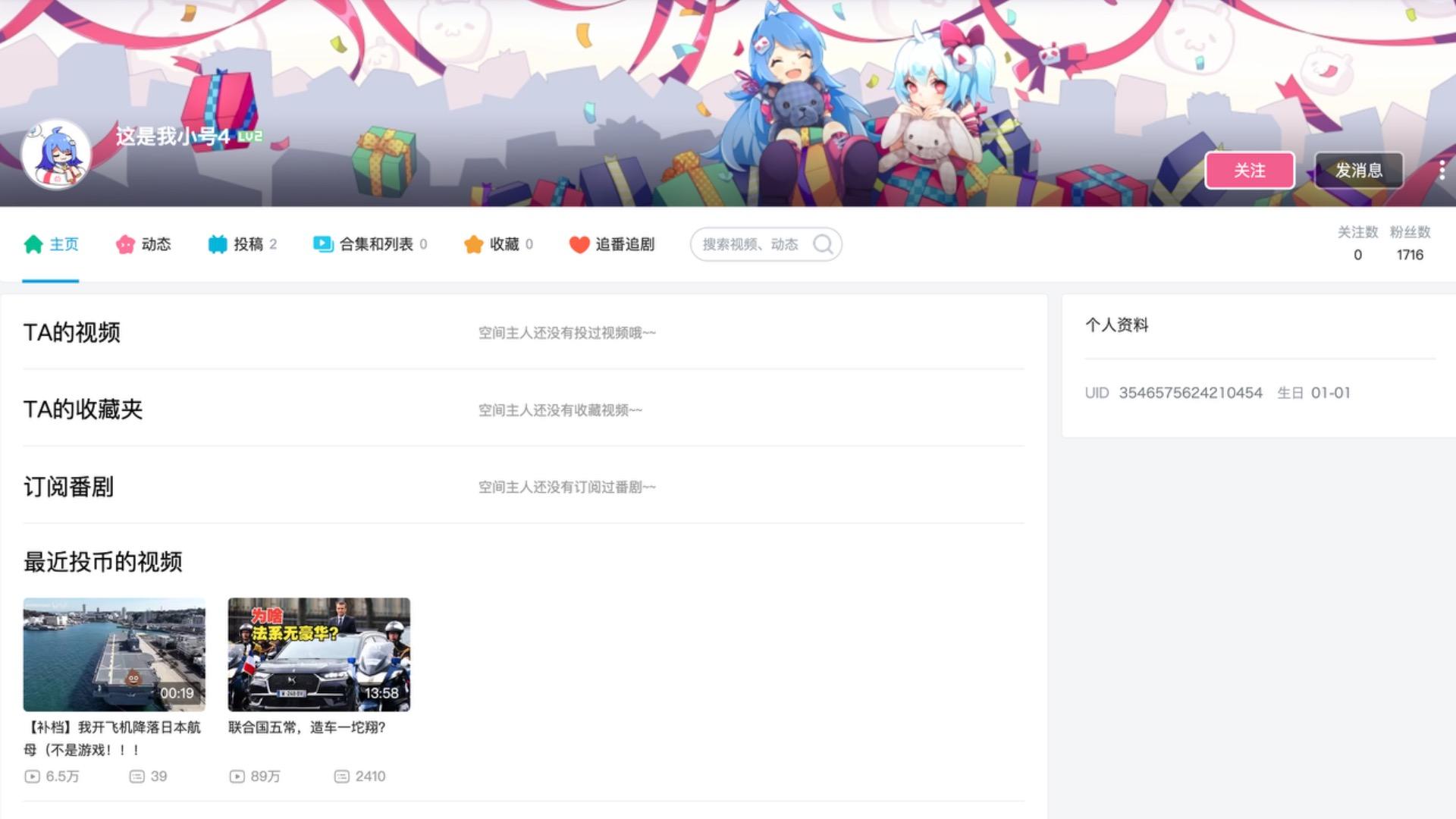私的興味の夏の甲子園!(10) 「横綱」大阪桐蔭から「金星」。近江・多賀章仁監督はこんな人

「いまでも信じられません。甲子園の1試合は練習試合30試合分の値打ちがあるといいますが、今日の勝ちは100試合分……」
大阪桐蔭に序盤、4点をリードされながら、小刻みな得点で食らいつき、8回に逆転。自ら「横綱」とたとえたチームからの金星に、近江(滋賀)・多賀章仁監督は「いまでもまだ、信じられません」と繰り返した。
かつて、じっくりと話を聞いたことがある。生粋の彦根育ち。生家は、琵琶湖べりに建つ浄土真宗本願寺派の賢学寺で、龍谷大で学んだ自身も、僧りょの資格を持つ。小学校2年のころ、三角ベースで野球を始めた。漫画『巨人の星』に夢中になり、プロアマ問わず、テレビの野球中継にかじりついた。
彦根南中野球部では、おもに遊撃。3年のとき、巨人・長嶋茂雄が引退し、セレモニーを見ながら「次の長嶋になるのは僕や」と思った。それだけ、腕に自信があった。甲子園に出場して、プロで活躍する。それが夢だった。
ただ失礼ながら、当時の滋賀県は、高校球界ではパッとしない。多賀が中学を終えるまで、センバツでは3勝しているものの、8回出場している夏は未勝利だった。つまり、滋賀の高校では夢の実現はおぼつかない。だから多賀は、お隣・京都の平安(現龍谷大平安)への進学を志した。実家・賢学寺の西本願寺系の学校だし、毎年のように甲子園に出場し、全国制覇もある強豪。だが、いざ入学してみると、
「なかなか大変なところに来てしまったな、というのが実感でした。先輩を見ると、こんなにすごいボールを投げるのか、とまるで別世界で。自分は必ずプロに行ける、という自信が弱まりましたね」
と多賀は振り返る。
「練習は厳しかったし、くじけそうにもなりました。ただ、親の反対を押し切って平安へ行きましたから、すごすごとシッポを巻くわけにはいかない。意地ですね。厳しさに負けたら終わりや、という気持ちはずっとありました」
その気持ちが実り、5月中旬には、レギュラーバッティングに参加するチャンスを得て3打数3安打。一塁手兼捕手としてメンバーに定着していったが、3年夏の3回戦進出が最高で甲子園には縁がなく、龍谷大に進むころには、夢はほぼあきらめた。
いずれは、実家の寺を継ごうか……ただ大学4年になると、指導者という進路も頭に浮かんでくる。最終的にキャッチャーを務め、野球のおもしろさ、深さを再認識したことも無関係ではない。結局大学を卒業後も、コーチを務めながら週2回ほど聴講生として授業を受け、教員免許を取得。地元・彦根で、近江のコーチになるのは83年のことだった。
1992年夏が私の原点
57年創部の近江の野球部は、81年夏に甲子園初出場。それを率いた田中鉄也監督のもと6年間コーチを務め、89年に監督に就任した。初めての夏は滋賀大会の決勝まで進み、八幡商に中盤まで4点をリード。だがそこから逆転負けを喫し、その後も八幡商・林幸輝監督は、何度も近江の前に立ちふさがる。90年夏の3回戦、91年夏の準決勝で敗れた相手は、いずれも八幡商だ。
ただ、92年夏。「私の原点」と表現するチームで、自身初めての甲子園出場を果たす。この年の滋賀県は、88〜91年と4年連続夏の甲子園に出場している八幡商、春の県大会を制し、近畿大会でも準優勝した比叡山の評価が高かった。一方の近江は、春は3回戦で敗れて夏の大会はノーシードだ。
だが、東大津との1回戦を逆転でモノにすると、その試合の途中から長谷川智一、2年生の鈴居高広という2人の投手がゼロ行進を続ける。準決勝では、長谷川の2安打完封で初めて八幡商に勝ち、比叡山との決勝は鈴居が3安打1失点で完投。守備陣も6試合で7失策と援護し、チームは1回戦の途中から決勝の2回まで、43回3分の2を無失点で守りきった。6試合の失点はわずか3。多賀はいう。
「飛び抜けた選手はいなくても、バッテリーを中心に、しっかりした守備で私に甲子園への道を開いてくれた。開会式の本番ではなく、リハーサルの入場行進でウチの生徒が出てきたときの感激は、いまでも忘れられません」
このとき、強気に内角を攻め、八幡商・林監督に「捕手のリードにやられた」といわしめたのが、主将の宝藤隼人だ。チームの支柱として、すばらしい統率力と人間的魅力にあふれていた。練習が終わり、多賀が帰ったあと、いったん帰るふりをしながらグラウンドに戻って練習を続けた世代である。
甲子園のベンチ入りメンバーは、当時15人。滋賀大会の登録18人から3人を外さなくてはいけない。このとき多賀は、選手間投票で決めさせた。すると結果は、15人のうち半分が2年生。3年生としては、できるだけ同級生をベンチに……というのが人情だが、主将の宝藤は「近江野球部のためには、多くの2年生に甲子園を経験してもらいたい」。そういうチームだ。まあ結局、多賀の意見もあって、2年生のベンチ入りは4人にとどまっているが……。
初めての甲子園は樹徳(群馬)に初戦で敗れたものの、このチームがひとつの分岐点だったと多賀は思っている。
「かつて四国遠征で試合をさせてもらった、松山商の守備が目に焼きついて離れないんです。ピッチャーが注文通り内野ゴロを打たせれば、センターラインが堅実に併殺を取る。派手ではなくても、できることを当たり前にやる守備に、名門のすごさを感じました。まだまだその域には達しませんが、92年のチームも、守りがすばらしかった。そういうスタイルを含めての、原点です」
滋賀県勢初の決勝に進出
2001年夏には、滋賀県勢として初めて決勝に進出し、準優勝。これも、大きな節目だった。竹内和也、島脇信也、清水信之介という「三本の矢」の投手陣に、扇の要としての捕手・小森博之の存在が大きい。中学時代、県大会の優勝投手だったが、同学年に好投手がそろうこともあって捕手に転向。捕球やリードに苦労する姿に、「キャプテンを辞めてキャッチャーに専念したらどうや?」と説得するが、最後は必ず「僕に主将をやらせてください」となる。
「捕手としての技術も成長しました。たとえば竹内のスライダーは、引っかかると大きく外に逃げていくし、左腕の島脇の縦のスライダーも、かなり落差があるんです。小森は、そういう暴れん坊のタマでも(笑)、包み込むようになんとか止めていた。包容力があるというか、われわれは“愛情キャッチング”と呼び、県大会から甲子園を通じて、暴投はあっても捕逸はひとつもないはずです」
もうひとつ、この準優勝チームの守備で出色なのは、ファーストの松村慎也だ。甲子園の5試合、3人の投手が奪った三振は33にとどまるから、野手の守備機会が多くなる計算。松村は、内野手からのむずかしい送球も、難なくさばいた。たとえば、内野ゴロでチェンジ……と思ったところで、ワンバウンド送球を一塁手がファンブルすると、投手は気落ちし、そこから傷口が広がる……高校野球ではありがちだが、このときの松村には、それが皆無だった。県大会と甲子園の10試合をノーエラー。多賀が敬意を抱く名門・松山商との準決勝では、1点リードの9回2死、ショートゴロを捕球した岡義政からのショートバウンドをしっかりと捕球し、ゲームセットとしたのも松村だ。
「四番の松村は、準々決勝までの3試合で9打数3安打2打点。決して、バッティングが不調というわけではありませんでした。それが準々決勝のあと、記者の方に聞かれたらしいんです、“グラブさばきがすばらしいね”と。すると“バッティングで貢献できていない分、せめて守りで、という気持ちだけです”。なんとかチームのために、という精神ですよね。
また、滋賀のチームがいつもお世話になっている宿舎の方が、あの年は“監督、今年の選手はいつにもまして礼儀正しいですね”と。本当にうれしかった。彼らは、選手である前に高校生です。甲子園というのは、子どもたちを成長させてくれるとあらためて思いました」
そう。「甲子園での1試合には、練習試合100試合分の値打ちがある」のだ。