村井邦彦×川添象郎対談【前編】日本文化を世界へ――「キャンティ」発アルファレコードへと続く刺激的な旅

日本の文化を世界へ紹介した、伝説的プロデューサーであり、レストラン「キャンティ」の創業者・川添浩史の歩みを辿る物語『モンパルナス1934〜キャンティ前史〜』
名曲「翼をください」や「虹と雪のバラード」をはじめ、日本の音楽史に残る作品を数多く手がけた作曲家・村井邦彦。荒井由実(松任谷由実)やYMO等を始め、錚々たるアーティストを輩出したアルファレコードの創立者でもある。そんな村井が総合カルチャーサイト「リアルサウンド」で連載していた、日本経済新聞編集委員・吉田俊宏氏との共著、小説『モンパルナス1934〜キャンティ前史〜』(blueprint刊)が4月30日に刊行され、話題だ。
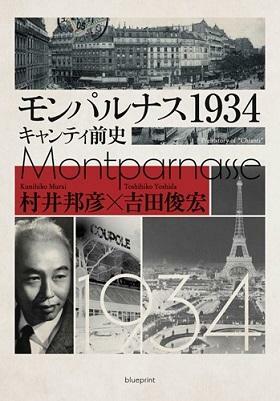
『モンパルナス1934』は、国際文化交流プロデューサーとして活躍した川添浩史(紫郎、1913~70年)の戦前のフランスでの青春時代を描いた、ヒストリカル・フィクション。川添は各界の著名人、文化人が集ったサロンとして知られる東京・飯倉のレストラン「キャンティ」の創業者でもある。村井もオープン当初から「キャンティ」に通い、川添に影響を受けると共に、そこに集う人達の感性と会話に大いに刺激を受けた。
「以前から川添浩史さんの生きた時代を書きたいと考えていた」という村井は、吉田氏と共に多くの資料と関係者の証言に基づき、大胆な創作を交えて、川添がパリのモンパルナスを拠点に活躍し始める1934年から、アヅマカブキ(日本舞踊)の一座を率いて欧米各地を回る中で梶子と出会って恋に落ち、夫婦でキャンティを開業するまでを描いている。
この小説について、村井と、川添浩史の実子で、村井と共にアルファレコードを創業期から支えてきた盟友、プロデューサーの川添象郎にインタビュー。村井にとって、アルファレコードの原点を探す旅とも捉えることができるこの小説について、そして二人にとってのアルファレコードという「場所」について聞かせてもらった。
「川添浩史さんは、夢を持っている若者をわけ隔てなく応援してくれた」(村井)
――村井さんは中学生の頃から「キャンティ」に通っていたとお聞きしました。
村井 そうなんです。川添浩史さんは、中学生の僕に対しても夢を語ってくれたし、大人になってからも色々なアドバイスをくれました。年齢に関係なく、夢を持っている若者をわけ隔てなく応援してくれる素晴らしい人でした。川添さんはアヅマカブキ(日本舞踊)や日本映画、日本の素晴らしい文化を海外に紹介する仕事をしていました。そんな話を聞いているうちに川添さんが生きた時代を、いつか書きたいと思っていました。
――村井さんと象郎さんはその頃からのお付き合いということですよね。
村井 象(しょう)ちゃんはその時ラスベガスとニューヨークにいたから、日本に戻ってきたのは64年だっけ?
川添 64年の終わりです。「キャンティ」は1960年にオープンして、その時はまだ日本にいたけど、それから数か月でアメリカに行きました。だからオープンしてから64年くらいまでの「キャンティ」のことは、クニ(村井)の方が詳しいですよ(笑)。
村井 64年から僕たちの関係が始まったから、もう60年近くになるね。
「好きなことをやっていた親父だったから、僕も自由にやらせてくれました」(川添)

――象郎さんの著書「象の記憶」でも浩史さんのことが書かれていますが、どんな父親でしたか?
川添 親父の話をするのは結構難しいですけど…。というのは僕が15~16歳までは親父とほとんど会ってなかったんです。僕の母親がピアニストの原智恵子で、国内外で忙しくコンサートをやっていたし、親父も僕が幼い頃は、ヨーロッパやアメリカで日本文化のプロモーションという仕事をやっていてほとんど海外に行きっ放しでした。おやじに会うのは「今度、飯、食おうよ」ってたまに電話がかかってきて、弟(光郎)と一緒に食べに行くくらいで。だから16歳までは、ほとんどおやじと過ごしていないんです。一緒に暮らすようになったのは17歳の時でした。鹿児島の全寮制の学校に行かされたり、新しいお母さん(梶子さん=タンタン)ができたり、高校を卒業してすぐにロサンゼルスに行かせてくれたり、色々ありましたが、親父も好きなことをやっていたからか、僕も自由にやらせてくれました。
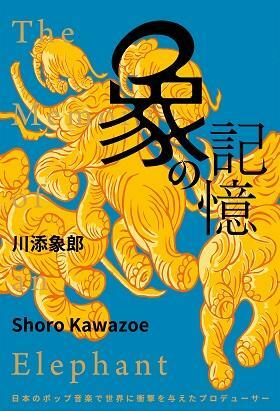
「『キャンティ』には日本舞踊家から歌舞伎役者、ブロードウェイの演出家、音楽家から、画家、建築家、作家、俳優と、日本だけではなく世界中から色々な人が集まる刺激的な場所だった」(村井)

――村井さんにとって浩史さんは“師匠”のような存在ですか?
村井 師匠というより、会った瞬間「面白い人だな」って思って、それはずっと変わらなかった。僕の周りに戦前からヨーロッパで生活をしていて、ヨーロッパ人やアメリカ人と友達になって色々やっている人って、当時はいなかったよね。「キャンティ」に行き始めると、浩史さんのパリ時代の友達がたくさん来てるわけ。「こういう人たちがいるのか」ってビックリしたし「この人はなんでこういう風になったんだろう」って、いつも興味を持って見ていました。
川添 ある日の「キャンティ」はこんな感じでした。奥のテーブルではハリウッド女優のシャーリー・マクレーンとシャンソン歌手のイヴ・モンタンに、作家の大江健三郎が拙い英語で文化論を語っていたり、その隣のテーブルでデザイナーのイヴ・サンローランとタンタンがニコニコ話をしていたり、別のテーブルでは作家の柴田錬三郎がスパゲティを食べながら親父と難しそうな顔して話をしていて、「何、話してるのかな」と思ったら、「あそこの蕎麦がうまい」って話をしていたり(笑)、そんな人たちが一堂に会してるのが「キャンティ」でした。
――そんな刺激的な空間に村井さんは10代の頃から入り浸ってたんですね(笑)。
村井 入り浸ってた(笑)。浩史さんが外国の人と話をしているのを聞いていると、彼がやっていることの背景のようなものがだんだんわかってきて、ますます面白くなってきて。なんといっても面白いのは、日本舞踊家から歌舞伎役者、ブロードウェイの演出家、音楽家から、画家、建築家、作家、俳優と日本だけではなく世界中から集まっている人の幅の広さ。
川添 そこにクニやかまやつひろし、ミッキー・カーチスとか、加賀まりことか、僕と同世代の若者がそこに入って、一生懸命大人たちの話を聞いてるわけ。みんなかわいがってくれて、ごちそうしてくれて、何かけしからんことすると怒ってくれて。すごく自由な空間でしたよね。もう今はそういうサロン的なお店、空間はないですよね。
「たくさんの友人との友情を大切にしたこと、それが親父の一番の財産」(川添)
村井 浩史さんはとにかく友達がたくさんいる人なんだよね。友達たちをすごく大事にして、友情を大切にした人だったね。
川添 そうだね。それが一番の大きな財産だったから。
村井 そう。戦争中からもそういういい関係だったけど、戦後、大きな仕事をするようになったときには、その人脈がものすごく役立つわけ。
川添 役に立ったね。
村井 だって、会社の名刺を持ってやる商売じゃないんだもん。お互いに若い頃からよく知ってるし、「この人は信頼できる」とか、「友情を持って接する人だ」とわかれば何か一緒にやりたくなるし、助けたくなる。浩史さんもそういう人たちを助ける。そういう人って当時の日本には本当にいなかった。僕と象ちゃんの関係もそうで、若い頃からの友達ってやっぱり特別なんだよね。
川添 親父が最初に海外に行って、一番仲良くなったのは写真家のロバート・キャパで、彼の面倒を見ている期間がありました。それで親父が初めて日本の芸能、アヅマカブキを紹介する欧米ツアーをやったとき、ニューヨークではロバート・キャパの弟でコーネル・キャパという写真家がいて、ニューヨークのジャーナリズムの世界では有名人なので、メディアに親父のことを「僕の友達だからみんな助けてやってほしい」って紹介して。それがアヅマカブキの大きな成功にもつながっています。
村井 つまり、ロバート・キャパと写真家たちは、新聞社、雑誌社と全部つながっていたから、ひと声で世界中の新聞がアヅマカブキを取り上げてくれる。浩史さんはそういう人脈を持った珍しい日本人なんだよね。
――そうやって日本の文化を海外に輸出する浩史さんの考え方や感性に、村井さんは大きな影響を受けたのでしょうか。
村井 そうですね、長年見ている間に「こういうことやってるんだ」「こういう考え方があるんだ」って教えられて、本人からはもちろん浩史さんの友達からも色々な話を聞きました。だから浩史さんのことは断片的にわかっているんだけど、つながっていなかったんですよね。それがこの本を書こうと思ったきっかけだし、浩史さんがやった仕事の全貌が、自分なりにわかってきた感じです。
川添 どういうモチベーションでこの本を書く気になったの?
村井 僕にとって興味のある人が何人かいたんだな。浩史さんとアルファの顧問やってくれた古垣鉄郎さん、この2人にはいつも興味持っていていつか書きたいと思っていたんだよね。
「まさか親父のことをこれだけ書いてくれる人が出てくるとは思っていなかった。ありがたいです」(川添)
――『モンパルナス~』はフィクションとノンフィクションを行ったり来たりしているような、詳細な描写が印象的です。
村井 僕は浩史さんの人生を本にしたいなと思ったんだけど、さっきその仕事の全貌が見えてきたって言ったけど、いくら調べてもわからないこともあるんですね。だからある程度想像で補わないと人生がつながってこない。「これはノンフィクションではなく小説にした方がいいんじゃないか」と、共著の吉田さん、象ちゃんとも話をして進めました。象ちゃんからもたくさん話を聞かせてもらったし、吉田さんと大量の文献や資料を読み、かなりディテールを追求しています。
――村井さんが浩史さんに憑依をして、吉田さんが村井さんに憑依をして書いてる、そんな感覚を覚えました。
川添 なるほど。
村井 そういう感じは、あるよね。
川添 でもよく書いてくれましたよね。僕はありがたいですよ。まさか親父のことをこれだけ書いてくれる人が出てくるとは思っていなかったからね。
――本の中でタンタンさんの「ヒロ(浩史)の歴史を調べてよ」「調べてよ。いつか必ず」という言葉が出てきます。
村井 タンタンは本当に浩史さんのことを愛していたし、その気持ちと僕の思いとを重ねた言葉ですね。。
川添 すごく印象的で、効いてるよね。フィクションの部分も多いけど、ほとんどもうノンフィクションと錯覚をしますよね。
「『キャンティ』は“子供の心を持った大人と、大人の心を持った子供のために作った”と浩史さんは言っていた」(村井)
――浩史さんは、当時の日本人としてはかなり先進的で自由な考え方の持ち主で、「キャンティ」にもそんな空気が流れていて。その空気にひかれて色々な人が集まってきて。それは浩史さんの息子さんである象郎さんにも受け継がれていて、自由を一番大切にしなければいけないということを、この本から感じます。
村井 僕はみっちゃん(象郎の弟=光郎)から聞いたんだけど、浩史さんの遺言書に「人間はもっと自由じゃなきゃいけない」ということが書いてあったよね。
川添 それは知らなかった。でも親父は詩人でもあって色々なキャッチコピーを書いてました。
村井 「キャンティ」は“子供の心を持った大人と、大人の心を持った子供のために作った”という言葉も、浩史さんの言葉だね。
――自由で、カッコいい人、多くのミュージシャンが集まっていた「キャンティ」で受けた刺激が、その後、村井さんがアルファミュージックを立ち上げるきっかけになっている、と考えていいでしょうか?
村井 そうですね。ここで影響を受けて会社を始めたわけだからね。
川添 当時15歳のユーミン(当時荒井由実)も、八王子から電車とバスを乗り継いで「キャンティ」まで来てたんだから、元気な女の子ですよね。
村井 何か面白いことがあると思ったんだろうね。僕もそうだったから。YMO以前から、例えば赤い鳥の最初のレコードはロンドンでレコーディングしたり、その後、前衛邦楽のレコードをフランスで発売したり、そういう、川添さんがやってきたようなことをずっと追い掛けてやってきました。それで大成功したのがYMOで、そこで活躍したのが象ちゃんです。
【後編】に続く










