brainchild's コロナ禍でロックバンドは何に気づき、何を思い、歌い、覚悟したのか

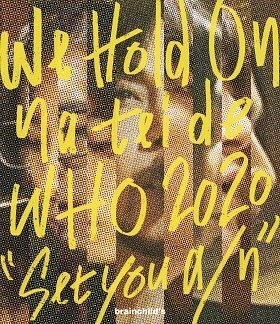
ドキュメンタリー映画のような180分の映像作品
EMMAこと菊地英昭率いるコラボレーション・プロジェクトbrainchild'sが、2020年9月から10月にかけて全5回行なった初の有料配信ライヴを再編集し、映像作品化したブルーレイ作品『brainchild's We Hold On na tei de WHO 2020 “Set you a/n"』が3月17日に発売され、好調だ。スタジオセッションライヴは未発表曲「Heaven come down」を含む全15曲と、メンバーそれぞれのドキュメンタリー映像、インタビュー映像など180分を超える大作で、コロナ禍でバンドが感じた生々しい言葉とメロディが剥き出しになった、まるでドキュメンタリー映画のような重厚感ある肌触りの作品だ。この作品について菊地、ボーカル渡會将士(FoZZtone)、ベース神田雄一朗(鶴)、ドラム岩中英明(WHITE LIE)、キーボードMAL(ArtyPacker)にインタビューした。
「インタビューとドキュメンタリー映像で、メンバーの人間性を掘り下げ、それを踏まえて曲を聴いて欲しかった」(菊地)
――今回の映像作品はオンラインライヴと菊地さんのインタビュー、そしてメンバーみなさの故郷やお世話になっている土地に行ったドキュメント映像を組み込んで、約3時間の超大作になりました。ご覧になった感想から聞かせてください。
神田 いいバンドだなって思いました(笑)。
――第三者が観ても、観終わった後まずそう感じました。
神田 すごい人たちが集まったバンドだなって、自分が参加しながらも素直に思いました。あと、チームがすごいなって。今、生配信ライヴは多いけど、その中でスタジオでしっかり作り込んだライヴをやって、それを真ん中に置いた“作品”を作るというコンセプトが凄いと思いました。そこが今回の作品のミソじゃないでしょうか。
――ライヴはもちろんですが、メンバーのみなさんのドキュメンタリーの映像がすごく“効いて”いますよね。改めて菊地さんのそれぞれのメンバーへの思いや、ストロングポイントを語ってくれていて、そこもいバンドだなって思いました。
菊地 インタビューしてくれる人のセンスがよかったのかもしれないですね(笑)。
岩中 このドキュメンタリーを撮った意味がすごく伝わってくるし、普通のライヴ映像とは違って、それぞれのパーソナルな部分も出ているので、いい作品に仕上がっていると思います。
菊地 メンバーが色々な場所にロケに行ったり、インタビューがあったり、そういうところを観ることができたのが、自分としてはすごく興味深かったです。普段は見られないメンバーの顔を観ることができました。brainchild’sとして、映画にもなりうるようなドキュメンタリー作品って今までなかったですし、このタイミングなので、それぞれの人間をちょっと掘り下げた内容にしたかったんです。こういう状況だからできた作品かもしれません。オンラインライヴというものに、僕は最初は懐疑的な部分がありました。もちろん何かしなければいけないというみんなの気持ちはわかります。でも音楽を生業としてやっている身としては、そんな簡単に、そんなことやっていいのかなっていう気持ちがすごくありました。だったらもっと音に焦点を当てたものを作品としてみんなに届けたいと思っていました。なので実際にこういう映像作品ができたのは、すごく嬉しかったです。
「この作品は、単に娯楽としての音楽というより、ちゃんと心臓、脳の奥まで届く娯楽になっている思う」(菊地)
――インタビューでの菊地さんの言葉や、メンバーの皆さんの言葉を聞いて、このバンドの音楽を聴くと、これまでとはまた違った聴こえ方がしてきます。
菊地 同じ曲でも、このコロナ禍でのみんなの考え方や人間性がわかった上で聴くと、歌詞も含めてまた違うものとして聴こえてくると思います。単に娯楽としての音楽というよりは、ちゃんと心臓に、脳の奥まで届く娯楽になったと思っています。
――映像の中で菊地さんはスタジオライヴについて「ライヴとレコーディングの中間というか、すごく疲れた」とおっしゃっています。
菊地 新鮮でしたけど、疲れました。普段やっているものと全然違うので、使う神経も違うと思います。さすがにそういう練習はしていないので(笑)。
――テイクを重ねた曲もあったのでしょうか?
神田 どの曲も最低2回で、3回目をやるかやらないかという感じだったと思います。
渡會 歌はしんどかったです(笑)

「今回の企画を通じて、地方に行けば行くほどコロナ感染者への偏見やバッシングが酷いことがわかった。それを伝えたかった」(MAL)
――ドキュメンタリー映像ではみなさんが、地元や地方でお世話になった、なっているライヴハウスの方やカフェの方を訪ね、エンタメ従事者の窮状を語るリアルな言葉がすごく伝わてきました。岩中さんは役者/演出家の友人の方と、下北沢に行っていましたが、舞台、舞台関係者のリアルな状況を知ることができました。
岩中 僕も本当は北海道に帰りたかったのですが、帰省となるとみんなからの帰ってくるなという空気感がすごくて。もちろん親に感染させてはいけないという気持ちはありつつも、白い目で見られる感が強かったので帰るのをあきらめて、下北沢でのロケになりました。あの対談では、ミュージシャンか役者かの違いで、やっぱりエンタメ従事者は大変だということがわかりました。
――MALさんは富山に帰られてお世話になったライヴハウスの店長とお話をされていました。
MAL 自分自身こうやってフィーチャーしていただくのは初めてだったので、勉強にもなったし、いい経験をさせていただきました。あの方は実際にコロナに感染してしまって、新聞の一面で取り上げられたようで、その時のバッシングの酷さを伝えてくれました。地方に行けば行くほど感染者に対しての偏見やバッシングは酷いようで、僕の知り合いで感染してしまった人は、引越しを余儀なくされたそうです。そういう偏見をなくすためにも、今回こういう映像を撮影できたことはよかったと思います。
菊地 さっきのONNY(岩中)の話にも通じるところがありますよね。東京って大都市がゆえに匿名性が髙いけど、でも地方だと全部わかってしまって、晒されて、正しい理解よりも先に偏見や差別につながっていくのかもしれませんね。
――仕事場でも家でも24時間一緒にいた奥さんには感染せず、息子さんが感染してしまったという事実も、改めてコロナの怖さを教えてくれています。
MAL あの言葉は衝撃でしたね。
「お店もバンドマンも同じ。やれないことを嘆いても仕方ない。できることのアイディアを膨らまし、前に進んでいく」(神田)
――渡會さんは大阪に行っていました。
渡會 ライヴでお世話になっているライヴハウスがあることもあって、大阪・京都行きを熱望しました(笑)。でも行ってよかったです。東京ではない、でも大きな街で、みんながどういう風にコロナを受け止めてるいるのかを、普通に街を歩きながら感じたかったんです。大阪の方が東京より若干元気がある気がしました。
――あのドキュメンタリー映像って、コロナ禍で変わったことや思いを、正解はないのですがそれぞれが確めに行く旅、そんな風に感じました。
神田 僕は地元の鶴ヶ島(埼玉県)に帰ったのですが、この一年、自分なりに色々新しいチャレンジをして、よく行っていたお店も色々大変なことがあったりしながらも頑張ってやっていて、またもう一回お邪魔して話をしても面白いなという感じが、あの時からしていました。お店もバンドマンも同じです。やれないことを嘆いても仕方がなくて、できることをやろうとアイディアを膨らませて、去年よりパワーが増してるいるのでは?という感じになっていると思います。そこはお互いに強いなと思いました。

「配信ライヴは最初は懐疑的だったけど、スタジオセッションライヴは新しい世界を教えてくれた」(菊地)
――菊地さんのインタビューの中で、ミュージシャンとしてこの状況にどういう風に向き合っていくべきか、自分がやりたいことだけをただやればいいのかという、疑問や問題提起するリアルな言葉が印象的でした。
菊地 性格上、下手な鉄砲数撃ちゃ当たるというタイプではなくて。もちろんそういうタイプの人もいて、それはそれでいいと思いますが、僕はそうやっていると、どこかで取り返しのつかないことが起こってしまうのでは?と危惧してしまいます。もちろん変化していくことはとても大切だし、していかなければいけないし、そうじゃないと残っていけないのはわかります。でもちゃんと吟味したいなって。
――「人間って結局ただの哺乳類じゃん」という言葉も印象的でした。
菊地 今まで好き勝手にやってきたけど、そうはいかない現実もあるわけで、それをちゃんと見ておかなければ足元をすくわれると思います。でもされど哺乳類っていうのももちろんあって、今までずっと生物として進化してきて、長けた部分もあるので、それはそれでいいところだと思うし、でもいいところだと思っていたけど、実は無駄な進化だったというところもあると思います。そういうことも全て含めて考えたほうがいいんじゃないかなって。何も考えずに普通に暮らしていけば暮らせると思うけど、こういう状況だからこそ少し“考えよう”ということです。
――映像終わりの曲と、映像がリンクしてるような感じがして、オンラインライヴで観た感覚とは違った感じ方で楽曲が飛び込んできます。
菊地 配信ライヴの時は5回にわけて観ていただきましたが、それぞれのドキュメント映像の直後に流れる曲の割り振りを考えて、構築していきました。
――スタジオライヴをやって、ますますリアルなライヴをやりたい欲求が増してきたのではないでしょうか。
菊地 本当にそうです。個人的にはいつもツアーをやっている時は、やるごとに満足していくんですけど、今回の配信ライヴは、日が経っても満足度が高いので自分としては珍しいと思いました。ライヴとはまた違った満足感があったので、不思議でした。ライヴが大好きだし、THE YELLOW MONKEYもライヴでのし上がってきたバンドなので、そこが生命線だと思っていましたが、違う世界もあるんだなって気づかせてくれたのが、今回のスタジオライヴでした。
「MALが入ったバンドの音を最初に聴かせるには、通常のライヴより今回のスタジオライヴの方が逆によかった気がする」(菊地)
――この一年で大きく変わった思いや考え方を教えてください。
MAL 僕はますます音楽離れが進みました(笑)。宅建の資格を取ったり。ただ、音楽から離れれば離れるほど、それは音楽から本当に離れているのではなく、音楽を俯瞰して見られるようになったということです。視野が広くなったというか、離れている間に勉強したことがそのまま音楽に活かせるので、アレンジの幅も自然に増えてきました。
神田 家を売れるキーボーディストです。
MAL 神田さんが最初に言っていたように、本当にいいバンドだなって思います。アレンジを組める人たちが揃っているので刺激を受けるし、勉強になります。このバンドに入って、コロナのせいではありますけどライヴができなくなるのは、僕が疫病神なのかなとか考えたり…。基本、ネガティヴなんです。
神田 だとしても天変地異レベルだから、相当だよ。神レベルだよ(笑)。
渡會 そこまでいったら誇っていい(笑)。
菊地 逆に、MALが入ったサウンドを聴かせるには、ツアーよりもこっちの方がよかったと思う。リアルなライブももちろんいいけど、音響も100%いいというわけではないし、どこでやっても100%満足できるものはないだろうから、それを考えると、このスタジオライヴの方がよかったと思う。
神田 我々もファンも、もうMAL君なしの音ではダメってなってる。
「全員のキャラが立っていて、それは音も同様で、誰一人埋もれていないバンド」(岩中)
「このバンドはとにかく“音がいい”人たちが集まっている」(神田)
――岩中さんは改めてbrainchild’sというバンドをどう捉えていますか。
岩中 いいバンドです。全員の音楽がしっかりあって、プラス、キャラも強いのがいいです。全員のキャラが立っていて、音もそうですが、誰一人埋もれている人がいません。
神田 とにかく“音がいい”人たちが集まっているバンドです。僕は音楽を聴くときに、メロディがいいとか歌詞がいいとか、そういうのももちろん大切なんですが、ずっと好きで聴いていられる音楽って、音がいいものなんです。逆にいうと、ボーカルがあまりタイプじゃなくても、サウンドがいいとずっと聴いていられます。なので、誰かのサポートでレコーディングに参加する時も、音がいい人が揃っていないと気持ちが上らないというか…。もちろん音がいいという価値観も自分の判断基準なので説明しづらいのですが、brainchild’sはみんな振り切ってめちゃくちゃいい音の人たちの集合体なので、本当に演奏していて楽しいんです。だからレコーディングやライヴでも、全員が音を鳴らすと塊になるんですけど、でもそれぞれの音の“粒”がきちんとあって、それぞれのパワーがないと成立しないアンサンブルだと思うので、そこが僕はbrainchild’sをやっていて一番ワクワクするところです。もちろん自分もそれに応えられる音を出さなければいけないので、日々研究をして進化していかなければいけません。そう思わせてくれるところが、このバンドのいいところだと思います。
「ロックンロールのような音楽が担う役割って、嫌なことを嫌ってちゃんと言うこと」(渡會)
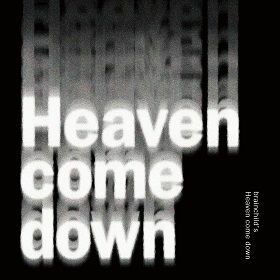
――ライヴで披露した新曲「Heaven come down」(4月10日配信リリース)は、渡會さんの怒りの歌詞が、今までのbrainchild’sにはなかった感触で、突き刺さってきます。
渡會 なかなかマスクが届かないなって時に書いたと思います(笑)。brainchild’sではなるべく社会批判みたいなものは歌わない方がいいなって、なんとなく思っていましたが、ロックンロールのような音楽が担う役割って、嫌なことを嫌ってちゃんと言うことだと思って。特にあのタイミングで世の中みんなが怒っていることをひしひしと感じていたので、そこはその怒りを素直に歌おうと思いました。
「ミュージシャンは社会の理不尽なことへの怒りをもっと主張すべきだし、歌うべき」(菊地)
菊地 このバンドの7期になってから、ワッチ(渡會)がそういう歌詞を書いていなかったけど、自分はずっとそういうことばかりやってきたから、また立ち戻れた感じがしました。この理不尽な世の中では誰だって怒って当然だと思ったので、そういうサウンドがあったら、怒っている歌詞を乗せるよねと思いました。海外だったらラッパーが反骨精神とかを歌ってくれるけど、日本って全くそれがなくて、お笑いにそれを感じるくらいで、だから音楽もそういう側面があってもいいと思うし、そのタイミングにワッチがこの歌詞を書いてくれたのは、こういう状況だけど、個人的は嬉しかったです。もっとこういう歌、主張をミュージシャンが歌うべきだし、やるべきだと思います。
――まだまだ先行き不透明ですが、今年brainchild’sとしてはどんな一年にしていこうと。
菊地 タイミングが難しいですが、アルバムは作りたいです。ツアーができるのであれば出したいです。はっきりしたことは言えませんが、できれば今年中には出したい。
――今回の映像作品はbrainchild’s入門編としてもすごくいい作品になりますね。。
菊地 ただ、これを観てライブに来ると、MCを聞いたら驚くかもしれないですね(笑)。あれ?こういう感じだったっけって(笑)。今回の作品はみんな二の線が強いので(笑)。










