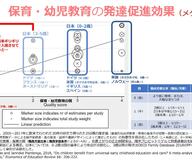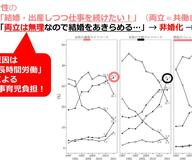コロナ後の社会――長期的にどう変わっていくのか(1)「不可知性」

Yahoo!ニュースでは、新型コロナウイルスがもたらす「社会変容」などへの不安解決に寄与するための特集サイト「私たちはコロナとどう暮らす」を開設している。
その中で、「第2波に備えていますか?」というアンケートがあり、すでに19万人以上の人々が回答している。
そして現時点(2020年6月18日)では、約7割もの人が「備えている」と回答している。
それだけ、回答者において「第2波」へのリスク意識が高いことがうかがえる。
興味深いのは、700件以上に上るコメントだ。
「備えるも何も…無限ループ状態じゃん
あちこちでクラスター発生のニュースが」(とよ ちびすけ きんさん)
「第二波?、日本の場合、まだ第一波の最中では…」(Masatoshi Ugajinさん)
「そもそも第1波がまだ終わっていない」と感じている人もいれば、「第何波まで続くか分からない」という無限ループを感じている人もいる。
このような不安を感じるなかで、「これからの社会が長期的にどう変化していくのか」は気になる点だ。
その点について、『感染症と文明』などの著書があり感染症の歴史に詳しい長崎大学熱帯医学研究所・山本太郎教授による話は、示唆に富んでいる。
山本教授によると、新型コロナのような新しいウイルスは、野生動物からヒトへと感染する形で一定頻度で発生してきた。ところが近年、エボラ出血熱や新型コロナなど、その頻度が高まっているという。少し時間をさかのぼるが、エイズもその1つだとした。
山本教授はその理由として、「人間による環境破壊で生態系が混乱を起こしている影響だ」と指摘。「開発や地球温暖化によって野生動物とヒトの暮らす空間が近づき、ウイルスがヒトに伝播しやすくなった」と述べた。
数年以内にはワクチンや治療薬が開発される可能性もある。未来は神のみぞ知るだ。しかし、一つはっきりしていることは、新型コロナウイルスが人類にとって決して最後の「新型」ウイルスとはならないだろうということだ。地球温暖化などの環境の急激な変化によって、地球上に人類に影響を与える新たなウイルスが登場する頻度は確実に上がってきている。
出典:「人類は新型コロナウイルスといかに共生すべきかを考える/山本太郎氏(長崎大学熱帯医学研究所教授)」ビデオニュース・ドットコム
つまり、人間による環境破壊を一因として、「新型ウイルス」の発生頻度は高まってきているという。
たしかに、大きな流行(その規模は様々だが)を引き起こした新型ウイルスは、スペイン風邪A(H1N1)(1918年発生)、アジア風邪A(H2N2)(1957年発生)、香港風邪A(H3N2)(1968年発生)、エボラウイルス(1976年発生)、ヒト免疫不全ウイルスHIV(1981年発生)、というように、かつては40年に一度から10年に一度のペースで発生していた。
しかし2000年代以降は、その発生ペースが、10年に一度どころか、10年に二度くらいのペースで発生している。
SARSコロナウイルスSARS-CoVは2002年に発生して774人以上が亡くなり、新型インフルエンザウイルスA(H1N1)は2009年に発生して1.8万人以上が亡くなり、MERSコロナウイルスMERS-CoVは2012年に発生して858人以上が亡くなり、そして新型コロナウイルスSARS-CoV-2は2019年に発生して40万人以上が亡くなっている。
ということは、もし仮に新型コロナが、ワクチン・治療薬の開発・普及や自然免疫などによって、「社会を非常事態にするウイルス」ではなくなったとしても(その社会を以下では「コロナ後の社会」と呼ぶことにする)、いずれまた「社会を非常事態にする別の新型ウイルス」が発生するかもしれない、ということだ。
なので長期的に見れば、「新型コロナ」に限らず、「社会を非常事態にする新型ウイルス」全般に対応できるように、「新しい生活様式」を模索していく必要がある。
では、「社会を非常事態にする新型ウイルス」というのは、どういうウイルスだろうか?
2000年代以降の他の新型ウイルス(SARS・新型インフル・MERS)は、現在と同じようなグローバル化の進んだ環境にありながらも、「新型コロナ」ほどには世界的な非常事態を引き起こさなかった。
その要因として、「新型コロナ」と比べると、「人間同士の感染力が弱い」(MERS)、感染力が強いとしても「潜伏期間が短い」(新型インフル)、潜伏期間が長いとしても「潜伏期間中の感染力がほとんどない」(SARS)、また「無症状率が低い」(SARS)、といった点を挙げることができそうだ。
つまり、「新型コロナ」は、従来の新型ウイルスと比べると、「人間同士の感染力が強い」「潜伏期間が長い」「潜伏期間中にも感染力が十分ある」「無症状率が高く、無症状者でも感染力がありうる」という点が、世界的非常事態の要因として挙げられそうだ。
これらの要因を、一言でいうと、「(感染力があるのに)人間には知覚できない場合が多い」、つまり、「不可知性が高い」、とまとめることができる。
「新型コロナ」によって引き起こされた世界的な非常事態を、「社会現象」として社会学的に見る場合、この「不可知性が高い」という点が、重要な鍵になるのではないかと私は思っている。
これから、この「不可知性」という概念を鍵にしながら、「コロナ後の社会」を、長期的な近代化論の視点で輪郭づけていきたい。(つづく)