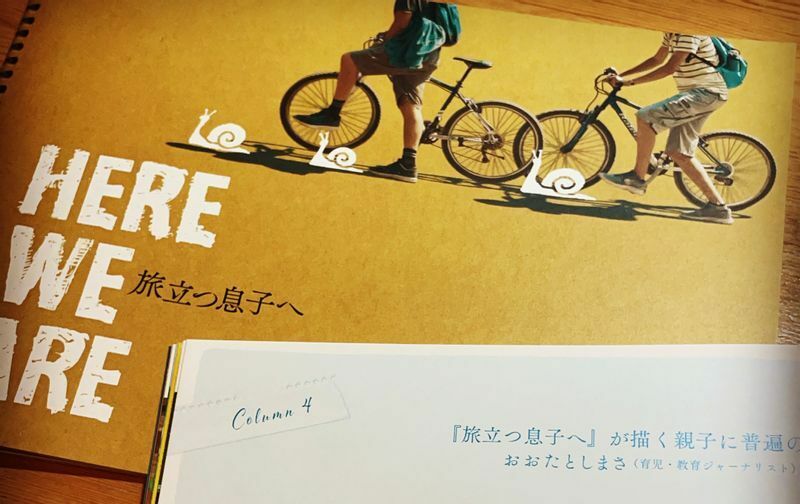ロボットのように完璧な親なんてつまらない。映画『旅立つ息子へ』が描く「子離れ」の瞬間【ネタバレあり】

イスラエルの映画『旅立つ息子へ』の劇場用パンフレットに寄稿した「解説」を転載する。この映画は、自閉症スペクトラムをもつ息子とその父親の物語であるが、すべての子煩悩な親にとって、胸がぎゅっと締め付けられ、そのあとじんわり温かくなる作品だ。劇場上映は終わっているが、現在オンデマンド配信で視聴可能。まずは映画の予告編を見てほしい。
映画『旅立つ息子へ』が描く 親子に普遍の摂理
子育ての本質は、親がいなくても子どもが生きていけるようにすることだ。つまり親の役割は、子どもにとっての自分自身の価値を日々減らしていくことだという逆説が成り立つ。「そんなに心配してくれなくても、もう大丈夫だよ」と言ってわが子が自分のもとを巣立っていく瞬間は親にとって、もっとも寂しくてもっとも幸せな瞬間だ。これが子育てにおける「幸せな逆説」である。
また、子どもを守るということは、両腕を広げて子どもの楯になることではない。自分がいなくても、わが子が自分の身を守れるようにしてやることだ。かといって、わが子がひとりで自分を守れるように鍛え上げる必要もない。親の代わりにたくさんのひととつながることができれば、社会ではなんとか生きていける。むしろ親として大切なのは、ひとは誰も、決してひとりでは生きていけないと教えることだ。
でもアハロンは、みんなの支援を拒絶した。ウリのことを愛し思いやることができるのは「私しかいない」と言い張り、ウリのために自分は「最善の選択をしてきた」と断言する。
作品中で妻・タマラとの別居の理由は明示されていないが、おそらく息子の養育方針の不一致であろう。他者の手を借りて息子を社会に適応させようとするタマラに対して、アハロンは自分の身ひとつで荒々しい世界から息子を守ってみせると意固地になったのではないか。
この決意を固めたとき、アハロンは「アハロン自身」として生きることをやめ、「ウリの父親」という役割に専念することを選んだ。「アハロン自身」を愛していたタマラが、家を出て行く選択をせざるを得なかったのも無理はない。
しかし離れてもタマラは、アハロンとは違う形で親の役割をまっとうしようとする。意固地なアハロンに対抗するべく、強引に、息子を施設へ入居させる手続きを進めてしまうのだ。このとき観客には、タマラが、仲良し父子の関係を引き裂く無慈悲な“悪役”に見えるかもしれない。しかし考えてみてほしい。このときタマラ自身に、“悪役”を演じるメリットは何もない。
ウリは、まったく異なる子育て観をもつ2人の親に、まったく異なる距離感からそれぞれに見守られて育てられてきたのである。期せずしてそれが、ウリの育つ環境の奥行きになっていた。夫婦の子育て観の不一致は、必ずしも子どもの育ちにおける不利を意味しない。
アハロンとウリの逃避行が始まる。自閉症スペクトラムのウリにとって、行き当たりばったりの旅なんて、パニックの連続でしかないと思われた。しかしそこでアハロンが見たのは、意外にもたくましいウリの姿だった。アハロンだけではない。ウリのことを一人では何もできない子と思っていた観客も、見事に裏切られる。逃避行がウリを成長させたのではない。ウリはすでに、親離れの準備ができていたのだ。
アハロンに対して、施設の職員は「彼(ウリ)は子供じゃない」と言い、実の弟は「誰も(自分を助けに)来ないと言うために田舎に住んだくせに」と指摘する。図星だった。みんながウリのことを愛し思いやっているのに、その役割を独り占めしたのはアハロン自身だった。ウリが自分を必要としてくれなくなったら、ウリのためにすべてをなげうった自分の存在価値がなくなってしまうから。アハロンは無意識のうちにそれを恐れていた。
自宅で父親と暮らすべきか、施設に入るべきか。「答え」はウリ自身が知っていた。でもウリはすべてを言葉にはしない。それはときにもどかしいが、ときにやさしい。ウリは、とてもウリらしいコミュニケーションの仕方で、それを父親に伝える。家に帰って星形のパスタを食べようと誘う父親に「僕はみんなと普通のパスタを食べる」と言うのだ。
さらにウリは、これまたとてもウリらしい方法で、アハロンに感謝を伝える。ペンで描いたボタンを押して自動ドアのなかへと吸い込まれていくその背中は、「お父さんが与えてくれた惜しみない愛情を糧にして、僕はこれからも生きていくよ」と語っている。
この瞬間、親としてのアハロンが昇華する。
親離れしたウリの背中を見届けたアハロンは、踵を返して歩き出す。そして、ウリと歩んで来たのとは別の方向へと目を向ける。アハロンもまた、子離れを果たし、いままでとは違う人生を歩もうと決心するのだ。
結局のところこの作品が描いているのは古今東西の親子に普遍の2つの摂理である。1つめは、親とは、子どもを導く存在だと思われがちだが実は、常に子どもの成長から一歩遅れて成長する存在であること。2つめは、子育ての最善・最短ルートを模索する親は多いがむしろ、回り道こそが親子にとってのかげがえない宝物になること。
ウリがもつ自閉症スペクトラムという個性と愛くるしさによって、観客の心情は見事にアハロンと同化させられてしまうのだが、冷静に考えると、アハロンの言動のほとんどは、はっきり言って過保護なダメ親の典型だ。
でも、ロボットのように完璧な親なんてつまらない。子どもの障害のあるなしにかかわらず、どんな親だって、親として一生懸命になればなるほど、多かれ少なかれアハロンのようになる。その姿こそが愛おしい。
ダメでいい、ダメがいい。だって親なんだもん。

■タイトル:『旅立つ息子へ』
■作品クレジット: 2020 Spiro Films LTD.
■公開表記: オンデマンド配信中
監督:ニル・ベルグマン
脚本:ダナ・イディシス
出演:シャイ・アヴィヴィ、ノアム・インベル、スマダル・ヴォルフマン
2020年/イスラエル・イタリア/ヘブライ語/94分/1.85ビスタ/カラー/5.1ch/英題:Here We Are/日本語字幕:原田りえ配給:ロングライド
PG12
※この記事は映画『旅立つ息子へ』の劇場用パンフレットへ寄稿した文章を転載したものです。