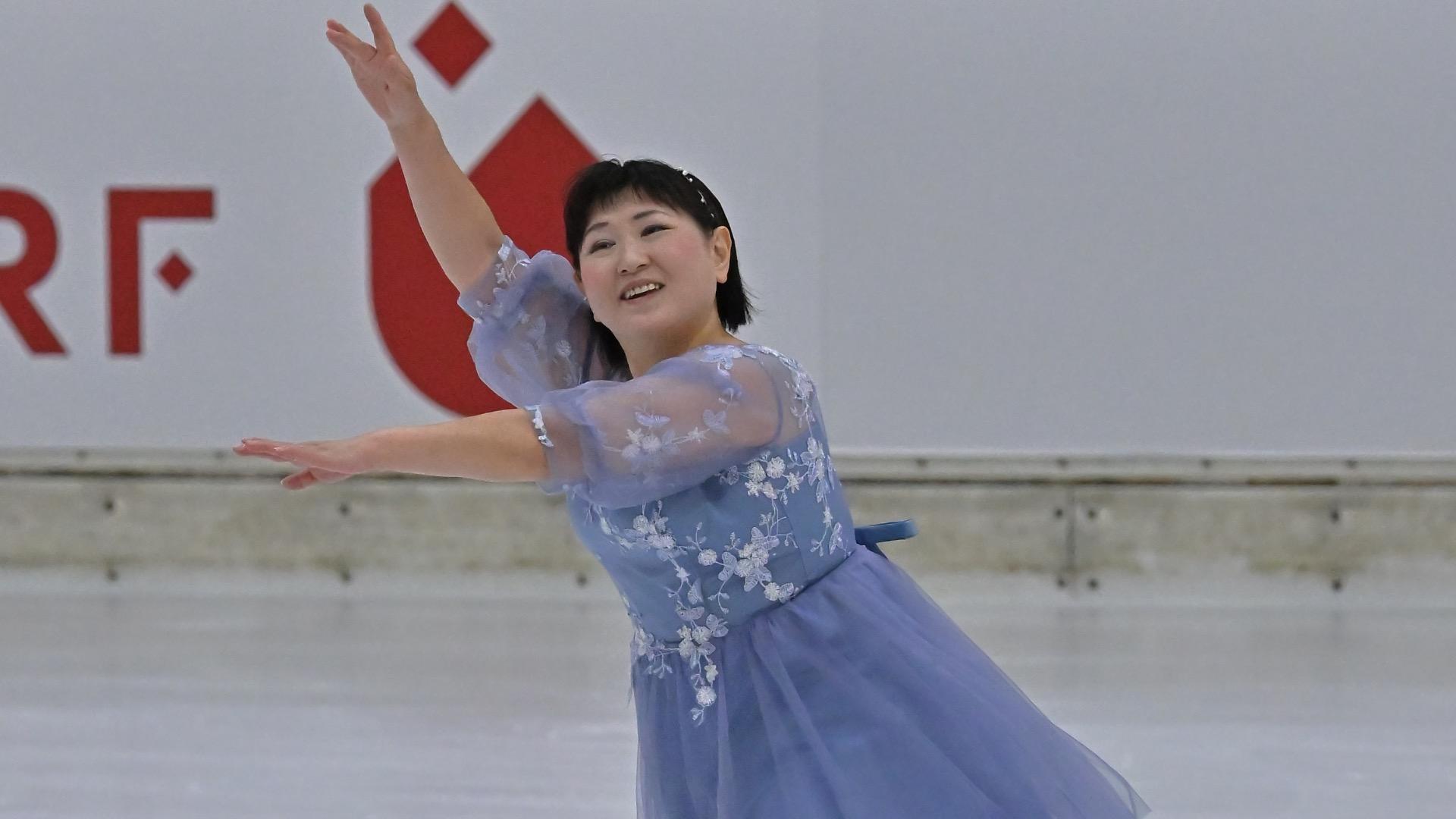政府にノーをつきつける若者たちと共に。弾圧の現場の最前線に立った「香港画」の監督が語る

現在、新型コロナウィルスの感染拡大に関するニュース一色になっているが、昨年のとりわけ下半期に国際ニュースとして数多く報じられていたのが香港の社会情勢について。ご存知の多いと思うが、いま香港の社会が中国政府からの圧力で大きく揺らいでいる。香港市民と警察が激しく衝突する映像を目にした人は多いことだろう。
いま、香港で何が起こっているのか?民主化デモに参加する若者たちは何を考え、何を訴えているのか?
その現場の最前線といっていい、香港民主化デモの真っただ中に飛び込み、当事者たちの姿と声を28分という時間の中に濃縮して記録したのが、ドキュメンタリー映画「香港画」だ。

香港の民主化デモを取材しようと思った理由
手掛けた堀井威久麿監督は、香港の民主化デモを取材するきっかけをこう明かす。
「2019年10月にたまたまCMの仕事で香港に滞在することになりました。
当時、すでにデモは起きていて、日本人の学生が逮捕されたりすることもあって、わりときな臭くなっていた時期だったと思います。当然ながら周りの方々には止められましたけど、渡航制限はかかっていなかったですし、僕自身はさほど恐怖心はなかったです。わりといろんな国を今まで旅してきて、危険といわれる国にいった経験もあるので、行くことに全然抵抗はなかったですね」
デモ参加者は学生主体、勇武派に女子が多いことに衝撃を受ける
そこで仕事のオフの日にデモ隊に遭遇。その場をなかなか離れなれなくなったという。
「偶然にも香港の中心街、九龍にあるネイザンロードで、バリケードを作るデモ隊に遭遇しました。そこで半ば巻き込まれるようになって、彼らの後をついていくことになったんです。
そこで、参加者が大学生、高校生、中学生もいて、若年層が主体ということに驚きました。また、勇武派(戦闘部隊)に女子が多くいたことにも驚きました。
そうした現実を目の当たりにする中で、自分の興味をかきたてられたというか。自分の心に高揚感のようなものが沸きたちました。
それは、自分も含めた日本の同世代はたぶん権力や政権、社会に反抗するっていうことを今までしたことがない。そこになにか負い目のようなことを感じていて、政府にノーをつきつける若者たちの姿を目の当たりにしたとき、何か時代が変わるんじゃないかといった熱を感じて、胸が熱くなった気がします。
あと、香港の40代の女性がこんなことを話してくれました。『今の若者たちを見て自分に罪の意識を感じる』と。『自分たちの世代は20代のころは割と享楽的な生活をみんなしてて、カラオケへ行って、ディスコに行って遊んでいて、そのツケをある意味、今の若者が払っているんじゃないか、だから、私たちは若者を支援する』とおっしゃっていた。

そこまで大層なことを僕は言えないんですけど、それでも自分たちが日本で生きてきて、なにも声をあげないできたことで、ある意味、今の若者たちに割を食わせているところがあるんじゃないかなと思ったんです。そういう意味で香港の若者を通して、自分自身がすべきことをしてきたのか、すごく考えさせられました。
それで気づけば、お昼の12時から夜明けの3時ぐらいまでずっとデモ隊と行動を共にしていました。彼らのデモはゲリラ戦を展開しているので常に神出鬼没。急に何千人が集まったかと思うと、急に消えて、また別の場所に何千人が集まるというのを繰り返しているので、追っていくのがものすごく大変だったんですけど、とにかく離れがたくて、あとを追っていました。
あとでグーグルのマップを見たら、30キロ近く歩いていました。体力的にはしんどかったんですけど、何かデモに参加している若者たちが『この先、どこに進んでいくのか』すごく気になる自分がいました」
気づけばデモ隊を追って30キロ近く歩いていた。そして記録することを決意
その日のうちにいまの香港を記録する意思を固めたという。
「その日のうちに、今回のプロデューサーを引き受けてくれて、撮影も一緒に行った前田(穂高)に相談しました。『作品にしたい』と。
前田は、僕が卒業して初めて作った映画に録音スタッフとして入ってもらった、いわば同志のような存在。ただ、その後、彼はいろいろあって、この業界から離れて、地元に帰って旋盤工の仕事をしていたんです。
でも、僕は彼がまだ映像を諦めきれない気持ちがあることを感じ取っていた。で、彼は語学がすごく堪能で、世界情勢や社会現象、世界で起きているさまざまな事件に関心を寄せていることを知っていた。
なので、もしかしたら、こういう作品ならば乗ってくれるんじゃないかと思いました。彼の業界復帰ではないですけど、新たな一歩になるんじゃないかなと思って誘ったところもあります。とはいえ、非常にリスクが高い撮影になることはわかっていた。なので、誘うべきか躊躇する自分もいました。
最終的に、前田からの返事はOK。『ぜひやりましょう』ときて、その場で香港を取材することを決意しました。
たぶん彼が乗ってくれなかったら、僕は決心できなかったと思います」

プロジェクトを決めた日の翌月には香港へ。つてのないゼロからの始動
こうして急遽、プロジェクトが始動することになる。
「とはいえ、僕は香港に知り合いがいたわけでも、特に関係性があったわけでもない。どう進めていくのかはまったくのゼロの状態からのスタートでした。
なのに無謀にも、プロジェクトを決めた日の翌月には香港にいくことを決めました。とにかく一刻も早く現地に入りたかった。というのも、香港の社会情勢が目まぐるしく移り変わっていた。若者が撃たれたり、警官に追われる中で亡くなってしまったりといった事件も起きていて、この先どうなるか分からない。海外からの撮影に規制が入る可能性もある。なので、急いで現地入りしたい気持ちがありました。
とはいってもつてもコネもなにもない。そこでまず日本で活動する在日香港人が主体となる民主派の団体に連絡をいれて協力を頼んでみました。すると、僕らの撮影日程と同じ期間で、帰国する香港人の若者(最終的に本作の出演者となるケン、ウイリアム)を紹介してくれて。彼らが僕らが香港とつながるひとつのきっかけをくれました。
そこからはわらしべ長者じゃありませんけど、いろいろと出会いが出会いを生んで、このようにさまざまな人を取材するとともに、多くの現場に足を踏み入れることになりました」
ただ、そんな綱渡り的なことだったとは信じられない高いクオリティの映像で香港の現実がしっかりと記録されている。
「幸運だったとしかいいようがない。
ある程度計画はしていたんですけど、結果的にはほとんど行き当たりばったりの撮影になりました。よく作品にこぎつけられたなと思います。
ただ、そもそもデモ自体がゲリラ的な集まりでのものだったので、そうせざるえなかった面もあります。
たとえば、非合法ではないデモに関しては日付が発表されて、何日にどこでやるというのは分かるので、それに合わせて行動することはできる。でも実際のデモはどこで起きるかわからない。
そして、映画に出てきたような、ああいった警官隊が暴力を行使する場面とかは当然予定にない。たとえ予定を立てていたとしても撮れるものでない。
はじめはどうすればいいのかわかりませんでした。けど、現地にいるとなんとなく肌感覚でわかるようになっていったんですよね。『あのあたりを撮っておいたほうがいいかもしれない』といったような予感めいたものを感じるようになっていった。
そこから、自分たちが何か計画を立てていくというより、香港の時代の流れのようなものに自分たちも合わせていこうというふうにシフトしていったんです。
なので、毎日、デモ隊の会話をSNSでチェックして、その日の行動を想像して現場に出掛けていって自分の感覚の向いた方にいく。ほんとうに無計画で、ある意味、自分の直感というか感覚を頼りに撮影していったところがあります」

夜のデモ隊を取材してまわるとだいたい帰りは朝方。その繰り返し
だいたいの撮影の1日の流れをこう明かす。
「さっきも少し触れたように現地に入って数日は、割と計画を立ててやろうと思っていたんです。たとえば、インタビューの時間を基本にして、この時間は、イメージカットで、この時間はデモの取材といったように。わりと既存のドキュメンタリー映画のようなスタイルで撮ろうとしていました。
ただ、どうもしっくりこない。現地の熱のようなものを感じる映像も撮れなくて、なにか形式ばった画しか撮れない。それも香港の時代の流れに身を任せようと思い、ある意味、計画性をもたないで撮影していった理由です。
ああ、あと、デモ隊の青年に『自分たちの闘い方はBe Waterなんだ』と言われて。彼らのスローガンのひとつなんですけど『流動的に闘う』という意味なんです。『じゃあ、自分たちもそういうスタイルにしていかなきゃいけないのかな』と切り替えたところもありました。
それで最終的に固まった1日の流れは、まず朝10時ぐらいに起きてSNSをチェックする。
それからインタビュー相手の交渉といったことをだいたい午前中にして、決まると、その日のうちに出掛けていってしっかりインタビューを撮る。それで夜から大体、ああした警官隊とデモ隊との衝突が起きるんですね。
それで夜に再びSNSをチェックすると、ここでこんな事件が起きているといった情報がのっていて、そこで現場に急行する。とくにデモが情報が入ってこないときは、ホテルへ戻って編集作業をする。それ以外の夜は出ていって取材する。夜のデモ隊を取材してまわるとだいたい帰りは朝方。その繰り返しでした」
香港の若者たちの言葉を届けたい
作品は、1ヶ月半の撮影期間を24時間(1日)の出来事にまとめ、抗議活動をする学生らのインタビューと、デモの実際の現地映像で構成されている。
収められている映像を見ると、デモ隊と警察隊の衝突といった現地の映像だけでも十分作品として成立できた気がする。ただ、本作はその中にインタビューをきっちりと入れ込むスタイルを選択している。
「当初は香港で起きている事象だけを切り取ろうかと考えていました。インタビューは映画として成立させるためのリスク回避として撮っていたところがあります。
でも、編集の過程で『彼らの声を入れてみてもいいんじゃないかな』と僕自分が変化していったというか。彼らの言葉をきちんと入れたほうがいいのではと思い始めた。
その意識の変化は、香港人である彼らが日本語を使って僕らにアピールしてきたので、その意図は伝えたいといいますか。義務感ではないですけど、やはり彼らの言葉を届けたい気持ちが芽生えたことは確かです。
それで最終的に、報道のような出来事の正確性を追求したり、香港の民主化デモの経緯や歴史を描く事よりも、香港という都市空間で起きている現象そのものを俯瞰することと、抗議を行う若者達の感情を描くことに重点を置いて、インタビューと現地で起きている現象の映像で構成することに決めました」

当初は、10分ぐらいにまとめることを想定
先述した通り、本作は30分に満たない28分の作品。実は当初は、もっと短い作品を想定していたという。
「最初は、もっとシンプルな、ミュージックビデオのように映像だけでみせていく10分ぐらいの作品を考えていました。
一つ影響を受けた作品があって、『Hotel 22』という短編映画なのですが、実は香港の女性監督さんが撮っている。サンフランシスコのホームレスが夜、暖をとるためにバスの中で朝まで過ごすという一日のお話なんですけど、細かく時間によって区切られて構成されているんです。それを見たときに、『あっ、こういう構成にしたら10分でもできるんじゃないかな』というアイデアが浮かんできて、『香港画』のベースになりました。24時間の構成というのは、もう、それを参考に作らせていただいてっていうのがあります。
それもあって10分ぐらいに当初はまとめようとしていた。
ですから、30分近くになってしまったというのは僕の中では予定外の展開というか。劇場公開作品としては、近年、稀に見る短い作品だと思うんですけど、自分の中では『随分長くなってしまったな』という感覚があります(苦笑)。
なぜ、短編にしたのかという質問をけっこう受けるんですけど、僕は今まで長編も短編も作ってきたので、自然な流れといいますか。無理に長編化する必要も、無理に短編にまとめる必要もない、その題材や素材を見た中で決まってくるだけで、どちらも普遍的な表現方法として変わりがないと思っています。
むしろ、当初は趣味的にYouTubeかなんかで個人作品として公開して、映画祭を回れればいいかなと思っていたのに、劇場公開していただけることになったのが驚きです。
香港についてみたい、知りたいという人がいるという表れだと思うんですけど、劇場公開はまったく撮影時には考えていなかったのでびっくりしています。よくぞこの短い尺の作品の劇場公開を決めてくれたなと、今は感謝しています」
(※後編に続く)

「香港画」
アップリンク渋谷、アップリンク吉祥寺、大阪・第七芸術劇場にて公開中。
広島・横川シネマにて1月22日(金)~31日(日)、名古屋シネマ―テーク、兵庫・元町映画館、新潟市民映画館シネ・ウインドにて1月23日(土)より公開
場面写真はすべて(C) Ikuma Horii