好奇心から無謀にもインド・バングラデシュに音楽の旅へ。映像制作未経験の若き女性のチャレンジ

『タゴール・ソングス』というタイトルを耳にして、ピンとくる人はどれぐらいいるだろうか?「イギリスの植民地時代のインドを生きた大詩人、ラビンドラナート・タゴールのこと」と説明されても「あぁ、あの」とうなずく人はごくごく限られるに違いない。
本作は、そんなちょっと接点がなかなか見出せないひと昔前の海外の偉人に焦点を当てる。しかも、手掛けたのは今回がドキュメンタリー映画制作が初めてという新人監督。まだ20代の彼女がインド、バングラデシュと実際に現地を訪れ、ノーベル賞も受賞しているタゴールの音楽を知ろうとした。こうして完成した作品は、タゴールの音楽の旅の記録である一方で、知的好奇心に導かれるように未知の世界に飛び込んだ新人監督の創作の初期衝動のようなものが封じ込められている。
頼んでもないのに届く「タゴール」情報
まず、この作品のはじまりは、大澤一生プロデューサーとまだ学生だった佐々木美佳監督の出会いにまでさかのぼる。
大澤「僕も参加しているとあるイベントの受付を手伝ってくれたのが出会い。当時、現役大学生で東京外語大の学生ですと。まずは挨拶を交わした。そのあとの打ち上げでのんでいたとき、ドキュメンタリー映画に興味がある、今、ベンガル語を学んでいて、実はタゴールという詩人がいて、彼について撮ってみたいと一気に話された。ただ、僕はタゴールと聞いてもよくわからない。写真をみせてもらっても、『なんだ、この仙人は』と(苦笑)。ノーベル賞をとったことがあるときいても、『へえ、そうなんだ、知らなかったごめん』といったぐらいでとくに話がはずむこともなく終わったんです。
でも、その後、頼んでもいないのに、タゴールについての追加情報が勝手に送られてくるんですよ(笑)。そうこうしていたら、まったくの別件でバングラデシュで撮影をする企画が立ち上がりかけた。それで、ベンガル語ができるというので、じゃあ手伝ってもらおうかと」
佐々木「通訳でも何でもしますよみたいな感じで」
大澤「じゃあ、実際に話が決まったらよろしくと。でも、その企画はさあという段階でダッカで日本人も巻き込んだテロ事件が起きて、ちょっといまのタイミングでは無理だろうと、立ち消えてしまった。ただ、それでも、佐々木さんには、何かタゴールについて映画にしたいという気持ちが消えていなかった」
佐々木「大学でドキュメンタリー映画の存在を知って、山形国際ドキュメンタリー映画祭などで実際に触れて、普通に生きてる人で物語を構築することがおもしろそうだなと思ったんですよね。それで、タゴールについての映画をみてみたい気持ちが芽生えた。歌なので、文字だけでは伝わらないものが絶対あると思っていて、それを大澤さんが察して助け舟を出してくれたんだと思います」
彼女の揺るがない意思の固さにかけてみよう
そこで、タゴールについての映画をやってみようかという気運が高まった。
大澤「選択肢は幾つかありました。まず、在学中だったので卒業制作として、映像で卒論と併せて作るというのもひとつの手じゃないかと。歌の話なんで、やっぱり言葉やテキストだけだと伝わらないところもあるので、実際行って自分ひとりで撮ってみるという案がまずありました。ただ、どうも意見を交わしていると、ちゃんとひとつの映画にまとめたい欲求が佐々木さんの中にある。
ただ、いきなり1本の長編映画を作るなんて無謀なチャレンジ。彼女の場合、映像制作を学んだ経験もないですからそうとうハードルは高い。でも、その彼女の揺るがない欲求にかけてみようと思ったというか。最後まで諦めない、意志の固さを感じたんですよね。それで、僕自身がプロデューサーとして製作に乗り出そうと腹を決めました」
彼女の知りたい、触れたいという気持ちにプロデューサーとして奮起した
なぜ、佐々木監督は大澤プロデューサーにタゴールの情報を伝え続けたのだろう?
佐々木「何でだろう(笑)。やはり映画を撮りたかったからだと思うんですけど、実は思い返しても、よく分からないんです」
大澤「僕からすると、(タゴールを)知ってもらいたいっていう気持ちがひしひしと伝わってくる。その貪欲さは、すごく映画を作る上では重要。実は技術よりも何よりも一番大事なことかもしれない。それを持っているのは僕の中ではけっこう、心を動かされたポイントだったんです。
自分で言うのもなんですけど、チャレンジングな企画だと思うんですよ。タゴールという題材は。言い方は悪いですけど、ビジネス的にめちゃくちゃなひきがあるわけではない。日本人にもほとんどなじみがない。ふつうに考えたら、企画としては成立しづらい。
ただ、彼女の知りたい、触れたいという気持ちに触れたとき、こちらもプロデューサーとして奮起したというか。こういう無謀かもしれないけど、ひとつのピュアな思いから始まる作品をやってみたいと思ったんですよね。どうなるかはわからない。でも、たぶん彼女がなにかを発見していく過程が映画になるんじゃないか。それにのってみようと」
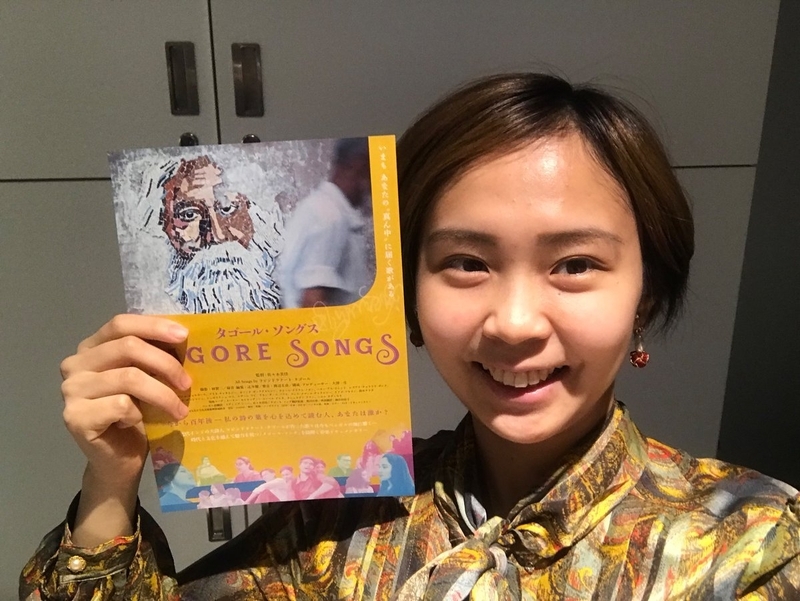
そう、まさに本作は、未知の世界に飛び込もうとする佐々木監督のある種の心意気がまず最初にある。こんな心から興味のあることに心の赴くままアクションを起こすような若いドキュメンタリストに出会ったのは久々かもしれない。
いわゆるセルフ・ドキュメンタリーがブームになって以降、なにかしら自分探しを軸にしたタイプの作品はいまも多い。その一方で、それこそ大澤プロデューサーが手掛けた『バックドロップ・クルディスタン』のような日本の若者が、なんだかわからないが問題意識をもってしまって、その思いに駆られるまま日本を飛び出し、海外にまでいってしまうような作品はめっきり減った。そんな未知の領域に飛び込み、何かを発見しようとする姿勢が佐々木監督には感じられる。
大澤「そうですね。感覚的には、『バックドロップ・クルディスタン』に似たところがありました。20代の兄ちゃんがクルド問題に首を突っ込むという無茶。同じようなにおいが、佐々木さんにはあった。そこで、もうポンとインドとバングラデシュに飛び込ませたいなと」
佐々木「私自身は、セルフ・ドキュメンタリーをいくつかみたことあるんですけど、あまり自分はやってみたいと思わなかったですね。それよりかは、自分の分からないものを探求した後に何が見えるかのほうが面白いなと」
撮影プランは、中島みゆきの『糸』?
こうして映画製作の経験が一切ない佐々木監督との映画作りが始まった。
大澤「とはいえ、映像・映画製作の経験が一切ないので、いきなりひとりは無理だろうと。そこでまず、日本映画大学時代のつてで、辻井(潔)くんにスタッフでついてほしいとお願いしました。彼には何度も作品の編集をお願いしているのですが、今回は編集に加え、録音も担当してもらいました。その経緯はというと、当時、彼がもう編集のデスクワークに飽き飽きしていたんです。もう素材だけ渡されて編集するのはつまらないと愚痴を言っているので、じゃあもう現場行ってこい。インドに行ってこいとなった(笑)。それで、編集マンでありつつ、現場のある種の総合的なディレクション的なポジションを担ってくれと。佐々木監督はその時点では素人ですから、なにもかも初めてだから、何を押さえればいいかとかまだまだ勘どころがわからない。その辺りを辻井くんにある種サポートしてほしいと思いました。
撮影に関しては、今回、初めて林賢二くんにお願いすることにしました。当時、彼は日本映画大学を卒業したばかりで。その卒業制作の作品を見せてもらったときに、ほんとうにすばらしい撮影だった。それから、作品自体も、ちょっと間接的にタゴールとつながる内容だった。そこで打診したら、やはり彼もすぐに興味をもってくれて、海外取材にもひじょうに積極的だった。それで、じゃあ、このチームでいこうと決まりました。
次におおまかな撮影プランを立てて。ずっと言ってたのは、これは、中島みゆきの『糸』だよと。縦の糸はあなたで、横の糸は私じゃないけど、タゴールと彼の影響を受けたいろいろな人の織りなすタペストリーみたいなもの意識して撮っていこうとだけ伝えました。
僕の仕事は、ここでほぼ終わり。あとは『じゃあ行っておいで』と送りだしました」
こうして映画作りに乗り出すことになった佐々木監督だが、そもそもタゴールになぜ興味を抱いたのだろう?
佐々木「実家が浄土真宗で仏教が身近にある環境だったのですが、その仏教がインドから伝わったことを知ったとき、そのつながりに興味をもって東京外国語大学に入り、ヒンディー語を学び始めました。そこからベンガル文学のゼミに所属して、研究対象を探しているときにタゴール・ソングに出会いました。
ベンガル語の教授が実は、日本人なんですけど、実際に学生のころにタゴール・ソングを習いに行って、タゴール・ソングの修士までおさめている。日本でタゴール・ソングを教えてる先生だったんです」
大澤「日本で唯一のタゴール・ソングの歌い手と言っていい奥田由香先生です」
佐々木「それで、タゴールは歌を2000曲以上書いていて、今でもその歌を教える先生や歌い手がいて、習い事として学んでいる子どもも多いと知り、驚きました。日本ではそういった世代を超えて、民族全体で共有していくような歌の文化は見当たらない。百年以上の時を超えて、ベンガルの人々の心に息づいているタゴールの曲ってなんなんだと思いました」

ベンガルの人々と自分との間にあるタゴール音楽の溝を埋めたい
そこでYouTubeで歌を実際に聴いてみた。
佐々木「正直なところ、何がいいのか分からなかったんですよね。メロディーにすごい特徴があるわけではないので失礼ながらピンとこなかったです(笑)。
奥田先生もいろいろと教えてくださって、ものすごくすばらしいものだということを力説してくださるんですけど、そういわれればいわれるほど、ちょっと私がきょとんとしてしまうところがあって(笑)。このわたしとベンガルの人々のギャップというか溝をなんとか埋めたい。なんでタゴール・ソングがベンガルのみなさんは好きなのか、どの曲がみんなのお気に入りなのかとか、そういうことを聞きたくなってしまった。
映像制作に踏み出す前は、タゴール・ソングを自分で翻訳して、歌の意味を理解しようとしたんですけど、どこか抽象的で、よく意味がわからない歌が多かった。なので、さらに溝が広がったようでもやもやがいつまでも解消されない。
なぜ、みんなインドの人、バングラデシュの人含めそこまで知れ渡っているソウル・ソングみたいになっているんだと、それが探求してみたいと思うきっかけでした」
100年前の詩が受け継がれ、現代はYouTubeで広がる
こうしてタゴール・ソングを探求する取材がはじまった。
佐々木「はじめは人によって思い入れの度合いが違うといいますか。ほんとうに貧しくて教育を受けられない家庭の人にとっては、タゴール・ソングよりももっと身近に感じられる大衆の歌がある。なので、まずはみんながみんな好きではないことに気づきました。当たり前といえば当たり前のことなんですけど。
でも、取材を進めていくうちに、熱狂的ではないけど、『自分の人生はタゴール・ソングによって支えられた』とか、そういう人が何人も出てきたんですね。タゴール・ソングと人生がリンクしている人がいる。曲よりも、タゴールの詩というほうが正しいのかもしれないんですけど、タゴールの歌であり、その詩、さらにいえばその言葉に大きな影響を受けている人がいっぱいいる。
実は、タゴール・ソングはパブリックドメインになったのはつい最近のこと。それまではおそらく、学校の中で教えられたり、親から子へ自然に伝えられていた。それで途切れそうになりながらも、ここにきてカバーがYouTubeとかで流されて、また広がる。
歌そのものに生命があるというか。この歌によって救われたり、生かされた人がそれをまた誰かに伝えるようなサイクルでつながってきているような気がしました。100年前の詩なんですけど、いまにつながる普遍性がある。だから、タゴール・ソングを学んで正当に継承している歌い手もいれば、ストリートのラッパーがカバーしたりもしている。
あと、バングラデシュやインドはまだ文字が読めない人がたくさんいらっしゃる現実がある。その中で、歌は耳から入ってくるので、それがメッセージとして伝わったところもあるかなと感じました。それゆえ、分け隔てなくあらゆる層になじみのあるものになったかもしれません」
作品には、バングラデシュを代表するタゴール・ソングの歌い手、タゴール・ソングの教師など、さまざまな人物が登場する。知りあいのつてをたどっての人、偶然出会った人、半々ぐらいだという。
大澤「バングラデシュに1度行ったことがあるというので、ちょっと当てがあると思ってたら、予想が外れて(笑)」
佐々木「ほとんど当てはなくて、知り合いの知り合いとか、ほんとうに小さなコネクションをたどって手探りでみつけていったことがほとんどでした。街中で偶然出会った人もいます。振り返っても、よくみつかったなと」
日本とタゴールの意外なつながり
その偶然出会ったひとりが、本作のキーパーソンにもあげられるコルカタ市内の大学に通い、タゴールの歌や詩を愛するオノンナさんだ。いまどきの大学生である彼女は、親の反対を押し切って初海外旅行で日本に来日。意外な日本とタゴールのつながりも伝えてくれる。
佐々木「ほんとうに偶然なんですけど、タゴールの生家があって。訪れた日はお祭りがあって、なにかその生家でもイベントをやっているんじゃないかということでとりあえず行ってみたんです。オノンナもそう思ってきたみたい。
そうしたら何もやっていなくて、それどころか門も閉まっていた。どうしようとうろうろしていたら、オノンナがけっこうめかしこんだ服装できていたので、『もしかして』と思って声をかけたんです。ほんとうに偶然の出会いでした」
大澤「よく『無理やり連れてきたのではないか』と指摘されることがあるんですけど、オノンナの来日は自分の意志。彼女はずっと海外に行ってみたいと話していた。ただ、お父さんがとても保守的で厳しくて、海外にひとりでいくのはもってのほかだった」
佐々木「それで仲介するわけではないんですけど、ちょっと家族で話し合われてはどうですかと提案したんです。そうしていざ話し合いの場になったら、大ゲンカになってしまった(笑)。ただ、あとで『いままで言えないでいたことがいえて、すっきりした』とお母さんはいっていて、みんな納得の場にはなっていたと思うんですね」
大澤「それだけのこと。作りこんでると思われがちなのですが…」
佐々木「あと、日本とタゴールのつながりについては、ノーベル賞も受賞しているタゴールではなく、みんなのタゴールという感覚に日本でもなってくれたらなという個人的な希望というか、思いがあります。単なる歴史上の偉い人じゃなくてもっと近いところにいる人なんだと日本のみなさんにも感じてもらえたらうれしいです」

このオノンナさんの来日は最後にすばらしい瞬間を迎える。これは作品をみて確認してほしい。
さて、こうして旅を終えたいま、タゴール・ソングの魅力をどう感じたのだろうか?
大澤「僕はタゴールは、シンガー・ソングライターなんだなと。プレスにも無理矢理やり書いてますけど、日本でいうとブルーハーツの歌と同じというか。あくまで個人的な見解ですけど、ベンガルの人々にとっては、カラオケで日本でいうと『リンダリンダ』を歌うような気持ちになっているんじゃないかと。どこか周りもだけど、自分を鼓舞するというか元気づける。そういう要素があるんじゃないか。あるいは、中島みゆきの『ファイト!』みたいな。作品内でも一番よく触れられている『ひとりで進め』は、ほとんと『ファイト!』じゃないかと思います」
佐々木「個人の生き方とか、孤独とか、愛という誰しもにとって普遍的なテーマがあって、とても言葉を大切にしている。そこに魅力の本質があるような気がしました。また、その言葉をストレートに受け止められる。それほどタゴールは人々にとって信頼のおける、尊敬を集める人格者だったのではないかと。だからこそ、みんなその言葉を信じるし、受けとめられる。それがめぐりめぐって、継承されてきた理由かもしれないとわたしは考えました」
完成までの道のりをこう振り返る。
佐々木「作ってる最中は、本当に無我夢中で。大変なことばかりで、『もう辞めてやる!』とか思ったときも正直ありました。でも、実際に完成して、プロモーションをする中で、だんだん見ず知らずの人に届いていく。こちらが予想もしないような声が届くこともあれば、わたしが感じてほしいと思うことがきちんと届いていることがある。いまは、映画を作るのは大変だけど、それ以上に喜びがある。もう次を作れたらなと思っています」
当初は4月18日の公開を予定。しかし、コロナ禍の影響で延期を余儀なくされた。その中で、まずは5月12日からデジタル配信の「仮設の映画館」で公開がスタート。6月1日からメイン館であるポレポレ東中野での公開がはじまった。ただ、この公開延期も作品を熟成させる期間だったと前向きとらえる。
大澤「なぜベンガルの人たちはこんなにタゴールに魅せられるのかという疑問から始まって、どうにか作品は完成した。でも、果たして、どういう人に見てもらえるだろうっていうのは、日本においては想像がつかない。シンプルに、果たして、お客さんは入るのかなと思っていたわけです。ただ、コロナの影響を受け始めて、公開延期が決まったぐらいから、映画が届きそうな手ごたえが出てきたんですよ。
そして緊急事態宣言が解除されたいまも、その手ごたえがあって。
いままだコロナ禍で、まだまだみなさん先がみえないので不安はぬぐえていない。自由が制限されたことでの鬱屈もまだ解消されていない。社会全体がいらだっているところがある。そういうときに、この映画であり、タゴールの音楽というのはちょっとそのささくれだった人の心を鎮めてくれるというか。なにか、気もちを落ち着かせてくれるところがある。
それから、タゴールの詩や歌はまっすぐな言葉で嘘がない。いま、とりわけ政治がいい例で、嘘や誹謗中傷の言葉が日々とびかっている。あまりにも乱暴で、耳をふさぎたくなる言葉が溢れてる。だから、どこか心の底で、嘘や欺瞞のない言葉をみんな欲しているんじゃないかなと。そこにタゴールの詩や歌は届くんじゃないかと思うんです。いま伝わる手ごたえがある。まあ、プロデューサーの希望的観測かもしれないのですが(苦笑)」
佐々木「公開が延期になったときは、正直、拍子抜けするところがありました。ただ、これは仕方ないこと。劇場が休業となってしまったわけですから。改めて劇場での公開もはじまって、いまは多くの方に届いてくれたらと思っています」

「タゴール・ソングス」
ポレポレ東中野にて公開中、長野 上田映劇にて7月4日(土)より、大阪 第七藝術劇場にて7月11日(土)より公開、神奈川県:横浜シネマジャック&ベティ/あつぎのえいがかんkiki/シネマアミーゴ、埼玉県:深谷シネマ/川越スカラ座、群馬県:シネマテークたかさき、長野県:長野松竹相生座ロキシー/松本CINEMAセレクト、愛知県:名古屋シネマテーク、京都府:出町座、兵庫県:元町映画館、新潟県:新潟市民映画館シネ・ウインド/高田世界館、富山県:HOTORI × ほとり座、石川県:シネモンド、広島県:横川シネマ、福岡県:KBCシネマ、鹿児島県:ガーデンズシネマにて公開予定。「仮設の映画館」でも配信中。
場面写真はすべて(C)nondelico










