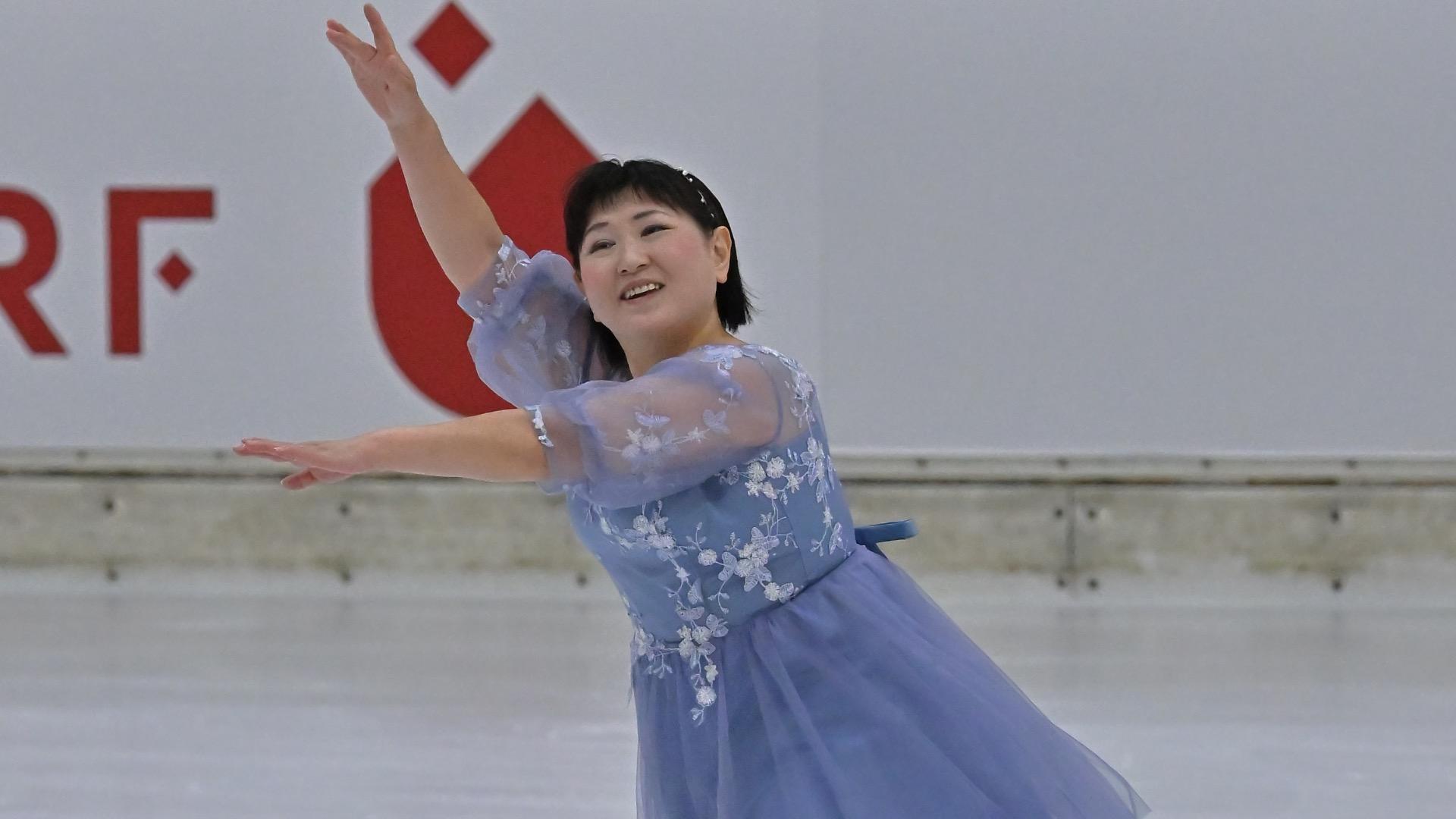思わず本に触れたくなる! ひとりの装幀家の手仕事を丹念に記録した『つつんで、ひらいて』

「活字離れ」「読書離れ」「本離れ」などという言葉がメディアで当たり前のように伝えられるようになってどれぐらい経つだろう。さらに出版不況ということもよく取り沙汰される。
もしかしたら、最近、ちょっと本を手にしていない人も多いかもしれない。
ただ、広瀬奈々子監督が手掛けたドキュメンタリー映画『つつんで、ひらいて』を観ると、きっと本を手にしたくなる。本屋に足を運べば本にもそれぞれ顔と個性があることにふと気づくかもしれない。
本の見方がきっとひとつ変わる。本作は、ひとりの装幀者の手仕事から、本の真実の世界へと誘われる。
亡き父の仕事、装幀と向き合ってみたい
広瀬監督は、本作のはじまりをこう語る。
「父が本の装幀家で、母もそうとうな読書家だったので、子どものころから本は身近なものでした。ただ、あまりに身近すぎることが逆に『読まなきゃいけない』というプレッシャーになって、子どものころはあまり本を手にしていないんです。どこか遠ざけていてすらいた。
わたしが本を自分から手にして読み始めたのは高校生くらいで、本格的に読み始めたのは大学に入ってから。本好きとはいえないくらい遅いんです。母の時代を聞くと、ドストエフスキーや大江健三郎、太宰治とかを小学校高学年から中学生くらいでふつうに通過している。わたしが手にしたのは大学生ですから、母の読書原体験に比べると、自分は圧倒的に弱い。
なので筋金入りの本好きとはいえないんです。ただ、その中で、自分がものをつくる仕事に就いたとき、亡くなった父の仕事、装幀家がどういうものなのかを知りたくなりました。なんとなくは理解していましたけど、実際のところまではわかっていなかった。それで、装幀家という仕事と向き合ってみたいなと。
最近急にふと思い出したことなんですが、大学在学時にドキュメンタリーを撮る課題があって、なにを撮ろうかと考えていたとき、父に『本についてのドキュメンタリーはどうだ』と言われたことがありました。
『そんな地味な題材、ドキュメンタリーになるわけないじゃん』と返した気がします(苦笑)」

ここから広瀬監督は本にまつわる装幀家のドキュメンタリーを模索しはじめる。すでにデビュー作として劇映画『夜明け』を発表しているが、今回の撮影はそれよりも前のこと。実は、このドキュメンタリー『つつんで、ひらいて』を1作目に考えていたという。
「わたしは社交的なタイプでもなく、コミュニケーション能力が高いとも言い難い。そこが弱点と自認していて、鍛えないとダメだという気持ちがあったんです。
その中で、フィクション映画を作る場合、監督がピラミッドの頂点に立たされ、それをたくさんの人に支えられるスタイルになってしまう。そういう大所帯でのリーダーシップを考える以前に、まずはもっともミニマムな形、一対一でフェアに作品を作っていく。そこに身を置いて自分の苦手を克服したかった。人とものをつくる自体を問い直したかった。
どんな場面も人対人で、少しずつ築きあげていくのが映画で。撮る側と撮られる側が対等な関係で常に一対一で向き合う、いわば原型といえるのがドキュメンタリーです。逃げ場のない対人関係の中に自分を立たせたいと思ったんです。
あと、映画の入口から出口までを経験したかったというか。企画の立ち上がりから、許可取りやお金のこと、どういう客層に向けてどう売るか、観客のみなさんに自覚的に届けるまでのプロセスを一度経験しておきたかった。このぐらいの規模だと自分で監督しつつ、自分でプロデュースするのは当たり前なんです」
日本を代表する装幀家、菊地信義のもとへ
こんな思いを抱きながら、スタートしたドキュメンタリーは、日本を代表する装幀家である菊地信義にカメラを向ける。ただ、はじめは体よく断られたそうだ。
「実家の本棚にあった菊地さんの『装幀談義』という著書を読んだのですが、これがおもしろくて。この人に会いたいなと。
それで連絡先をなんとか入手して、お電話とファックスで連絡をして、実際にお会いして、打診しました。
でも、菊地さんから『なんで僕に関心があって、なにを撮りたいの』と追及された上、『僕は映像はあまり好きじゃない。これまでいろいろと依頼を打診されているけど、すべて断っている』といわれて……。もうすべて否定されたのでこれは『ダメだ』と。
ただ、1か月後ぐらいに、再度お電話し、もう一度お会いすることになりました。こちらとしては、どうやって説得しようかとあれこれと想定して臨んだんですけど、行くと菊地さんは『いいことを思いついたんだよ。僕の頭に小さなカメラをつけて、手元をカメラで撮るのはどうかな』と撮影プランを提案されてきた(笑)。こちらは戸惑うばかりであっけにとられたんですけど、なんとかご了承いただけたのかなと思いました。
振り返ると、菊地さんにわたしの覚悟を試されたのかもしれません」
菊地さんのペースと言葉にのみこまれてはダメ
菊地信義という巨人と向き合った印象をこう振り返る。
「ちょうど取材を始めたのが映画の冒頭と同じで、菊地さんと関係の深い、作家の古井由吉さんの『雨の裾』のデザインが終わって、あとは出版するだけというときだったんです。つまり、菊地さんのひとつの仕事が終わったところから取材を始めたんですね。
そのときに、菊地さんが『雨の裾』の装幀について、解説してくれたんです。ものすごく饒舌に、装幀のことから自身の人生観や哲学まで一気に語られたんです。
そのお話は確かにすばらしくて、ものづくりを志す者として刺激を受けることも多く、感銘を受けたんですけど、わたしとしては一方でこう思ったんです。『この菊地さんのペースと言葉にのみこまれてはダメだな』と。
すべて言葉で説明しつくされて、結論づけられてはいけない。言葉だけで、菊地さんという人や装幀の極意、仕事への情熱といったようなことをわかったような気になってはダメ。逆を言うと、それほど菊地さんの言葉や語ることに、こちらがもうひれ伏してしまって疑問の余地を挟むことがないぐらい説得力がある。そこに私自身が圧倒されてしまうと、菊地さんの表面をなぞるプロモーションで終わってしまうと思いました。それでは表層になってしまう。
ですから、わたし自身、そうならないように最初の段階でかなり警戒しました。菊地さんのペースには巻き込まれないようにと。菊地さんも菊地さんで、探っていたみたいで。周りに『何を望んでいるのかさっぱりわからない』ともらしていたそうです」

いわば言葉に寄らないで、人間・菊地信義に迫ろうとした。
「まず饒舌な菊地さんからできるだけ言葉を引いていこうと思いました。言葉で武装する人だなというのが第一印象だったので。その完全武装した鎧を脱がせていくというか。こういう言い方が適当かわからないんですけど、ある意味、菊地さんをモノと見立ててあらゆる角度から撮っていこうと。
たとえば、菊地さんがどの紙にしようかと紙を触っているときであったりとか、紙の上に文字を置いてあれこれ考えているところとか、その表情や目つき、しぐさでも雄弁になにかを語っている。そこから本というものを問い直す作業を、この映画でできないかと考えました。
事実、菊地さんの書かれた著書の言葉や文字に心を惹かれた自分もいるし、その語りこそが菊地信義だという人もいると思うんですけど、菊地さんの本質に触れるために敢えて菊地さんの美学から一度離れる判断をしたんです。
おそらく本質というのは、ご本人のいう『僕はからっぽだ』というところにつながる。無心に仕事に情熱を注いでいるところだったり、一冊の本にむきあっているところであったり、そういった菊地さんがシンプルにものごとと対峙しているところにカメラを据えようと思いました。そうすることで、本や装幀や仕事に対しての菊地さんの思いや格闘が浮かび上がるのではないかと思ったんです」
お互いに腹の探り合い?いい形の共犯関係を築けた
変にくみしない。そのことが菊地の素といもいうべき、ピュアな瞬間をとらえている。
「たぶん菊地さんが撮ってほしいものと、実際に私が撮ったものは違うと思うんですよね。
ただ、相手の撮ってほしいことばかりを撮っていたら、私の作品と言えるものにはならなかったでしょう。
お互い、完成形が見えていて、そこに共にむかっていっての3年間ではなかった。腹の探り合いといいますか。互いに相手の望むことに安易に乗らない。そのことをやり続けた。相手のことがわからず、決してわかった気にもならず、興味が持続した。だから3年も続けられた気もするんです。相手の言い分を鵜呑みにしないのは、その人へのリスペクトがあってこそだと思うんです。いい形の共犯関係が築けたとわたし自身は思っています」
こうして生まれた作品は、菊地信義という装幀家をつぶさに見つめる。そこからは知られざる装幀の世界、プロフェッショナルな仕事の世界、デザインというアートの世界、そして人間・菊地信義が見えてくる。また、一冊の本ができるまでに、どれだけの労力が注がれているかを知る機会にもなるはず。そのことを前にすると、きっと本が人肌を感じられるぐらいぬくもりのあるもの、愛しいものに思えてくることだろう。
広瀬監督自身はこんなことを感じたと明かす。
「菊地さんが著書で書かれているんですけど『本というのはモノである』ということを実感したというか。本は手で実際に触って感じるものなんだなと思いました。
菊地さんは触感をものすごく大切にされている。言葉に紙というモノが切り離せないものと考えられている。文章を書くときに、思考を促すこともあれば、言葉を触って感じることで、考える力を促すこともある。考える力を鍛えるところの原点に触感がある」
一方で、本をめぐる状況も見えてくる。かつてはあった紙や印刷に関する技術が刻一刻と失われつつあり、本の存在がどんどん消えゆきつつあることをわたしたちは目の当たりにすることになる。
「20年前に比べて出版の売り上げが半分になったといわれています。しかも、出版業界は二極化が進んでいて、大手ばかりが潤って、小さなところはどんどん苦しくなる。いまの日本の映画界と似ているなと思いました。
ほどよいバランスを保った中間層がない。大手はビジネスばかりを優先させて、クオリティがないがしろにされている。もっと質を求めていかないと、映画も本もとりかえしのつかないところにいってしまうのではないか。そうした怖い時代になるのではないかということが頭をよぎりましたね。
そうならないためにも、わたし自身、いい仕事をしていい映画を作っていかないといけないと思いました。やはり、いい仕事をしていることは強みになる。いい作品を作っていたら、必ず見てくれている人がいて、手にとってくれる人がいる。それは菊地さんの仕事が証明していると思います」
こういう状況にも菊地は下を向いているわけではない。
「菊地さんご自身は『紙の本は絶対になくならない』と断言しています。菊地さんは現状に対して決して後ろ向きなわけではありません」
菊地信義という装幀者の仕事や本への情熱はまだ冷めていない。装幀から本の可能性を見い出そうとしている。
たかが、1冊の本かもしれない。でも、それが生まれるまでには、さまざまな人が関わり、その想いが注がれている。
本作は、その舞台裏を、ひとりの装幀家を通して、つぶさに見つめる。これまで1万5千冊の本をデザインしたひとりの装幀家の魂の宿る仕事に触れてほしい。

東京・渋谷 シアター・イメージフォーラムにて公開中。
全国順次ロードショー
場面写真はすべて(C)2019「つつんで、ひらいて」製作委員会