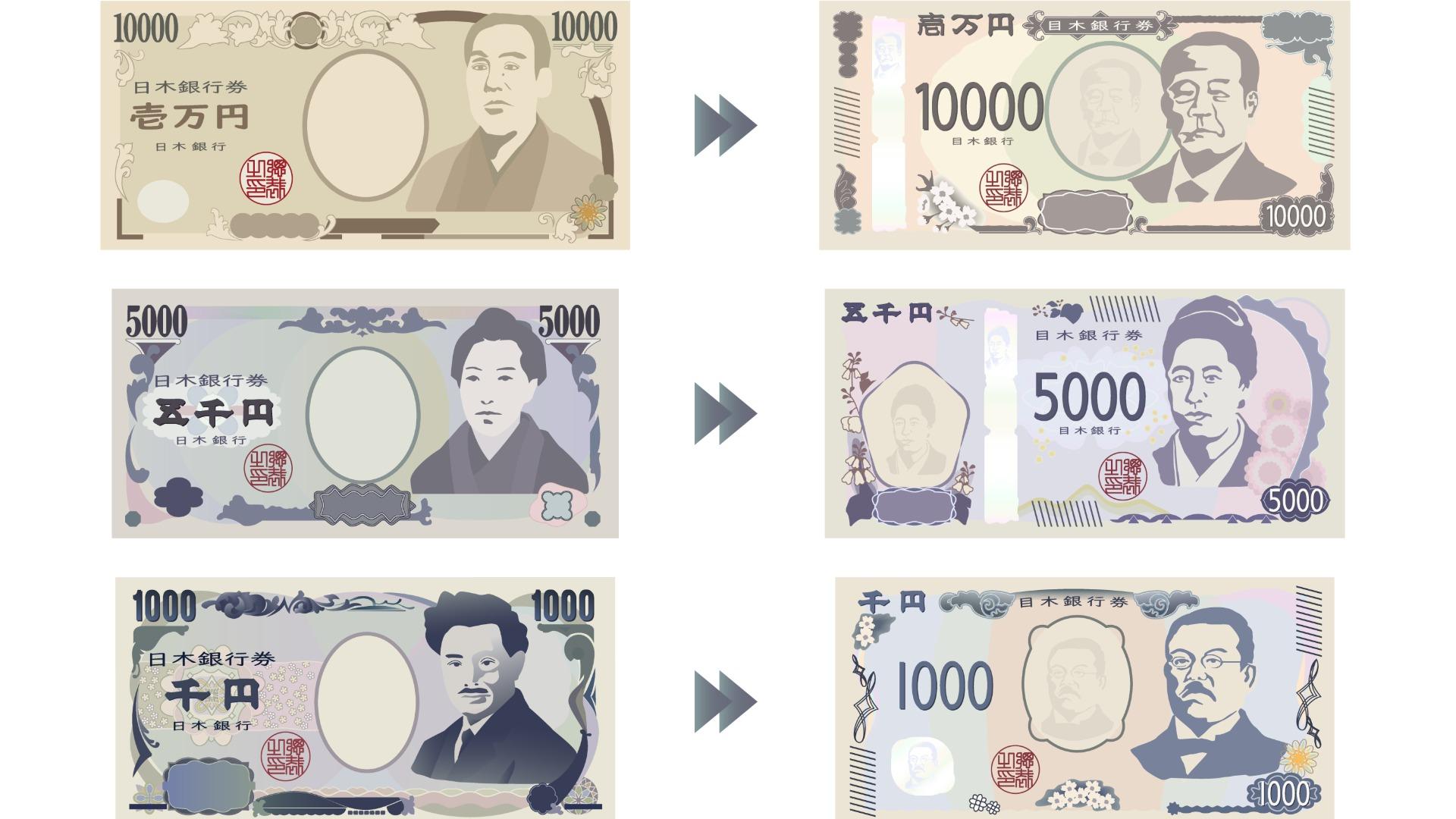ラグビーW杯、自治体のゴールも大事
ラグビーの2019年ワールドカップ(W杯)日本大会まであと6年となった。あまり世間で認知はされていないが、実はゆるやかに準備が動いている。27日、日本大会組織委員会が会場選定に向けた説明会を東京都内で開き、東日本の16の自治体が参加した。
28日は大阪で、29日には福岡で説明会を開催し、3都市で合わせて38自治体が参加する予定となっている。W杯の成否はなんといっても、開催地の盛り上がりである。ということは、会場選定がW杯成功のカギを握るといってもいい。
W杯の試合会場は10~12カ所を予定している。アジアで初開催となるW杯だから、国際ラグビーボード(IRB)の開催基準(ガイドライン)はある程度、緩和されるだろう。自治体は10月に発表される開催基準を踏まえ、来年10月までに申請書を提出することになる。開催地は2015年3月頃に決まることになっている。
説明会の後の記者会見で、IRBのキット・マコーネルW杯事業部長は「自治体の関心が大きい」と歓迎する。「日本でのW杯が成功すると信じている。W杯を契機に日本でラグビーが普及・発展して、さらにアジア全域でも広がっていくのが目標ではないか。W杯では、日本全国が盛り上がっていくようなカタチにしたい」
自治体の関心事はもちろん、何を基準に選定されるかということである。スタジアムの規模、施設、設備のほか、宿泊施設、交通アクセスなどの要素も加味されることになる。マコーネル事業部長によると、IRBのW杯基準ではスタジアムの観客席は最低1万5千人となっている。ただ問題はロッカー室やドーピング室、プレスルームなどの施設、とくに日本のスタジアムには比較的少ないホスピタリティールームをどう条件付けるのか、だ。
ホスピタリティールームとは、飲食もできるスポンサーやVIP向けの部屋をいう。従来のW杯では、スタジアムの外に仮設テントを設けるなどして対処したところもある。
「大会は6年後」と、マコーネル事業部長は言う。「テクノロジー、設備に関しては大きく変わっていくだろう。現存のスタジアムを活用しながらも、いかにハイレベルなものに持っていくかが大事です」
会見では、スポーツ紙の記者から「釜石の開催の可能性は?」というストレートな質問も飛び出した。同事業部長は苦笑しながら、「日本全土を巻き込みたい。まだ具体的な申請の段階には至っていない。日本協会、日本の組織委員会と一緒にディスカッションしていくことになる。特定の自治体との話に入っているわけではない」とかわした。
釜石は東北のラグビーのメッカであり、被災地の復興のシンボル的な街である。ただ現状でいえば、W杯会場になりうるスタジアムはまだ、ない。IRBではW杯開催の1年前までに完成すればいいことになっているが、まずは10月に出る開催基準に沿ったスタジアムを造る計画を作成しなければならない。要はその予算措置である。
会場選定で、大事なことは2つ、ある。1つは、開催都市の目的。マコーネル事業部長は期待する。「開催都市でもゴールを明確にしてほしい。W杯はビジネスのチャンスにもなるし、観光の活性化にもつながる。経済効果、環境改善、いろんなメリットにもなる」と。
もう1つが、W杯の認知を高め、ラグビーの普及・発展に役立てることである。いわば「W杯キャンペーン」の一環とし、ここでラグビーファンを拡大する。今のところ、W杯の開催地に興味を示す自治体は組織委からは非公開とされているが、選定レースをオープンにした方が盛り上がると思うのだが。