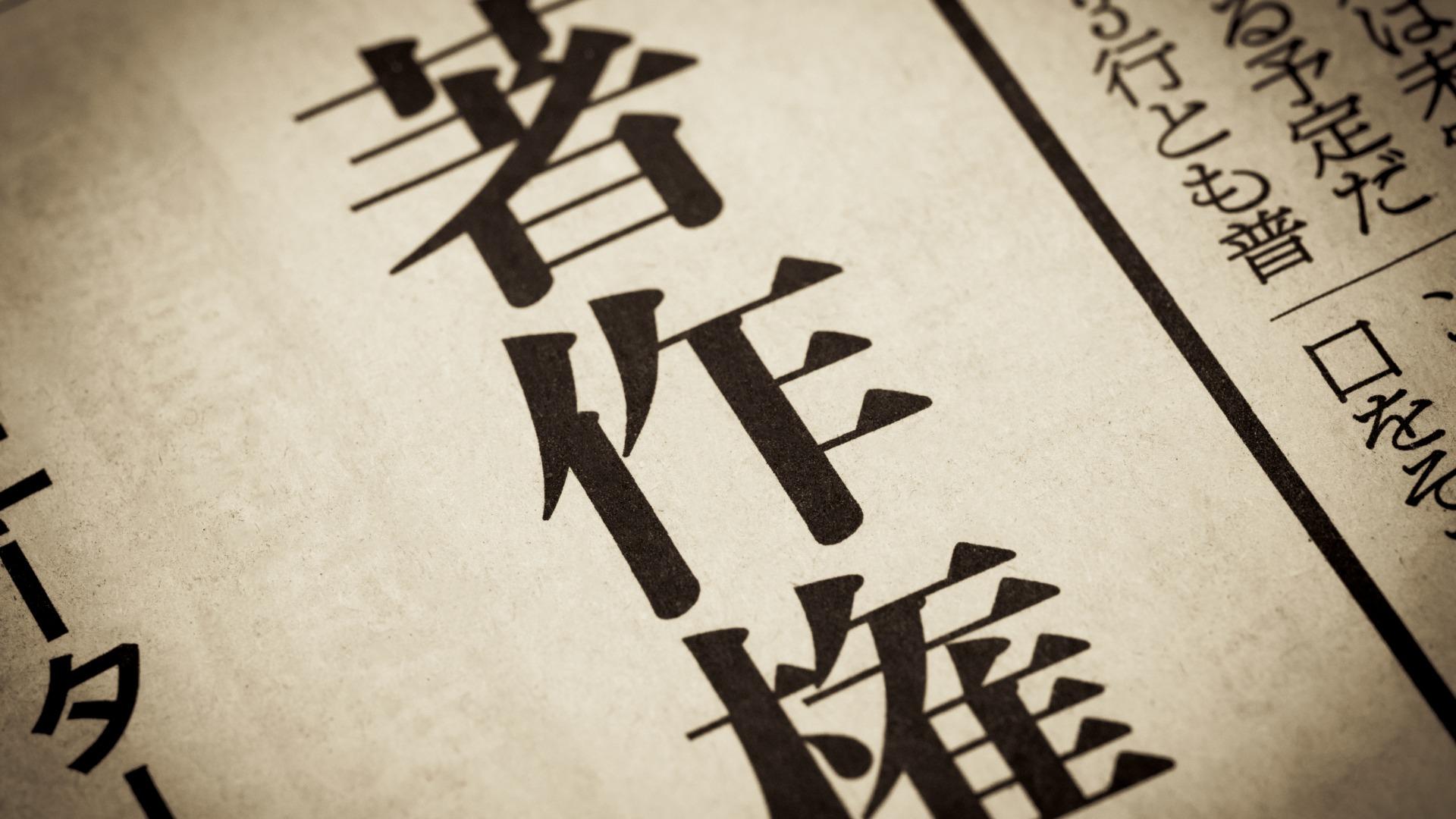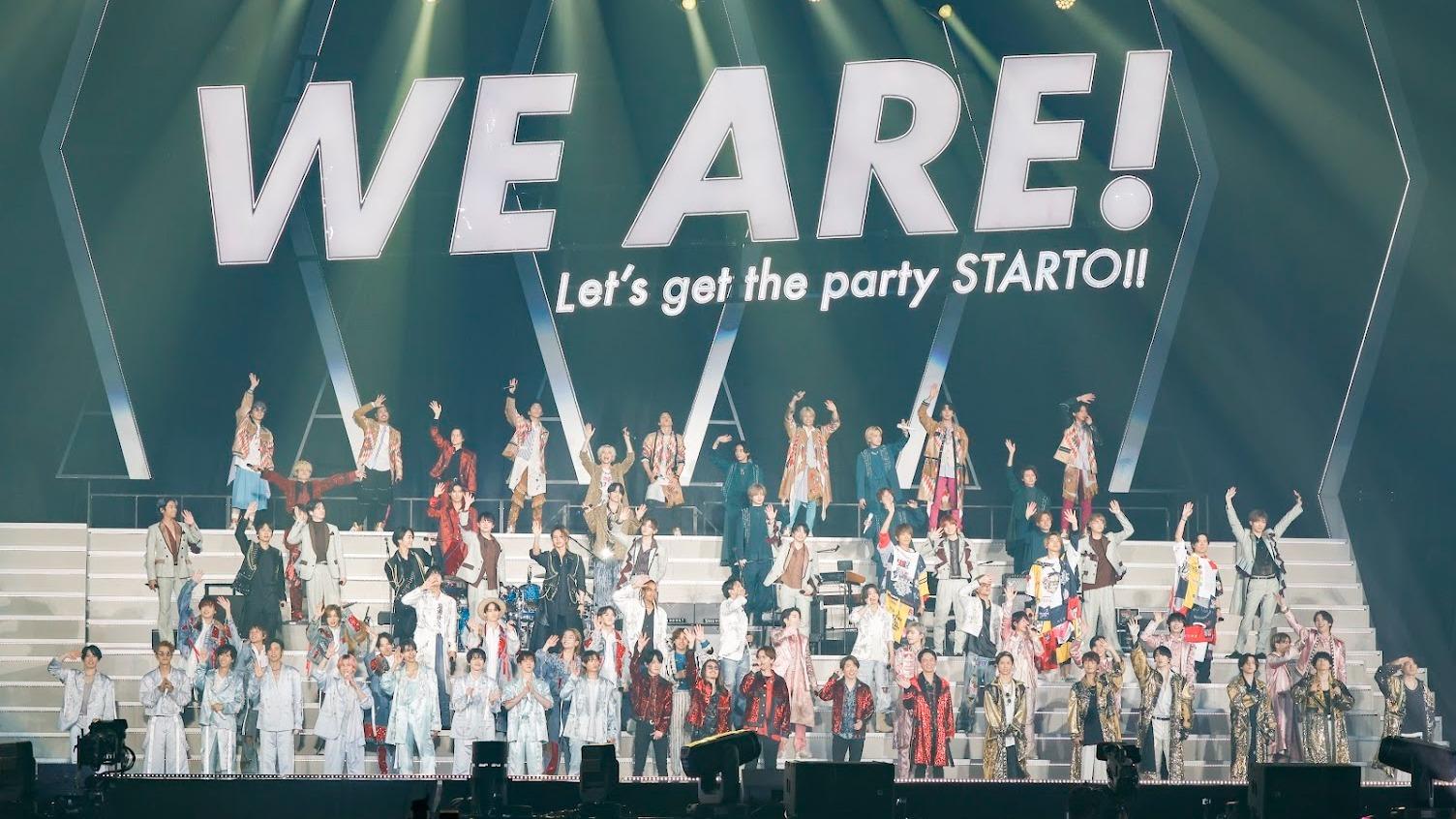今年度負けなしの横山泰明七段(39)王座戦で強敵・広瀬章人八段(33)を降してベスト8進出

5月26日。東京・将棋会館において第68期王座戦挑戦者決定トーナメント(本戦)1回戦▲横山泰明七段(39歳)-△広瀬章人八段(33歳)戦がおこなわれました。
10時に始まった対局は20時6分に終局。結果は88手で横山七段の勝ちとなり、ベスト8進出を決めました。
過去の両者の対戦
横山泰明(ひろあき)七段は1980年生まれ。2002年10月、21歳で四段に昇段しています。
広瀬章人八段は1987年生まれ。2005年4月、18歳で四段に昇段しています。
両者の初対戦は2005年度C級2組順位戦でした。

両者はともに四段。また両者ともに振り飛車党でした。この時は先手の横山四段が四間飛車に振っています。対して広瀬四段は居飛車穴熊に組みました。
中盤では広瀬四段が角銀交換の駒損ながら飛車を成り込んで優勢に。しかしそこから横山四段が粘り、形勢は巻き戻ります。
終盤はまた広瀬四段が突き放して勝勢に。しかし横山四段が不屈の粘りを見せ、勝敗不明となります。延々と続く攻防の中、いつしか手数は200手を超え、それでも決着がつかない。
横山四段の受けが実を結び、ついに勝ちになったかと思われたところで、痛恨の敗着が出ます。すぐに寄せに出れば横山勝ちのところ、一手受けに回ったため、速度が逆転。奨励会時から終盤力に定評のあった広瀬四段はそれを見逃さず、穴熊の遠さをいかして一手勝ちを収めました。
総手数は224手。有望な若手同士が力の限りを尽くして戦った名局でした。

その後、広瀬現八段は2期目でC級2組を通過。一方で横山現七段はC級2組を抜けるのに12期かかりました。
両者2度目の対戦は2009年の王位戦予選準決勝。両者はともに五段でした。
横山五段先手で、戦型は角換わり。横山五段が棒銀に出て先攻する形となりました。横山五段の技がきれいに決まって、中盤では優勢に。しかし横山五段に失着が出て、広瀬五段が逆転。終盤で広瀬五段は誤らず112手で押し切りました。
広瀬五段にとってこの逆転勝ちは大きかった。広瀬五段は予選を勝ち抜いて王位リーグに入ります。
2010年。広瀬五段は王位リーグで快進撃を見せました。挑戦者決定戦では第一人者の羽生善治名人にも勝ち、あれよという間に王位挑戦権を獲得します。
そして深浦康市王位に挑戦した七番勝負は4勝2敗2千日手で制して、23歳五段で初タイトルの王位を獲得しています。
横山七段、相掛かりで快勝
横山七段は二次予選で木村一基王位、飯塚祐紀七段を連破して本戦に勝ち上がってきました。
本局は広瀬八段、横山七段にとって3回目の対戦となります。
本年度はここまでコロナ禍の影響で、対局の進行がかなり遅れてきました。広瀬八段にとっては本局が本年度初の対局となります。
一方で横山七段は本年度5戦して全勝と好調です。
振り駒の結果、先手は横山七段に。戦型はともに飛車先の歩を伸ばして交換し合う、相掛かりとなりました。
かつてはともに振り飛車党だった両者も、キャリア途中でフォームチェンジをはかり、現在では居飛車で臨むことがほとんどです。
序盤、広瀬八段は飛車を一つ寄せて「縦歩取り」の姿勢を見せます。「縦歩取り」と言っても、実際に歩を取れるかどうかはわかりません。横山七段は金を一つ上がって縦歩取りを受けます。
広瀬八段が飛車を元の位置に戻す。横山七段が金を引く。広瀬八段が飛車を寄る。横山七段が金を上がる。
両者が同じ手順を繰り返して、局面は千日手模様となりました。もし千日手が成立すれば、先後を入れ替えて指し直しとなります。公式戦の統計では先手の勝率がわずかによく、もし指し直しとなれば、後手番の側が上手くやったということになります。
同一局面が4回生じて千日手が成立する少し前。先手番の横山七段は角を交換して手を変えました。
横山七段はあえて相手に縦歩取りを実現させ、歩損はするものの、代わりに相手陣左隅に生じたスキに角を打ち込み、馬を作る順を選びます。
広瀬八段は横山七段の馬を封じ込める作戦です。相掛かりではしばしば生じる攻防で、この馬を使うことができるかが勝負の大きなポイントとなります。
広瀬八段は馬を封じ込めている側とは逆サイド、右辺で積極的に動きます。対して横山七段は広瀬八段の揺さぶりに冷静に対応。ポイントを重ねて優位に立ちました。
終盤力に定評のある広瀬八段も、逆転を狙うには差がつきすぎてしまったようです。最後は横山七段が桂で歩を取った手が攻防の決め手となり、広瀬八段が投了しました。
桜井門下2人が勝ち上がる
横山七段はこれで今年度6戦全勝。成績部門で全棋士中のトップに立っています。
トーナメント表を見ると、横山七段のすぐ隣りの山は、まだ二次予選決勝・藤井聡太七段-大橋貴洸六段戦の結果が確定していません。ほどなくそちらの対局もおこなわれることになるでしょう。その勝者は斎藤慎太郎八段(前王座)と対戦します。
横山七段の師匠は桜井昇八段(79歳)です。同門で1歳上の飯島栄治七段(40)は先日、王座通算24期のレジェンド・羽生善治九段(49歳)に勝ちました。
もし飯島七段、横山七段ともに準々決勝で勝てば、準決勝で両者は対戦することになります。
昨年度のB級2組順位戦には飯島七段、横山七段の他に中田宏樹八段、村山慈明七段と、25人中4人が桜井門下でした。
横山七段は2年連続7勝3敗。そして2年連続次点で昇級を逃しています。
また飯島七段は4勝6敗と例年ではセーフと思われる成績で降級点がついてしまい、無念の降級となりました。
昨年度B級2組で苦い思いをした桜井門下の2人が奮起して、今期王座戦本戦では強敵を破って勝ち上がっている。そんな見方もできそうです。
王座戦は1983年度からタイトル戦に昇格しました。
その少し前の1981年度。桜井八段(当時六段)は王座戦で活躍しています。

桜井六段は二次予選では二上達也棋聖(81年度最優秀棋士)に勝って本戦進出。1回戦で加藤一二三九段(81年度十段位獲得、翌82年度名人位獲得)、2回戦で桐山清澄八段(81年度名人挑戦)を連破してベスト4に進出するという快進撃を見せました。
今期王座戦で飯島七段、横山七段がかつての師匠の成績を上回れば、それもまた恩返しと言えるのかもしれません。