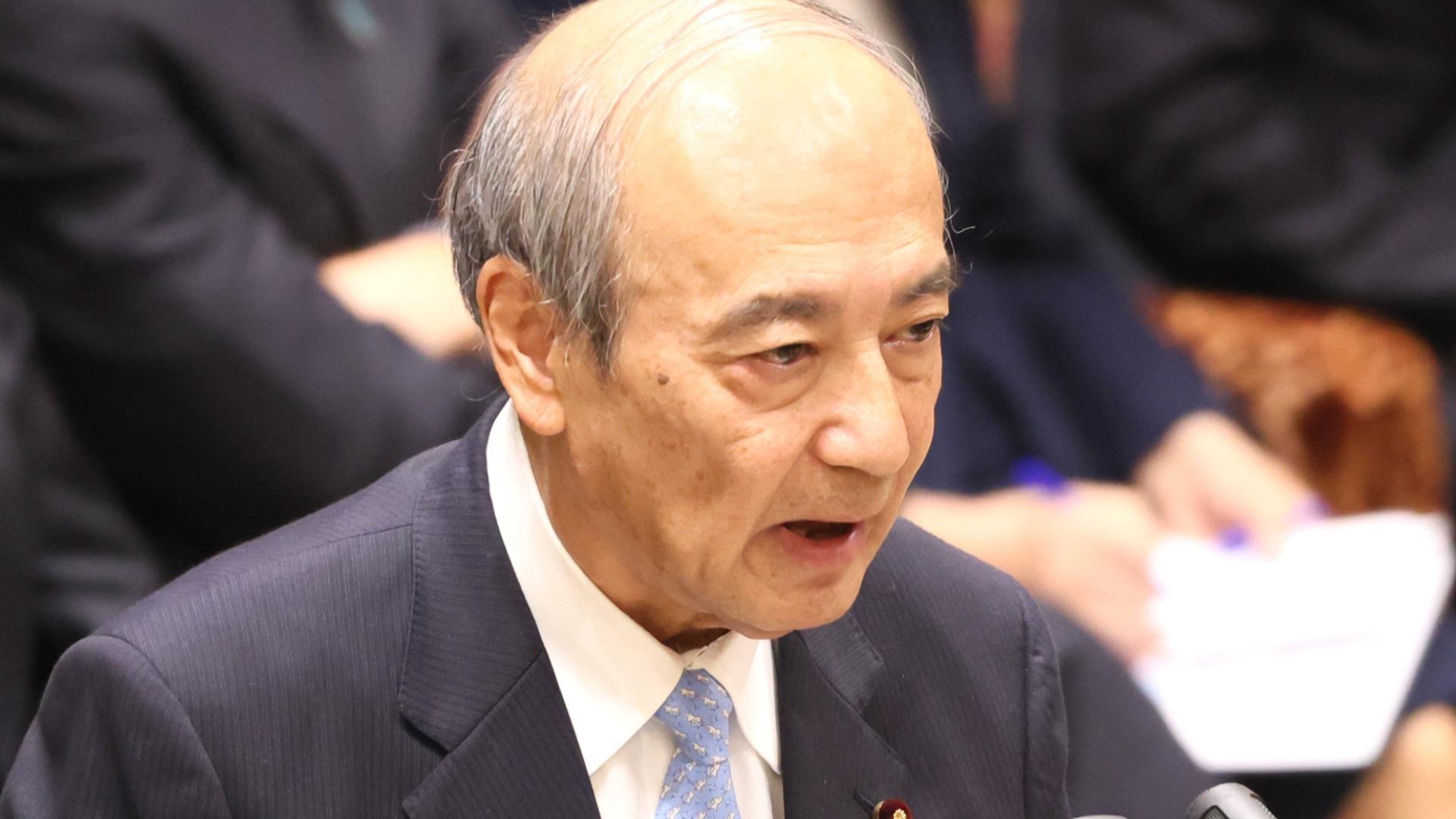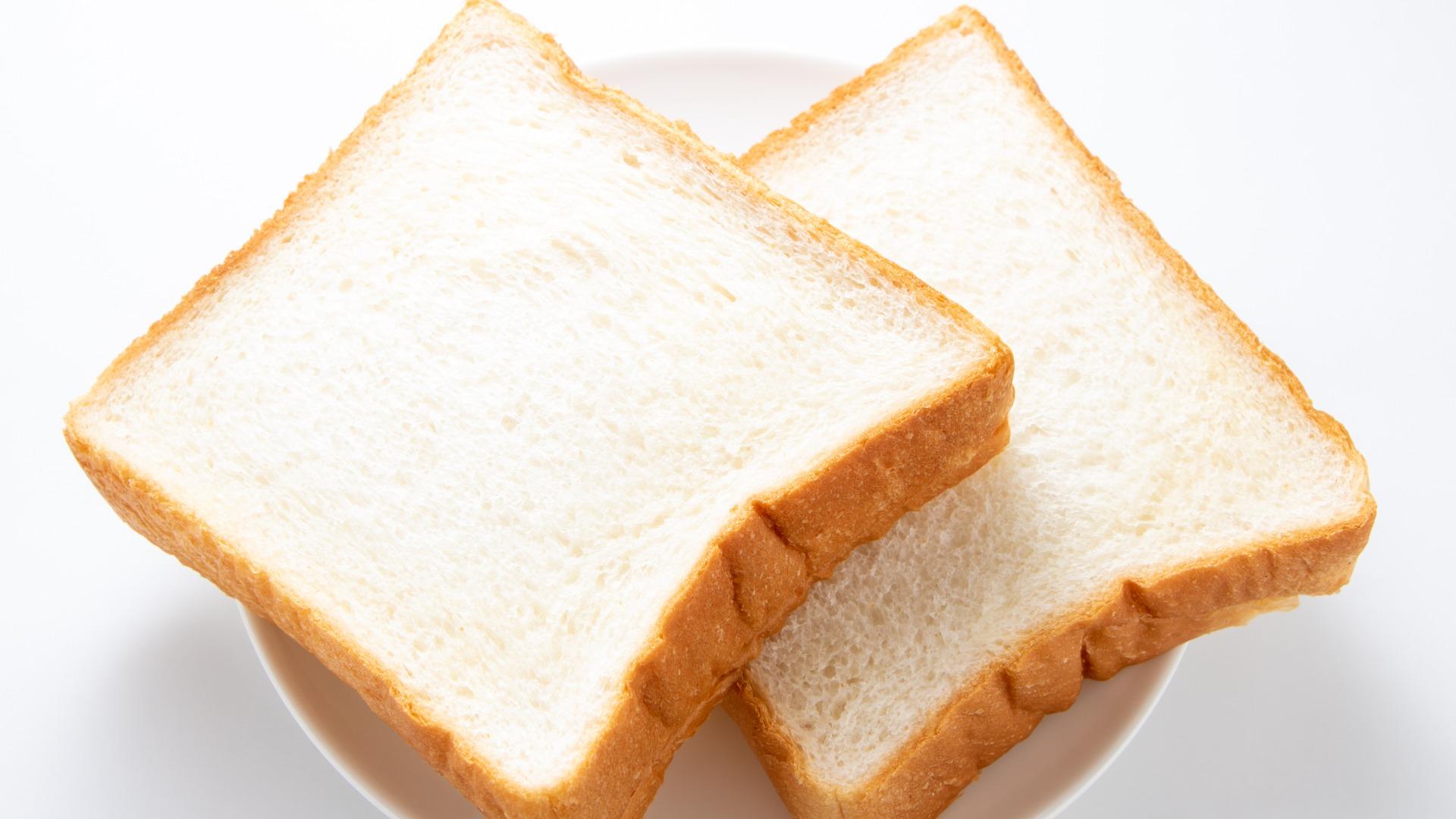日本型デフレを回避せよ 欧州中銀、量的緩和へいよいよ正念場
スーパー・マリオの胸の内
「スーパー・マリオ」の異名を取る欧州中央銀行(ECB)のマリオ・ドラギ総裁が2日付ドイツ経済紙ハンデルスブラットのインタビューに量的緩和(QE)への意欲を強くにじませた。
「6カ月前に比べ物価安定という目標に到達しないリスクが高まっている。低インフレが長引き、それに対処する必要があるなら、金融政策のサイズ、スピード、中身を調整する技術的な用意はある」
ドラギ総裁は昨年4月から選択肢の一つとしてQEを俎上に乗せてきた。
「やるべきことをやる」と11月の講演で追加緩和への決意を示したのに続き、12月のECB定例理事会ではQEを実施するかどうか判断するタイミングについて「来年初め」と明言した。
域内のデフレがもはや否定できないほど目の前に迫ってきたためだ。
欧州単一通貨ユーロ圏(19カ国)のインフレ率は目標の2%を大幅に下回り、たった0.3%。ギリシャ、スペインの物価指数はすでにマイナスで、デフレの初期段階と言ってもおかしくない。
ポーランド、ハンガリー、ブルガリアといった他のEU(欧州連合)加盟国にもデフレの暗雲は漂い始めている。
タカ派(金融引き締め派)で、財政赤字を中央銀行が肩代わりすることになる量的緩和、つまり景気刺激策としての国債購入に拒絶反応を示すドイツ連邦銀行(ドイツ中銀)のワイトマン総裁が欧州「北部」の中銀総裁と肩を組んで「反対、反対」と叫んでも、ユーロ圏全体に目配せするドラギ総裁は前に進むしかない。
デフレか、禁じ手QEか
日本が1990年代の金融バブル崩壊後、長期のデフレに陥り、今なおデフレ脱却に七転八倒している。ここは日本銀行、米連邦準備理事会(FRB)、英イングランド銀行のQEを見習う以外に道はない――。
米MIT(マサチューセッツ工科大学)でノーベル経済学賞受賞者モジリアニの指導を受け、イタリア人では初めてMITの博士号を取得したドラギ総裁はそう考えているに違いない。
これに対して、ハイパーインフレや中銀の国債購入で2度にわたる通貨崩壊を経験したドイツにとって、金融危機回避という緊急避難のための国債購入には目をつぶれても、景気刺激策としてのQEを許容するわけにはいかない。
「借金は罪」「強い通貨こそが強い経済をつくる」のであって、日米英型のQEは政府や経済をスポイルするだけだという信仰がドイツにはある。ドイツ連銀内では「中銀による国債購入は最初は上手く行っても、いずれコントロールできなくなる」といわれている。
ドラギ総裁とワイトマン総裁の対立は、量的緩和からうまく抜け出すことができた米国と、量的緩和から侵略、戦争、崩壊という破滅の道をたどったドイツの歴史的経験の違いに由来している。
2011年の3年物資金供給策でECBのバランスシートは一時3兆ユーロを超える水準にまで拡大。12年には、ドラギ総裁が「やれることは何でもする」と宣言、金融危機対策として1~3年物国債の無制限購入を表明し、ユーロ危機を封じ込めた。
ヘッジファンドが国債を大量に購入、ECBは国債を購入せずに済んだため、「ドラギ・マジック」と称賛された。
「北部」の銀行が早期返済を進め、ECBのバランスシートは2兆ユーロ程度まで縮小。「貸し剥がし」が広がり、欧州の景気を腰折れさせてしまった。ドラギ総裁はデフレ回避のため、何が何でもECBのバランスシートを3兆ユーロにまで戻す考えなのだ。
追い詰められたECB
ECBも手をこまぬいてきたわけではない。
14年6月
政策金利を0.25%から0.15%に引き下げ
銀行がECBに余剰資金を預け入れた場合に手数料を課す「マイナス金利」(マイナス0.1%)を導入
9月
政策金利を0.15%から0.05%に引き下げ
「マイナス金利」をマイナス0.2%に引き下げ
10月からABS(資産担保証券)とカバードボンド(担保付債券)の買入れ開始
9月からECBは、固定金利0.15%で資金を4年間供給するプログラムを開始したが、英誌エコノミストによると、4千億ユーロの貸し出し枠があるのに銀行は9月と12月、2120億ユーロしか借りなかった。
バランスシートを1兆ユーロ増やそうと思えば、これまで禁じてきた国債購入に踏み切るしかない。昨年第3四半期で銀行が保有する国債は6.6兆ユーロもある。1兆ユーロぐらい、余裕で購入できるというのがドラギ総裁の算段だ。
エコノミスト誌は量的緩和は早くて1月、3月にずれ込む可能性があり、購入枠は最大でも5千億ユーロ止まりになりそうだと予測している。量的緩和の効果と言えば、また別の問題になってくる。
ユーロ圏はリトアニアの加入で19カ国。19カ国にそれぞれの国債があり、償還年限や利払い方式にも違いがある。ギリシャの国債を購入するのか、それともドイツ国債か。短期国債か、それとも長期国債か。1月22日に開かれるECB定例理事会が紛糾するのは必至だ。
3日後の25日にはギリシャ総選挙が控えている。過半数にわずかに届かないものの、緊縮策の撤回を求める左派政党連合、急進左派連合(SYRIZA)が第1党になる見通しだ。ドイツなど欧州「北部」が量的緩和や緊縮策の転換に反対すれば、ギリシャの国内世論は先鋭化する。
14日には欧州司法裁判所(ECJ)が、ドラギ総裁が12年に主導した国債の無制限購入について正当か否かの判断を下す。
ギリシャの10年物国債の金利はすでに9%の大台に乗っている。欧州司法裁判所の判決、ECB定例理事会、ギリシャ総選挙の結果次第で高騰する恐れが膨らむ。欧州からしばらく目が離せそうにない。
(おわり)