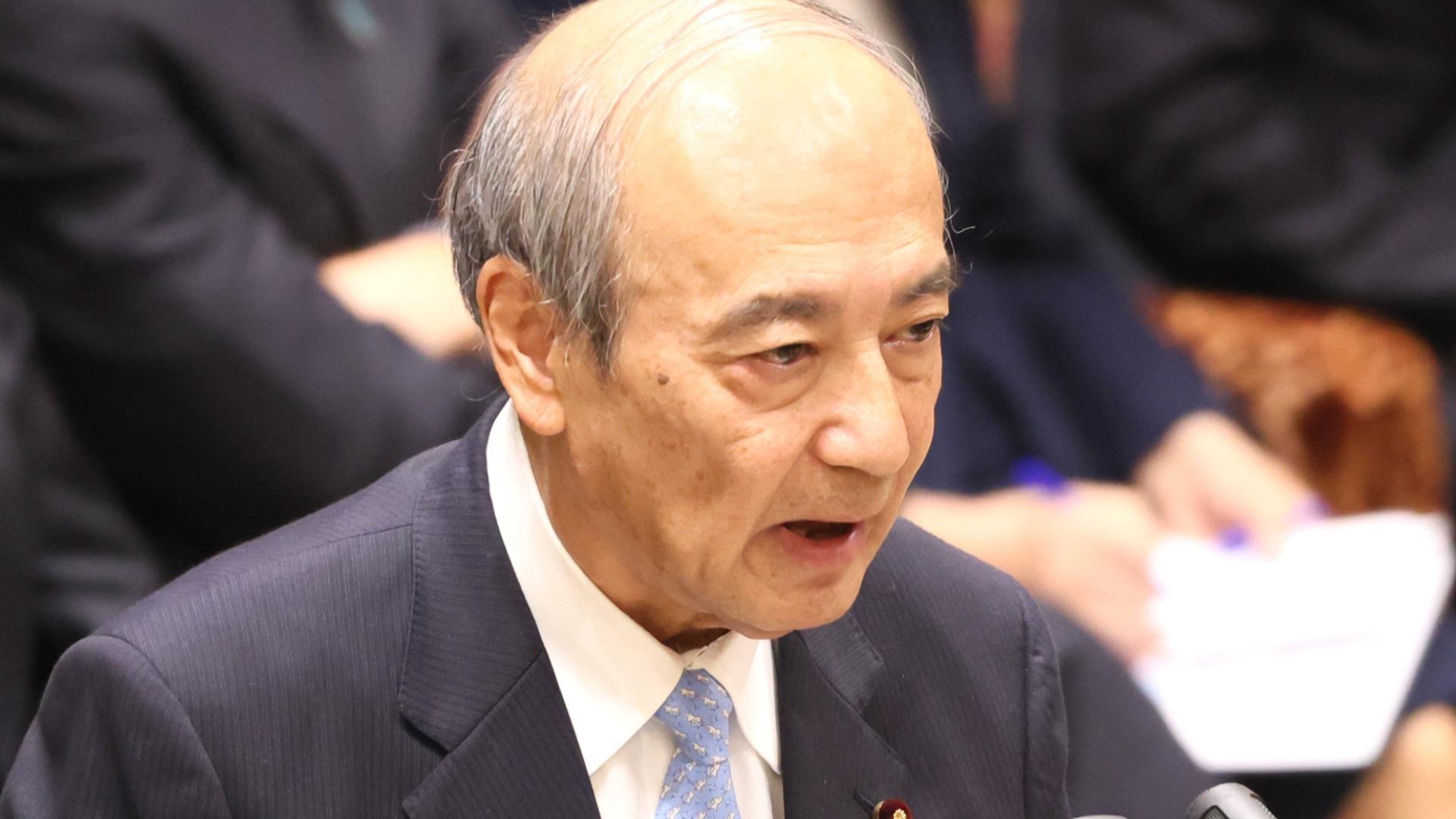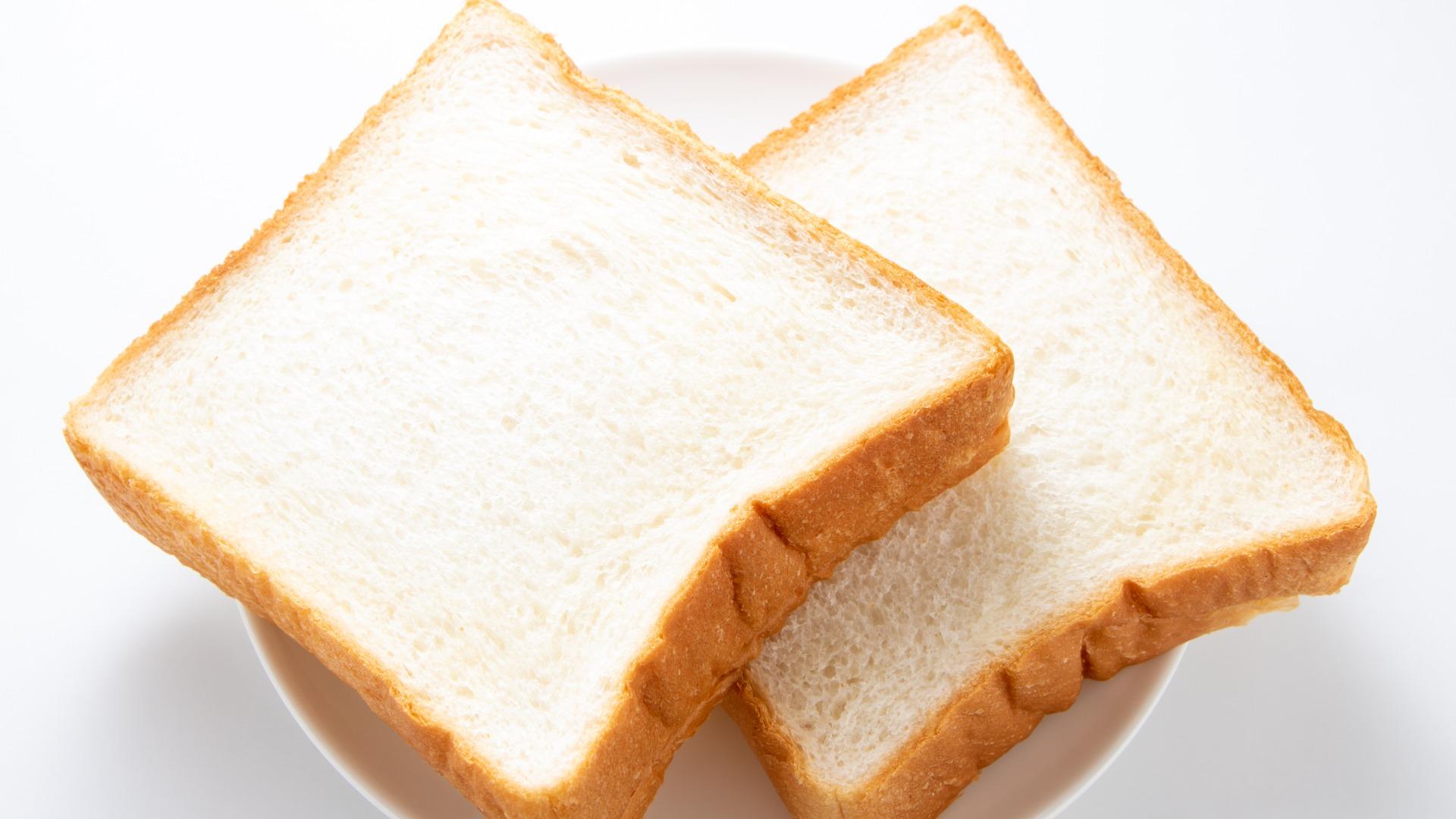「うちの子の写真はもう増えないんですね……」 ペットの死と供養の最新事情とは?

「うちの子の写真はもう増えないんですね……」というメールが、以前がん治療をしていた飼い主から届きました。SNSが盛んないまは、ペットたちは、フォトジェニックな存在。毎日、彼らはたくさん写真を撮られています。愛犬、愛猫が亡くなったと実感をするのは、この時代、写真が増えないことかもしれません。現代のペット供養を見ていきましょう。
人間界では「仏壇離れて」「仏壇ジマイ」
人間界では、この数十年の間に仏壇離れが進み「仏壇ジマイ」なる新語も登場しているそうです。「手土産を仏壇にお供えする行為はマナー違反?」などの記事がネットで話題になりました。その反面、ペットたちは、手厚く供養してもらい仏壇ではなく、祭壇を作ってもらっている子は多くいます。
なぜ、ペットの祭壇が増えるのか
・ペットの寿命が延びたら
いまや犬や猫は、家族の一員。寿命が延びて、室内飼いの子が多くなったので、より絆が深くなったのが理由です。「写真が増えない」とメールをくれた飼い主は、中型犬のがん治療を2年間にわたり手厚くされ、もうじき17歳というところで見送っています。最後の1年は、仕事も辞めて、24時間、愛犬と一緒にいました。いままで、手間も時間も共有している犬や猫を亡くしたからといって、すぐに忘れさることができません。人間の子どもで考えると高校2年生になるまで育てた子を思い出さないわけはないですね。
・飼い主と一緒にペットはお墓に入れないから
亡骸を荼毘に付すと、遺骨が残ります。もちろんペット霊園などもあるのですが、倒産などがニュースになるケースもあります。市営の斎場の慰霊碑に手を合わせていたのに、なんとそこに遺骨が納められていなかったことも問題になっています。それで、遺骨を自宅に持ち帰っています。人間だと同じお墓に入れるのですが、多くのお墓は、人間だけでペットはNGのところが多いのが現実です。「うちの子が亡くなりました。あの世で再会したいので、一族の墓に納骨してもらえないでしょうか」が叶えられない。それで、祭壇を設けているのです。
(最近になり、ペットと一緒に入れるお墓も出きましたがまだまだ少数です。ペットを先にお墓に入れるために、飼い主がそのようなお墓を購入というケースもあります。)
ペットたちの供養の現実
愛犬、愛猫が亡くなり、荼毘に付した骨を自宅に持ち帰るケースが増えています。以下のようにされています。
・お手元供養
仏壇ではないですが、リビングルームなどの家族がいつもいるところに、写真とお花をお供えして、遺骨を供養しています。
そのような用品もいまの時代に合うようにたくさん売っています。人間の仏壇は、あまり人が行かない暗い部屋にあるイメージですが、ペットの場合は、明るいところにあることが多いです。

↑冬の時期なので、寒くないように、マフラーなどもありますね。この子が好きだった果物がお供えされています。

↑丸いフォームほっこりする。お手元供養用
飼い主がペットの供養をすることのメリット
亡くなった子に、このように供養をすることは、飼い主にどんな恩恵があるのでしょうか。
・ペットロスの軽減
十数年間、文字通り苦楽を共にしたペットたち、飼い主にとっては何事にも替え難い存在です。そんな子たちが、目の前からいなくなると、喪失感にさいなまれる人は多くいます。帰宅して、いつもポチが迎えに来てくれたのに、それがない現実を知ったときに、亡くなったことを改めて思い知るのです。供養をちゃんとすることで、ペットロスが軽減されるといわれています。
・精神の拠り所がある
家の中に、手を合わせる場所が祭壇になります。帰宅して「ただいま、ポチ」といえるところがあるだけで、心の拠り所になります。そして落ち着けるのです。


↑上記とは、マグネットでつながっていて、それを外すと遺骨入れが現れます。
まとめ
手土産を仏壇に置くことは、マナー違反ではないか?とネットで話題になりました。
ペットの場合は、がん治療をしていたご家庭にお菓子を送ったとき、飼い主から「うちの子の前にお供えしています」というメールが届きました。
日本人の仏壇離れが背景にあるかもしれません。一方、長年一緒に暮らしてきた亡きペットにお菓子をいただいたことを報告して「供物のお下がりをいただく」という考え方は、ペットを飼っていた人たちの間では、ごく自然なことになっています。こころの絆として、飼い主が辛いときでも傍らにいてくれたペットたち、今日の出来事を話すことで、飼い主は、ずいぶんと落ち着くものです。
そんなことから、室内飼いになり長寿になった彼らは、明るい場所に供えられて、そこには新鮮な花と彼らが好きだったトリーツ(特別なご褒美)がある風景がペットの世界では広がっています。