ボカロ小説の第二の波 ヨルシカ、YOASOBI、カンザキイオリ
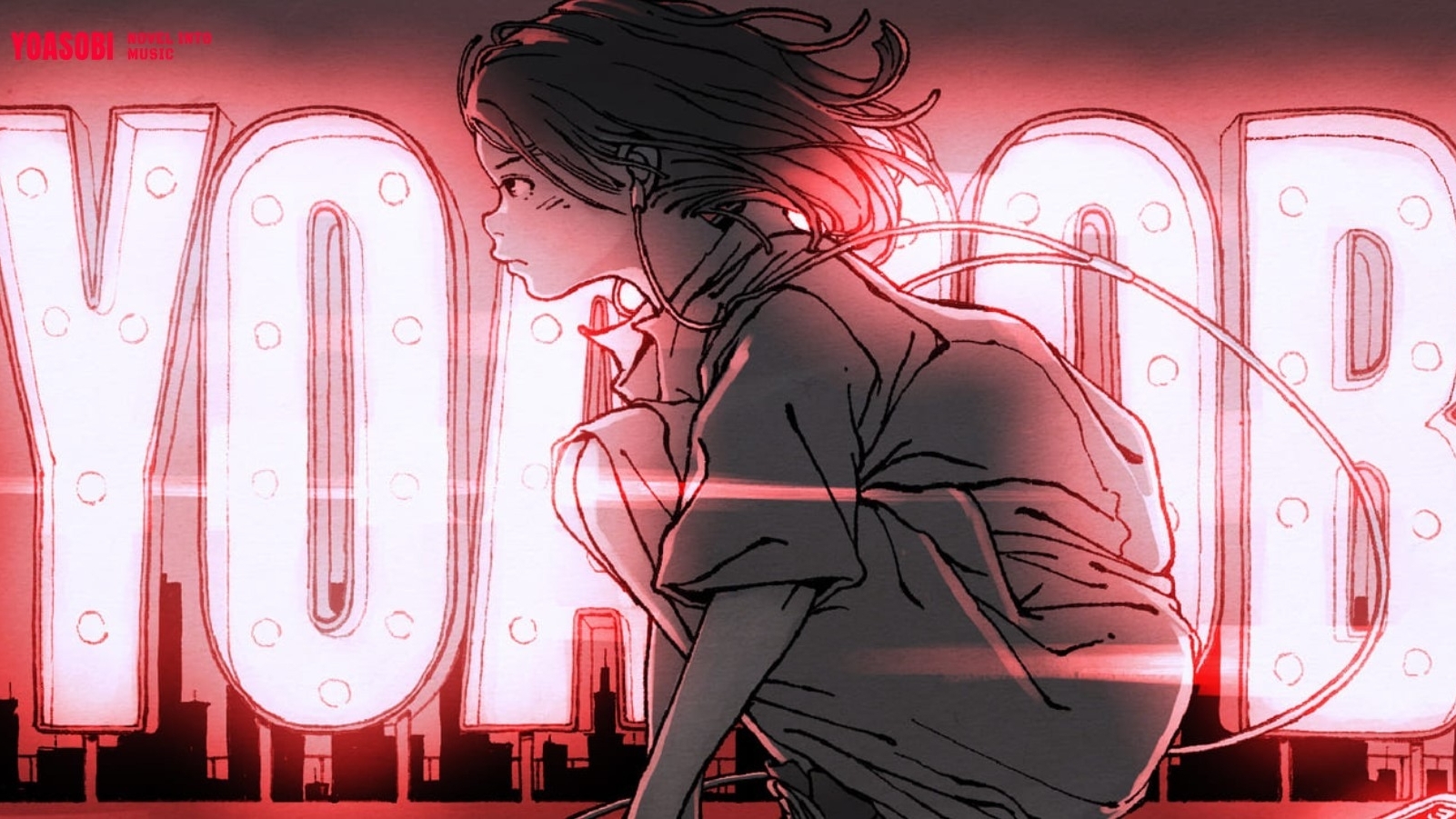
2010年代前半にブームとなった「ボカロ小説」が2020年になって再び注目を集めている――ただしかつてとはやや違うかたちで。
■そもそもボカロ小説とは?
ボカロ小説とは、基本的には「ヤマハが開発した合成音声ソフト・ボーカロイド(代表的なものは初音ミク、鏡音リン・レンなど)を用いてつくられた楽曲を原作とする小説」のことだ。
事実上の嚆矢は2010年に刊行された悪ノP(mothy)による『悪ノ娘 黄のクロアテュール』(PHP研究所)。
ボーカロイドを使った曲自体は、初音ミクが2007年に発売されると、前年にサービスが開始してネット民を惹きつけていた動画投稿サイト「ニコニコ動画」でブームとなり、2020年現在に至るまで、ボカロ文化は数々の名曲と数多のクリエイターを輩出している。
その盛り上がりのなかで、物語性の高い楽曲が投稿され始める。初期の注目作が2008年4月に投稿された悪ノP「悪ノ娘」「悪ノ召使」だった。
悪ノPの「P」とは「プロデューサー」の意だ。ただし音楽プロデューサーではなく、作曲者を意味する。これはもともとニコ動上で、プロデューサーになってアイドルを育成するゲーム『THE IDOLM@STER』の動画が人気となり、その投稿者を「○○P」と呼称したことがボーカロイド楽曲・動画に転じて、ボカロ曲の作曲者・投稿者をやはり「○○P」と呼ぶことになった(当初は動画サイトのユーザーによるコメントなどから「○○P」と「他称」されるケースが多く、わざわざ「○○P」と自称する投稿者は決して多くなかったことから、「○○P」という呼び方自体が徐々に廃れていった)。
ストーリー性のあるボカロ楽曲は、動画サイト上での人気に留まらず、二次展開され始める。たとえば2007年にhukeが描いたイラストを元にsuperellのryoが2008年6月に発表した楽曲「ブラック★ロックシューター」((BRS)は早くも2009年にOVA(オリジナルビデオアニメ。テレビ放送や配信を前提としない、有料でパッケージ販売されるアニメ)化され、2012年にはTVアニメ化もされた。
そして10年8月に『悪ノ娘』が初の本格的なストーリー性をもったボカロ小説として刊行されるとヒットし、シリーズ化されて累計発行部数は100万部を超えた。PHP研究所は猫ロ眠@囚人P『囚人と紙飛行機』やhalyosyによる卒業ソングを小説化した『桜ノ雨』などを次々に成功させ、KADOKAWAや一迅社も追随してボカロ小説刊行ラッシュが2012年頃から起こる。
■ボーカロイドキャラクターの二次創作から、Pオリジナルキャラの小説へ
なかでももっとも商業的に成功を収めたのが、じん(自然の敵P)が2011年から展開するカゲロウプロジェクト(カゲプロ)の小説版『カゲロウデイズ』(KADOKAWA、KCG文庫。2012年より刊行)である。
カゲプロは、『悪ノ娘』的な「ボーカロイドキャラクターの二次創作」から「ボーカロイドを使った楽曲ではあるが、P(プロデューサーオリジナルキャラクターのノベライズ」へとボカロ小説の流行をシフトさせた作品でもあった。
『悪ノ娘』『囚人と紙飛行機』『桜ノ雨』はいずれもミクやリン・レンなどボーカロイドキャラクターがモデルの人物が登場する楽曲であり、小説版にはミクやリン・レンの版権元(ボーカロイドの発売元)であるクリプトン・フューチャーメディアとボーカロイドの開発元であるヤマハのマルシー(著作権表記)が入っている。ボカロキャラを原案として商業出版が許諾された二次創作である、というスタンスだった。
ところがカゲプロに登場するキャラクターは――緑色の長髪少女エネはどう見ても初音ミクがモデルではあるものの――じんのオリジナルキャラクターである、という立場で曲も小説も作られている。
これはリスナー・読者からすると、原案であるミクやリン・レンの雰囲気を踏襲していないわかりづらさは生じるものの、P側、出版社側がIP展開が圧倒的にコントーラブルになるという利点があった。
ミクやリン・レンなどの二次創作であるかぎり、楽曲を原作に小説化、マンガ化、映像化するにあたっては、すべてクリプトンにおうかがいを立てなければならない。ボーカロイドキャラクターの権利は当然、その発売元にあり、許諾を得ないで勝手に運用・利用することはできないからだ。
クリプトンは当時から現在に至るまで、ボーカロイドキャラクターが登場する作品の映像化を(「マジカルミライ」などのボカロが登場する公式のライブイベントの映像を除けば)許諾していない。
「ブラック★ロックシューター」のアニメ化は、huke・クリプトンがともに「BRSはミクではない」という共通認識に立っていたから可能だった(デザイン的には誰が見てもわかるレベルで似ていたこともあって発表当初は“誤認”され、問題となったためにのちに公式声明が出された)。
また『桜ノ雨』は実写映画化されているが、これはボカロキャラの二次創作ではないように登場人物の設定を変えたことで実現している。
そうした例外を除けば、ボカロ曲を代表すると言っていい「千本桜」ですら、小説版は刊行され、少なくないファンがアニメ化を待望したが、映像化は実現していない。
しかしカゲプロのように「ボカロを使った曲ではあるが、登場するのはPオリジナルキャラ」という体裁にすれば、Pが自由に、映像化をはじめととする二次展開の権利のコントロールができる。小説版を原作にして映像にするのであれば、原作者の委任を受けた出版社が主導して映像化に動くことができる。
したがって、ビジネス的にプロジェクトの大規模化が見込める作品であれば、「Pオリジナルキャラ」のほうが望ましい。
そしてカゲプロの音楽展開はソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)からなされた。
SMEは子会社にアニメーションの企画・製作を手がける――今となっては『FGO』(Fate/Grand Order)の会社というイメージのほうが強いだろうが――アニプレックスを抱えており、アニメと音楽(アニソン、劇判)の連動に長けていた。
こうしてニコ動で爆発的な人気を得ていたカゲプロは、小説、マンガを仕切るKADOKAWA、音楽、アニメを仕切るSMEによる一大プロジェクトとして展開された。
ところが、2014年4月から放映されたカゲプロのTVアニメ『メカクシティアクターズ』は、『化物語』や『魔法少女まどか☆マギカ』の大ヒットで名高いアニメーション制作会社シャフトが手がけたにもかかわらず、アニメファンから酷評される低クオリティな出来であり、盛り上がりに水を差した。
その後もPオリジナルキャラを使ったボカロ小説としてLastNote.『ミカグラ学園組曲』(2013年よりMF文庫Jから刊行)が15年4月にTVアニメ化、れるりり『脳漿炸裂ガール』(13年より角川ビーンズ文庫あら刊行)が15年7月に実写映画化されるもいずれもヒットに至らなかったことで「ボカロの映像化は売れない」という印象を出版・映像関係者に与え、期待が終息していく。
並行して、PCによる視聴が中心だった時代には圧倒的な影響力をもっていたニコ動が、2010年代に起こったスマホシフトへの対応に出遅れ影響力を失ったことで、ボカロ文化の勢いも落ち着き、小説も売れ行き不振となっていき、第一次ボカロ小説ブームは終わった。
2020年現在もシリーズが続き、小説でも人気を維持しているのは『告白予行練習』を代表とするHoneyWorks(ハニワ)作品くらいしかない。
■2020年から第二次ボカロ小説ブームは始まるか? ヨルシカ、YOASOBI、カンザキイオリ
そこから約5年を経て2020年、ヨルシカ『盗作』(ユニバーサルJ)、YOASOBI『夜に駆ける』(双葉社)、カンザキイオリ『あの夏が飽和する。』(河出書房新社)と、再びランキング上を賑わせるボカロ小説が登場した。
これから第二次「ブーム」と呼べるまでに後続が登場するかはまだわからないが、規模はともあれ第二の波が始まったとみなすこととしよう。
ただし、第二波の実質は第一波の『悪ノ娘』ともカゲプロとも違う。ポイントは三つある。
第一に、ありようとして「ボカロ小説」というより「ボカロP小説」になっている。
より正確に言えば「ボカロPとして活動している(活動経験のある)ミュージシャンが関わる、楽曲と小説が連動したプロジェクト」になっている。
ヨルシカはボカロPとして活動していたn-bunaがボーカリストsuisと組んで2017年に結成したバンドであり、ヨルシカ楽曲にはボーカロイドは使われていない。なお、『盗作』は2020年7月に発売されたヨルシカのメジャー3rdアルバムのタイトルであり、n-bunaが書いた同名の中編小説は、初回限定盤で読めるが、書籍として一般流通しているわけではない(2020年10月時点。奥付のクレジットを見ると早川書房の編集者の名前があり、今後、同社から書籍化される可能性がないとは言えない)。
YOASOBIは、ボカロPのAyaseとシンガーソングライターのikura(幾田りら)による音楽ユニットであり、楽曲の元になった短編小説集が20年9月に刊行された。ヨルシカは、ソニーミュージック――そう、カゲプロにも関わったあの――が運営する小説投稿サイトmonogataryに投稿された小説をもとにAyaseが楽曲をつくり、ikuraが歌うというプロジェクトだ。ヨルシカではやはりボーカロイドは用いていない。
カンザキイオリは2014年からボカロPとして活動をはじめ、20年2月に発表した(私家版の)長編小説『獣』を改稿した『あの夏が飽和する。』を同年9月に刊行。カンザキはボカロPとして活動し、その楽曲を元に小説化したから、ヨルシカやYOASOBIとは違う。しかし、以下で述べる理由もあいまって、カンザキ作品もボカロ小説というよりボカロP小説と呼んだ方が適切なように映る。
第二に、内容が「キャラクター小説」から「一般文芸」的なものに変わっている。
第一次ボカロ小説ブームから生まれた人気作品は基本的にボーカロイドキャラクターの二次創作にしろ、Pオリジナルキャラの小説にしろ、「キャラクター小説」だった。それらはいずれも、大塚英志言うところの「まんが・アニメ的リアリズム」に基づいて創作され――現実の人間を写生したかのような「自然主義的リアリズム」に基づく“人物”ではなく、誇張された感情表現や振る舞い、口調を特徴とする“キャラクター”を軸に読まれる――、キャラクタービジネスを展開できることが視野に入れられた作品群だった。
ところが『盗作』『夜を駆ける』『あの夏が飽和する。』はいずれもキャラクター小説ではない。『盗作』の登場人物は「泥棒」「少年」といった役回りはあるが名前すら出てこない。『夜を駆ける』所収の小説は、死神のような存在や予知夢といった超自然現象は出てくるが、キャラクター小説というより、『五分後に意外な結末』などのYA(ヤングアダルト)向けの短編小説のようなタッチで書かれている。『あの夏が飽和する。』は現代日本を舞台に家庭内不和が原因で起こる高校生の出会い系利用や殺人などを描いた作品で、登場人物たちはキャラクター然としておらず、一般文芸的な内容だ。
そしていずれも、装丁はいわゆるライトノベル風のキャラクターイラストを表紙にしたものではない。
もともとの楽曲を聴いても、「青春の全部に君がいる/風が吹けば花が咲く」(ヨルシカ「爆弾魔」)、「僕の目に映る君は綺麗だ/明けない夜に溢れた涙も/君の笑顔に溶けていく」(YOASOBI「夜を駆ける」)、「あてもなく彷徨う/蝉の群れに/水もなくなり/揺れ出す視界に」(カンザキイオリ「あの夏が飽和する」)など、いずれの曲でも視覚的な表現や情景描写(を通じての感情表現)は鮮烈だが、キャラクター性の表現に力は注がれていない。たとえば第一波の作品で言えば『ミカグラ』と比べてもらえば一目瞭然だ。『ミカグラ』では楽曲のMVや小説では、キャラクターのかわいさの表現に心血が注がれていた。それが第二波作品では、キャラクターから情景に焦点が移っている。
そして第三に、キャラクターメインの作品でなくなったことによって「キャラクター語り」よりも「クリエイター語り」がされやすくなっている。
『悪ノ娘』、カゲプロ、『ミカグラ』、ハニワ作品はクリエイター(P、作家)側について語られるよりもはるかに多く、登場キャラクターについての語りが流通した。ともすれば楽曲(音楽)に関する感想以上に、だ。
だがヨルシカ、YOASOBI、カンザキイオリについては、楽曲についての語りがもっとも多く、そして小説/曲の登場人物と比べればアーティスト側に関する語りのほうが多い印象がある(ヨルシカのメジャー1st、2ndアルバムで展開されたエルマとエイミーの物語に関しては例外的にキャラ語りが中心的だったものの)。
これらはいずれもボカロ文化なくしては生まれなかった才能や作品ではある。しかし内容や消費のされ方が、キャラクター文化に根ざすボカロ文化のものというより、J-POPや一般文芸に近づいている――だからカンザキ作品も「ボカロ小説」というより「ボカロP小説」と呼ぶほうが適切に思える。
■ビジネス的に見ると何が違うか? 「ボカロ小説」から「ボカロ文芸」へ
総じて、第一波のときの人気作品のようにキャラクターやストーリーを音楽や物語で展開して売るものというより、第二波作品はあくまで音楽そしてアーティスト自体を核として、その世界観を表現するために物語を補完物、従属物として用意したものに見える。
YOASOBI楽曲の原作になった小説『たぶん』は20年晩秋に映画公開予定であるように、第二波も第一波のときのように多メディア展開することでブームを大きくし、アーティストや企業側からすると収益最大化を意図するのであろうことは変わらない。
ただそれはキャラクター商品を売るためではなく、アーティスト/プロジェクトを表現し、売るために行われる。
言いかえれば「作品」自体というより、作品を通じて「作家」を売る戦略に変わっている。この流れはボカロキャラの「二次創作」から「オリジナル」キャラへという変化をさらに推し進め、「キャラクタービジネス」ではなく「アーティストビジネス」へ転じたものと捉えられる。
楽曲と小説を連動させるという形式は第一波と変わらないが、流行り廃りの激しいキャラクタービジネスではなく、中長期的にファンとの関係を前提に継続しやすいアーティストビジネスの一翼を担うものとして、小説は位置づけられる。
第一波と第二波作品の違いは、受け手(受容者、消費者)側からはどう捉えられるか。
先ほど第一次ボカロ小説ブームは2015年頃には終わったと書いたが、それでも例外的にカゲプロとハニワは中高生に支持され続けてきた。全国学校図書館協議会と毎日新聞社が毎年行う「学校読書調査」の「読んだ本」ランキングを見ると、この二作品は中高生、とくに中学生女子が読んだ本の上位に2010年代後半以降も食い込んでいる(ハニワはシリーズが継続しているからまだわかるが、カゲプロは完結後も読まれ続けている点がきわだって驚異的だ)。
つまり本を読む中高生にはカゲプロやハニワ作品は一定程度いまも認知されていると考えられる。
それを踏まえるならば、『盗作』『夜に駆ける』『あの夏が飽和する。』の表紙がキャラクターイラストを据えたマンガ・アニメ文化的なものではなく一般文芸風の装丁になっているのは、これらの作品が、カゲプロやハニワのイラストやデザインが年齢的ないし趣味嗜好的に子どもっぽく見える層を向いているからかもしれない。
つまり、第一次ブーム発の作品とは異なるセグメントに向けられていると捉えうる。
隣接ジャンルの動きから類推するなら、もともとはティーンが中心的に読むものだった「ライトノベル」から大人向けを謳う「ライト文芸」が派生したように、第二次作品は、中高生向けの「ボカロ小説」から派生した、やや年齢が上向けの「ボカロ文芸」なのだとみなすこともできよう。
■それでも連綿と受け継がれるモチーフとフォーカスされる感情
このように、第一次ブームの人気作と第二波作品はさまざまな点で異なる。
それならもはや「ボカロ小説」と形容しないほうがいいのではないか、と思うかもしれない。
しかしそれでもボカロ小説には第一波のころから継承されているものもあり、その文化的な連続性ゆえに、私は同じ言葉で形容したいと思う。
第一波と第二波に共通するのは、過剰さ、過激さだ。
第一次ブーム期の作品では、たとえば『悪ノ娘』は主人公の片割れとも言うべき王女(暴君)が親族、家臣を含めて殺しまくり、自らもギロチンにかけられる。カゲプロの登場人物は、たとえば孤児院出身でいじめられた経験やDV経験を持っており、自殺・病死・轢死など死の体験と生前の強い願いがあいまって異能力を獲得する。中二病的とも言えるダークな世界観、悲痛さが描かれていく。
もっとも、第一波作品でも『ミカグラ』やハニワ作品はかわいさが前面に出ているが、それはそれで過剰な情報量と誇張された感情が充満している。
第二波作品はどうか。『盗作』の主人公は窃盗犯を経てパクリで生計を立てる音楽家と、雑貨店から母が作ったガラス細工を盗んでは破壊する少年の物語だ。『あの夏が飽和する。』では、養護施設育ちの主人公が、逃避行の果てに自殺した想い人の幻影を追って出会い系を使って知り合った少女に想い人を重ね、少女は溺愛する父がかまってくれないことで父の代理物として男性を求め、そして家族から虐待やネグレクトを受けている少女の友人が望む一家惨殺計画に巻き込まれていく。『夜に駆ける』収録の作品は、4編あるうちの1編は「夏祭り」というリア充的なモチーフで書かれているが、ほかは「自殺」や「世界の終わり」、別れた恋人が部屋に舞い戻ってきて行う模様替え、である。
まったくさわやかさとは縁遠い。
この過剰さ、過激さは、もともとボカロ曲が主流のJ-POPやアニソンのオルタナティブとして、それらが(放送コードに対する配慮などいくつかの理由から)使わないモチーフや言葉、フォーカスしない感情――しかし、たしかに需要はあるもの――を積極的に描くことで人気を獲得してきた流れゆえだろう。
第二波のプレイヤーたちもやはりその流れのなかで存在感を放ってきた。つまり親和性があった。
キャラクターではなく情景を通じた心理描写に焦点をシフトさせてはいるが、作品で描かれるモチーフや感情は、やはり連綿と続くボカロ文化由来のものだ。
そういう意味でもこれらの作品は、外形的には「一般文芸」に近づき、第一波とはおそらくやや異なるセグメントをターゲットとしているとしても、実質においては固有のジャンル性を持つ「ボカロ小説」なのだと言っておきたい。
■第二波のゆくえ
今後どれだけほかの作品・作家が現れるのか、それらがどんな広がりを見せるのか、あるいはここで取り上げた三者がどんな展開を見せるのかについては現時点ではまだわからない。ヨルシカやYOASOBI発の作品がかつてのカゲプロのように若年層において社会現象となる日も遠くない気がするし、カンザキ作品が映画やドラマになる未来も想像できる。
いずれにしても、だ。
ヨルシカもカンザキイオリも「心の穴」というモチーフを使う。その穴は普通の行為では埋められない。過剰で過激な行為でなければ埋め合わせできない、あるいは穴を埋めようとすることが社会的に逸脱した行為を招く、という展開を描く。
カゲプロは8月15日がループする話だった。作中では一切触れられないものの、日本人にとっての終戦記念日である。受け手からすれば、作中に登場する、惨劇が繰り返される「終わらない世界」と日本の敗戦の記憶が重ね合わせられ、そこから抜け出せないというイメージを少なからず抱かせるものだった。傷つき欠落した存在であるという感覚があった。
このような「現在の私(たち)は本来のありようから疎外・逸脱・壊れた状態にあり、回復したい/埋め合わせしたい」とする考え方は「疎外論」と言われ、近代社会の成立以降、いつの時代も急進的な若者を惹きつけてきた。
欠如を埋めようとする過剰な運動がボカロ文化のひとつの特徴であるとするなら、どんなかたちであれ、今後もこうした表現は変奏され続けるだろう。
その新たな動きが見えたときはまた取り上げ、記録することとしたい。










