「R-1」はなぜ「どれもつまらない」とおもう人を生みだすのか ピン芸のもつ致命的な限界
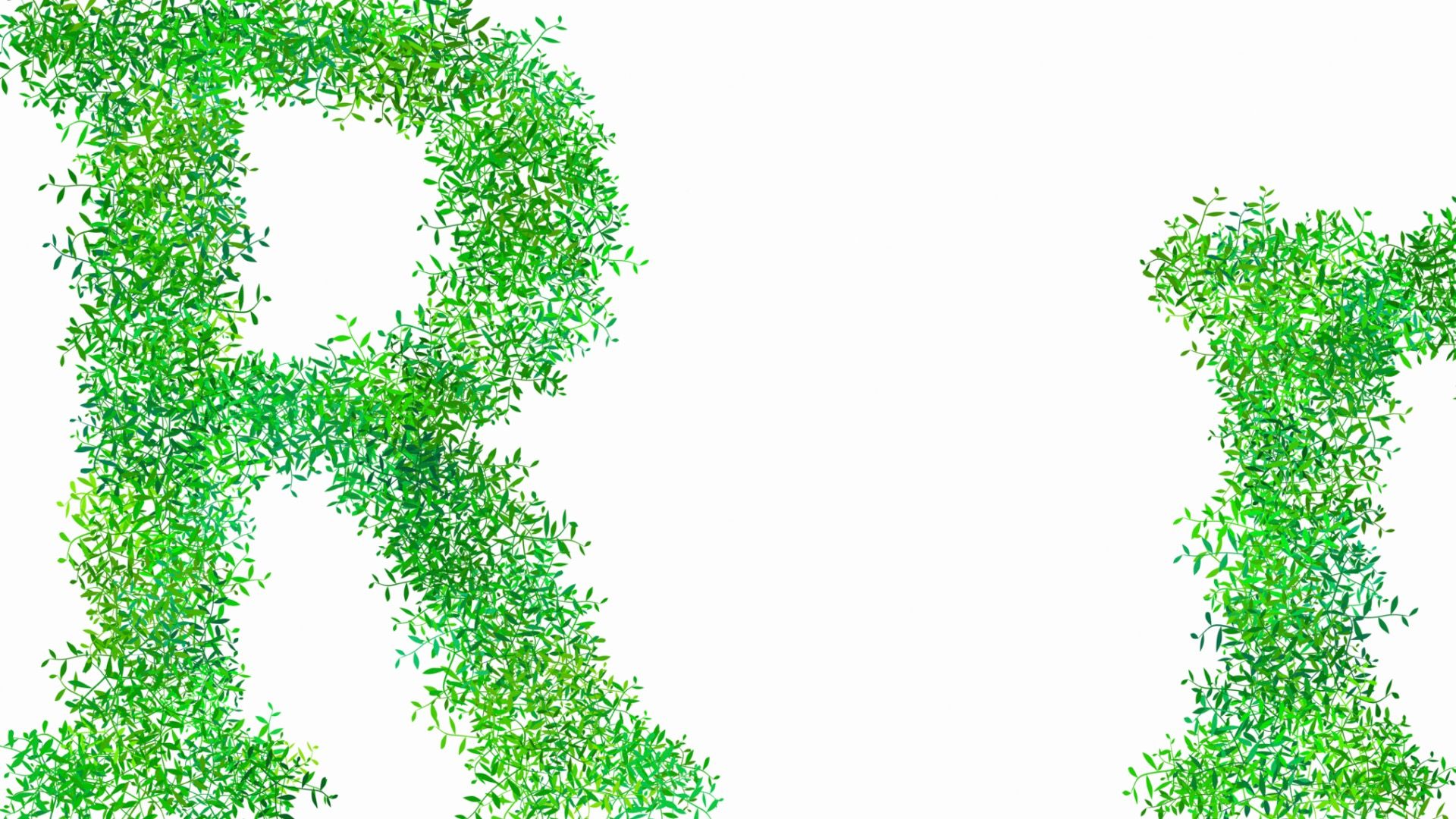
今年の『R-1グランプリ』はコンパクトに放送された。
正味120分の放送だった。
M−1グランプリは、ここのところ「216分」の放送時間を取っているので(つまり3時間36分)それに比べると半分近い(55.5%)短さである。
テンポはいい。
でも「すごく急いでる感じ」もつきまとっていた。
2時間できっちり終わったのはよかったが、また、あまり落ち着いて見ていられる番組でもなかった。
審査員の得点表示が番組途中で変わった
たとえば、審査員の採点結果を見せる時間が、詰められた。
しかも番組途中から短くなったのだ。
最初と2番目の出演者(“マツモトクラブ”と“ZAZY”)はM−1と同じように審査員の採点を一人ずつ紹介してくれた。
「陣内さん89点、友近さん89点、ホリさん93点……」と7人の採点がひとつずつ読み上げられ、それに視聴者の採点(1点か3点か5点)が加えられた合計点数が表示された。緊張感のあるシーンである。
ただ、視聴者のTwitter採点の表示に手間取ったためか、3番目(“土屋”)からいきなり審査員7人全員の採点を一挙に見せるようになった。
審査員7人ぶんと視聴者採点が表示され、前の人と比べてどう違っているのだろうという推察をする間もなく、どきどきする時間が削られ、すぐに、合計点数も出されていた。
3番目以降、10人目までその方式で得点紹介されたのだ。
ずっと急いている感じが出ていた
「何だか急いでる感じ」が醸し出されていた。
そもそも、途中で方式を変えたところが、かなり「手違いのまま進めている」という気配が強かった。
採点を見せる画面は、上に大きな枠が2つ用意され、審査員の顔とその採点が示される枠だったが、後半はそこが使われなかった。黒いままであった。
まあ、これで番組が終わりまで放送できるのなら(こうしないと最後が見られない可能性があったのなら)これで仕方がないとおもって見守るしかなかった。
あまり落ち着いて見られる気配ではなく、テレビ視聴にあまりいい影響を与えてなかったとおもう。
審査は現場でおこなわれているので、そこには影響がなかったとおもわれるが、テレビを通して、急がないと、という気分にさせられたのはたしかである。
リアルタイムに見たあと、夜中に見返したが(ネタ部分は通算5回見た)、見れば見るほど、おもしろさを感じられた。
見返すときには「急いている感じ」で追われないため、純粋にパフォーマンスを見ることができる。
そのときに、パフォーマーたちの狙いがやっとしっかり届いてきたのだ。
何だかもったいない。
「ピン芸」は強い芸ではない
あらためて「ピン芸」はさほど強い芸ではないのだな、ということにおもいいたる。
「舞台でのピン芸」では、短い時間で客を取り込めるものではない。
寄席に行けばわかる。
「R-1」のRはもともと「落語」から取ったものである。
落語は(あくまで落語の話であるが)きちんと噺を聞かせるには、どんなに短くても7,8分は必要である。
昔ながらの寄席における芸人の持ち時間はだいたい8分から12分で、ピン芸を楽しむためには本来はそれぐらいの余裕が必要なのだ。
正式な芸人ではない「前座」は、最初に出てきて3,4分ほどで高座を終える(ことがある)が、まず誰も笑わない。3,4分の高座だと、だいたい「一回も笑いが取れない」のがふつうである。
前座ながらに笑いを取ろうと工夫する若手もときにいるが、だいたいその工夫はスルーされてしまう。
彼らのそういう哀しい努力が踏み台となって客席全体の空気が醸成されていき、あとから出る芸人は笑いを取りやすくなっていく。
それが「R」落語の世界である。
どうしても「唐突で不親切」になるR-1の芸
でも「R-1グランプリ」はテレビショウであり、ネタ見せのショウである。
落語を見せる場ではない。落語家も挑戦しているという話を何度も聞いたことがあるが、最終戦にまで残っているのを見たことはない。
だから3分で笑いは取れない、などと古典芸能的な暢気なことは言っていられない。
いきなり尖った設定で、客の懐に飛び込んでいかないといけない。
無理めのつかみで客に迫って、そのままぐいぐいと笑いに直進しないと、このコンテストでは高評価を得られない。
だから、最初から奇妙なテンションだったり、事件(出来事)の途中から見せるコントだったり、あまりふつうの状態では始まらない。
言ってみれば、唐突で不親切なお笑いである。
それが「短い時間で見せるピン芸の宿命」である。
だから見ているほうはそこで入り込めないと、ずっとおもしろくない。
極端な話、何をやっているのかわからないままである。
笑う方向の説明がないので、笑うための準備も理解も追いつかなければ「言ってることはわかるが、何がおもしろいのかまったくわからない」まま3分が過ぎてしまう。
2人、3人とそういうパフォーマンスが続くと、見てるほうはだんだん腹が立ってきてしまう。
おもしろくも何ともない悪ふざけの連続に見えてきてしまうのだ。
そうなると最悪である。どうしようもない。
そういうときは見るのをやめればいいとおもうのだが、それはそれで勇気がいるので、そういう決断もなかなかできない。最後まで見てしまって、ただ愚痴っぽくなるばかりである。
見てるほうから近寄っていくとピン芸はわかりやすい
あらためておもうのは、こういう短い時間で見せるピン芸は、見てるほうも少し芸人に近寄っていかないと、存分には楽しめない、ということである。
一人芸なので、事前の説明がとても少ないから、見てるほうはそこを想像して、忖度して、その世界により近づいていくと、楽しめる可能性が高まるのだ。
なぜテレビを見るのにそんなことをしなくちゃいけないんだと言われればそのとおりで、実際にそういうことをしないのがふつうだろうけれど、でも通して見て哀しい気分になるのを避けるには、それしかないんじゃないだろうか。
現場の客はパフォーマーに寄っていっている。
席から動いちゃだめだし、スマホを見ちゃだめだし、喋っちゃだめで、ものを食べながら見てはだめで、とても不自由で窮屈で、ただ、パフォーマンスを見るしかない。つまり、現場の客はパフォーマンスに近づいていかざるをえない。
それがピン芸を見せやすい場なのだ。
それをテレビで見せようとしているのだから、そこがむずかしい。
深夜にもう一度みるとわかる『R-1』のおもしろさ
今回、深夜に見返しているときにそれを痛感した。
ライブ放送の、何やら焦っている気配の漂うなかで見てるときは、私もいくつか芸に近寄れず、おもしろさが感じられなかった。
審査員の採点と自分の感覚がずれていた。
それが夜中に落ち着いて見返してみると、落ち着いているぶんゆっくりと芸人に近寄っていってるようで、そうすると、みんなおもしろいのだ。めちゃめちゃおもしろいものもいくつかあった。
だいたい審査員の採点と同じ感想を持った。(古坂大魔王がZAZYを完璧ですと言ったのは、三回目に見たときにすごく得心した。つまり三回見ないと得心しなかった)。
夜7時からのライブ放送でもそういう気分で見られればよかったとおもうが、なかなかそうはいかないのだ。
バラエティ番組としての『R-1』の限界
コンテストとはいえ、テレビのバラエティである。
何かをしながら、飲みながら、LINEがくればスマホをチェックしながら、眺めている。
こっちから近寄っていない。そっちから近寄ってきなさいよという(そんなに偉そうな態度ではないにしても)そういう気分がある。だから、わからないものに対しては、腹が立ってしまう。
でもほんとうは、やさしい気持ちで、つまり、なんかわからないけどおもしろいんじゃないかな、という態度で見始めないと、おもしろさになかなかたどりつきにくい。面倒な話ではあるが、どうもそういうことのようである。
そこが『R-1グランプリ』のむずかしいところだろう。
ピン芸人の立場からいえば、それぐらいの気持ちを持ってくれてもいいんじゃないかなということになるが、でもいっぽうではただのテレビ番組でしかないわけで、そんなに真剣にバラエティを見ないのは、ふつうの行為である。
ひとつ歯車が合わなかっただけで、もう気持ちが離れてしまい、最後までおもしろくない。
ピン芸のコンテストをテレビでおもしろく見せるのは、かなりむずかしい。毎年「R-1」を見るたびにそうおもってしまう。
もう少しパフォーマンス時間を長くすれば、芸人の魅力があますところなく伝わってくるだろうが、でも7分芸を10人も見せられたら、それはそれで集中力が続かず、見ていられない。
7分芸を3人だったら楽しく見られるだろうが、でも3人しか出てこないコンテストはあまり魅力的ではない。そのへんがむずかしい。
しかし、この番組があるからこそ注目される芸人もいるわけで、それだけでもこの番組の存在には大きな意味がある。
3分のピン芸はあまりつぶしがきかない
また、ピン芸人として「とてもおもしろい3分芸」を練り上げたところで、テレビのネタ見せ番組以外では、あまり有効に使えない。つぶしがきかない。ほかでの活躍につながらない。
劇場などのライブ会場でも、客を前にしてそんな忙しい芸ばかりを披露しているわけにはいかないだろう。
R-1優勝芸人のうち、その後、さほど有名になれなかった芸人がままあるのは、そのへんの事情によるとおもわれる。
だから、コンビの片一方が出てきていたり、バラエティタレントとしての能力の高い人が出てきたりして、『R-1』はただのピン芸人の大会ではなく、「一人で3分舞台をどうもたせるか」が評価される場になっている。それはそれでいい。
ゆりやんレトリィバァとZAZYの一騎打ち
2021年のファイナルステージは、ゆりやんレトリィバァとZAZYの一騎打ちの様相であったが(かが屋 賀屋は演技は飛び抜けてうまくてそこは鮮烈な印象が残ったのだけれど、あと2人と比べると笑いどころとしての破壊的部分が少なくて、たぶん勝ち抜けないだろうなというのは審査前から感じられた)、この2人のパフォーマンスの評価が高かったのは、どちらも「3分芸」としてぴったりそのテレビサイズに収まっていたところにあるとおもう。
ゆりやんもZAZYも時間サイズのいい芸で、短い時間のなかに緩急をつけている。一本調子になっていない。そして、あれ以上続いたらぜったい飽きてくるという世界で、そのへんの見切りがとてもうまい。
変な世界を作り上げる能力とともに、同時にどれだけナンセンスな笑いを突っ込めるかという部分が注目されるわけで、ふたりともそのポイントでのパフォーマンス力があたまひとつ抜けていた。そのへんは見事だった。
テレビで見せる「ピン芸コンテスト」というのは、そこだけに存在する独特の世界であり、かなり特殊な才能を要するので、トップになってもまだまだ苦難の続く不思議なポジションのようである。
優勝した瞬間、ゆりやんはガチで泣いているように見えたので、それはそれで心動かされるシーンであった。










