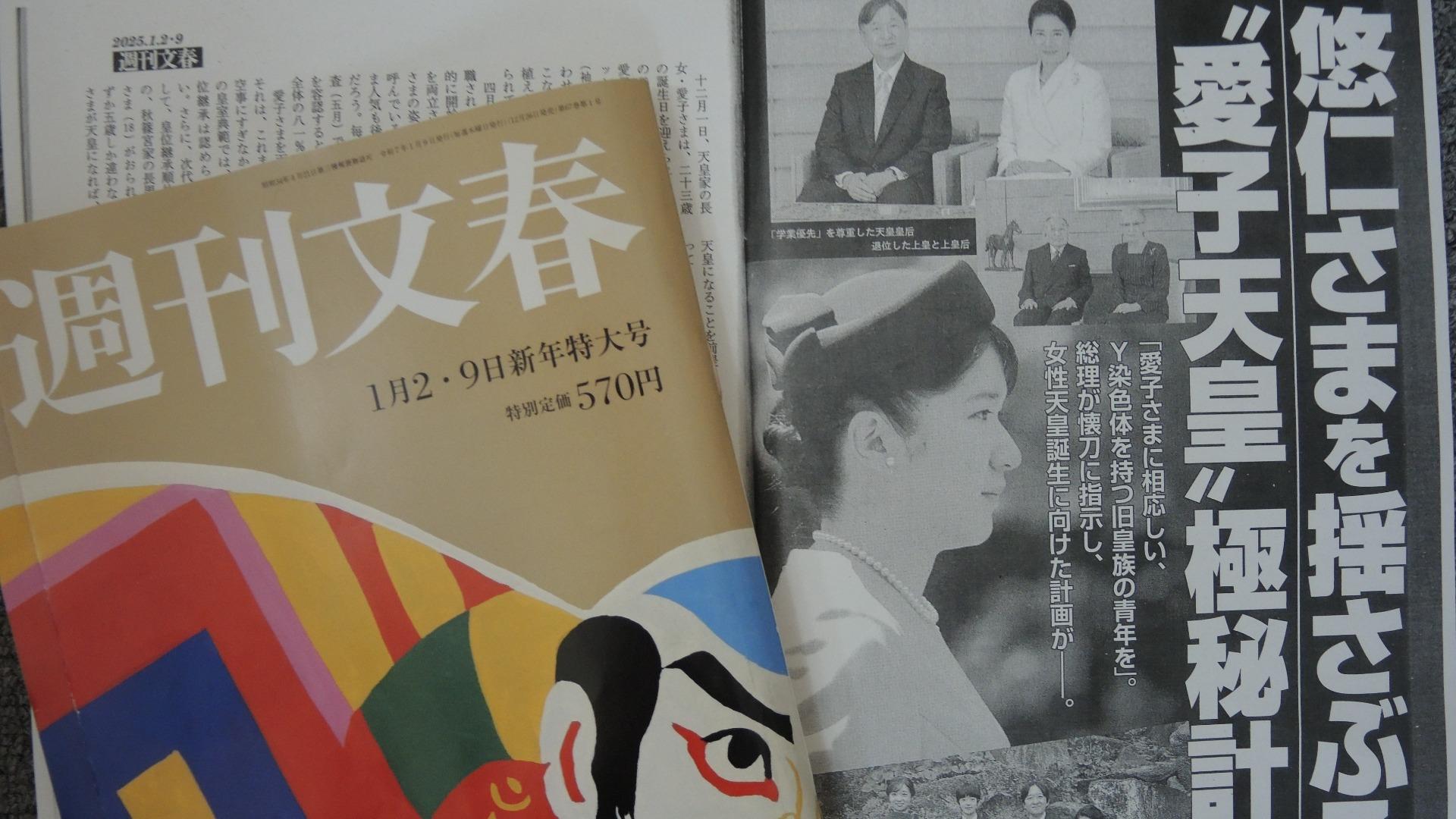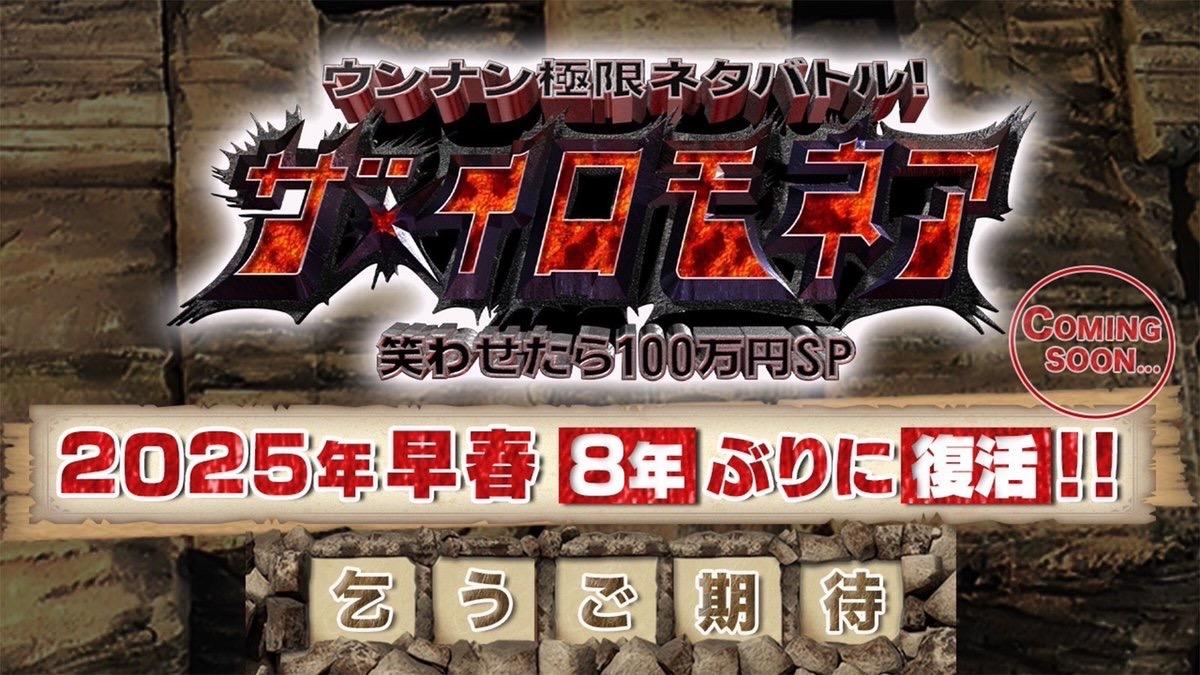結婚について知っておきたい法知識20~「子の命名」のルール

結婚して子どもが生まれるとなると、まず「どんな名前にしようかな」と考えると思います。では、どんな名前でも付けてよいのでしょうか。今回は命名のルールについて見てみましょう。
●子の名の命名義務者
名は氏(名字)と結びついて個人を識別し、その同一性を示すものです。そして、出生した子の名は命名行為によって定まります。
実は、民法には命名行為について規定がありません。
戸籍法は、父母その他を出生届義務者と規定しています(戸籍法52・56条)。事実上、この義務者が命名したものが、その子の名となります。
戸籍法52条(届出義務者・資格者)
1.嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
2.嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
3.前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、次の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
第一 同居者
第二 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
4.第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。
戸籍法56条(公設所における出生)
病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。
●出生届の届出期限
出生届は子が出生してから14日以内にしなければなりません(戸籍法49条1項)。
なお、海外で子が出生した場合は3か月以内にしなければなりません。
戸籍法49条
1.出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
2.届書には、次の事項を記載しなければならない。
一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二 出生の年月日時分及び場所
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 その他法務省令で定める事項
3.医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
●命名のルール
では、どんな名前を付けてもよいのでしょうか?
戸籍法は、子の名に用いることができる文字を次のように規定しています(戸籍法50条)。
戸籍法50条 (子の名に用いる文字)
1. 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2. 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
●子の名前に使用できる文字
そして、「常用平易な文字」(ふだん使用する理解・解釈がすぐに出来る文字)は次のように範囲が定められています(戸籍法施行規則60条)。
戸籍法規則60条(常用平易な文字の範囲)
戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
子どもの名前を考えたら、法務省の「子の名に使える漢字」で検索してみましょう。法務省のホームページでは,戸籍のオンライン手続に使用することを目的として整理した文字の情報を検索することができます。また,子の名に使用することができる文字(人名用漢字等)についても検索することができます。
名前は「個人を識別する」という機能があります。生まれてくる子に対する思い入れが強すぎて、難解な名前を付けると将来社会生活上不便を強いられることがないとも限りません。
名の果たす「機能」と親の「思い入れ」をうまくバランスをとって命名するとよいのではないでしょうか。