追悼・上岡龍太郎
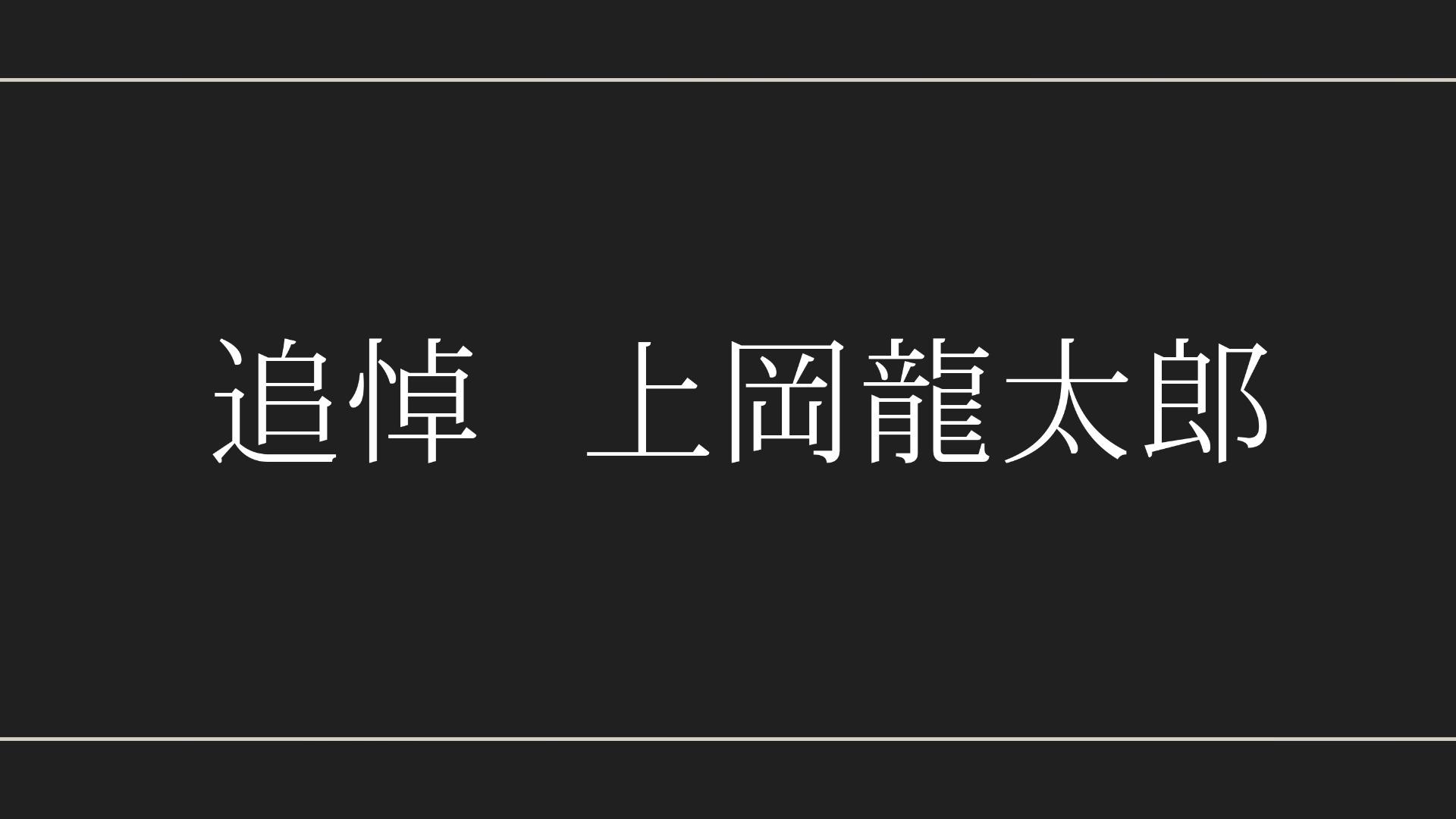
2000年に芸能界を引退した上岡龍太郎さんが、5月19日に大阪市内の病院で肺癌と間質性肺炎のため亡くなった。
息子で映画監督の小林聖太郎は、こうコメントを寄せている。
とにかく矛盾の塊のような人でした。父と子なんてそんなものかもしれませんが、本心を窺い知ることは死ぬまでついに叶わなかったような気もします。
弱みを見せず格好つけて口先三寸……。運と縁に恵まれて勝ち逃げできた幸せな人生だったと思います。縁を授けてくださった皆様方に深く感謝いたします。
(「ORICON NEWS」2023年6月2日)
「弱みを見せず格好つけて口先三寸」まさに、上岡龍太郎はそんな男だった。
「芸は一流、人気は二流、ギャラは三流」をキャッチフレーズに、立て板に水のような話術で人気を博し、『探偵!ナイトスクープ』(朝日放送)の初代局長として唯一無二の番組のカラーを作り上げ、『EXテレビ』の読売テレビ制作の火曜・木曜、いわゆる「大阪エックス」では「テレビ論」をテーマにした先鋭的な企画を連発した。
その木曜エックスの初回放送(※注)はいまでも語りぐさになっている。だだっ広いスタジオには、ブラウン管テレビと椅子がひとつだけ。スタッフもいない。そこに上岡龍太郎がやってきて、固定カメラのワンショットで約1時間「テレビ論」を語るというものだった。ここで上岡は「テレビの面白さは、素人が芸をするか、玄人が私生活を見せる。この2つにひとつ」などと今でも色褪せないテレビ批評を語るのだ。
他にも「視聴率」をテーマに「この番組が終わったら、チャンネルをNHKの教育テレビ(現・Eテレ)に合わせてください」と呼びかけたり、深夜番組的なお色気企画を痛烈に皮肉った「低俗の限界」という企画で「猥褻」とは何かという問いを投げかけたりしていた。
人気絶頂のまま自ら引退を決め、それから復帰することなく潔く幕を綴じたことを含め、上岡龍太郎は存在そのものが極めて批評的であった。
その功績はあまりにも大きい。
そして忘れてはならないのは、『鶴瓶上岡パペポTV』(読売テレビ)だろう。
むく男、むかない男
「見てるあんたも同罪じゃ。」
『鶴瓶上岡パペポTV』では、そんな鮮烈なコピーが書かれたセンセーショナルなポスターが作られた。 コピーを際立たせるのは、その写真。燕尾服姿にきめた二人の男が立っている。 笑福亭鶴瓶と上岡龍太郎である。
しかし、下半身はなにも履いていない。 局部がモザイクで隠されているだけ。まさに「見てる」僕たちに「同罪」だと訴えかける。
コピーを書いたのは鶴瓶が「毒の人」(※1)と称する糸井重里。写真を撮ったのは浅井慎平。
それは番組の精神を如実にあらわしていた。
撮影はすぐに終わった。 何枚も撮ることなく、浅井は「いいよ!」「いいですね!」と下半身丸出しの男を手早く撮影した。 準備中も上岡はぶらんと丸出しのまま何も言わず堂々と待っていた。
一方、鶴瓶は違った。 撮影風景を見ていた糸井はこう証言している。
「上岡さんはそういう時に『騒いだら負けや』って思ってるからなんにも言わずにぶらんとさせてるのよ。ところがこの人(鶴瓶)は人間が小さいから(笑)、一緒に写る時に負けてはいけないって気持ちがあるらしくて後ろを向いてはちょっと揉むのよ(笑)」
鶴瓶は笑いながら述懐する。
「ふふ。揉むのと同時にね、むくねん。あの時に包茎やと思われると一生言われるから。仮性包茎やけど。むくけど戻るんですよね」
「でもちょっと大きくしてるから戻りにくいわけ(笑)」(※1)
そうしてできあがったのが「むいてる男」と「むかないでじーっと動かない男」という対象的な二人の男が対峙しているポスターだ。
「おまえ、俺の悪口をいうてるやろ」
『パペポTV』は1987年4月14日からよみうりテレビで始まった。当初は関西ローカルだったが、88年10月から日本テレビでも放送されるようになった。
もともとプロデューサーの岡島英次、ディレクターの白岩久弥、放送作家の疋田哲夫が考えていた鶴瓶のパートナーは、別の人物が想定されていたがNGが出て、代わりに鶴瓶本人が希望し(岡島という説もある)、先輩格である上岡龍太郎がパートナーに選ばれたのだ。
そのパイロット版の『鶴瓶・上岡激突夜話』は、疋田が構成を務めていた行き当たりばったりの街ブラロケ番組の源流といえる『夜はクネクネ』(毎日放送)の“スタジオ版”として企画された。二人がスタジオで行き当たりばったりのトークをする。つまり雑談だ。それを時間の限り行った。
番組は好評だったためすぐにレギュラー化に向けて動き出した。 しかし、いくら深夜の関西ローカル番組とはいえ、ただ「2人でトークする」という企画書では、通してくれない。 そこで一計を案じ、書かれたのは「雑談選手権」という企画だった。 リングを作って、なにかひとつのお題について2人が話す。そしてそれに点数をつけて勝敗を決めるというものである。「それではすぐ終わってしまいますよ、番組としては」(※2)と鶴瓶が笑うように、 もちろん、こんな企画は端から方便だった。
始まってみれば、スタジオで対峙した2人が、ただ60分“雑談”をするというシンプルな番組になったのだ。
上岡龍太郎は、この番組についてこのように振り返っている。
「ぼくはね、全編アドリブやったんやけども、鶴瓶ちゃんは、ネタを今度はこれ言うて、あれ言うてと、いつも用意してたみたいやね。小さいメモ帳をネタ帳にして、中身を書かずにタイトルだけを羅列してたよ」(※3)
鶴瓶もそれを裏付けるように語っている。
「僕の頭の中では、なんか一時間しゃべらないかんというなんかがあるわけですよ。細かな組み立てっていうのはないけど、きっかけだけは、アッこんな話もあったなんて思いながら舞台にあがるわけですよ。向こうは僕がなんでくるかわからないんですよ。それをね、全部吸収しながらパーン、パーン……、払いながらね」(※4)
この二人のやり取りは瞬く間に評判になり、『パペポTV』は関西を代表する人気番組になっていった。
その1~2年目、鶴瓶は「僕の手柄だ」(※4) と思っていたという。自分が構成を考えて話しているからこその人気だと考えたのだ。 そんな思いが透けて見えたからだろうか。 なにも不満や悪口も言っていないにもかかわらず、「大阪スポーツ」で2人の「不仲説」が報じられた。
鶴瓶はその記事が出たことを知らぬまま『パペポTV』の本番の舞台に上った。 すると、上岡が口を開いた。
「おまえ、俺の悪口をいうてるやろ」
鶴瓶は戸惑った。悪口を言ったことはないが、心の奥底で悪感情がないわけではなかった。だから鶴瓶は「はい、言ってます」と答えたのだ。
その言葉に上岡は怒るどころか、うれしそうな表情をして、鶴瓶から自身の悪口を引き出していったのだ。
「あー、この方は凄い人やな」(※4)
鶴瓶はそのことを実感したのだ。
正反対の「正直さ」
鶴瓶と上岡は対照的だ。
たとえば、素人に対峙するときにその違いがあらわになる。
あるとき、上岡は海女さんの取材に行った。
「なんかええ話ありますか」と本番前に取材した。すると「シケの時にね、二人で潜っていって一つのアワビを取り合いして沖に上がったら、親子の海女だった」という話を聞いた。シケの時には親子でも取り合いする、そのことがすごいなと思い、「それを本番でまた聞かせてください」とカメラを回した。
すると彼女は、「あれはシケの日だった。親子の海女が……」と語りだしたのだ。先にオチである「親子」を言ってしまっているのだ。
上岡龍太郎は、それを「台無し」だと考える。だから素人が“嫌い”なのだ。
だが、逆に素人好きの鶴瓶はそれを「オモロイ」と考える。
「お笑いにはいろいろな考え方あると思うんですけど、予測もしないアクシデントが起きたとき、いかにそれをおもしろくするのかっていうのが僕の中ではプロなんです。それはアクシデントに見せないでいかにおもしろいなって思うように逆転するかっていうのがプロだと僕は思ってるんですよ。それは予定調和にないことが一番いいんですよ」(※5)
また、鶴瓶はこの番組が始まった後は、「よそでは絶対に会わないでおこう」と決めた。新鮮さを大事にしたいからだ。
だが、上岡は違った。平気で対談などを持ちかけた。
「それで飽きられたらそれでええやん」と。
「あの人はそのまま」なのだと鶴瓶は言う(※6)。
執拗なまでにオカルトを批判するのも、最初は「そんなことテレビで言わんでいいやんか」と思っていたが、上岡がテレビでも「そのまま」だから言っているんだとわかって、納得した。自分に正直なのだ。
その正直さに鶴瓶は惹かれた。
「龍太郎師匠が可愛いのは、普段は『キーッ』となって怒らない、愛した人にはパーンと叩かれても、なんでも許してしまう人なんですよ。で真剣に笑うんですよ、あんだけ長いことお笑いやってはっても。真剣な目して笑うんですよ。本人は自分が全然おもしろない男やということを知ってはるんですよ」(※6)
その「正直さ」は2人の数少ない、しかし重要な共通点のひとつだ。
だが、その「正直さ」の向かう方向がまったく別の方向だから、対照的に見えてしまう。
上岡は鶴瓶を「なんの衒いもなく、優しさを口に出せるタイプ」だと評している。
「彼は、どこかでドン臭さが人間の愛なんだと、才能をごまかしているとこがある。愛や優しさがすごい貴いもんやと、世間にコメントしたがるところがある」(※7)
愛や優しさが貴いものだ。それは上岡も認めている。だが、「もう、ええっちゅうのに」と感じてしまうことがある、と。
それに対し上岡は自らのスタンスをこう語っている。
「自分の優しさを隠して人の悪口言うという上質なユーモアをやるわけです。ハッハッハ。 毒を思い切り出すことで、毒も薬であることを言いたい」(※7)
その「毒」と批評性は、いまもテレビに有効な薬であるに違いない。
(引用元)
※1 『チマタの噺』16年4月12日
※2 『アサヒ芸能』93年9月9日号
※3 戸田学:著『上岡龍太郎 話芸一代』
※4 『婦人公論』95年12月号
※5 『サワコの朝』15年10月3日
※6 『婦人公論』94年4月号
※7 『週刊朝日』89年8月18日号
(※『パペポTV』に関する記述は拙著『笑福亭鶴瓶論』より加筆・修正の上、抜粋したものです。トップ画像は筆者作成)
(※注 ご指摘を受け修正しました)










