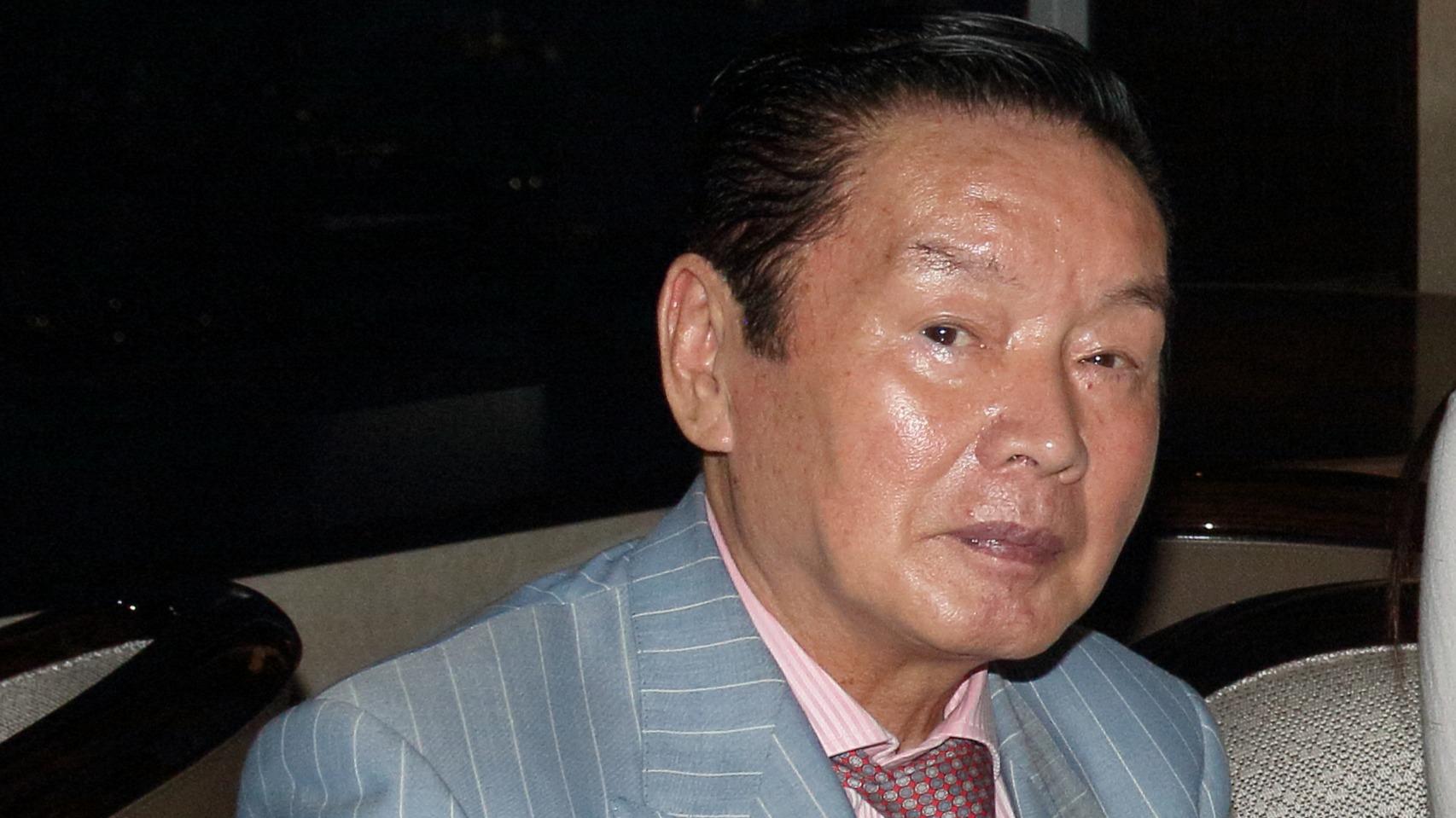渋谷慶一郎のアンドロイド・オペラ『MIRROR』が問いかける「生命と非生命の境界線」

6月18日、東京・恵比寿ガーデンホールにて開催された渋谷慶一郎の作曲・プロデュースによるアンドロイド・オペラ『MIRROR』を観た。
ステージ中央には人工知能(AI)を搭載したアンドロイド・オルタ4が屹立し、ピアノを奏でる渋谷と40人編成のオーケストラがそれを囲む。オルタ4はオーケストラを指揮し、合成音声で歌う。客席の周囲に配置されたスピーカーによる立体音響の電子音楽、映像、照明もあいまって、神秘的で荘厳な空間を作り上げる。他に類を見ないパフォーマンスだ。
最も印象に残ったのは、単に先鋭的なテクノロジーを駆使していることではなく、それを用いて「人間とは何か?」もしくは「生命と非生命の境界線はどこにあるのか?」といった哲学的な主題に挑み、答えのない問いかけとして音楽劇の表現に結実させていることだった。
同作は二部構成で、前半は2021年に新国立劇場で初演した『Super Angels』の抜粋、後半は2022年にドバイ万博で発表し2023年にパリ・シャトレ座で上演した『MIRROR』が披露された。『Super Angels』には視覚や聴覚に障害を抱える子どもたちで構成するホワイトハンドコーラスNIPPONが児童合唱として参加。『MIRROR』には高野山真言宗の僧侶4人が参加し、千二百年以上の歴史を持つ仏教音楽である声明とのコラボレーションが繰り広げられた。

伝統的なオペラと同じく、アンドロイド・オペラもアリア(歌唱)とレチタティーヴォ(語り)によって構成される。
まず目を見張ったのは、アンドロイドと声明と電子音だけで構成された『MIRROR』のレチタティーヴォのパートだ。オルタ4は僧侶たちが唱える声明の旋律をリアルタイムで解析し、即興的に生成したメロディを歌う。歌詞は声明によって唱えられる経典をAIが学習し新たに生成したテキストだ。つまり、AIとアンドロイドによる最先端のテクノロジーが、古来から受け継がれてきた宗教的な祈りと向き合い、融合するさまが表現されていた。
オーケストラによるドラマティックな演奏の上でオルタ4がどこか金属的な歌声を響かせるアリアのパートにおいても、声明は大きな存在感を見せていた。「アンドロイドは鏡である」という言葉から始まる1曲目の「MIRROR」から、「私はただの機械か、それ以上の存在なのか?」と歌う「The Decay of the Angel」など、歌詞には終わりゆく世界の中でアンドロイドが自らの存在に悩み自問自答するような言葉が綴られる。その言葉を通して、生命とは何か、死とは何かといったテーマが浮かび上がってくる。声明の響きは、そういった深遠な表現に確かな説得力を与えていた。
オルタ4の動きも印象的だった。単に口や手を動かすだけでなく、鳴っている音楽の脈動にあわせてロボットアームの上の身体全体を揺らす。まるでアンドロイドが呼吸しているかのような感覚がそこに生まれる。
『Super Angels』では、ホワイトハンドコーラスNIPPOINの子どもたちが手話のハンドサインで歌う「手歌」を披露。ダイナミックな手歌とオルタ4の動きとのコラボレーションにも魅了された。また、この手歌の動きは独自に開発されたウェアラブルデバイスによってセンシングされ、スクリーンに映し出された映像とリアルタイムで同期していた。こうしたテクノロジーによる身体表現の拡張も刺激的だった。
渋谷は今回の公演を自身の集大成的な作品と位置づけている。テクノロジーの進化が可能にした音楽芸術の新たな領域を堪能した。