日本を代表する演出家・串田和美「肩書は役者」中学時代に嗅いだ“匂い”のせい?80歳までやめられず!
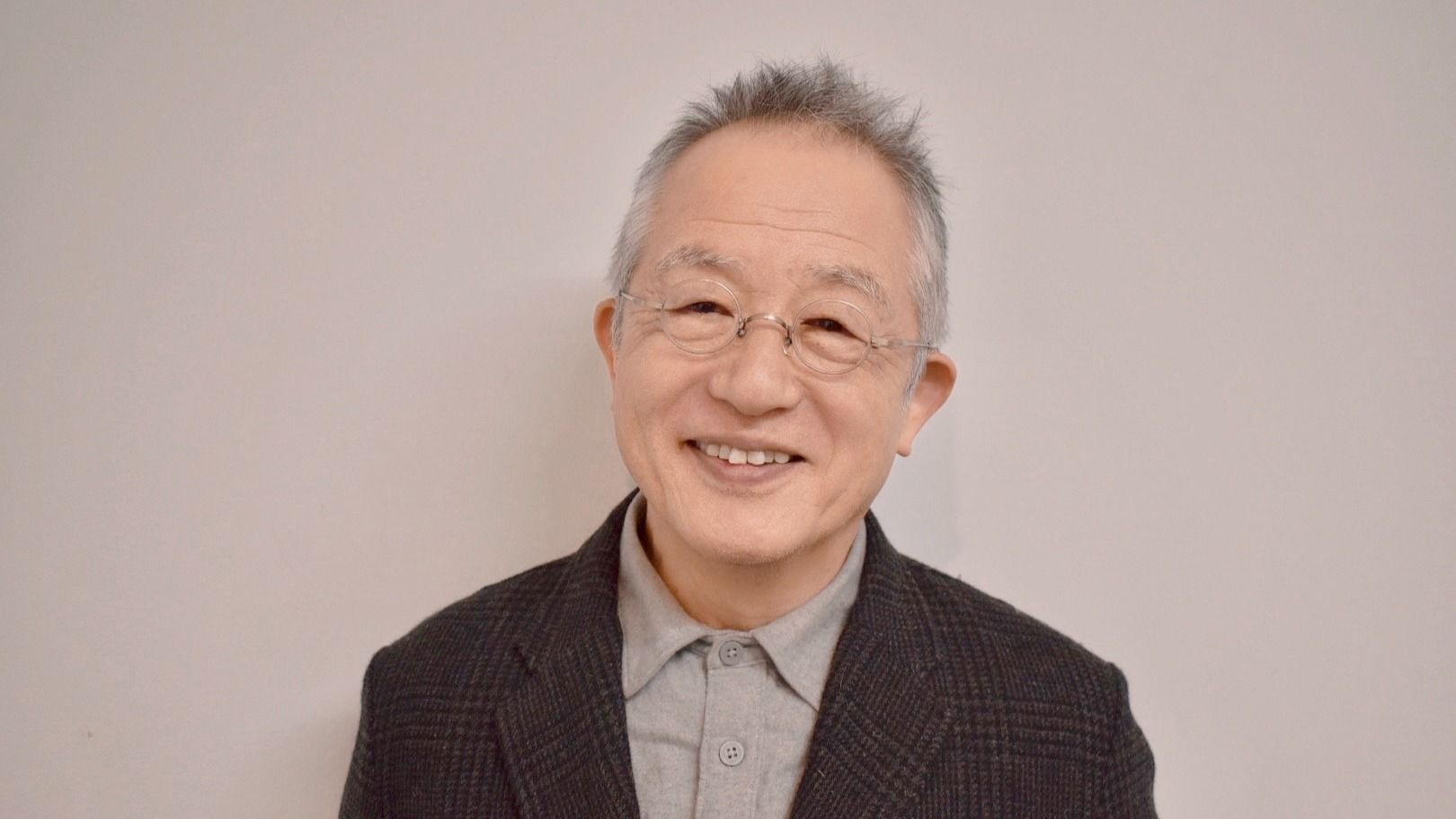
演出家・串田和美さんは「自由劇場」から数々の作品を世に送り出し、シアターコクーンの初代芸術監督を務め、長年演劇界をけん引してきた存在です。ところが、根底にあるのは「役者・串田和美」としての思いでした。幼い頃から持っていた芝居への慕情、才能ある演劇人たちとの出会い、ものづくりへの飽くなき探求心、すべてが串田さんの中で息づいています。
―演出家のイメージが強いですが、今作『博士の愛した数式』では主演。“役者・串田和美”ですね。
僕は役者です。何か肩書を1つと言われたら「役者」と答えます。演出をやらないで済むならその方がいい(笑)。僕は(十八代目)中村勘三郎さんに会わなかったら、こんなに演出をやっていなかったと思います。彼と出会ったことにより、演じることを誰かに託すのもいいのかなと、分身のような思いを持つようになったんです。
―勘三郎さんとの出会いは大きかったんですね。
当時、僕が芸術監督をしていたシアターコクーンに松竹の方がいらして、「ここで歌舞伎をやらせてもらえないか」とおっしゃったんです。その時は「歌舞伎はここに合わないだろう」と思いました。
あまりに熱心だったので、勘三郎(当時・勘九郎)さんに会いに行って話したけど、何かピンとこない。勘三郎さんは「僕は演出はできない」と言うし、僕も「歌舞伎なんて分からない」と返す。
後日、勘三郎さんが僕たちの上演していた『三文オペラ』をコクーンに観に来られて、「面白い!僕も出るよ」ということになったんです。これが「コクーン歌舞伎」の始まりです。初演の『東海道四谷怪談』は、僕は監修という形で。2本目の『夏祭浪花鑑』から演出になりましたが、まず歌舞伎における舞台用語が分からなかった。
例えば、一般的に舞台で「顔寄せ」と言うと、出演者・スタッフが初めて集まることを言いますが、歌舞伎では社長も幹部もずらりと並んでいてビックリしたし、進行の仕方も全く違います。舞台監督がいないし、呼び名も違えばルールも違う。

―同じ舞台でも、まったく流儀が違う。
最初は「稽古に1週間は多い」と言われて(歌舞伎は3~4日程度)、そこを2週間にするのが革命で、20日間にするまでに大変な時間がかかりました(笑)。
だけど、あのチームがものすごく一生懸命。「本物の土を敷いてむしろをかけて『夏祭…』をやりたい」と言ったらそれは面白いと、本当に土を運んできてやりました。僕がめちゃくちゃなことを言っても、一生懸命考えてくれる人たちでした。
舞台の奥が開いてパトカーが出てくるようにもしましたし、客席に向かってバッと飛び出したところで終わる米映画『明日に向かって撃て』(1969年)のようなラストシーンにしたい、と言うと誰も無理だとは言わない。「空中で止まるにはどうすればいいんだ」とギリギリまで一生懸命考えてくれた。勘三郎さんが「橋之助が飛び出したら紐で押さえて暗転にしよう」と言うんだけど無理ですね。何度か実験したけど絶対落ちるんです。子供みたいに実験する皆を見て、この人たち何かいいな、違う星のそっくりな場所に来てしまったような、よく知っているような、まるで知らないような不思議な感覚。これは一緒にできる、と思いました。
―ここまで唯一無二の演出をされるのに、なぜ役者を目指していたのですか?
芝居は、戦争中に疎開先の山形県で3歳の時に観た村芝居が初めてでした。むしろで作った小屋、ぶら下がっている裸電球、おにぎりを持ちながらの観劇、周りの農家の方たちが笑っている口の中、そんな光景がずっと頭にありました。
中学では、講堂で上学年による『うりこひめとあまのじゃく』を観ましたが、後ろから「やめろ!」とかヤジが飛ぶんです。上級生は怖いなと思っていたら、そのヤジを飛ばした人が舞台に上がっちゃって先生も出てきて…これ全部芝居だったんです。芝居とはこういうことなのか!と衝撃でした。

ヤジを飛ばしていた上級生が、この間亡くなられた俳優座の山本圭さん、うりこひめは長山藍子さん、初代水戸黄門・東野英治郎さんの息子の東野英心さんもいました。
面白いと思って演劇部の部屋を覗いたらテーブルに小さな缶があって。開けたら不思議な匂いがしたんです。その時、笑い声が聞こえたので振り向くと顧問の先生がいて「その匂いを嗅いだらもうやめられないよ」と言うんです。「今嗅いじゃったよ」と思いましたが、それはドーラン(舞台で使用される化粧品)で、言われたとおりやめられなくなりました(笑)。
その顧問の先生は、文化祭でひとりで白塗りでタイツを履いてパントマイムをやっていた、変わった先生でしたね。
1960年代、六本木で佐藤信さん、斎藤憐さん、吉田日出子さんらと「自由劇場」を始めました。しばらくしてバラバラになりましたが、またいろいろな若い役者が集まって来たんです。笹野高史さん、高田純次さん、イッセー尾形さんとか、稽古が面白くなかったら明日来ないかもしれないような人たちばかりだったので、その場を何とかしようという思いから演出をするようになりました。
―今回『博士が愛した数式』に主演されますが、きっかけは?
演出家・加藤拓也さんとの出会いです。彼との出会いは2018年かな。電話があって「一緒にやりたいんです」と言われました。じゃあ会おうと思い、吉祥寺の丸井の前で待ち合わせたら子供みたいな人が立っているから「君かい?」と聞いたら「そうです」と。その時、彼は24歳でした。
―そんな加藤さんと一緒に「やろう」となった。
喫茶店に入って話しているうちに面白そうだなと思って。突っ張っていないし謙虚だったし、人として何とも言えない感じるものがありました。20代の若い人が、当時70代の自分に声をかけてくれたのも嬉しかった。
そして、彼の書いた『今日もわからないうちに』と言う芝居に出演しました。それから僕が、この本(『博士の愛した数式』)を好きだと話したら、彼にとっては再演したい大好きな作品だと言うので、じゃあやろうということになったんです。
―作品の魅力は。
“記憶”というものにずっと興味がありました。忘れてしまっても、匂いのように残っているものもある。そんな“記憶”とは何だろうと思っていたんです。小川洋子さんの原作小説は、出版(新潮文庫刊、2003年)されてすぐに読みました。
映画化された作品も観たけど、自分が感じ取ったものとは違いました。でもそれは当然で、小説も演劇も解釈は自由です。今回の舞台もそうです。自分が感じたのとは違うものだし、僕は小川洋子さんの原作から加藤拓也さんが読み取った新しい作品に参加するつもりです。

―演出家でもある串田さんが、人に演出されるのはどういう気分ですか。
楽しいです。ものを作っている同士だからぶつかりもするでしょうけど、話をしながら受け止めていきたいです。加藤さんは僕の演出スタイルとは全然違うので、それを読み取ることが大切だと思っています。
―セリフの記憶はいかがですか。
ダメですね。自分が書くものは自分の生理に合っていますけど、他人が書いたものだと、どうしてこういう順序で話すんだろうとか、まず語順を自分に植え付けるところから始めるので大変です。
ものすごい量の数字が出てくるから、だんだん青ざめてきています。聞いても分からない数字があると思うんだけど、これはバレる、バレないとか分けて覚えるのもね。このとおり言わないとまずいだろうなあ(笑)。
―役者に大事なことは何ですか。
役者は“絵の具”ではなく“絵描き”であると思っています。大きく言えば絵描きは演出家なのだけど、それぞれが創作の絵描きであること。演出家である絵描きが「君は赤いからここにいる」と言ったら、オリジナリティを持った赤として、そこにいたいと思う。誰でもいいわけではなく、自分がやることの意味を探すことが大切だと思います。理解して、その絵の具をどう使うかを自分で決める、そうありたいなと思います。
感覚の話でいうと、吉田日出子さんがスゴかった。役の生い立ちや時代背景を説明しても「分からない」と言うけど、「日が差した光の中に、ひゅっと目に入る埃(ほこり)みたいに登場して」と言うと、がぜん目が輝いて「分かった」と、本当にそういうふうに出てくるの。カッコイイでしょ?
―今の演劇界をどう見ていますか。
小学校の頃、未来都市を描いていたのと似てはいるけど、これじゃないな…というような感じでしょうか。海外に憧れていた頃と比べて、今は日本も豪華になってたくさん劇場もできたけど、こういうことだったのかなと。演劇はもう少し一緒にやるものだったし、あまりにもシステマチックになっているような気もします。もうちょっと混乱したり道に迷ったりしながら作っていくものでもいい。怖いことではあるけど、偉大な失敗というのもあるんです。

■インタビュー後記
質問する度に「うんうん」と前のめりで聞いてくださった串田さん。人生の大先輩がこんなに楽しそうに聞いてくれたらこちらもうれしくなってしまい、気づけば“楽しい”という感情で埋め尽くされていました。80歳という年齢にも驚かされましたが、見た目もお話も肌も、すべてが若々しいのです。ご本人は「分からないよ」とのことでしたが、何をしても楽しそうな姿が印象的でした。理由はこの辺りにあるのでしょうか。
■串田和美(くしだ・かずよし)
1942年8月6日生まれ、東京都出身。1966年「自由劇場(後にオンシアター自由劇場と改名)」を結成。代表作に『上海バンスキング』『もっと泣いてよフラッパー』など。1985年「Bunkamuraシアターコクーン」初代芸術監督に就任(1996年任期満了)。『コクーン歌舞伎』を始め、『平成中村座』での歌舞伎演出も多数。2003年「まつもと市民芸術館」館長兼芸術監督(現在は総監督)に就任(『博士の愛した数式』を最後に退任予定)。『博士の愛した数式』は2/11~16、長野・まつもと市民芸術館小ホールにて、2/19~26、東京・東京芸術劇場シアターウエストにて上演。










