あの戦争の死者の気持ちを「代弁」できるのか? 思想家が綴った「声なき死者」への思い

夏は死者の「思い」をよく聞く季節だ。ある人たちは「国家のために亡くなった英霊」の思いを代弁し、ある人たちは「戦死者の悲劇」を雄弁に語る。
残された言葉や、遺書だけを頼りに戦死者の思いを語っていいのか。勝手に死者の代弁者になることはかえって彼らを冒涜するーー。1960年6月、「わだつみ会」(日本戦没学生記念会)の会報に一本のエッセイが寄せられた。
わだつみ会は戦後初期のベストセラーになった戦没した学生たちの遺文集『きけ わだつみのこえ』刊行を契機に集った平和運動団体である。
彼らの活動に本質的な批判を投げかけたエッセイの著者は、思想家・藤田省三(元法政大教授、2003年死去)。タイトルは「室町二丁目の戦死者」といった。
戦後を代表する政治学者・丸山眞男の門下生で「天皇制社会」の構造や「戦後精神」を鋭く分析した藤田が、なぜ「遺書」を頼った平和運動に批判的だったのか。彼の言葉から「声なき死者」を思うこと。その思想が見えてくる。
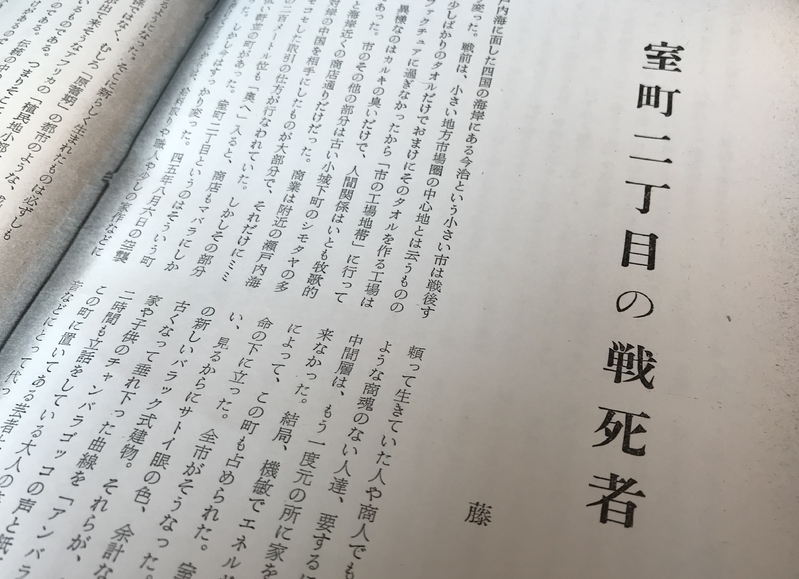
遺書を書き残した人の戦死だけが問題なのか?
わだつみ会は「再び戦争の悲劇を繰り返さないため、戦没学生を記念することを契機とし、戦争を体験した世代とその体験をもたない世代の交流、協力を通して戦争責任を問い続け、平和に寄与することを目的」とした組織である。
藤田は彼らの運動を「遺書集を平和運動に結びつけることだけに専念」するか、「逆に遺言を読んで感じ入ることばかりしている」と評した。
その行き着く先は遺書を頼りに、遺書を書き得た人の戦死だけを問題視することではないかと藤田は問う。
言葉を残さずに死んでいった人たち
彼が淡々と綴るのが、生まれ故郷である愛媛県今治市「室町二丁目」の死者の姿である。以下、エッセイに綴られたエピソードを抜き出しておこう。
室町二丁目はタオル産業で知られる今治市の奥にある「古い低い軒並みの町」で商店もまばらにしかない。そんな街が1945年8月6日の空襲ですべてが焼け、地区の若者は戦争で多くが亡くなった。
亡くなったのはいろんな職業を転々とできるような器用さを持った若者ではなく、自分の定職をもって、少しずつであっても良い日常を送るよう努力していくことしかできないような若者たちだった。
特攻隊で死んで行く前夜に……
例えば、洗濯屋の職人でやがては独立して立派な洗濯屋を持ちたいと思っていた「喜―さん」「利兄やん」、ちょっとズボラな「藤田の洲ちゃん」である。彼らは「誰一人として遺書や遺書らしい言葉を残さないで」20代前半で死んだ。
「喜―さん」は働くことが特に好きだったが、だからと言って「何かに成ろうという気持を持っていなかった」。いま風に言えば、上昇志向とともに意識高く職場を転々とするのではなく、自分のポジションで頑張ろうとするタイプだ。
「利兄やん」はビルマで戦死した。最後は脚気になり、ぬかるみを歩く行軍に堪えることができず、隊から遅れてしまいそのまま亡くなったという。
「藤田の洲ちゃん」は成績のいい弟「礼ちゃん」や従兄弟の「史朗さん」に囲まれながら、優秀な兄弟を嫉妬することも反感を持つこともなく、のんびりと「僕は(※階級が低い)一等兵がええんじゃ」と答える人だった。
「洲ちゃん」は1945年4月、特攻隊として死んでいった。最後の晩に開かれた送別会でも泣き出した友人を前に、「君たちが泣くと僕が困るじゃないか」と言ってたしなめた。
どこまでも自分のペースを崩さないタイプなのだろう。正装で特攻隊に行くとなっていたのに、「死ぬるのにいい服を着るのは勿体ない」と普通の服で行ったという。
総じて、彼らは社会で何かを成し遂げるという気力を持っていない。だが、「自足の精神においては非常に優れた人たち」だったと藤田は回想する。
もっと言えば、「進歩主義者でもなく又反動でもなく保守的な人達であった。生きようと努めるがどうしても駄目な時には運命と考えて静かに従う以外にする術を持たなかった」人たちなのだと。
「声なき死者」の声
彼はさらに筆を進める。
そんな彼らは「自分の死を或いは無意味を世に問おうなどとは思い付きもしなかった」。彼らは遺書などを残すこともなければ、遺言を託すこともなく、ただただ死んでいった。
なぜ藤田が「わだつみ会」のような平和運動に批判的だったのか。
藤田は彼らのような遺書を書き得なかった、いわば「声なき死者」を考えていたからこそ、遺書頼みの運動にはどうしても懐疑的な姿勢をとらざるを得なかったのだ。
彼もまた、敗戦直前の1945年2月〜8月にかけて陸軍予科士官学校に在籍していた。その時の校長は、無謀かつ杜撰な計画で多くの死者を出したインパール作戦の中心にいた人物だった。藤田自身もまた声なき死者になる可能性をリアルに感じていたのではないだろうか。
我々の言葉を死んだ人に押し付けていいのか?
彼はわだつみ会に対して、遺書を残さなかった戦死者の調査をしてみてはどうかと提言している。
それをせずに遺書集を単純に「平和運動」に利用したらどうなるか。藤田は辛辣に綴る。
《「死んだ人は語れないのだから我々が代って言う」という精神は必要だが、過ぎると我々の言葉を死んだ人に押し付ける。》
よく調べた上で、彼らが生きていたらそう言うであろうということを「丹念に探し出して」言うべきなのではないか。エッセイは強い言葉で結ばれる。
《探り当てる努力もしないで、勝手に代弁者になることは却って彼等を冒涜する。又死ぬ前の彼等の発言だけに陶酔して「彼等の戦後」を考えないことにも無論賛成はできない。》
死者を代弁する人たち
夏は死者を代弁する人たちが熱くなる季節でもある。
安易な代弁は藤田に倣って言えば、自分たちの思いを死者を利用して語っているにすぎない。都合よく死者の声を利用して、代弁者になることは「却って彼等を冒涜する」。
今の時代に残っている戦争体験の背後には、全国無数に存在する「室町二丁目」の死者がいる。言葉にできないまま亡くなっていた全国の「喜―さん」「利兄やん」「藤田の洲ちゃん」がいる。
語られている経験なんてほんの一部に過ぎず、あの戦争のすべてを語ってはいない。声にできないまま亡くなっていった死者の声を聞こうとすることでしかわからないことがある。
戦後73年に藤田の批判は極めて現代的な意味を持つ。いま必要なのは残っている声だけで分かったような気になってはいけないということ。無数の声なき死者の存在に敬意を払い、残された言葉がすべてではないと謙虚に受け止めること。これである。










