悲運の俳人、富田木歩の軌跡
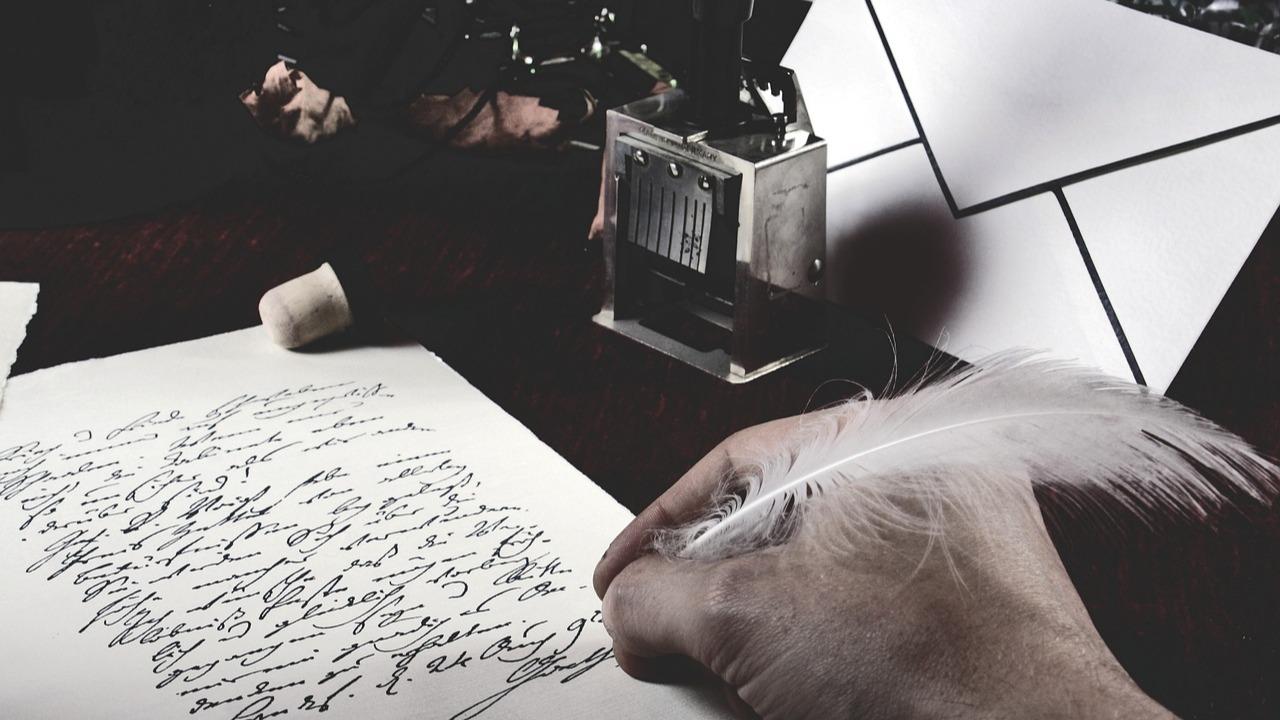
大正時代は文芸が盛んな時代であり、俳壇も非常に賑わっていました。
そんな大正俳壇には将来を待望視されながらも、歴史の闇に飲まれてしまった俳人がいます。
今回は悲運の俳人、富田木歩について取り上げていきます。
木歩の人生の始まりとその苦難
木歩、その本名を一(はじめ)と称したこの少年は、波乱と貧苦に満ちた家柄に生まれ落ちました。
向島小梅村にて代々百姓を営む旧家、富田家にとって、木歩の父・丑之助は厄介な存在だったのです。
丑之助は博打好きで派手好き。
祖父が築いた花街や資産は彼の手によって散財し、ついには1889年の大火によって、名だたる「富久」の屋号も灰となってしまいました。
その後、向島の一角で鰻屋「大和田」を細々と営む一家へと成り下がり、木歩はその次男として産声をあげたのです。
しかし運命は無情です。木歩は一歳の頃に高熱を患い、両足の自由を失ってしまいました。
丑之助の身勝手な消費は止むことがなく、一家の貧しさは増すばかりです。
木歩は幼いながらも、家の中で這いつくばりながら過ごし、養子に出されるはずだった約束も破られてしまいました。
さらに弟妹が次々に生まれ、その中には聾唖の弟もいたのです。
家は、生活をやりくりする余裕もないほど逼迫していました。
木歩は生まれ持った頭脳明晰を誇っていたものの、学校に通うことは叶いませんでした。
しかし彼は「いろはがるた」や「軍人めんこ」などの遊びを通して文字を学び、姉たちから教えを受け、独学で読み書きを覚えていきます。
巌谷小波の少年雑誌や「少年世界」などの本は、木歩にとって知識の扉を開く貴重な手引きだったのです。
木歩の家庭の困窮は、隅田川の決壊による大洪水によりさらに悪化しました。
この災難により、二人の姉は上州の遊郭へ売られ、木歩も玩具作りの内職を手伝うことになったのです。
その後も災難は続き、1910年にもまた大洪水が発生し、家は大打撃を受けました。
翌年には父も世を去り、家計は兄の金太郎に委ねられることになったものの、状況はますます厳しくなっていきました。
そして1913年、16歳になった木歩は「口減らし」のために、近所の友禅型彫師の店へ奉公に出されたのです。
しかし、彼の身体は四つん這いで移動するのがやっとであり、奉公先では陰湿ないじめも待ち受けていました。
そのような状況の中、木歩は半年足らずで奉公先を去り、再び家に戻るも、そこには彼の居場所がなかったのです。
大和田の店が立ち行かない中、木歩と母は叔母の家に身を寄せました。
その生活は決して豊かではなかったものの、叔母の善意によって支えられたのです。
この頃、木歩は自作の義足で歩こうと挑戦したものの、夢は儚く潰え、失意の中でさらに深い孤独と向き合うことになりました。
しかし木歩は、心の中で輝きを見出していたのです。
従兄弟の富田松雄が買い与えてくれた少年雑誌で、俳句という日本特有の詩形に魅了されました。
そして「吟波」という俳号で句を詠み始め、やがて「ホトトギス」や「やまと新聞」の俳壇にも投句するようになり、その才能は次第に認められていったのです。
厳しい日々の中で、俳句は木歩にとって唯一無二の心の拠り所となりました。
世間に背を向けられ、家族に疎まれても、彼は短い言葉に思いを込め、人生を詠むことで、少しずつその孤独を癒していったのです。
貧しいながらも充実していた青年期
木歩が臼田亞浪の俳句に心を寄せたのは、ただの偶然ではありませんでした。
「現実を詠む」と評される亞浪の句風に、自分の境遇に向き合い詩を生む道を見出したのです。
華美な自然を描くのではなく、足が利かない自分の目線から、周囲の貧しくも懸命に生きる人々や日々の些細な出来事を詠む。
木歩にとって、これは「歩けない自分で生きる」という覚悟そのものでした。
1915年、その決意を胸に木歩は「石楠(しゃくなげ)」へ句を投じ始め、親族の援助で母や弟妹たちと共に仲之郷曳舟通りの棟割長屋へ移り住みました。
長姉の富子は再び向島に戻り、妹の久子は小樽で商人のもとに身を寄せ、家族はそれぞれが生計を立てるようになっていたのです。
木歩と母は内職で人形の屑削りをし、さらに駄菓子屋を始めたものの、生活は一向に楽にはなりません。
そんな中、木歩は長屋の入口に「小梅吟社」の看板を掲げ、近隣の若者が集う場を作りました。
旧友の米造も上京し、米造には「波王」という俳号を授けたのです。
彼らはただの俳句仲間以上であり、木歩を「いっちゃん」と呼んで親しむ気さくな関係でした。
俳句を学ぶというよりは、駄菓子屋で藤八拳や花札を楽しみ、まき子や隣家の小鈴の美貌に見惚れては、若者たちは笑い声を上げたのです。
「小梅吟社」は青年たちの倶楽部として、日々賑わいを見せていました。
俳人で作家の吉屋信子は後年、木歩のことを「明朗で柔和、決して陰気ではなく、若い宗匠ぶりが自然と人を惹きつけた」と回顧しています。
不遇の中でも彼の目には希望が宿っていました。
長屋の六畳一間から溢れる若者たちの声、それは貧しいながらも暖かな暮らしを照らす木歩の青春そのものであったのです。
木歩と声風の出会い、そして友情の絆

1917年、20歳の新井声風は慶應義塾大学に通う学生で、父は浅草で映画館を経営する事業家で市会議員という、世間的にも恵まれた家庭の出でした。
一方、富田木歩は貧しさと身体的な制約を抱え、家族も離散しがちだったのです。
そんな彼が唯一の希望とする俳句の道で出会ったのが、声風でした。
声風は木歩の詠む俳句に以前から興味を持っており、同じ臼田亞浪の門下生として、いつか会ってみたいと願っていました。
そしてその年、声風は木歩の住む長屋を訪ねます。木歩の小さな棲居には「正岡子規遺稿」「荷風傑作抄」などが積まれ、俳句への情熱が溢れていたのです。
この出会いをきっかけに、異なる境遇ながらも二人は尊敬し合う親友となっていきます。
声風は、木歩に読ませるために「ホトトギス」「中央公論」などの新刊雑誌を持参し、知識を広げる手助けも惜しみませんでした。
声風の飾らない友情とその周囲の世界を通して、木歩は貧しいながらも新しい視点や芸術的な感覚に触れる機会を得たのです。
そんな穏やかな日々も束の間、木歩にとって重要な人物だった俳句の弟子、波王が隅田川で溺死する悲劇が起きました。
波王の訃報を伝えに、聾唖者である弟の利助が必死に長屋へ走って帰り、木歩と妹たちは悲嘆に暮れたのです。
この事件の後、木歩の妹たちも家を去っていきます。
木歩は次々に訪れる別離と喪失を、俳句という詩の中に昇華させるほかなかったのです。
やがて声風は木歩の才能を世に知らしめるため、自ら編集する同人誌「茜」で木歩の特集号を組むことを決意します。
その内容は、若き俳人としての木歩を「生活派の詩人」と評価し、各界から賞賛を集めました。
さらに声風は臼田亞浪に「石楠」での掲載を願い出たものの、亞浪の承諾は得られなかったため、別の俳誌「曲水」に掲載を依頼します。
こうして木歩の名前は俳句界で一気に注目を集めることになりました。
しかし、波王の死に続く不幸は木歩の身近にも次々と襲いかかります。
弟の利助は結核で、さらに妹まき子も病で亡くなり、最後には母も他界したのです。
木歩の心身はすっかり疲弊し、病がちとなりました。
友人たちはそんな木歩を支えるため、俳句界の著名人たちの短冊を集め、「木歩短冊慰安会」を企画し、彼の療養資金を募ったのです。
こうして集められた金額が木歩に渡されると、彼は涙をこらえきれず、友人の心意気に深く感謝しました。
このような支援を通して、木歩は一時回復し、再び句作に励むことができたのです。
そして、1923年、木歩は一人暮らしを始め、俳句三昧の日々を取り戻しました。
しかし彼と声風の友情は依然として続き、互いの俳句への情熱は変わらなかったのです。
その年の夏、友人たちが集まり、亡き波王を偲び、暗い隅田川の流れに短冊を浮かべる夜の船遊びを催しました。
その場に木歩も参加し、かつての弟子や妹たちの想いと共に、句作に生きる誓いを新たにしたのです。
だが、この穏やかなひとときも束の間、木歩と声風の運命には苛酷な試練が待ち受けていたのです。
関東大震災と木歩の最期

1923年9月1日、関東大震災が発生しました。
午前11時58分、凄まじい揺れが大地を襲い、下谷の凸版印刷にいた新井声風は、その衝撃に驚愕しつつ、浅草の自宅で家族の無事を確認したのです。
そしてすぐさま親友・木歩の安否が気にかかり、急いで彼の住む須崎町へと向かいました。
途中、「花勝」という小料理屋に立ち寄ると、木歩の姉・富子が動けない弟を案じていたのです。
声風が木歩の家にたどり着いたとき、そこに人影はありませんでした。
近くの土手に戻って探すと、桜の木陰にゴザを敷き、木歩が妹の静子や「新松葉」の半玉たち数人に囲まれて座っていたのです。
女手ばかりで動かすこともままならず、声風は木歩の帯で体を自分の背にくくりつけ、浅草の「花勝」を目指して逃げ出しました。
すでに火の手があちこちで上がり、土手の上は逃げ惑う人々であふれていました。
声風は痩せ細った木歩を背負いながらも、その重みと火災の混乱に苦しみ、途中で一度川沿いの鉄柵の前に木歩を降ろさざるを得なかったのです。
鉄柵を越えるには木歩を置いていくしか道がありません。
声風は、やむを得ず「木歩君、許して下さい」と告げ、木歩の手を握りしめたのです。
木歩は無言で声風の手を握り返し、声風は川に身を投げて泳ぎ出しました。
これが二人の今生の別れとなったのです。
数時間後、対岸にたどり着いた声風が振り返ると、向島の土手は火の旋風に飲み込まれ、あの場所にいた人々の姿は消え去っていたのです。
こうして木歩は26歳の短い生涯を終えました。
震災後、声風はその作品を集め続けました。
木歩の俳句原稿『すみだ川舟遊記』も焼失してしまったものの、声風はあらゆる雑誌に掲載された木歩の句や文章を丹念に収集し、整理していったのです。
その結果、1934年には『木歩句集』『木歩文集』が、翌年には『富田木歩全集』が出版されました。
木歩を悼む俳人たちは、震災から1年後、墨田区向島にある三囲神社の境内に木歩の句碑を建立し、「夢に見れば死もなつかしや冬木風 木歩」という句を刻んだのです。
この句碑の文字は臼田亞浪によるもので、木歩の親族や友人俳人たちが集まり、ひとときの祈りを捧げました。
さらに1989年には、木歩終焉の地である枕橋近くにも「かそけくも咽喉(のど)鳴る妹よ鳳仙花 木歩」の句碑が建てられたのです。
木歩の最期の地を訪れるとき、声風は「木歩をあの墨堤の地獄に残さざるを得なかった瞬間から、自らの詩魂は衰えた」と述べています。
その苦悩を抱えながらも、声風は木歩の句を伝え続け、後半生をかけてその業績を後世に残すべく尽力したのです。
震災によって肉親と家も失った木歩だったものの、その詩の魂は声風の手によって多くの人々に伝えられていきました。
今日も、9月1日近くの日曜日には小松川最勝寺で、木歩を偲ぶ会が営まれ、かつての俳友や後の世の俳人たちが集い、彼の句を詠み交わしています。
木歩の詩の魂は、声風によって今もなお生き続けているのです。
参考文献
花田春兆(1975)「鬼気の人-俳人富田木歩の生涯」こずえ社










