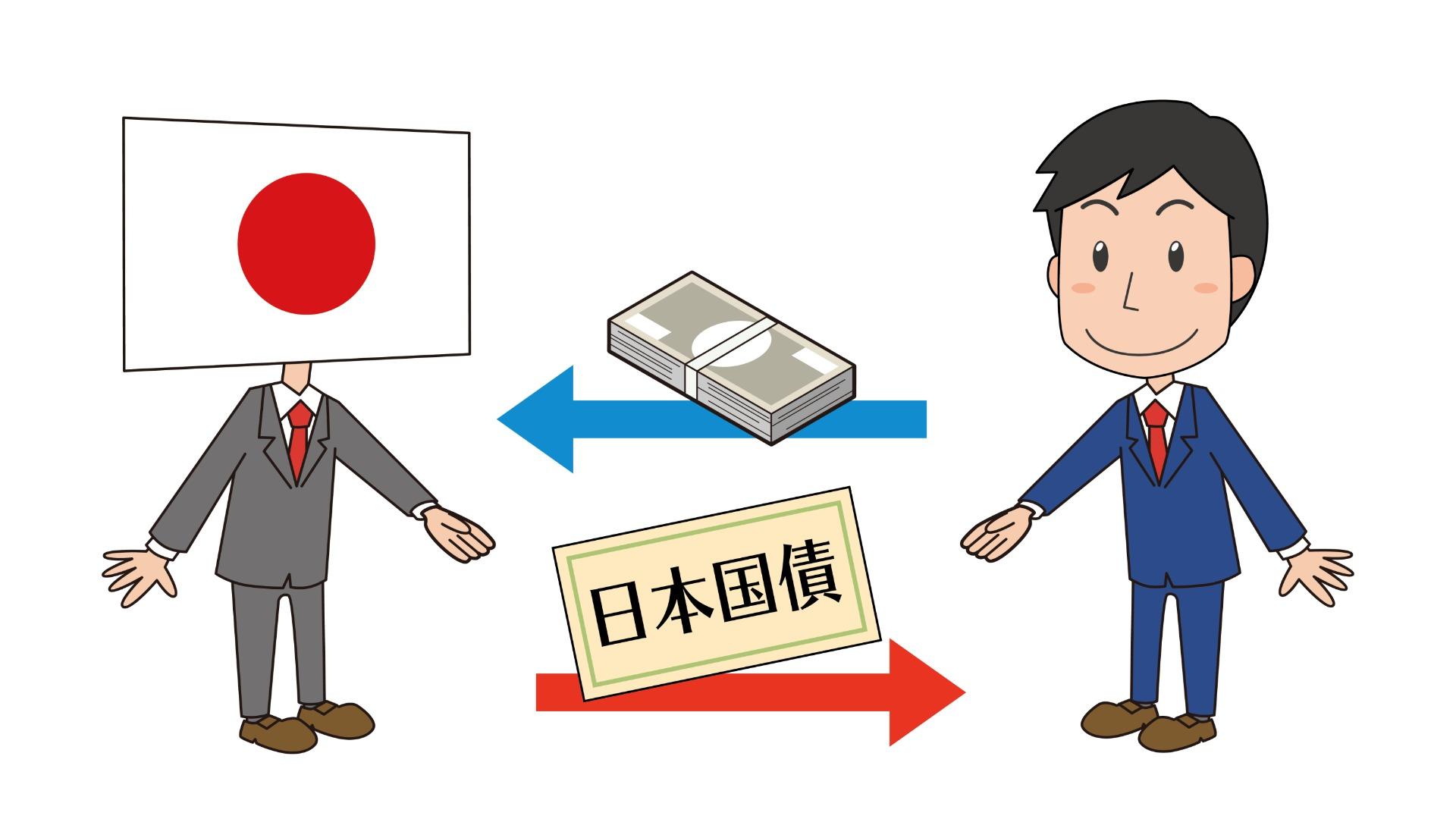地震予知も可能になる? 昆虫の耳とロボットをつなぐ実験にイスラエルで成功

イスラエルのテルアビブ大学で、死んだバッタの耳をセンサーとして使う実験に成功した。
死んだバッタの耳はロボットにつながれており、ロボットはこの耳を使って音を検出し、それに応じて反応したのである。
昆虫の耳を研究して、機能を真似した機械をつくるのではなく、死んだ昆虫の耳そのものを使ったところが面白い。
「生物のシステムを(人間の)テクノロジー・システムに統合するという、前代未聞の試み」と、ZME Scienceのサイトは報告している。
(注:バッタはlocustの訳。蝗害ではイナゴと訳すこともある)
「これまで科学者たちは、皮膚や筋肉の組織を機械に使用して、ある程度の成功を収めてきましたが、感覚器官にはありませんでした」。研究に携わった同大学のベン・マオズ博士は『The Times of Israel』に語った。
この実験は、生き物のパーツが、未来のマイクやカメラになるための道を開く可能性があるという。
マオズ博士は、さらに語る。
「生き物の感知能力は、人間がこれまでに作ったどの発明よりもはるかに優れていますが、この実験は、それを私たち人間の技術に統合することが可能であることを示しています」
「我々が実証した原理は、嗅覚、視覚、触覚などの他の感覚にも応用できます。
例えば、生き物の中には、爆発物や麻薬を検知する驚くべき能力を持つものがいます。生物の鼻を持つロボットを作れば、現在では不可能な方法で人間の命を守り、犯罪者を特定するのに役立つかもしれません。
病気を検知する方法を知っている生き物もいます。地震を感知できる生き物もいます。可能性は無限です」

どのような実験か
それでは、具体的にどのような実験なのだろうか。
バッタの耳は、体から取り外されたにもかかわらず、その機能は維持された。この器官に酸素と食物を供給する「イヤー・オン・ア・チップ(Ear-on-a-Chip)」と呼ばれる特殊な装置のおかげである。
出力に接続されたワイヤーによって、バッタの耳から電気信号を取り出し、増幅してロボットの処理装置に伝送することができる。
実験中、研究者たちが手で打った音を一回出すと、バッタの耳がその音を拾い、その信号がロボットに前進するように命令した。これは事前にプログラムされた指示である。同様に、二回手を打ったのを聞くと、ロボットは後方に移動した。
「聴覚を選んだのは、既存の技術と簡単に比較できるからです」とマオズ博士は言った。
そして博士は、同大学の動物学部で働く、バッタの専門家であるアミール・アヤリ教授と密接に協力した。
先立ってアヤリ教授の研究室では、バッタの耳を分離して、特性を明らかにすることに成功していたのだ。
アヤリ教授と研究者たちは、高跳びするバッタにそっくりなロボットを開発しようとしていた。いつか軍事や捜索救助活動で人間に取って代わることができると期待してのことだった。
生き物のシステムは飛び抜けて優秀
「バッタの耳は、マイクよりも優れているのだろうか? それは重要な問題ではありません」と、ZME Scienceのサイトの記者は書いている。
なぜなら、この研究の目的は、生物のシステムを、人間のつくるテクノロジーのシステムに統合することを可能にする、あるいはその逆を可能にすることで、私たちができることの限界を押し広げることだったからだという。
同記者は続ける。
ーーこのテクノロジーは印象的かもしれないが、それは10億年以上の進化の産物である生物のシステムに比べれば、何というほどのこともない。
人間の脳は、既存の世界では、最も複雑な情報処理装置であり、電球よりも少ないエネルギーしか使わない。
たった1グラムのDNAは、215ペタバイト(2億1500万ギガバイト)のデータを保存できる。
このように、生物学をテクノロジーのシステムに融合させることに大きな可能性があるのは、明らかであるーーと。
マオズ博士は言う。「生物のシステムは、電子システムに比べて無視できるほどのわずかならエネルギーしか消費しないことを、理解するべきです。それはミニチュア(小型)であるため、非常に経済的で効率的です」。
電子産業での開発が減る可能性?
マオズ博士は、生き物のパーツを使用する可能性は非常に高いため、ますます高度化する電子産業の開発を続ける必要性を、減らすことができるだろうと述べた。
それに、例えば蚊のような虫は豊富に供給されており、その使用は強い倫理的な反対意見を引き起こす傾向がないため、体のパーツのベストな供給源になるだろうと、示唆している。
「ロボット工学の分野で、はるかに面倒で費用のかかる開発を冗長にする(不必要にする)かもしれません」
マオズ博士(Ben Maoz)と、アヤリ教授(Amir Ayali)、Idan Fishel氏、Yossi Yovel教授らのチームは、査読付きジャーナル『Sensors』に成果の詳細を記した論文を発表した。