明智光秀や豊臣秀吉も行った兵糧攻め、城内で人肉も食す地獄絵図に…過酷な籠城戦4選
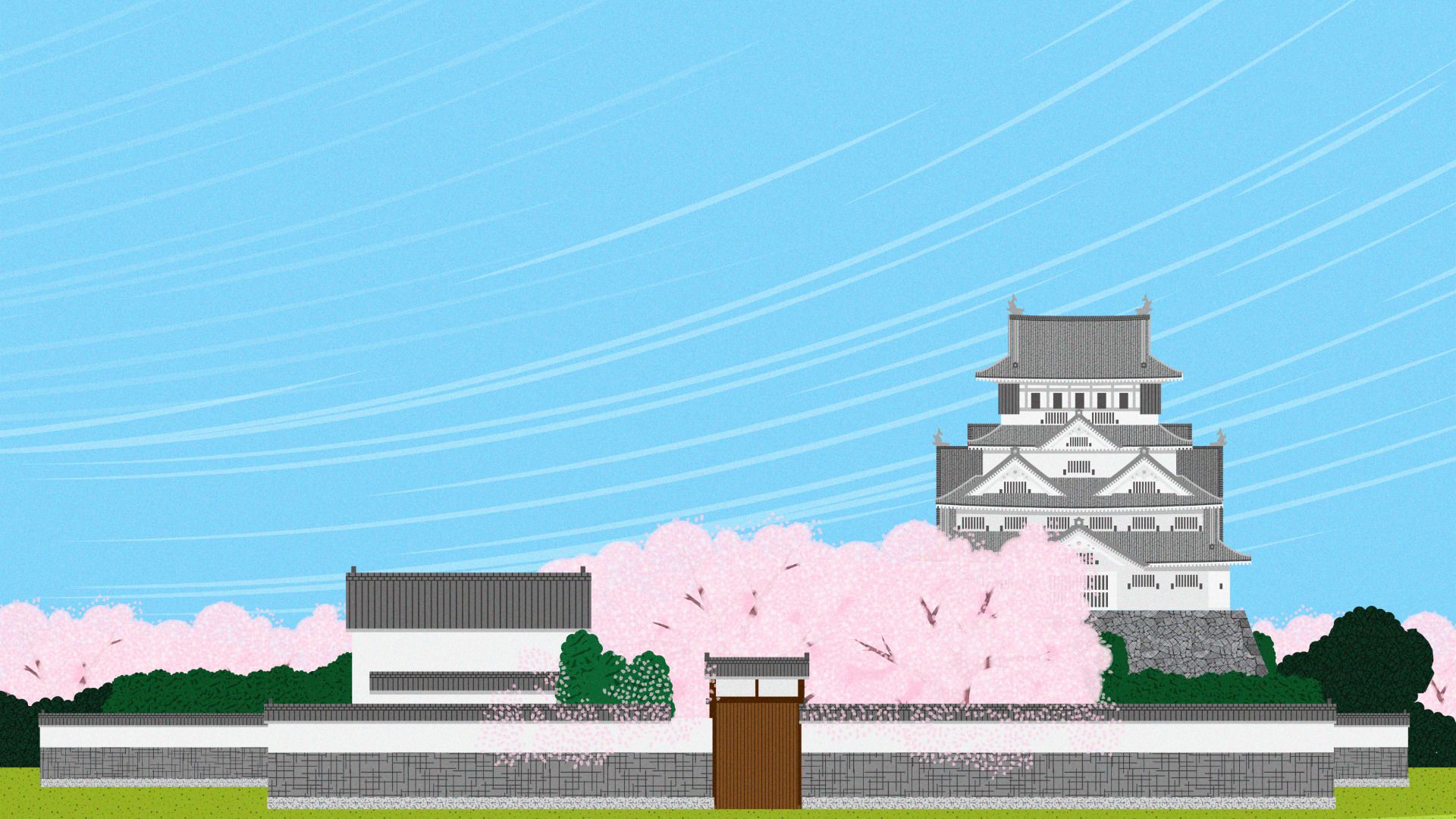
昔から「腹が減っては戦(いくさ)ができぬ」というが、まったくその通りで、兵糧がないと戦いに勝てるわけがない。兵糧攻めは「戦わずして勝つ」という戦いの王道で、敵が空腹で音を上げるのを待つ作戦だった。以下、有名な4つの籠城戦を紹介することにしよう。
■八上城の戦い〔攻城:明智光秀 VS 籠城:波多野秀治。兵庫県丹波篠山市〕
八上城の戦いは、天正6年(1578)3月~天正7年(1579)6月の間に攻防が繰り広げられ、明智光秀の勝利に終わった。とはいえ、光秀は開戦当初から積極的に攻めていたのではなく、織田信長から大坂本願寺を攻撃するよう命じられるなど、各地を転戦していた。
光秀が八上城の兵糧攻めを本格的に行ったのは、天正7年(1579)のことである。たちまち波多野氏が籠る八上城では、兵糧が尽きていった。光秀は八上城の周囲に付城を築き、城内に兵糧を運ばせないようにした。やがて、八上城内から助命と退城について、光秀に懇望してきたのである。
すでに籠城衆のうち4・5百人が餓死し、城を出て来た者の顔は青く腫れており、人間の顔をしていなかったという。光秀は近いうちに八上城を落城させ、1人も討ち漏らしてはならないと配下の者に命じた。
この惨状については『信長公記』も記しており、籠城した者ははじめ木の葉を食べていたが、のちには牛馬を口にしたという。そして、城から逃げ出した者は、容赦なく斬り捨てられた。こうして波多野氏は降参し、八上城は落城したのである。
■上月城の戦い〔攻城:毛利輝元 VS 籠城:尼子勝久。兵庫県佐用町〕
上月城の戦いは、天正6年(1578)4月~同年7月の間に攻防が繰り広げられ、毛利輝元の勝利に終わった。この前年、羽柴(豊臣)秀吉は毛利方の上月城を攻め取り、尼子勝久を城主とした。毛利氏はこれに対抗して上月城を奪還しようとすると、秀吉は織田信長の指示もあり、同城を見捨てた。
尼子氏は秀吉に見捨てられると、兵糧の供給が困難となり、徐々に尽きていった。同年5月、毛利方の吉川元長は書状の中で、尼子方の落人から聞いた話として、「上月城には水も兵糧もまったく残っていない」との情報を得ていた。吉川元春もこの情報を得ており、城を落とすべく、城の周りに堀や乱杭を築いた。
結局、上月城は毛利氏の兵糧攻めに耐えかねて、降参。尼子勝久らは捕らえられ、先頭に立って指揮していた山中鹿介は殺害されたのである。
■三木城の戦い〔攻城:羽柴秀吉 VS 籠城:別所長治。兵庫県三木市〕
三木城の戦いは、天正6年(1578)2月~天正8年(1580)1月の間に攻防が繰り広げられ、羽柴秀吉の勝利に終わった。合戦当初は別所氏が戦いを有利に進めたが、徐々に形成は逆転。秀吉が攻勢に転じ、三木城に兵糧が搬入できないように、交通路を遮断した。
三木城内では兵糧の補給路が絶たれたので、兵糧が底を尽くと、餓死者が数千人に及んだという。はじめは糠や飼葉(馬の餌)を食していたが、それが尽きると牛、馬、鶏、犬を食べるようになった。それだけで飢えを凌げなくなると、ついには人を刺し殺し、その肉を食らったと伝えている。
『別所記』には、最初は雀を取って口にし、のちに鼠や軍馬を食べようとしたが、それは叶わなかったと伝える。『別所軍記』には、ほかに犬、鶏、雉をも食べたと書かれている。とにかく口に入るものは、何でも食べたのである。その凄まじい光景は、後世まで語り継がれた。
■鳥取城の戦い〔攻城:羽柴秀吉 VS 籠城:吉川経家。鳥取県鳥取市〕
鳥取城の戦いは、天正9年(1581)6月~同年10月の間に攻防が繰り広げられ、羽柴秀吉の勝利に終わった。秀吉は開戦と同時に米を買い占め、兵糧の補給路を断つと、鳥取城内は飢餓に苦しんだ。城内に逃げ込んだ農民は、すぐに餓死してしまった。将兵も木や草の葉を食し、稲の根っこを口にしたという。
その情景は、「餓鬼のように痩せ衰えた男女は、柵際へ寄ってもだえ苦しみ、「ここから助けてくれ」と叫んだ。叫喚(大声を上げて叫ぶこと)の悲しみ、哀れなる様子は目も当てられなかった」という凄惨なものだった。
悲劇はさらに続き、「(秀吉軍が)鉄砲で城内の者を打ち倒すと、虫の息になった者に人が集まり、刃物を手にして関節を切り離し、肉を切り取った。(人肉の)身の中でも、とりわけ頭は味がよいらしいとみえて、首はあっちこっちで奪い取られていた」という惨劇が繰り広げられたのである。
◎まとめ
織豊期(16世紀後半)になると、籠城戦が盛んになった。攻める方は兵糧の補給路を断ち、周囲に付城を築いて兵糧攻めを行った。敵が餓死しても、一切容赦をしない作戦だった。むろん、現代においては、籠城戦どころか、戦争そのものがあってはならないことである。
【この記事は、Yahoo!ニュース個人編集部とオーサーが内容に関して共同で企画し、オーサーが執筆したものです】










