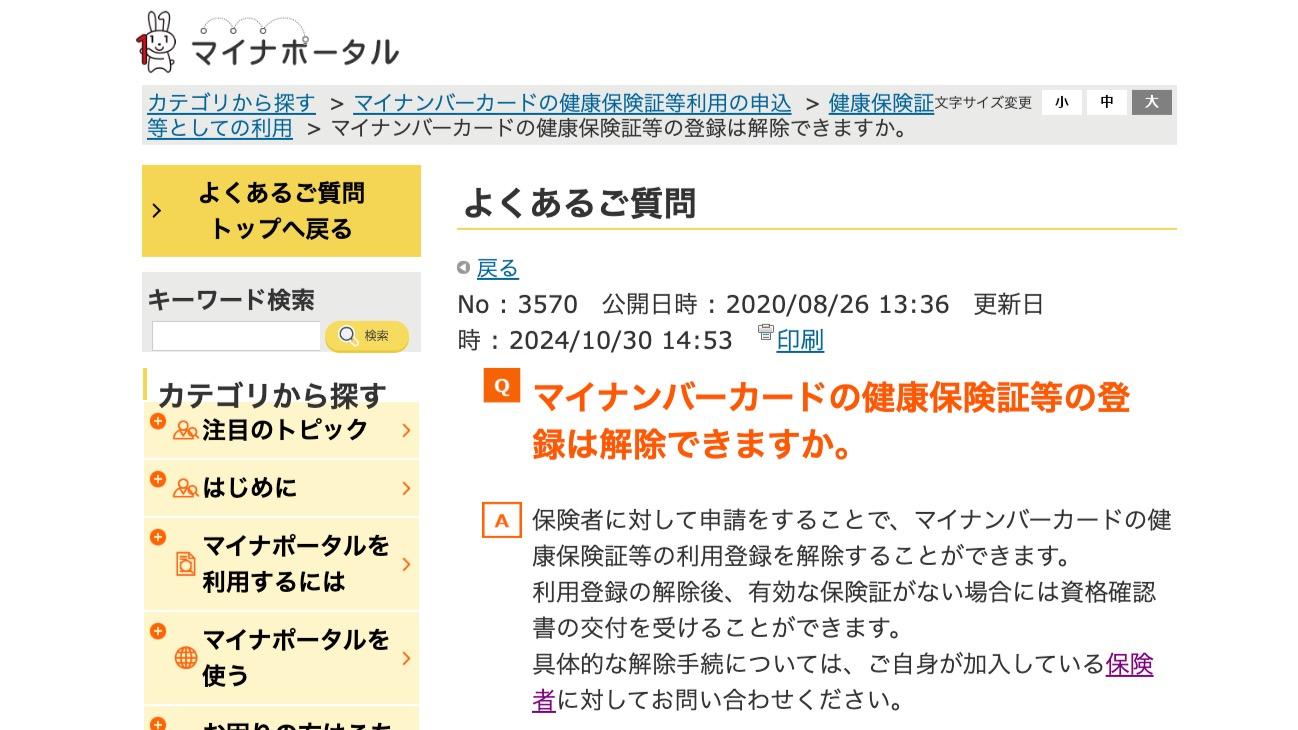桜の開花はヒカン桜で始まり、ソメイヨシノをへて、最後は千島桜

植物の発芽や開花、紅(黄)葉、落葉などの日を毎年同じ場所で標本を決めて観測することを植物季節観測といいます。また、動物の出現や渡り鳥の去来、鳴き始めなどを観測することを動物季節観測と呼び、季節の進み・遅れや農作業の適期などを知るのに役立っています。
植物季節観測で、世間の関心を一番集めているんは、冬の終わりを告げるとされる桜の開花です。
桜の開花
桜の観測は、有人の気象官署で行っていますが、その方法は、気象台の構内や近くにある公園等の桜の中から、その地域を代表する桜を標本木とし、この標本木で「5~6輪以上の花が開いた状態になった最初の日」が桜の開花日です。
また、標本木で「約80%以上のつぼみが開いた状態になった最初の日」が桜の満開日です。
しかし、桜の種類は、全てソメイヨシノではありません。
桜の標本木の種類
桜の標本木は、ほとんどがソメイヨシノですが、沖縄県と鹿児島県の奄美大島では「ヒカン桜」、北海道の稚内・旭川・網走・帯広・釧路は「エゾヤマ桜」です。
平成22年に測候所が無人化となり、桜の観測をやめるまで、北海道の根室は「千島桜」を観測していました。
これらの地域では、「ソメイヨシノ」が育たないからです。
このため、日本での桜の開花は、沖縄県の「ヒカン桜」で始まって、「ソメイヨシノ」をへて、北海道の「エゾヤマ桜か千島桜」で終わります。
桜の開花前線のスタートとゴール
一月中旬から下旬になると、沖縄県や奄美大島で桜開花のニュースが流れます。
今年は那覇で1月14日と、平年より4日早く開花を観測しました。
桜の開花日の同じ地点を結んだ線が桜前線ですが、島嶼部は線を引きにくいことなどから、桜前線のスタートは、九州、四国、本州で桜が開花した時からです。
今年の桜前線のスタートは東京で、3月21日に平年より5日早く開花しましたが、そのほかの地方では平年より遅く、次に開花したのは福岡で、3月25日になってからです。その後、桜前線は南から北へ、麓から山麓へと平年より遅く移動していましたが、暖かさから徐々に速度を増し、東北地方で平年より早くなって、北海道の函館に上陸したのは4月27日と平年より3日早くなりました(図)。

そして、5月14日、釧路地方気象台が平年より3日早く桜の開花を発表しました(昨年よりは4日遅い)。
これが全国の気象台が観測する桜の開花の最後です。
ただ、平成22年に根室測候所が閉鎖するまでは、多くの年で根室が桜の開花の最後でした。
ただ、根室測候所と同じ標本木を使って根室観光協会が引き継いで観測しています。
根室観光協会は、平年より3日早い5月15日に開花宣言をしましたので、これで、今年も桜前線が実質的にゴールし、全国で冬が終わりました。
北海道東部は、この頃、いろいろな植物が花を咲かせますが、「もんしろちょう」が見られるようになるなど、動物も活動を活発化します。長かった冬が終わり、ようやく春となったのです。
しかし、北海道東部は、過去には、6月になっても氷点下の日があるなど、冷え込む日がありますので、夏になってもストーブを仕舞うことはできません(表)。

根室の千島桜
近年は、都市化の影響で、東京などの大都市での桜の開花が早まる傾向がありましたが、全国のほとんどの測候所が閉鎖されるまでは、桜前線は愛媛県の宇和島測候所から始まって、北海道の根室測候所がゴールインでした。
日本の桜の開花は、沖縄のヒカン桜で始まり、ソメイヨシノをへて、最後は北海道の千島桜で終わることになります。
根室市の清隆寺は、千島桜の名所となっていますが、発祥の地とされています。
というのは、北方領土の国後島にあった桜が清隆寺に植えられ、綺麗な花を咲かせる変種が千島桜となり、これが根室測候所など、根室近辺に植えられ、広がったとされるからです。
千島桜は、しっかりと根をはり、厳しい寒さと強い風に耐えて咲く桜です。このため、樹高が1~5メートルと、他の桜に比べて背が低い桜です。
北海道東部の5月下旬は、桜の木の下で花見はできませんが、花びらを間近に見ることができる桜の季節の始まりです。