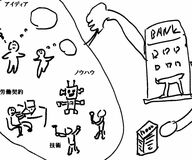ヒゲとルール~使用者は労働者にどこまで<身だしなみ>を求められるか

ヒゲでの不利益処分は違法との判決
大阪市の交通局の地下鉄運転士が、ヒゲをはやしたことで人事上の不利益処分を課され、その不当性を争った裁判の判決が先日出されました。
下記報道によると、大阪地裁は、判決で「ヒゲを生やしていることが人事評価で主要な減点要素となったのは、人格的利益を侵害するもので違法」として、大阪市に44万円の支払いを命じたとのことで、労働者側勝利となっています。
この判決に対し、吉村洋文大阪市長が、以下のツイートをしてプチ炎上しています。
市長という要職に就いているのに、報道を見て、条件反射のように「なんだこの判決」として、「控訴する」というのは、正直、冷静さを欠いた感情的な対応なので、「なんだこの市長」という感想しかありませんが、ここでは、この点はおいといて、「ヒゲとルール」について考えてみたいと思います。
ヒゲも服装も自由が原則!
まず、そもそもヒゲをはやすことはその人の自由である、というところからスタートする必要があります。
労働者は使用者と労働契約を結んでいますが、奴隷契約ではありませんので、私的な行為を会社から制限される理由はありません。これはヒゲだけでなく、服装、髪型、髪の色、ピアス、タトゥ、その他諸々全て同じです。
これが原則です。
しかし、いくら自由だとしても、その自由が仕事に影響してくる場合もあります。
その場合、私的な領域の行為であっても、使用者は、それを制限することになります。
その典型的な例が「身だしなみ」という理由での服装や髪型、そしてヒゲに対する制限です。
たしかに、接客業で接客側がヒゲをはやしていることについて、違和感を覚える人はいるでしょう。
他方、なんにも気にしない人もいるでしょう。
また、ヒゲといっても、無精ヒゲやきれいにそろえてはやしているヒゲで与える印象が違いますし、ヒゲをはやす部位や長さも、アゴヒゲ、口ひげ、大久保利通風、ちょびヒゲ、虎ヒゲ、関羽雲長風など、いろいろあります。それぞれ、印象が違います。
ヒゲと裁判例
では、裁判ではどのように判断されているでしょうか。
先の大阪市交通局では労働者側が勝利していましたが、ヒゲをめぐる裁判はほかにもあります。
ハイヤーの運転手の「口ひげ」
まず、ハイヤー運転手の「口ひげ」につき、運転手が、これを剃る義務がないことの確認を求めた事件があります(イースタン・エアポートモータース事件・東京地裁昭和55年12月15日判決)。
この事件では、乗務員勤務要領という社内ルールが定められており、そこに「髭(ヒゲ)を剃ること」と明記されていました。
裁判所は、ヒゲをはやすことは本来的には自由としつつ、労働契約では契約による制限もあり得るとして、口ひげについても、企業経営の必要性から合理的な規律を定めた場合は、労働者はこれに従う義務がある、としました。
そして、ハイヤーの運転手は、「多分に人の心情に依存する要素が重要な意味をもつサービス提供を本旨とする業務」だとして、「従業員の服装、みだしなみ、言行等が企業の信用、品格保持に深甚な関係を有するから、他の業種に比して一層の規制が課せられるのはやむを得ない」としました。
そして、社内ルールの「髭を剃ること」の「髭」について、次のように判断しました。
不快感を伴う「無精ひげ」とか「異様、奇異なひげ」を指しているものと解するのが相当である。
出典:前記判決文
異様、奇異なひげ・・・。現代で大久保利通や関羽のようなヒゲをはやすと、これに該当するのでしょうか。
いずれにしても、上記のように「髭」を限定解釈したことになります。
そして、裁判所は、「原告は髭を剃つてハイヤーに乗務する労働契約上の義務のないことを確認する。」との労働者勝利の判決を下しました。
郵便局員のヒゲと長髪
次にヒゲがらみでは、郵便事業者に勤務する労働者が、伸ばしたヒゲと長髪であることを理由に人事評価でマイナスに評価され、賃金カットされたり、上司らからヒゲを剃るよう執拗に求められたことに対して、損害賠償金等を請求した事件があります(郵政事業(身だしなみ基準)事件・大阪高裁平成22年10月27日判決)。
この事件では、使用者が「身だしなみ基準」というものを定めたのですが、その時点で、既に労働者は20年以上にわたってヒゲをはやして仕事をしていた、という事案です(長髪については10年以上)。
第1審の神戸地裁では、
使用者が,事業の円滑な遂行上必要かつ合理的な範囲内で,労働者の身だしなみに対して一定の制約を加えることは,(中略)企業としてのイメージや信用を維持するために直接に顧客や取引先との関係を持つ労働者に服装や髪型等の身だしなみを制限するなどの場合があり得るところである。
出典:神戸地裁平成22年3月26日判決
として、その上で、
ただし,労働者の服装や髪型等の身だしなみは,もともとは労働者個人が自己の外観をいかに表現するかという労働者の個人的自由に属する事柄であり,また,髪型やひげに関する服務中の規律は,勤務関係又は労働契約の拘束を離れた私生活にも及び得るものであることから,そのような服務規律は,事業遂行上の必要性が認められ,その具体的な制限の内容が,労働者の利益や自由を過度に侵害しない合理的な内容の限度で拘束力を認められるというべきである。
出典:神戸地裁平成22年3月26日判決
としました。
そして、被告における男性の長髪及びヒゲを不可とする基準について、
いずれもこれを長髪及びひげについて,一律に不可と定めたものであると解する場合には,被告に勤務する男性職員の髪型及びひげについて過度の制限を課するものというべきで,合理的な制限であるとは認められないから,これらの基準については「顧客に不快感を与えるようなひげ及び長髪は不可とする」との内容に限定して適用されるべきものである。
出典:神戸地裁平成22年3月26日判決
その上で、不当な評価によって下げられた賃金と慰謝料30万円を使用者に支払うよう命じる労働者勝利の判決を下しました。
これに対し、使用者は、大阪高裁に控訴しましたが、大阪高裁も神戸地裁の判断を支持し、控訴を棄却しました。
ちなみに、高裁段階で使用者は、「YAHOO!ニュース」のインターネットアンケートで25%が接客業でのヒゲに強い抵抗を感じるとの結果が出たことを証拠として提出したようですが、「接客業での「ひげ」に対して強い抵抗を感じるとした者の比率は25%にとどまっており,1番高い率の回答は「手入れの度合いによる」というものであって,むしろ,ひげに対する顧客の意識,好悪の感情も多様化していることがうかがわれるという見方もできる」と、逆に労働者に有利に使われてしまい、結果は覆りませんでした。
「身だしなみ」を理由に何でも求められるわけではない
これらのような判決の論理を見ると、冒頭のニュースであった大阪地裁の判決は、極めて妥当な判決であり、これに「なんだこの判決は」なんて言っている場合ではないことがわかります。
従業員の身だしなみについては、ヒゲのほかにも髪型などもありますが、基本は同じです。
いずれも個人は自由であるということを大前提に、職場においては私的領域をいたずらに侵害しない程度の最小限度の制限・規制であれば可能となります。
したがって、むやみな一律規制や硬直的な運用による労働者に対する不利益処分はトラブルの元となります。
大阪市には、ぜひとも冒頭の大阪地裁の判決を教訓にしてほしいですね。