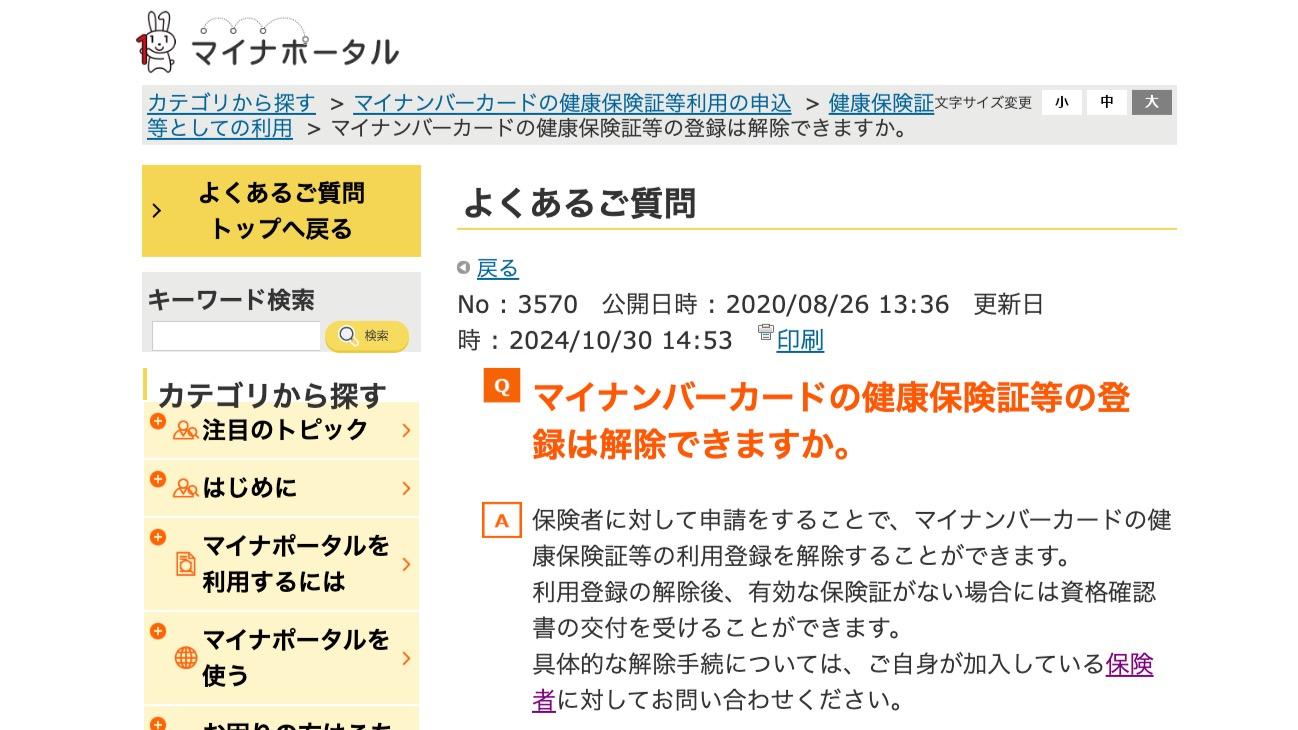ストレスと上手に付き合うためのリラクセーション法を心療内科医が解説

日常生活の中でストレスを受けることは避けられませんが、ストレスの程度が大きかったり、ストレスを受ける期間が長かったりすると、心や身体に影響してしまいます。
そのような時には、ストレスと上手に付き合うためにリラックスすること(リラクセーション)が重要になってきます。
リラクセーション法には、深呼吸や筋弛緩法など、さまざまな方法があります。
その中で、心療内科で広く用いられているものに自律訓練法があります。
自律訓練法を3ヶ月以上継続することで、約8割の人の症状が改善し、なかには睡眠薬や抗不安薬を減量できたり、中止できたりすることが報告されています(自律訓練研究. 16: 10-18, 1996)。
実際に自律訓練法を続けている人の多くが、これらの薬を減らしたり、やめたりすることができています。
そこで、今回は、リラクセーション法の一つである自律訓練法について解説します。
自律訓練法とは?
自律訓練法は、自己暗示によるリラクセーション法です。つまり、自律訓練法を行うことで、心と体をリラックスした状態にすることができます。
体がリラックスすると、筋肉の緊張がゆるみ、重力によって、手や足が重たく感じるようになります。
また、体がリラックスすると手先や足先の血流が良くなり、実際に手先や足先の皮膚の温度が上昇します。
そのため、逆に「手足が重たい」、「手足が温かい」と自己暗示をかけることによって、リラックスした状態に導くことができるようになります。
自律訓練法には、緊張の緩和や疲労回復といったさまざまな効果が出てきます。
自律訓練法の効果

自律訓練法は、病気の治療だけではなく、健康の維持・増進や病気の予防にも効果があるため、企業や学校でも取り入れられています。
自律訓練法がうまくできるようになると、手足の血流が増えて体の表面の温度が上がるだけでなく、リラックスした時に現れる脳波のα波が増えることが示されています。
これらの変化に伴って、不安・緊張の緩和、不眠の改善、疲労の回復といった効果が認められています。
このように、自律訓練法を行うことで自分自身の心や体をリラックスさせることができるようになります。
ただし、病気によっては、まれに状態を悪化することがありますので、病気で通院中の方は主治医に相談してから始めてください。
自律訓練法を行う場所と姿勢

自律訓練法を行う場合は、リラックスできる場所で行いましょう!
なるべく静かな環境で行い、家で行う場合には部屋の明かりを暗くして落ち着ける場所で行ってください。
姿勢は、あおむけに寝た状態、またはイスやソファーにすわった状態で行います。
イスにすわった状態でうまくできるようになれば、通勤・通学の電車の中や職場や学校のトイレの中など、いつでもどこでも自律訓練法を行うことができ、いつでもどこでもリラックスできるようになります。
また、ベルトや時計や指輪など体を締めつけているものは、ゆるめたり、はずしたりして行ってください。
自律訓練法の方法
まずは、軽く目を閉じて、全身の力を抜いて、ゆっくり深呼吸をしましょう!
深呼吸だけでも、リラックスできることも多いと思います。
その後、下記のリストの順番に、それぞれ3回ずつ繰り返して心の中で唱えてみましょう。
- 「気持ちが落ち着いている」
- 「右手が重たい」
- 「左手が重たい」
- 「両手が重たい」
- 「右足が重たい」
- 「左足が重たい」
- 「両足が重たい」
- 「気持ちが落ち着いている」
- 「右手が温かい」
- 「左手が温かい」
- 「両手が温かい」
- 「右足が温かい」
- 「左足が温かい」
- 「両足が温かい」
- 「気持ちが落ち着いている」
自律訓練法後の消去動作

自律訓練法が終わった後は、リラックスしている体の状態に意識を向けます。その後、しばらくして次に説明する消去動作を行います。
自律訓練法でリラックスした状態の時には、立った後にふらついたり、手や足など体に力がはいらない状態になってしまう可能性があるため、そうならないように、消去動作を行います。消去動作の方法は、以下の通りです。
- 両手を握ったり(グー)、開いたり(パー)を10回程度繰り返します。
- 両手をグーにしたままで、腕の曲げ伸ばしを10回程度繰り返します。
- 最後に背伸びをした後、ゆっくりと目を開けます。
この消去動作は、1回の自律訓練法を行ったら、その後に必ず行うようにして下さい。
自律訓練法の直後に眠る場合には、消去動作をしなくても大丈夫です。
日常における自律訓練法の練習
自律訓練法と消去動作を3回連続して行い、これを1セットとして、1日3セット程度(朝、昼、寝る前など)やってみるようにしてください。
最初のうちはあまり重たさや温かさを感じることがないかもしれませんが、あまり気にせずに毎日やってみてください。
うまくできるようになったら、左右別々の公式(「右手が重たい」、「左手が重たい」、「右足が重たい」、「左足が重たい」、「右手が温かい」、「左手が温かい」、「右足が温かい」、「左足が温かい」)は、省略しても大丈夫です。
また、「重たい」と「温かい」を別々に行わずに「重くて温かい」として一緒に行っていただいても大丈夫です。
実際の自律訓練法のやり方を動画を見たい場合には、下記のYouTube動画がおすすめです。
ストレス解消!リラックス効果!自律訓練法 ー実践編ー
まとめ

ストレスと上手に付き合うためにリラックスすること(リラクセーション)が重要になってきます。
そこで、今回は心療内科で広く使用されているリラクセーション法である自律訓練法について解説しました。
自律訓練法は、病気の治療のためだけではなく、健康の維持・増進や病気の予防にも効果があります。
自律訓練法を継続すると、うまくリラックスできるようになり、よく眠れて疲労が回復するといった効果がありますので、ぜひ試してみてください。