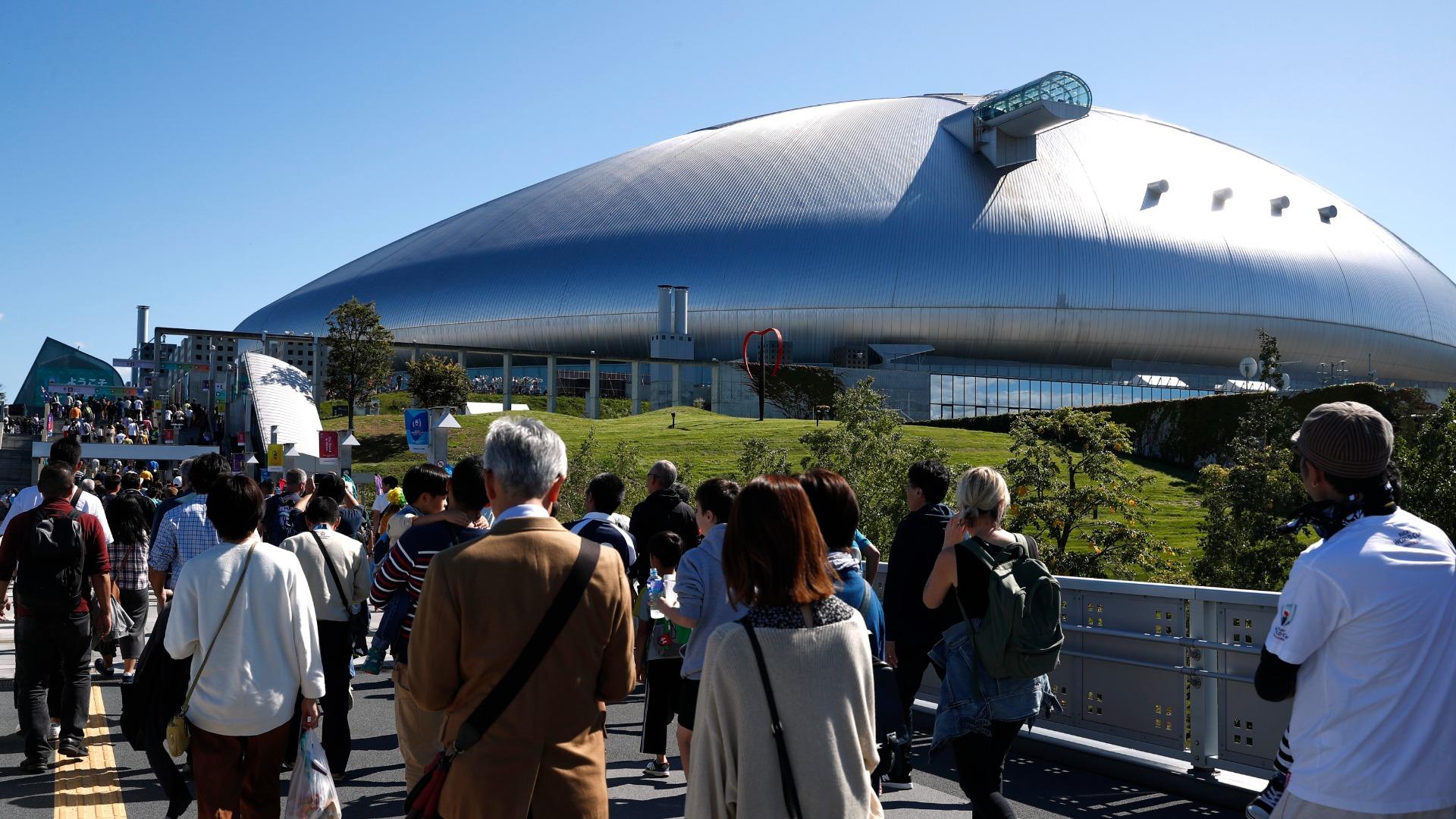【子育て】コロナ禍の子育てが子どもに与える影響!発達に遅れが…私たち親ができることとは。

こんにちは!さっこせんせいです☆
先日京都大、筑波大の研究チームが、コロナ禍で育った5歳児の発達に遅れが生じているという研究結果を発表しました。今回はそんな【コロナ禍の子育て】についてお伝えしていこうと思います。
コロナ禍の子育てが子どもに与える影響

コロナ前の娘の子育てと、コロナ禍での息子の子育て
娘が5歳の時、息子は1歳の時にコロナが流行し始めました。ですから下の息子は、子どもにとって大事といわれている幼児期を思い切りコロナ禍で過ごしたことになります。
上の子との子育ての違いは、私自身も強く感じていて、娘のときにはいつでも支援センターや公園に遊びに行ったり、ママ友との交流が多かったのに対し、息子の時には、緊急事態宣言が出ていたこともあり、あまり外出はせずに人との関わりが明らかに少なくなっていました。感染を気にするあまり、友達を遊びに誘うこともできなくなっていました。
コロナ禍で育った子には発達に遅れがある
冒頭でも少しお伝えしましたが、コロナ禍を経験した5歳の発達について調査したところ、コロナを経験していない5歳児のデータと比べるとその発達に4か月もの遅れがあったそうです。
うちの息子もまさに5歳児。そんな研究結果を耳にすると、とても不安になります。もちろん、全ての5歳児に当てはまるわけではないでしょう。しかし、そんなことを言われてしまったら、私と同じ様に不安になるママは多いと思います。
たしかにコロナ禍において、人との関わりが希薄になり小さいうちから学ぶべき「人間関係」の分野では劣る面があることは認めざるを得ないと思います。実際、発達の遅れが著しくみられた項目は「大人とのコミュニケーション」と「しつけ」だそうです。中には、テレワークになったママパパと、いつもよりも濃い時間を過ごすことができた子もいると思います。しかし、この研究結果を他人事として受け止めず、大事なのは、これから私たち親が子どもに何をしてあげられるかだと思います。
そこで、まずは子どものコミュニケーション能力を高めるために私たちができることをお伝えします☆
子どものコミュニケーション能力を高めるには

▷ままごと遊びをする
子どもはままごと遊びから社会性を身につけていきます。親子でするも良し!また、友達やきょうだいとままごと遊びを通してやりとりを学んでいきます。その中でもちろん思い通りにいかないこともあると思います。ママ役をやりたい子が2人いたり、おもちゃを取り合ったり。しかし、その経験が子どもを成長させてくれます。すぐに親が口を出すのではなく、少し様子を見てみてください。もしかしたら「ママ役は2人でやろう!」なんて風に、決まるかもしれません。
▷家族会議を開く
家族で話し合う場を設けてみてください。話す内容は自由ですが、子どもが小さいうちは「1日のうちで一番楽しかったこと」や「行ってみたい場所」なんかでもいいですね。食事をしながらの会話でも十分です。
大切なのは、人前で自分の意見を伝える経験です。自分が話したことに家族が反応を返してくれれば、人に話をすることが好きになります。また、人の話を聞く経験も大切ですから、子どもだけが一方的に話すのではなく、親である私たちの話も聞いてもらいましょう!
▷色々な家族と交流する
やはりコロナ禍では、ここの経験が少なかったと思います。自分の家族以外の人との関わりは、子どもにとってとてもいい刺激になります。当たり前だと思っていたことが当たり前ではなかったり、他の子との関わりは自分の思うとおりにいかないことばかりでしょう。
また、自分の親が他の大人と話している姿からも、コミュニケーションや関わり方を学んでいきます☆
わざわざ約束をしなくても、支援センターや公園などで出会った人たちと関わるだけでもOKです☆
▷スキンシップを大切にする
スキンシップをしてもらうことで、”オキシトシン”という愛情ホルモンが子どもの脳内に分泌されます。このオキシトシンが分泌されやすい脳になった子は、大人になった時も相手への信頼感や安心感が得られるようになり、周りの人と良好な人間関係が築けると言われています。安心感や信頼感を感じながら過ごしてきた子は、他人に対しても寛容にいられるようになるからです。
ただなんとなく子どもと関わるだけではなく、これらのことを意識していくと、子どものコミュニケーション能力を高めていくことができます!この4つのポイント、もしかしたらもうできているという方も多いのではないでしょうか?無理に学ばせることはなく、普段の何気ないやり取りや関わりの中で、コミュニケーション能力は高めていけるということです!
こどもの「しつけ」について

もうひとつ発達の遅れとして言われているのが「しつけ」の面だそうです。しかしここは難しいところで、「しつけ」は小さいうちからするべきだと唱える人もいれば、小さいころの「しつけ」は意味がない!という人もいます。
図書館や電車の中など、静かにしなければいけない場面では騒がないこと。テーブルの上にはならないこと。など、ある程度のルールは、親として子どもに伝えていく必要はあると思います。しかし「しつけ」となってしまうと、途端に子どもに厳しくなってしまうと思いませんか?
これは私の考えですが、コロナ禍で子どもと親が過ごす時間が多くなったことで、子どもがやるべきことも親が手を貸すようになったり、子どもが考える場面が少なくなったことも、「しつけ」の面での発達低下に表れているのではないでしょうか?実際に私がそうだったのです。子どもとの時間が増えたことで、自分自身もストレスが増え、できるだけ効率よく物事を進めたいがために、手を貸す場面が増えたり、私が決定したことを行うことが増えました。
私たち親が子どもにしてあげるべきことは、「しつけ」をしっかりする。ということよりも、「子どもが決める(考える)場面を増やすこと」ではないかと思います。何をして遊びたいのか、どんな服を着たいのか、こんな時どうしたらいいのか(どうしたいのか)など、子どもが自分で考え、決断する経験は、「しつけ」を、身につける部分でとても重要になってきます。なぜなら「しつけ」とは、本来親から教えてもらうばかりではなく、自分で気が付き身につけていくべきものだからです。
なんだか今回は堅苦しい話になってしまいましたね(汗)【コロナ禍で育った5歳児に発達の遅れ】なんて言葉を目にして、私自身ものすごく不安になったんです。私のように不安になったママたちが、『今後の関わり方でいくらでも挽回できる』ということを知って、少しでも安心してもらえたらと思い記事を書きました☆子どもは大人に比べて柔軟ですから、これからの私たちの関わり次第で十分変われます!
同じコロナ禍子育て真っ最中のママたち!一緒に頑張りましょうね☆応援しています!
最後までお読みいただきありがとうございました☆