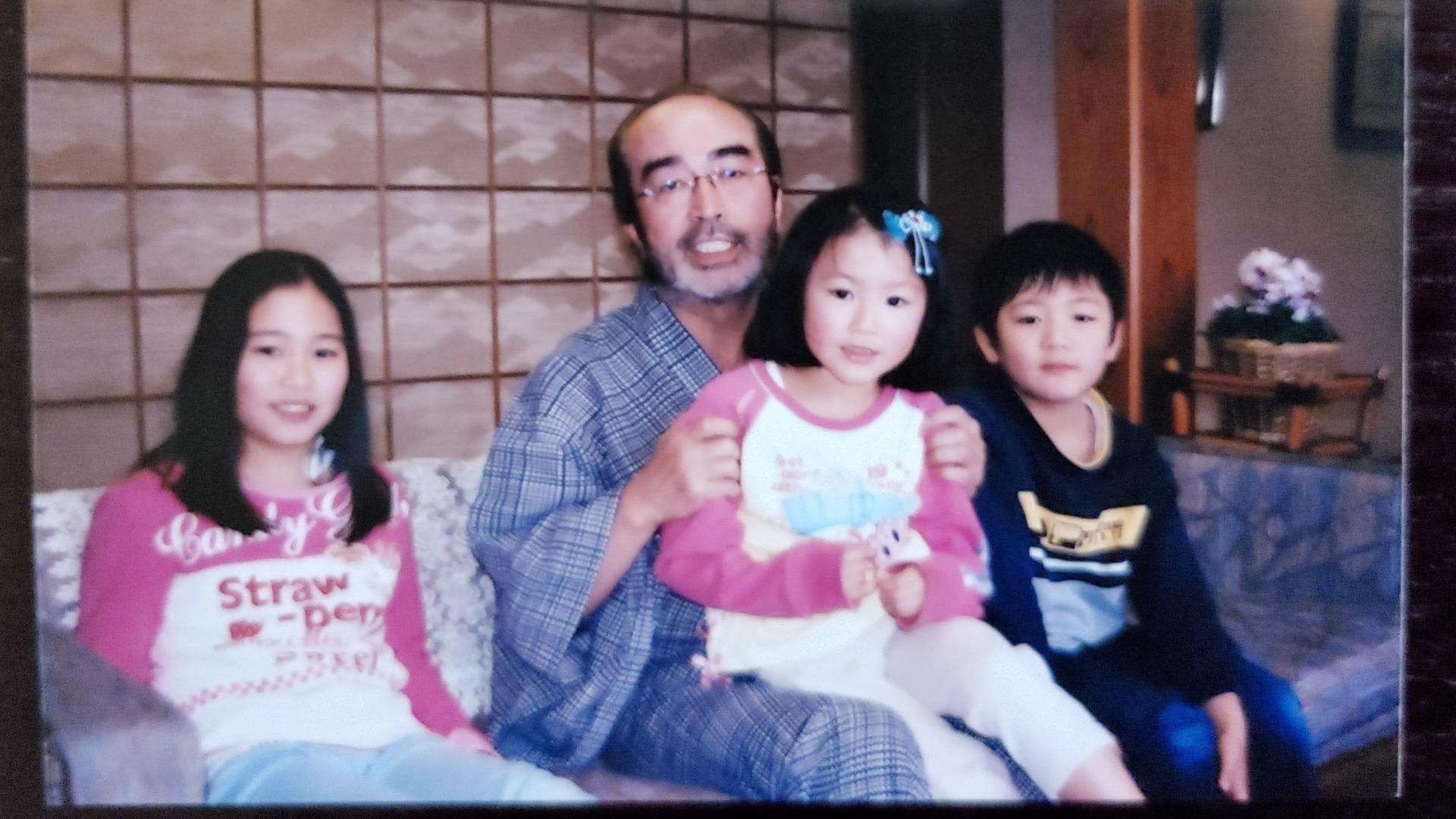「外国がルーツの子どもたちは日本語で日常会話はできても授業が理解できていない」に取り組む株式会社

「外国人の親をもつ子どもたちも、日本語がまったくできないわけではありません。普通の会話はできます。ただ勉強では、長い文章問題とか数学でも文章題などの細かなニュアンスがわからない。それで成績が良くならない。だからサポートが必要なんです」
そう語るのは、日本語が原因で学校の授業・生活に困難を抱える子どもたちを対象にした学習塾「トレボル NIHONGO教室」で教室長を務めている西涼光(にし・りょうこう)さんだ。その教室にかよっている中学生の女の子が、ちょうどやってきた。
「なぜ、この教室にかよってるの?」と訊くと、「学校の勉強についていけないから」と笑いながら答えてくれた。日本語での会話は、聞くことも話すことも問題ないようにおもえる。それでも、勉強にはついていけないのだ。
外国人労働者が増えている日本には、親と一緒に来日する子どもたちや、来日した外国人両親のあいだに日本で生まれた子どもたちが増えている。そういう外国をルーツとする子どもたちの多くは日本の公立学校にかよっているが、日常会話はできても授業にはついていけない場合が多いという。
家では日本語ではなく母国語で会話しているし、生活慣習も母国と同じようになる。日本人の家庭で育った子には当たり前でも、外国がルーツの子どもたちには理解できなかったりすることも多いのだ。授業を理解するには、そういった言葉や生活における細かいニュアンスが実は必要だったりする。
それが理解できないために、外国にルーツをもつ子どもたちは授業を理解するのに苦労することになる。そして、安易に「勉強の遅れた子」のレッテルを貼られてしまう。その困難を取り除くには、ただ言葉としての日本語を教えるのではない指導が必要になる。
「学校では先生次第ですね。意識が高くて、面倒見のいい先生に当たれば、日本語も上達するし、授業にもついていけます」
と、西さん。ただし、そんな教員にめぐりあえるのは、ごくごく稀だという。ただでさえ多忙をきわめている教員は、教室では少数にすぎない外国にルーツをもつ子どもたちに多くの時間を割くことも、気を遣うこともできないからだ。彼が続けた。
「だから、教室で放置されてしまっている子どもたちが少なからずいるのが現実です」
前回の記事でとりあげたような、特別支援学級にいれられてしまうケースまでもでてきてしまうことになる。現在の学校では、充分な対応ができていないのだ。
西さんは、高校を卒業してからの2年間、南米ボリビアで暮らしていた。「勉強にも身がはいらなくて大学進学も考えていない状態だったので、『南米に行ってこい』と父親にいわれたからです」といって、西さんは笑った。
ボリビアには西さんの伯母が住んでいた。最初は1~2カ月くらいの滞在予定だったが、スペイン語を勉強したりボランティア活動をしているうちに、2年が過ぎてしまったそうだ。
日本に帰ってから1年間の受験勉強期間を経て、西さんは横浜市立大学に入学した。そこで出会ったのが、外国をルーツとする子どもたちの学習支援をする学内サークルだった。卒業するまで、このサークルでの活動は続いた。
彼は卒業して一流といわれる企業に就職するのだが、6年後には辞めてしまった。「それまで長崎で働いていたんですが、教員資格をとるための勉強を横浜で始めました」と、西さん。
横浜に戻ってみて、そこで目にしたのは、外国をルーツにしている子どもたちが授業についていけない現状だった。西さんがいう。
「6年前と何も変わっていないんですね。ジッとしていられなくなって、この教室の起ち上げに加わりました」
「トレボル NIHONGO教室」は、「株式会社NIHONGO」が運営しており、今年4月にスタートしている。現在の生徒数は15人で、まだまだ黒字化には遠い。「わたしも無給です」と、西さんは笑う。
自治体として、外国をルーツとする子どもたちの学習支援をしていないわけではない。しかし、ほとんどがボランティア団体への「丸投げ」でしかない。補助金がついても、充分な人件費を払えるほどの額ではない。そこにかかわるのは、年配者が多くなってしまう。
「こういう活動を持続可能なものにしていくには、事業として成り立つようにしなければならないと考えています。だから、株式会社としてやっていく道を選択しました。どうビジネスモデルと確立していくか、まだまだ暗中模索ですけどね」
と、西さんは語る。外国人労働者の受け入れ拡大を目的とした新在留資格「特定技能」を盛り込んだ改正出入国管理法は、今年4月1日に施行された。ますます外国をルーツにする子どもたちも増えていくはずだ。わずかな予算でボランティア団体などに「丸投げ」する状態のままで放置するのか、国や自治体、そして外国人労働者を受け入れる企業の姿勢が問われている。