PM2.5と花粉症・ぜんそく・アトピー性皮膚炎の関係 - 最新の研究で明らかに
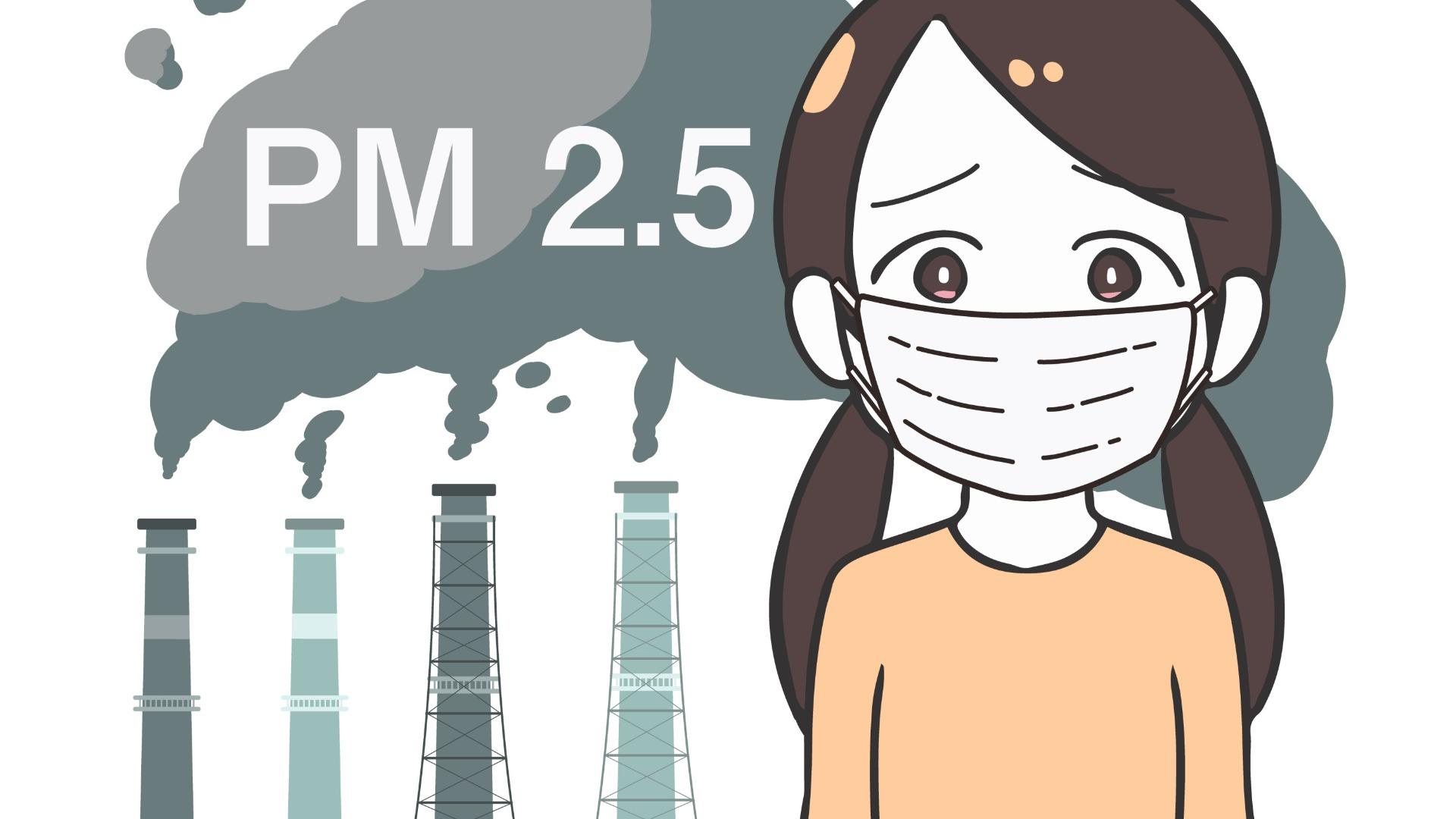
【大気汚染が引き起こすアレルギー性疾患の増加】
近年、花粉症やぜんそく、アトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患が世界的に増加傾向にあります。その原因の1つとして、PM2.5に代表される大気汚染物質の影響が指摘されています。PM2.5とは、大気中に浮遊する微小粒子状物質のうち、直径が2.5μm以下の粒子を指します。ディーゼル車の排気ガスや工場の煙など、人為的な活動により発生することが多いとされています。
PM2.5は非常に小さいため、肺の奥深くまで入り込み、ぜんそくや気管支炎などの呼吸器系疾患を引き起こすことが知られています。また、PM2.5に含まれる有害物質が皮膚のバリア機能を低下させ、アトピー性皮膚炎の発症や悪化にも関与していると考えられています。実際、大気汚染レベルの高い地域ほど、これらのアレルギー性疾患の患者数が多いことが疫学研究で明らかになっています。
【最新のAI技術を用いた大気汚染と疾患の関連性予測】
韓国の研究チームは、グラフ畳み込みニューラルネットワーク(GCN)という最新のAI技術を用いて、大気汚染物質の濃度からアレルギー性疾患の患者数を予測するモデルを開発しました。GCNは、地域間の相関関係を考慮しながら、時系列データから空間的なパターンを抽出することができます。
研究チームは、2013年から2017年までの5年間にわたる韓国の医療保険データと大気汚染物質の濃度データを用いて、花粉症、ぜんそく、アトピー性皮膚炎の3つの疾患について分析を行いました。その結果、PM2.5の濃度が高いほど、これらのアレルギー性疾患の患者数が増加することが明らかになりました。特に、花粉症との関連性が最も強く、PM2.5の濃度が上昇すると、1日後の花粉症患者数が有意に増加することがわかりました。
【皮膚疾患への影響と今後の課題】
今回の研究では、PM2.5がアトピー性皮膚炎の患者数にも影響を与えていることが示唆されました。PM2.5に含まれる有害物質が皮膚のバリア機能を低下させ、アレルゲンの侵入を容易にすることで、アトピー性皮膚炎の発症や悪化につながると考えられます。ただし、アトピー性皮膚炎は遺伝的要因や免疫異常など、複合的な原因で発症するため、大気汚染との因果関係を明確にするためには、さらなる研究が必要でしょう。
今回開発されたGCNモデルは、大気汚染と疾患の関連性を予測する上で非常に有用なツールになると期待されます。このモデルを活用することで、大気汚染の健康影響をより正確に評価し、適切な対策を講じることができるようになるでしょう。また、日本でも同様の研究が進められ、大気汚染対策と疾患予防に役立てられることを期待したいと思います。
参考文献:
- Jeon HJ, Jeon HJ, Jeon SH (2024) Predicting the daily number of patients for allergic diseases using PM10 concentration based on spatiotemporal graph convolutional networks. PLoS ONE 19(6): e0304106. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0304106










