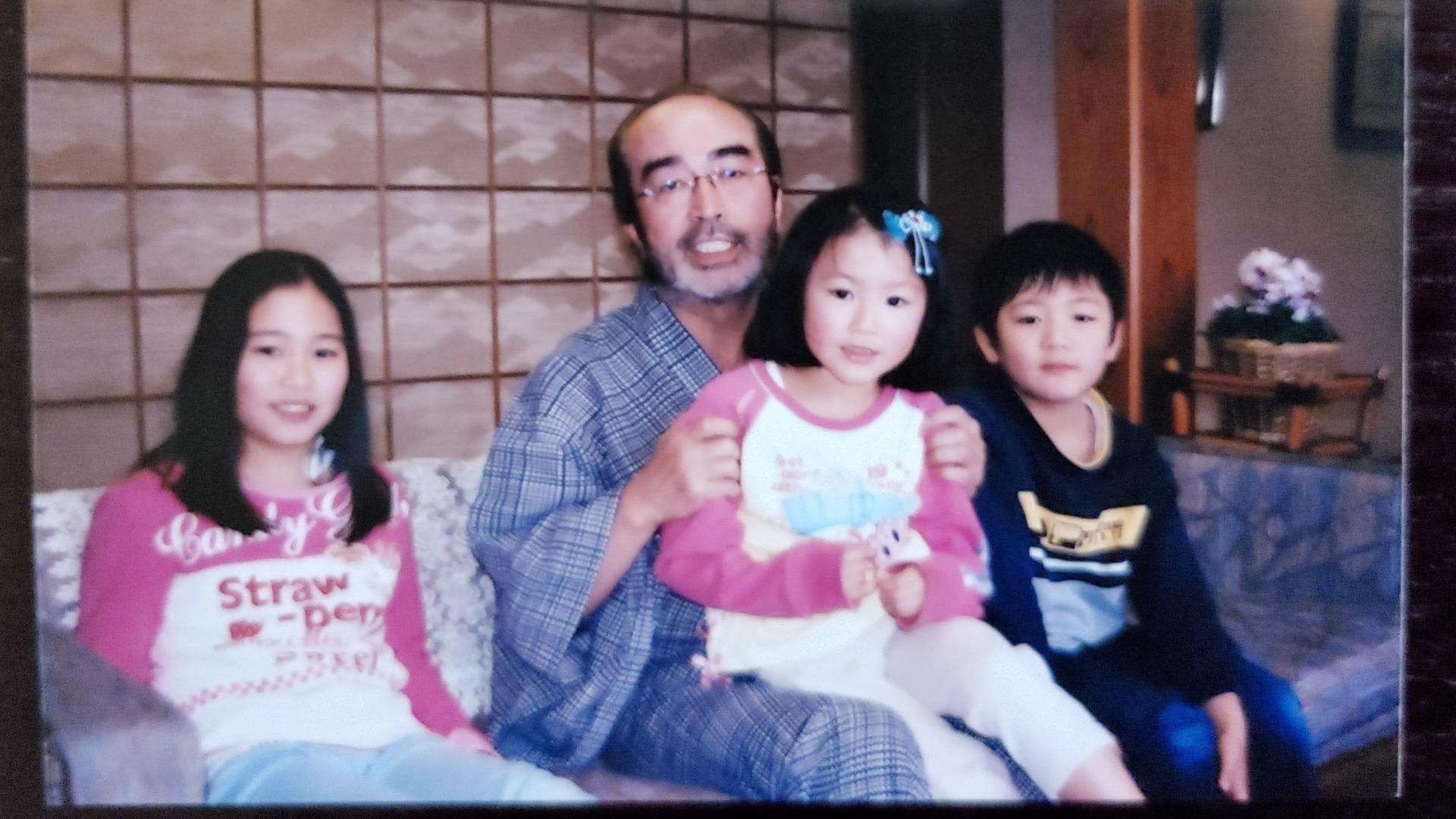樋口尚文の千夜千本 第65夜「だれかの木琴」(東陽一監督)
忘れ物を思い出したように、ひょっこり軽やかに撮る
映画監督のなかには永遠の現役投手のように錯覚してしまうタイプがいて、たとえば本格的な長篇を最後に撮ってからまる20年も経っていたマイケル・チミノにはまだまだ何かやばい作品をたくらんでいるのではないかと秘かに期待を寄せていた気がする。そうこうしているうちにチミノの訃報に接し、実はもう77歳だったのか、それなら動かざること山のごときチミノにももう少しじたばたして欲しかったと残念な気持ちを禁じ得ないのだが、そんな折からチミノよりも年長の東陽一がひょっこり新作を放ってくれたことを無条件に喜びたい。
気づけば40年近く前の作品である『サード』の鮮やかな記憶が薄れない東陽一も、今やなんと82歳。そのことを新作『だれかの木琴』の試写で知って、これまたしたたかに驚いた。次いで作品を観たらば、その軽快さにも輪をかけて吃驚させられた。同じ齢の時分の、晩年の黒澤明が、最後の最後まで「従来のクロサワ」を裏切らない重厚さと脂質を窮屈に「待望」されながら、(本人はもっと軽快でありたかったはずなのに)力んだ映画づくりに勤しむほかなかったのに対して、このたびの東陽一があらかじめ余計なことを望まれず「ひょっこり」新作を撮り、その内容が若々しく「軽やか」であったというのは、特筆すべきことだろう。
『だれかの木琴』は、ごくささやかでシンプルな物語である。郊外の新居に引っ越してきた主婦の小夜子(常盤貴子)は、その地ではじめて入った美容院のスタイリスト海斗(池松壮亮)になぜか心とらわれる。海斗も定番の営業メールを送っただけでやけに丁重な返事をくれる小夜子のことが、ちょっと変わっているかなと思いつつ、せっかく指名してくれるお客なので普通に接する。そうこうしているうちに、小夜子はじわじわと海斗に惹かれる度合いが増してゆき、急に彼の家を訪れたりして海斗の彼女のアパレル店員(佐津川愛美)を怒らせてしまったりする。
こう記すと小夜子は特異なストーカーのように思われてしまうかもしれないが、たとえば同様に女子のストーキング(正確には尾行だが)を描いた『二重生活』のように窃視する側される側に際立った情況がある訳でもなく、小夜子は何から何までごく普通の平凡な主婦で、その平凡さに救いがたい虚無を感じたりしているのでもない。典型的なサラリーマンである夫・光太郎(勝村政信)は仕事熱心で、適当に浮気めいたこともしているが、小夜子には優しいし、家庭を不安にさせるような要素は見当たらない。まあよくいそうなタイプの、平凡でつつましく常識的な夫にして父である。中学生のひとり娘かんな(木村美言)もまじめなよく出来たお返事のよい子で、これまたまるで心配がない。
すこぶる贅沢というのでもないが、そこそこ豊かで何不自由ない暮らしを、小夜子は営んでいる。常盤貴子の表情が絶妙で、格別に愉しく弾けている訳でも、暗く打ちひしがれている訳でもなく、ほどよい安楽さのなか、その手ごたえのなさによって生殺しにされているような表情を一貫させている。彼女がそこから解放されるのは、エンディングタイトルも終わった後のお茶目なサーヴィスカットの一瞬くらいで、全篇にわたって常盤貴子は、小さな幸せに馴致されてぼんやりしているような表情を欠かさない。この常盤の役づくりは、さりげなくもよくよく考え抜かれたものだが、それを東陽一一流の生成りのカメラアイで静かに凝視し続ける。
その世間的な尺度でいえば何不自由ない小夜子が、しかしなぜともなく(自分でも気づいていない心の渇きを癒すかのように)海斗とのふれあいに執心する。ここで面白いのは、東陽一がまるで小夜子をストーカー的に描こうとしていないことだ。小夜子は確かに海斗の家を急に訪れたりと奇妙な行動に走ったりもするが、常に分別をわきまえ冷静なのである。そんなふうでありながら、やはり心の空隙を埋めるために、つい海斗の力を借りてしまう。そういった小夜子の冷静さを海斗は繊細にキャッチしているので、もちろん面倒には感じながらも出来る範疇では彼女に応えてやろうとする。だからこそ海斗は小夜子が申し出た訳でもないのに、彼女を自室にあげたりしてかえって恐縮されたりする。だが、ここまで繊細に理解していない海斗のガールフレンドは、小夜子のことを欲求不満の不審な主婦とみなして抗議する。
面白いのは(あえてどんなことをするのかは伏せおくが)この事態を心配してヒステリックに小夜子の行状について抗議行動に出る海斗のガールフレンドのほうが、当の小夜子のストーカーめいた静かな彷徨よりもずっと極端に見えることだ。そして落ち着いた海斗はこの彼女の行動に失望を隠さないが、ここで気持ちをあらわに語り合うだけこの若い二人は見込みがあるかもしれない。逆に、妻の秘めたる行動について知るところとなった夫の光太郎は、小夜子のこの身の程をわきまえた小さな脱線が訴えるものを真摯に受け止めようともしない。「私の妻はそんなストーカーみたいなことをやるわけがない」と事実から目をそらし、妻のしたこと、つまりは妻に向き合おうとしない。勝村政信も、この妻への当たりは柔らかいが、外で適当にガス抜きして妻を放置気味の、よくいそうな夫像を好演しているが、この終盤の光太郎のありようにふれて、観客はなぜ小夜子が海斗との交流に走ったのかという理由がはっきりと見えてくることだろう。
東陽一の愛すべき佳篇のひとつに川上麻衣子主演の『うれしはずかし物語』があるが、あの作品でも寺田農と本阿弥周子のベテラン夫婦がそれぞれこっそり愛人とつきあっていて、なんとなくそれを互いに察知してはいるのだが、阿吽のごときすっとぼけた呼吸でまずいところにはふれずに夫婦関係の破綻を除けてまわるところが笑わせたが、ああいう大人の味を出すほどには今回の小夜子夫妻は泥臭い関係性が薄く、それぞれ孤立しているように見える。そういう点で、『だれかの木琴』は『うれしはずかし物語』のような艶笑コントにはならないのだが、東陽一はこのどこか未成熟でぎくしゃくした夫婦像を、優しい視線のメルヒェンとして軽やかに描いてみせている。
かつて五木寛之は、今の社会は人間が何か愁いに沈んでリカバリする自然な過程を許容せず、なんでも「鬱病」のレッテルを貼って無用の投薬を施しては余計に症状を悪化させると語っていたが、今作の東陽一も小夜子のことを終始全く普通の主婦として描いており、そんな彼女が空虚な気持ちを修復するために(いけないことと自覚しながら)ついつい海斗に接近してしまうことなど大げさに「ストーキング」呼ばわりすることでもなかろう、という構えに見える。そして東は、小夜子のリカバリ行為を優しく、泰然としたまなざしで見つめおおせる。
羽仁進や黒木和雄ら異才を続々輩出した岩波映画製作所の出身である東は、監督としての出発当初は『沖縄列島』『やさしいにっぽん人』『日本妖怪伝・サトリ』などの作家的なドキュメンタリー、劇映画を経て『サード』で華々しい評価を集めるまでかなり作家的なタイプの監督と目されていたが、以後数々の商業作を任されてからは実にさまざまな企画を手がけ、しなやかにそれらの映画のヒロインたちの粋をすくいあげてきた。アート作品と見なされた『サード』にあってさえも、まだ無名に等しかった森下愛子というヒロイン像が鮮やかな自然体の視線で描かれて印象的だったが、以後、『もう頬づえは着かない』の桃井かおり、『四季・奈津子』『マノン』の烏丸せつこ、『ラブレター』の関根恵子、『ザ・レイプ』の田中裕子、『ジェラシー・ゲーム』の大信田礼子、『セカンド・ラブ』の大原麗子、『湾岸道路』の樋口可南子、『化身』の黒木瞳、『うれしはずかし物語』の川上麻衣子・・・と東陽一はヒロインを静謐に見つめる作家という立ち位置をじわじわと築き上げ、それは世紀をまたいで『わたしのグランパ』の石原さとみ、『酔いがさめたら、うちに帰ろう。』の永作博美、そして今作の常盤貴子へと脈々と更新されてきた。
80代の名匠ともなればただでさえ自在な身動きのきかない立場になりそうなところを、東陽一がこうして多彩な企画との出会いを「ひょっこり」愉しみながら、相変わらずの「軽やかさ」でそのヒロインの魅力を見つめている、というのは実に望ましきことである。ちなみにヒロインである常盤貴子のことばかり記してしまったが、小夜子を引き立たせ、リアリティを持たせる本作のエンジンである海斗役の池松壮亮の職人的に練られた演技もさすがで、それを眺める東監督の満足が伝わってくるようであった。