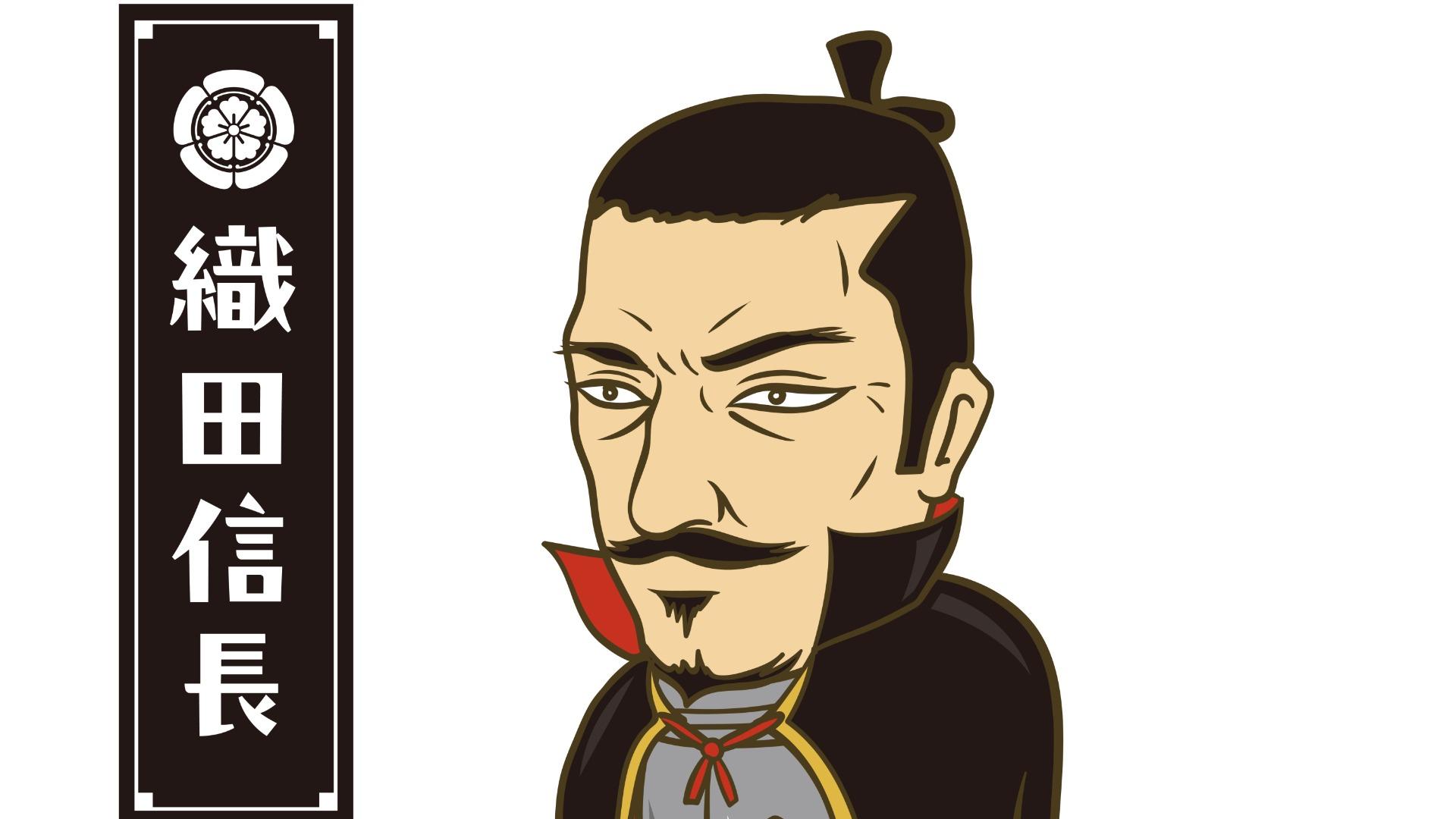朝露踏んでも地方病、地方病と人々の戦い

人類の歴史は病気との戦いの歴史と言っても過言ではありません。
日本においても甲府盆地にて地方病が蔓延しており、地方病との戦いは山梨県の歴史に大きな比重を占めているのです。
この記事では地方病との戦いの軌跡について引き続き紹介していきます。
朝露踏んでも地方病
日本住血吸虫の中間宿主がミヤイリガイであると解明されたことで、その生息地が地方病の流行エリアと完全に一致することが判明しました。
これにより、ミヤイリガイが生息する場所はそのまま地方病の有病地とされ、山梨県では1933年に甲府盆地の10,023ヘクタールが初めて地方病有病地として指定されたのです。
しかし、その後の調査により有病地の範囲はさらに拡大し、1935年には19,635.5ヘクタールと、広範囲にわたって指定されました。
特に有病地の中でもミヤイリガイの生息密度が高い場所は、甲府盆地の西部に集中しています。
西側に位置する釜無川沿岸は特に生息密度が高く、反対に笛吹川沿岸や荒川周辺では比較的密度が低かったと言われています。
この地域では、ミヤイリガイの密度が非常に高く、一部では1平方メートルあたり100匹以上が採取されるほどです。さらにひどい地域ではミヤイリガイが何層にも重なり、草屋根や窓枠にまでびっしりと群がることもあったと伝えられています。
このように、ミヤイリガイは水中だけでなく陸上にも生息し、広い行動範囲を持っていました。
そのため、草むらを素足で歩いただけで感染の危険があり、「朝露踏んでも地方病」という言葉が甲府盆地の農民の間で生まれたほどです。
感染リスクが高く、予防が困難な状況は、当時の農民にとって恐怖の対象となっていました。
しかし、ミヤイリガイ撲滅運動の成果により、有病地の指定面積は徐々に減少しました。
1960年から1974年にかけて、3回にわたり有病地の指定が解除され、1977年には指定面積が約半分にまで縮小されたのです。
ミヤイリガイを一匹残らず駆逐せよ!

ミヤイリガイが日本住血吸虫の中間宿主であることが解明されると、「地方病の撲滅はすなわちミヤイリガイの撲滅である」という共通認識が地域に広がりました。
1914年、土屋岩保は中巨摩郡国母村で初めて硫酸を使った殺貝実験を行い、以後さまざまな方法が試みられましたが、
労力や経費に見合った決定的な方法はなかなか見つけられなかったのです。
その中で、地域住民が自発的にミヤイリガイを拾い集める活動が始まりました。「ミヤイリガイをなくせば地方病はなくなる」という思いから、女性や子供たちまで動員され、箸を使って小さなミヤイリガイを一匹ずつ集めるという、気の遠くなるような作業が行われたのです。
1917年から8年間にわたり、この活動は続けられ、合計で約96俵分ものミヤイリガイが採取されました。
しかし繁殖力の強いミヤイリガイの完全駆除は難しく、さらなる有効な撲滅方法が求められたのです。
1924年、内務官僚出身の本間利雄が山梨県知事に就任すると、地方病撲滅活動に新たな動きが起こりました。
本間は広島県での経験をもとに、生石灰を利用した殺貝方法を山梨県でも導入しようとしたのです。
この方法は、京都帝国大学の藤浪鑑が考案したもので、生石灰を用いることでミヤイリガイの神経系統を麻痺させ、24時間以内に90%以上を駆除することができるというものでした。
しかし、山梨の有病地は広島と比べて16倍以上の面積を持つため、生石灰の散布作業は容易ではありませんでした。
それでも、地域住民の強い願いと協力により、1925年に『山梨地方病予防撲滅期成会』が発足し、生石灰の散布が開始されたのです。
この活動は、行政と地域住民が一体となって進められ、寄付金の割合が予算の8割を占めるなど、住民の熱意が伺えます。
こうして、行政と地域住民によるミヤイリガイ撲滅活動は長期間にわたり継続されました。
石灰散布から始まり、アセチレンバーナーによる火炎放射、天敵を用いた捕食、PCPによる殺貝、用水路のコンクリート化など、あらゆる手段が試みられ、地方病の根絶という目標に向けて、世代を越えた取り組みが続けられたのです。
最終的に、この活動は地方病の終息を迎えるまで続けられました。