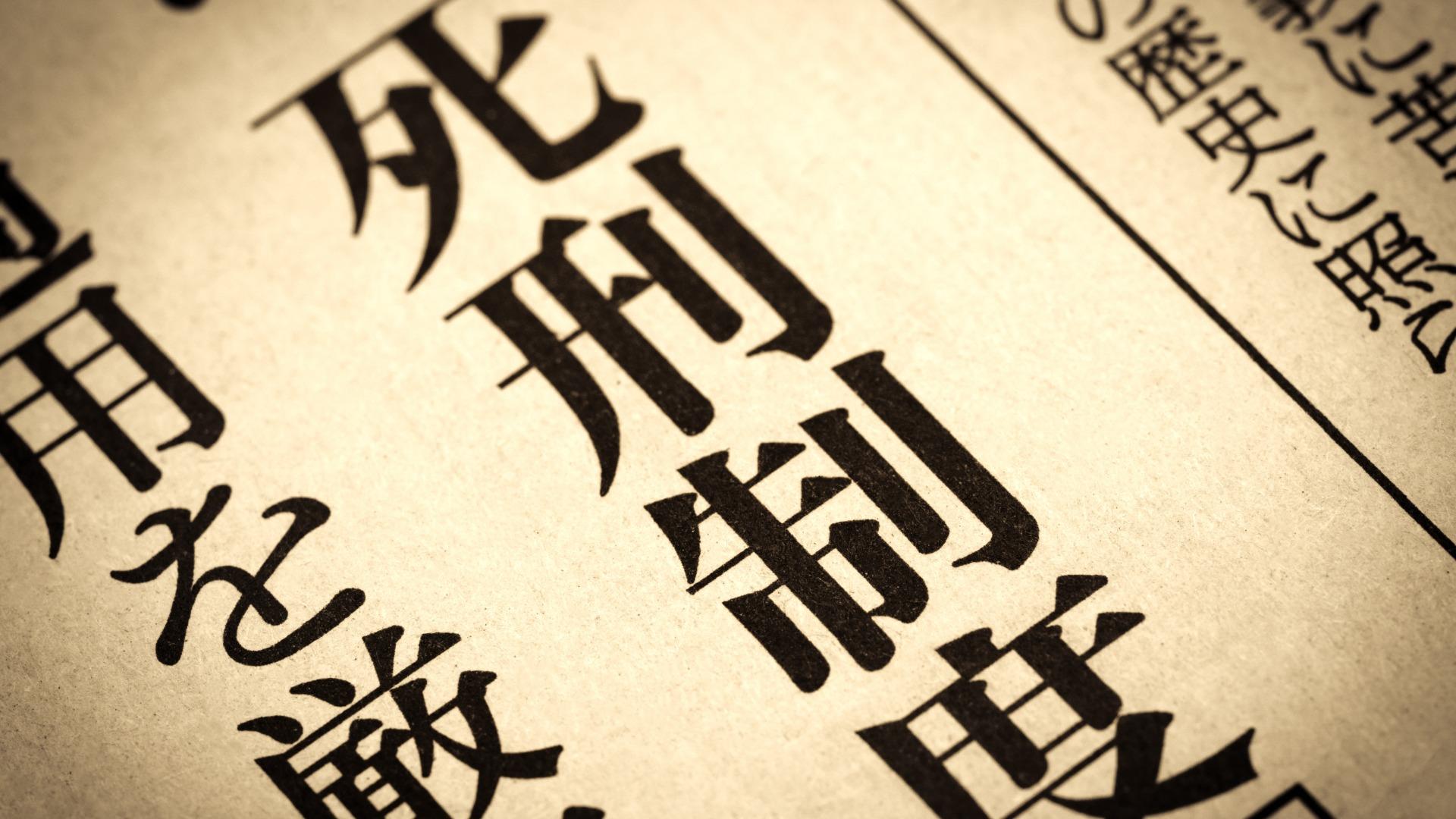「小学校のクラス分けに影響大」保育園や幼稚園から学校に共有する情報とは?要注意保護者情報も

現役保育士(幼保英検1級)です。
保育園や幼稚園を卒園して、小学校に入学すると今度はクラス編成や席次が気になりますね。
前回の記事では、小学一年生のクラス分けにまで大きな影響を及ぼす幼保小連携と要録の仕組みについて紹介してきました。
「小1のクラス分けや席次は保育・幼稚園からの情報で決まる」幼保小連携とは?現役保育士が紹介
制度で定められた書類である、保育所児童保育要録(幼稚園幼児指導要録・幼保連携型認定こども園園児指導要録)以外にも、保育園や幼稚園からは様々な情報が小学校に提供されます。
今回は、要録以外に小学校に提供される情報について紹介していきます。

保育園や幼稚園と小学校との意見交換会
卒園が迫ると年長クラスの担任の先生は大忙しです。
要録以外に提出を求められている情報を持って、園児が入園する予定の小学校を訪問するなどの仕事が加わります。
要録という書類だけを見ても子どもたちの個性については伝わりにくいので、口頭でも小学校の先生方とコミュニケーションを取るということですね。
小学校との意見交換に際し、提供を求められる情報は市区町村によって様々ですが、一例を紹介しましょう。
小学校の先生がクラス編成で参考にしたい情報一覧表
小学校の先生方は、クラス間で差が生じないようにバランスよく子どもの個性を振り分けてクラス編成をしたいと考えています。
このため、リーダーシップがある子、運動が得意な子など特にクラス編成時に考慮したい要素を持った子が誰かが識別できる一覧表が存在する場合があります。
保育園や幼稚園側は、一覧表を受け取ると次の通り、園児名と◯を記載していくのですね。
このような要素は、要録にも同様の内容が記載されますが、ぱっと見ではわかりにくいです。
クラス編成時に特に重視したい項目だけを一覧にしているので、小学校の先生から見ると分かりやすいですね。

このような一覧表への◯の記入のほか、「あなたの保育園の卒園児だけで2つのクラスを作った場合、適切だと思われるクラス分けはどのようなものですか」といった質問がある場合があります。
保育園や幼稚園側は、小学校の質問の意向に沿って各個性をバランスよく配置した意見案を提出します。

小学校には複数の保育園・幼稚園から子どもが集まります。
小学校側は、各園からのクラス編成案を合体してクラス編成案としてまとめるのですね。
小学校入学後の卒園児からの報告を聞いても、概ね保育園側が出したクラス編成案どおりで小学校のクラス編成が決定しているように見えますよ。
喧嘩ばかりの子ども同士は別クラスに
このとき、喧嘩をよくする子同士で、保育園でも座席を離すなどの対応をしていた子などは、別のクラスにして報告することが多いです。
いつも一緒にいる割に、いつも喧嘩ばかりのりょうすけ君とよう君。
喧嘩が終わると、「小学校に行っても同じクラスかなあ」などと呑気な二人でした。
これまで重ねてきた保護者面談の経緯なども考慮し、ここはクラスを別にした方が良いと保育園側は判断。
小学校入学後は、保育園からの申し送り通り別々のクラスになった2人ですが、結局、毎日学童では一緒に過ごしているとのことです。
保護者の対応に配慮を要する
子ども自身の個性の他、保護者の対応に配慮を要する子は誰かという質問事項も含まれています。
保育園・幼稚園側からは嘘偽りなく、在園中に意見ではなく明らかにクレームばかりを言ってきたことがある家庭や、対応が難しかった保護者などがいれば◯を記載して報告します。
そのような子のクラスには、小学校においても保護者対応に長けた担任を配置したいのですね。
まとめ
小学一年生のクラス分けにまで大きな影響を及ぼす幼保小連携について紹介してきました。
なお、幼保小連携には保育士と小学校の先生など大人同士の連携の他、園児と児童との交流など子ども同士の連携も含まれています。
今後、小学校訪問や小学校の生活体験など、保育園・幼稚園でも就学に向けた様々な取り組みが増えていくでしょう。
幼保小連携や保育所児童保育要録(幼稚園幼児指導要録・幼保連携型認定こども園園児指導要録)の概要については、以下の記事で紹介しています。
合わせて参考にしていただけると幸いです。
関連記事