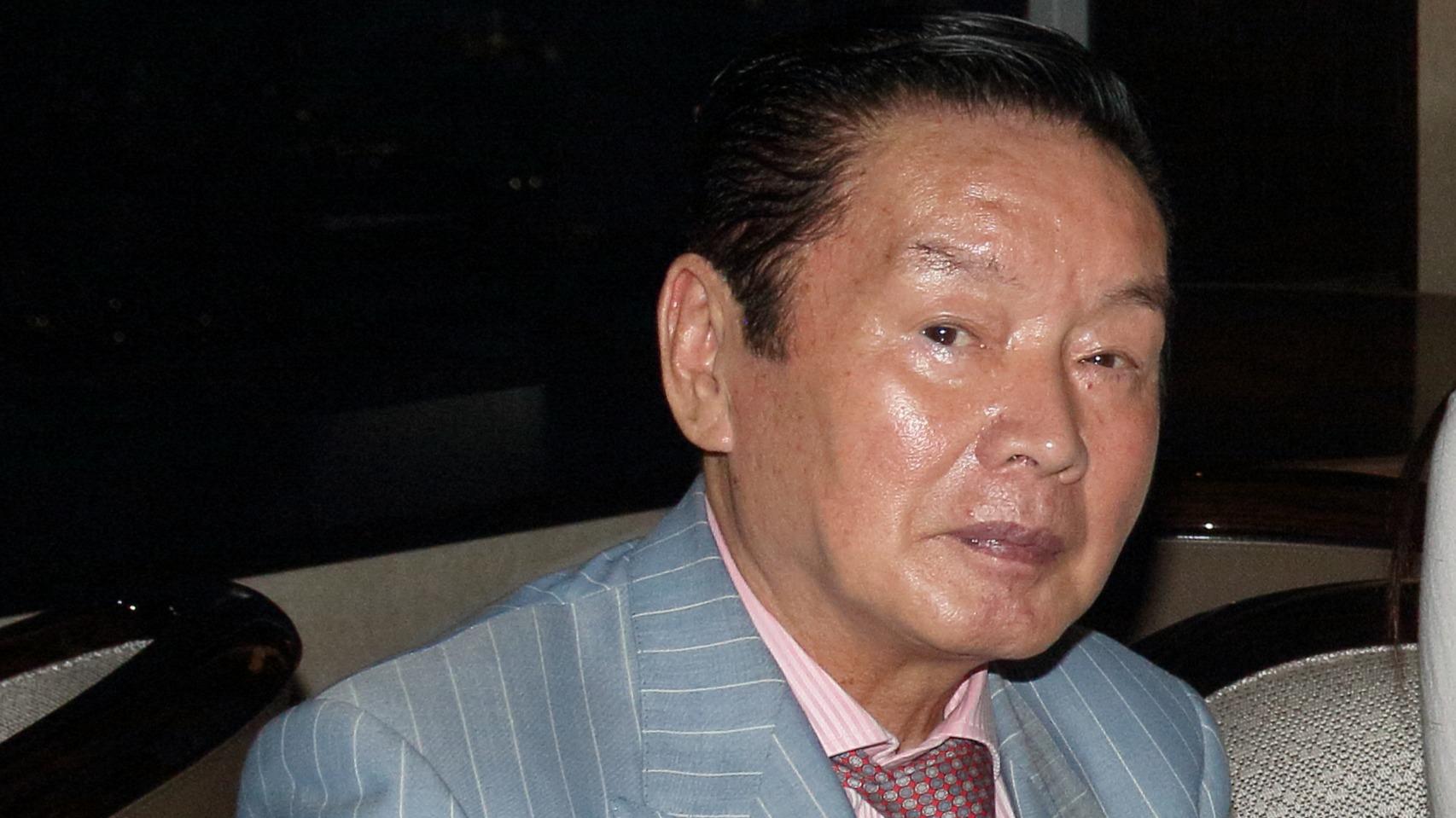吉田拓郎・浜田省吾・尾崎豊…多くのアーティストが信頼を寄せる音楽評論家・田家秀樹の原点と80年代音楽

80年代の音楽はシティポップだけじゃない――音楽評論家・田家秀樹氏の著書『80年代音楽ノート』が伝える80年代音楽シーンの実状
「今の日本のポップミュージックのインフラが整えられた“開拓時代”が70年代だったとしたら、それらが一斉に開花していったのが80年代だった」――音楽評論家・田家秀樹氏は著書『80年代音楽ノート』(ホーム社刊)のあとがきでそう述べている。昨今のシティポップ人気で80年代は“シティポップ全盛時代”という認識が多くの人に中にあるようだが「それだけじゃない」(田家氏)ということを教えてくれるのが『80年代音楽ノート』だ。

新しいものが次々と出てきた80年代は、日本の音楽シーンの中でも重要な位置づけだ。そんな時代に田家氏はアーティストのツアーに密着したリ、時には海外レコーディングにも帯同し、新たな音楽が生まれる瞬間を目の当たりにしてきた。そしてアーティストと至近距離で対峙し“現場”で見たこと、感じたことを我々に届けくれた。田家氏にインタビューし、彼が音楽を生業としていくことに大きな影響を及ぼした吉田拓郎、浜田省吾、そして尾崎豊について、さらに80年代の音楽シーンでは何が起こっていたのかを紐解いていきたい。
「あの頃、僕は田家秀樹になりたかったんだ」(作家・重松清氏)
『80年代音楽ノート』の帯には人気作家 ・重松清氏からの“田家さんはいつだって「あの日の、あの瞬間」にいたんだ”という推薦コメントが躍っている。音楽ライターの経験もある重松氏は、学生時代に田家氏が書いた吉田拓郎や甲斐バンド、浜田省吾についての記事や本を読み、先日行われた田家氏との代官山 蔦屋書店でのトークイベント 『あの頃、僕は田家秀樹になりたかったんだ――重松清』でも「田家さんの文章に多大な影響を受けた」と語っていた。重松氏は田家氏の著書『小説吉田拓郎 いつも見ていた広島~ダウンタウンズ物語』(小学館文庫)の解説文も担当している。
「僕はまともに社会に入れなかった人間。吉田拓郎さんの『イメージの歌』を聴いて『俺たちの歌だ』って思った」
1946年生まれの田家氏は同い年の吉田拓郎に多大な影響を受けている。田家氏は1960年代の学生運動が盛んな政治の季節に大学生活を送り、自らも学生運動に身を投じていた。そして1969年タウン誌の先駆けとなった「新宿プレイマップ」創刊編集者になる。
「就職試験は全部落ちて、面接で喧嘩もしたし(笑)、まともに社会に入れなかった人間でした。縁あって新宿のタウン誌の編集者になって、69年新宿駅西口地下広場で起きたベトナム戦争の反戦運動『フォークゲリラ』の現場にもいました。彼らがやろうとしてることや思っていることはよくわかって、同じような気持ちを抱えながら生きている人という連帯感がすごくありました。同時に、『これ音楽でやることじゃないんじゃないかな』という思いもありました。だったらデモ行けよ、ヘルメット被れよという思いもあって。ところが拓郎さんの『イメージの歌』(1970年)を聴いた時『俺たちの歌だ』って思ったんです。学生運動をしていた仲間の多くは会社員になっていて、でも拓郎さんの歌を聴いた時、音楽で仲間がいると思えた。浜田省吾さんの『路地裏の少年』(1976年)を聴いた時も『俺の歌だ』って思えたんです」。
編集の仕事を辞めたあと、 田家氏は当時若者に絶大な支持を得ていた『セイ!ヤング』(文化放送)など数々のラジオ番組の放送作家として活躍していた。
「深夜放送だった『セイ!ヤング』がメジャーになって、サブカル的な雰囲気だった深夜放送に出ると売れるというある種のステータスになったんです。それで“あっち側” (歌謡界)の人たちがパーソナリティとして登場するようになった。その時『俺はこういうことがやりたくて、ラジオをやってきたのかなって思い始めたんです』」と、30歳を目前に「このままでいいのか」という思いを抱きながら、75年『つま恋』で吉田拓郎の歌を聴き、音楽に関わることを意識し始める。
「75年の『つま恋』のオールナイトコンサートでした。最後の『人間なんて』を6万人以上の観客が涙を流しながら大合唱しているのを聴いて、膝が震えて、音楽はすごいと心の底から思い、音楽の側にいようと思いました。これが自分にとって最大の転機だったと思います」。
「あっち側」と「こっち側」のとの境界線がなくなり、のちに「J-POP」といわれる音楽が生まれたのが80年代
当時はテレビを含む歌謡界が「あっち側」、フォークやロックの新興勢力が「こっち側」と言われていた時代。その境界線がなくなりのちに「J-POP」とい
われる音楽が生まれたのが80年代だ。
吉田拓郎の実像を伝えきれなかった。「僕らが至らなかった」
70年代のことを田家氏は「音楽が音楽として語られることが少ない時代だった」と回想する。その時代の最大の“被害者”が吉田拓郎だという。「俺はフォークじゃない」と言い続けてきた吉田に対して田家氏は「発信側として僕らの力が足りなかった、という気持ちが強い」と語ってくれた。
「拓郎さんは、自分のことがちゃんと世の中に伝わってないとよく言ってました。俺はフォークじゃない、ロックなんだって言い続けた人。アマチュア時代の拓郎さんはR&Bのバンドを組んで米軍岩国基地で歌っていました。フォークとして語られているけどものすごく緻密に計算して、ロックミュージックを作っているのに、そういうことを誰も語ってくれないじゃないか。メディアがそういう扱い方をするからだ、と。そして彼は自分で語るようになっていきました。2019年のツアーも自身の曲だけで構成して、吉田拓郎が語り、伝えるという場にした。僕らが至らなかった。拓郎さんすみませんでした、と言っても遅いですが(笑)」。
「一番インタビューした」浜田省吾は、「長年取材をしてきてあんなに誠実に生きて、誠実に音楽をやっている人は他にいるのだろうかと思ってしまいます」
田家氏は吉田拓郎と並んで、自分にとって80年代を代表するアーティストとして「一番インタビューしている」という浜田省吾を挙げてくれた。浜田は「日本語のロック」の新しい幕をその手で開け、ポップミュージックが「夢」や「恋」を歌うように、「環境」や「反戦」や、大都市の住人にはわからない地方都市の若者の焦燥という“リアル”を、誠実に伝えてきた。
「長年取材をしてきて、あんなに誠実に生きて、誠実に音楽をやっている人は他にいるのだろうか、と思ってしまいます。浜田さんと出会っていなかったら、こうなっていないと思います」。
尾崎豊と出会い「自分の好きな音楽が世代を超えてつながったと思った」
『80年代音楽ノート』の中で、田家氏は尾崎豊との出会いを大きな衝撃だったと語っている。
「時代が変わってしまって、もう自分のやることがないのかなと思っていた矢先に尾崎に出会いました。85年当時のライヴで『テープの中身は例えばブルース・スプリングスティーンやジャクソン・ブラウンや佐野元春や浜田省吾なんかを好んで聴いていたんだぜ。そんな俺をクラスのみんなは白い目で見やがった。それでも 俺は負けなかった!』と叫んでたんです。それを聴いて『自分の好きな音楽が世代を超えてつながった』と思って、やるべきことがあるんじゃないかと思いました。当時尾崎の音楽への反応は賛成派と否定派、真っ二つでした。支持していたのは10代の中高校生か、僕ら世代の学生運動を知っている、ちょっとやさぐれてるおじさんで、20代前半の業界の人たちは否定派でした。それで世代を繋げられると思ったんです。それと、当時尾崎の周りには音楽業界以外では生きられないような、言ってみれば音楽難民のような人が多かった。難民というのはそこから逃げてきた人。でもその逆で、音楽の世界に逃げ込めた人。音楽の世界じゃなかったらまともな人生を送れないかもしれないと思ってしまう人が集まっていました。自分もずっとそういう人間だという思いがあったので、それが面白かったです(笑)」。
吉田拓郎や浜田省吾を聴いた時と同様に田家氏は「自分ひとりじゃないんだ」という思いを尾崎にも感じた。
“日本のウッドストック”と呼ばれた伝説の日本初のオールナイトロックフェス「BEAT CHILD」(87年)
新しい音楽が次々と生まれた80年代の中で、「語り継がれる伝説のライブイベント」として紹介されているのが、1987年8月5、6日に行われた大規模チャリティコンサート『HIROSHIMA 1987―1997』(広島ピースコンサート)と、同22、23日に熊本で行われた「BEAT CHILD」だ。「広島」に出演したバンドやアーティストの有志にBOΦWYらが加わり13組が出演した、のちに“日本のウッドストック”と呼ばれた日本初のオールナイトロックフェスだ。
タイトルの発案者は佐野元春。阿蘇山麗の野外劇場に7万人を超える観客が集まったが、豪雨になり、しかし当時まだ野外フェスのノウハウがなく、深夜の中止は逆に行き場を失った観客には危険ということで続行された。機材もほとんどが使えなくなり、それでもライヴは続けられ、現場にいた田家氏はここで見た光景は今も忘れられないという。このイベントの全貌は2013年にドキュメンタリー映画『ベイビー大丈夫かっ BEATCHILD 1987』として公開されたが、TV放送、DVD化、ネット配信がない。記録がほとんど残っていないこのイベント、それが伝説といわれる所以だが、そんな中で田家氏が2013年に西日本新聞で9回に渡り連載した、このイベントを内側と外側から克明に捉えた記事 は、貴重な資料となっている。

「『ひとりロックの殿堂』『ひとりJ-POPの殿堂』になりたかった」
田家氏は90年代に入った頃から「ひとりロックの殿堂」「ひとりJ-POPの殿堂」になりたかったと教えてくれた。その一環がFM COCOLOで2014年から続く「J-POP LEGEND CAFE 」という、日本の音楽の礎となったアーティストにスポットを当て、本人とその関係者にインタビューし掘り下げていく番組だ。
「殿堂入りするようなアーティストの仕事をしたいという思いと、そういう人たちと出会ってきたことを自分の誇りにしたいという気持ちと、殿堂入りするようなアーティストに出会いたいっていう気持ちが今でもあります」。

田家氏は1970年代から2020年代まで携わってきた、聴いてきたアーティストの作品=CD約1万8千枚を、台湾・清華大学図書館に寄贈した。この取り組みは2018年からスタートし、4年の時間をかけて台湾に運ばれた。日本の音楽への興味が年々高くなっている台湾だが、1949年~87年までは戒厳令が敷かれ、あまり日本の音楽を聴くことができなかった。そんな歴史背景を聞いた田家氏が、自身のCDがこの期間の音楽文化の空白を埋めるのに役立てばと実現させ 、多くの学生に喜ばれている。

最後に『80年代音楽ノート』について田家氏は「80年代にリアルタイムで聴いていた人にはもちろんですが、 父親、母親の青春時代はどういう時代だったんだろう、どんな音楽が流れていたんだろうという、あの時代をよく知らない人、シティポップから入って興味がある人に読んでもらえると嬉しい 」と語ってくれた。時を経て知る真実と、今の音楽に通じる深く、濃い源流を知ることができるはずだ。
「90年代ノート」も連載がスタート
『70年代ノート』に続くこの『80年代音楽ノート』。そして『90年代ノート』の連載も各地方紙でスタートしている。今も日々インタビュー、ライヴと、現場でアーティストの感性、言葉と向き合う田家氏の目を通して、90年代の音楽シーンがどう映っているのか、気になるところだ。