『THE SECOND 2024』勝敗を左右した「一般審査員との距離感」と「1点・2点・3点の重み」
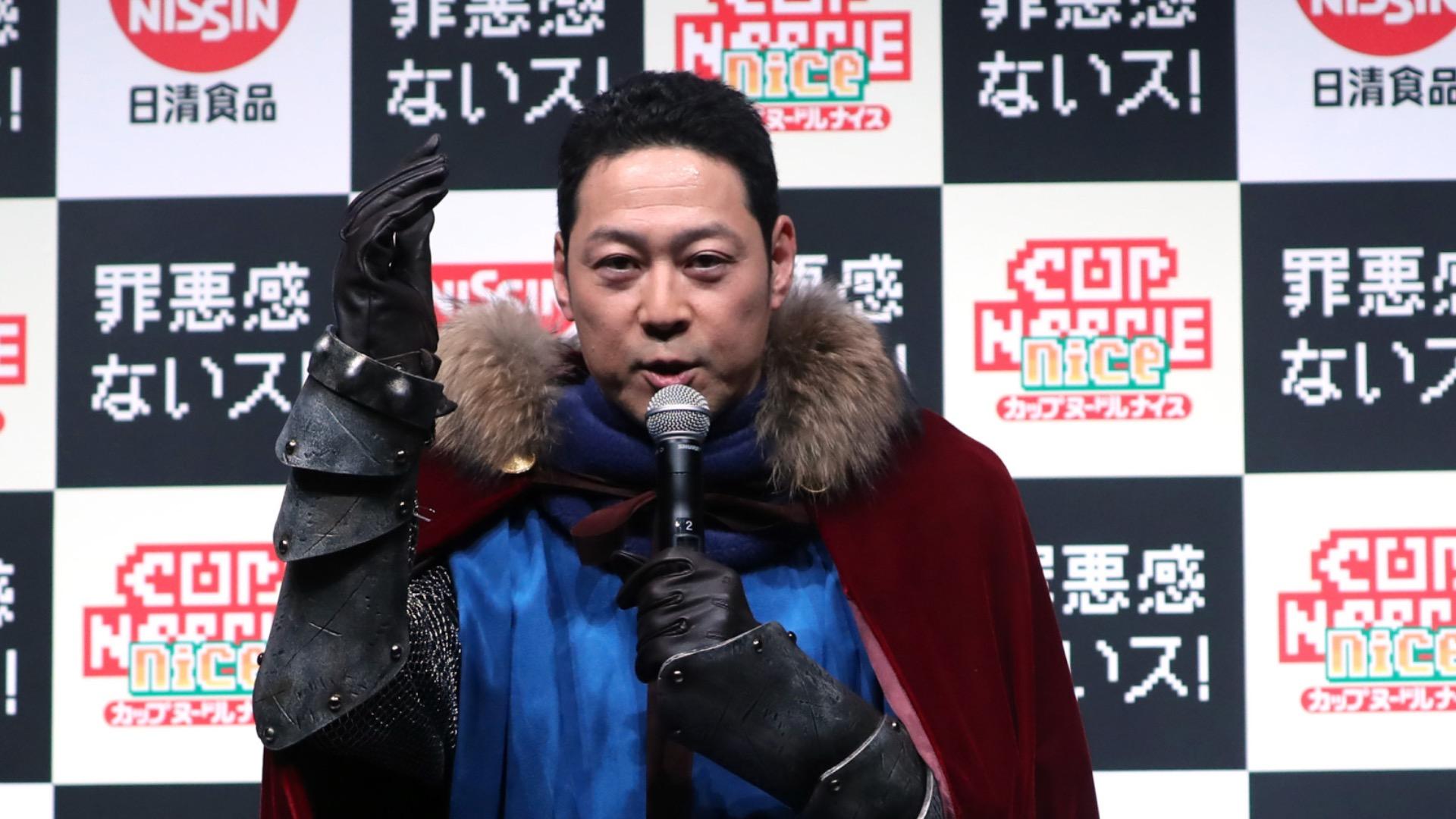
“セカンド戦士”にとって青色は、トラウマの色になるのではないだろうか――。
結成16年以上の漫才師を対象としたお笑いの賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2024』のグランプリファイナルが5月18日に開催され、結成19年目のガクテンソク(よじょう、奥田修一)が2代目チャンピオンに輝いた。
一般審査員が何点をつけたかが分かる、点数分布図の発表段階で「負けた」とボヤく
同大会の特徴の一つは審査システムである。同じ大型漫才賞の『M-1グランプリ』は、漫才の実績があるお笑い芸人たちが審査員をつとめ、各自100点満点で採点する。一方『THE SECOND』は、番組が集めた一般100人が「一般審査員」としてファイナリストたちを審査・採点する。
一般審査員たちはファイナリストたちのネタを見て、「とてもおもしろかった」と思えば各自3点、「おもしろかった」と思えば各自2点、「おもしろくなかった」と思えば各自1点をつける。そして「どの座席の一般審査員が何点をつけたか」という結果を分布図としてあらわしながら、合計得点を集計する。またその分布図では、3点は赤色、2点は緑色、1点は青色という風に色分けされている。そのためパッと見て、3点の赤色が多ければ勝利が確信でき、2点の緑色が多ければ「どうなるかな」とすぐに結果がつかめず、1点の青色が多ければ敗色濃厚であることが分かる。
準決勝の金属バットは、分布図公開の時点でガクテンソクより点数が下回っていることが分かったため、合計点数が発表される前から「負けた、負けた」とボヤいて、司会の東野幸治を呆れさせた。また決勝戦では、先攻のザ・パンチの分布図公開の段階で点数が低いことがうかがえたため、一気に敗戦ムードが広がり、なんとも言えない空気が広がった。そうやってちゃんと結果が出る前から落胆を隠さないファイナリストたちを見て、東野幸治が「(そういう反応をするのが)『THE SECOND』名物ちゃうぞ」と嘆く場面も。
ななまがりとタモンズの一戦は一般審査員のシステムの妙が結果に
ただ、『THE SECOND』では“よほどのこと”がなければ1点をつけられることはない。傾向として、一般審査員の多くは基本的には2点以上をつける。一般審査員は審査評のときに意見を求められる場合もあるので、1点をつけるのであればちゃんとした理由が必要だ。1点をつける責任が重いのだ。
2024年大会でも優勝したガクテンソクは、1点をつけられたのは準決勝の1人だけだった。あと、1回戦のななまがり対タモンズは一般審査員による採点システムの妙が出た。ななまがりは1点が3人、2点が26人、3点が71人、タモンズは1点が1人、2点が29人、3点が70人。ななまがりは3点の数は僅差で上回ったが、1点も多かったことが響き、1点差でタモンズに敗れたのだ。
ちなみに2023年大会では、結果的に優勝するギャロップが準決勝で囲碁将棋と対戦。囲碁将棋は1点が0人、2点が16人、3点が84人だったのに対し、ギャロップは1点が2人、2点が12人、3点が86人だった。こちらは「1点はなんとか2人で食い止め、2点の人数も抑えられるだけ抑えて、3点の数で挽回した」という形でギャロップが勝ち上がった。
つまり、3点をどれだけ多く獲得できれば問題ないが、それよりもまずは1点をどれだけ少なくできるかが「勝敗」の鍵になってくる。その上で、2点が占める重要性も大きくなっていく。
金属バットのネタに対する一般審査員の反応「『子ども』っていうワードが出てヒヤッと」
誰もが認めるおもしろいパフォーマンスができれば、大勢が3点をつけて勝ち抜けるだろう。ただ、技術などあらゆる面で漫才を知り尽くすプロの芸人審査員であれば審査・採点基準もはっきりしているだろうが、一般審査員は当然そこまで及ばない。
一般審査員はやはり、純粋に「自分としておもしろかったかどうか」という感覚的な評価に頼ることになる。
お笑いに限らず、映画、音楽、演劇などどんな分野においても相手の「感覚」に訴えかけるのは、もっとも難しいことである。そう考えると、プロの芸人の審査員数名を唸らせること以上に、100人の一般審査員に高く評価してもらう方が大変なようにも思える。
実際、準決勝の金属バットのネタ終わり、コメントを求められた一般審査員が「『子ども』っていうワードが出た瞬間、ヒヤッとした」と話していた。「子ども」という社会的に慎重さが求められるものが話題に出たことで無意識的に身構えてしまったのだ。ただそれこそがまさに一般的な感覚ではないか。このあたりがプロの芸人審査員の感覚とはちょっと違うところでもあり、一般審査員がジャッジするということは、そういう一般的な感覚も審査基準に入ってくる可能性が高いということだろう。
ななまがりとタモンズの一戦では、どちらも個性が際立つキャラクターがネタ中に登場。それを受けて東野幸治が「どちらも1点がつくのも仕方ないネタ」という風に言いあらわした。奇抜なキャラクターは爆発力もあるが、その分、好みもはっきり分かれるため「1点」がつくことも多いだろう(ランジャタイが予選にあたる「ノックアウトステージ16→8」で1点9人を記録して敗退したことが番組中で触れられていたが、ランジャタイもまさに奇抜な芸風だ)。
ネタ内容やチョイスされたワードで一般審査員がなにか違和感や不快感を覚えた場合、それが採点に響くことは十分にありえるだろう。そうなると今後「戦い方」として意識するものがいくつか出てくるかもしれない。
すぐにネタの本題へ入るか、一般審査員に話を振って歩み寄ってから本題へ入るか
『THE SECOND』の戦い方で大事になるのが、そういった感覚の一般審査員たちの気持ちをどのようにつかまえるかである。つまり一般審査員との「距離感」がポイントなのだ。
「戦い方」の選択肢は大きく分けて二つ。一つは、登場してすぐに本題に入って「ネタのおもしろさ」で真っ向勝負を仕掛けること。これはおそらく、ネタに絶対的な自信があるからではないだろうか。優勝したガクテンソクはそのパターン。ななまがりもこのストロングスタイルに当てはまる。ななまがりは恒例のツカミをやったあと、すぐにボケの森下直人が奇怪なキャラクターになりきり、初瀬悠太も翻弄される“役”に入り込む。ネタ時間をフルに使って自分たちのネタの世界を見せ切っていく。「距離感」という部分では決して一般審査員と近くないが、とにかく笑わせることで一般審査員とまじわっていく。
もう一つは、ネタにはもちろん自信はあるが、一般審査員にも話を振るなど良い感じで客席を温めながら本題に入っていくやり方。準優勝のザ・パンチがそのパターンで、低姿勢で登場し、客席の顔色もなんとなく伺いながらまず場の雰囲気と自分たちの存在をなじませていく。そうやって自分たちから、一般審査員に歩み寄って心をつかもうとする。スペシャルサポーターの博多大吉(博多華丸・大吉)が「(劇場では)今、このスタイルでザ・パンチは爆笑だし、出番もトリをとっている」と話していたように、これは客席の生のリアクションへの対応が求められる“劇場型”の戦法と言える。ちなみに2023年大会準優勝のマシンガンズもここに分類されるだろう。ネタ時間が4分の『M-1』であれば瞬発力が求められるため、いわゆる“客席イジり”にそこまで時間を使えないが、ネタ時間6分の『THE SECOND』ではそれも“一手”なのだ。
まだ2回目の開催ということで、傾向面はこれからさらにいろんなものが見えてくるだろう。ただ必ず言えることは、『M-1』同様、『THE SECOND』もファイナリストと審査員の間にはさまざまな“関係性”が生まれるということ。審査をするのがプロではない分、それが勝負の分かれ道となる可能性も大きい。










