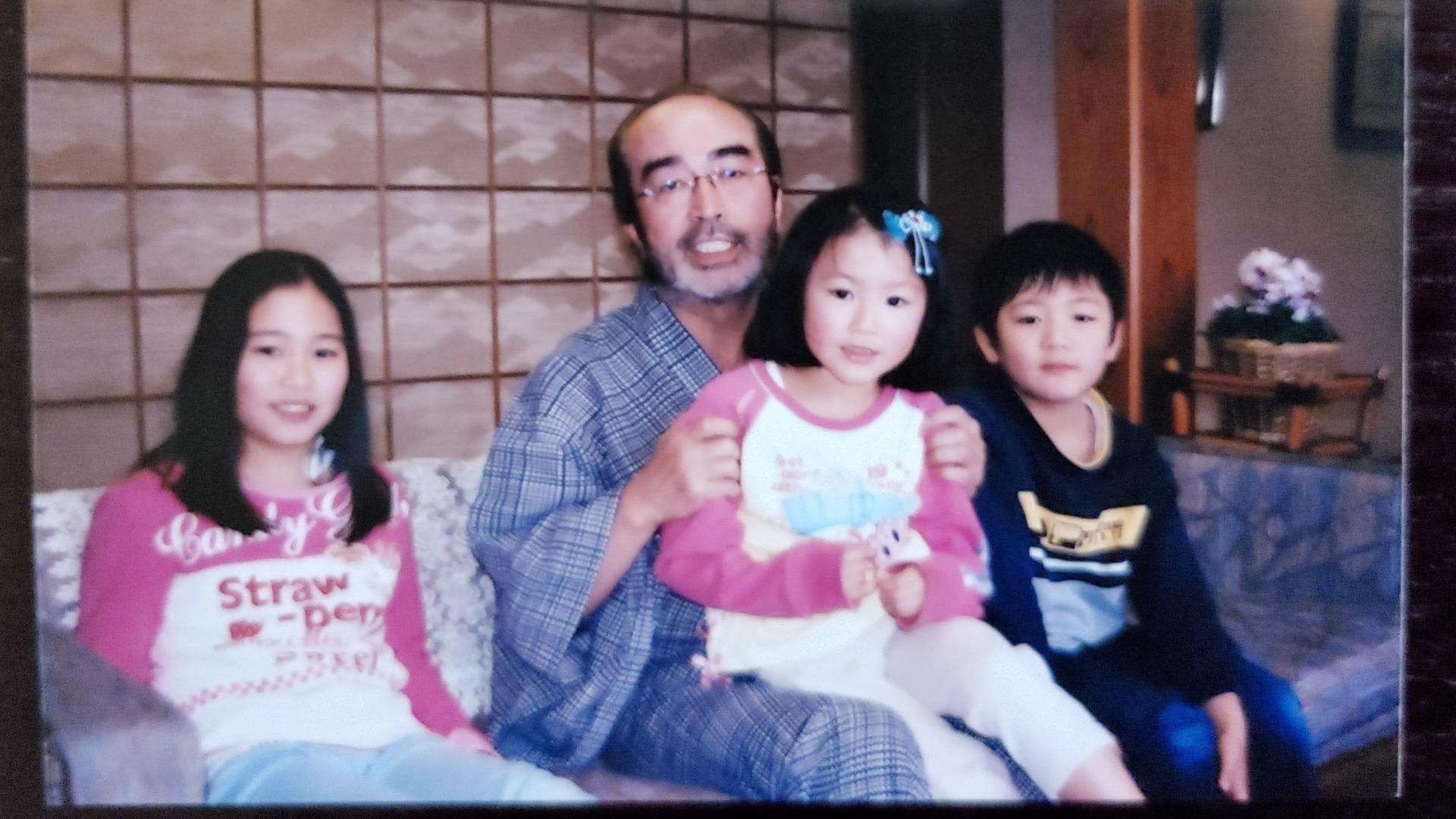支配下契約⇒1軍昇格⇒プロ初出場、初打席、初守備…怒濤の急展開を引き寄せたヤクルト・大村孟選手

■初の1軍昇格は突然やってきた
「緊張マックス(笑)」。
東京ヤクルトスワローズの大村孟選手はプロ初出場をこう振り返った。野球人生最大の緊張だった。2万7千人を超える観客が見つめる神宮球場で、初出場、初打席、そして得点の起点となる貴重な初四球を選んだ。さらにファーストで初守備にも就いた。
1軍に昇格して2日目。前日は朝からファームの戸田球場にいた。2安打1打点と好調な打撃そのままに気を吐いた。六回が終わったとき、急遽、高津臣吾2軍監督から告げられた。「神宮に行け」と。川端慎吾選手の頭部死球による脳震盪措置の代替選手としての昇格だった。
発つ前、初の1軍昇格なのになぜか笑顔がなかった。「バタバタすぎて、そんな喜びに浸るヒマないもん」。そう言い残し、慌てて身支度をしてゲーム開始前の神宮に滑り込んだ。おそらくすでに緊張していたのだろう。
■もっとも尊敬する人

2016年育成ドラフト1位で入団し、2年目の開幕を迎える直前の3月20日、吉報が届いた。悲願の支配下契約ー“本当の野球選手”になれたのだ。もらった2ケタの背番号は「59」。
春季キャンプはファームスタートだったが途中で1軍に呼ばれ、オープン戦でそのバッティングが評価された。支配下契約するための指標は「1軍で通用するかどうか」(小川淳司監督)だった。大村選手はそれをクリアしたということになる。
「これだけやって支配下になれなかったら、クビってこと」と、あますところなく力を出しきった。今年支配下契約されなければ、それが何を意味するかは自身が重々わかっていた。
支配下契約、そして1軍昇格。この喜びを伝えたい人はたくさんいる。家族、これまでお世話になった人、支えてくれた人…その中に大村選手が尊敬し、心酔している人物がいる。元千葉ロッテマリーンズの投手であり、アメリカや台湾など海外6カ国でプレーした経験のある小林亮寛さんだ。


小林さんは現在、福岡市内で「コビーズ」というトレーニングスタジオを経営し、野球少年からプロ野球選手までトレーニングをサポートしている。大村選手の支配下契約、1軍昇格を我がことのように喜んでくれた。
ルーキーイヤーの昨年も支配下登録のチャンスがあったが、ちょうど6月くらいから右肩を痛めていた。明るさがウリの大村選手もさすがに落ち込み、自身の“持ってなさ”を嘆いた。そんなとき、小林さんからかけられた言葉が心に沁み入った。
「この期間はきっと自分にプラスになる。マイナスに考えないほうがいい」。
そこで、できることをしようと再び前を向いた。幸いにも、キャッチャーとして出場はできなくとも打つことはできたので、「バッティングだけでも見てもらえる」とファーストや指名打者で出場し、打つことでのアピールに専念した。
■さまざまな経験からのアドバイス

大村選手が小林さんに出会ったのは2年半前。どうしてもプロ野球選手になりたかった大村選手は、育成契約からでもとドラフト指名を渇望した。入りさえすれば、這い上がる自信はあった。しかし社会人から育成指名を受けてプロに行くことは不可能に近い。
そこで一念発起し、当時所属していた九州三菱自動車を退社して独立リーグからプロを目指すことにしたのだ。退社後、ルートインBCリーグの石川ミリオンスターズに合流するまでの期間、トレーニングしていたのが「コビーズ」だった。紹介してくれたのはチームメイトの谷川昌希投手(阪神タイガース)だ。約3ヶ月、ほぼ毎日通ったという。


「亮寛さんはいろんな経歴を持たれている。いろんな野球観を聞いた。アメリカの独立リーグにも行かれている。自分でも勉強されてるし、知識がすごい。体の使い方や技術面も教わった」。聞く話すべてが新鮮だったし、心に響いた。
石川に行ってからも、ことあるごとに相談に乗ってもらった。ドラフト指名がかかったときは「コビーズからのプロ第1号だな」と大喜びしてくれた。
「亮寛さんは日本のプロでは成功していないけど、さまざまな経験をされた。『日本のプロがすべてではないし、今いるところがすべてではない。考えすぎちゃいけない』と、ずっと言ってくれていた」。
進路に行き詰まったとき、先行きが不安になったときなど、ともすれば周りが見えなくなり、視野が狭くなってしまう。しかし小林さんの話を聞くと前を向けるし、気持ちが楽になる。
この度の支配下契約、そして1軍昇格で、小林さんから受けた多大な恩に報いることができた。
■生まれてすぐに与えられた野球道具

大村選手が野球をはじめたきっかけはお父さんだった。「オヤジが野球好きで。オヤジも高校の途中までやってたらしくて、最後までできなかったから息子にやってほしいっていうのがあったんだと思う」。生まれてすぐに与えられたおもちゃはバットとグラブ、ボールだった。
「毎週土日はオヤジとキャッチボール。チームにも入ってないのにずっとやらされて、何回ケンカしたことか(笑)」。キャッチボールは楽しかったが、たまには別の遊びもしたい年頃だった。

チームに入ったのは小学3年の秋だ。近所のグラウンドで遊んでいたら声をかけられた。「キャッチボールをしてみ」と言われ、披露すると「明日から来い」と所属することになった。「幼なじみもいたし、なりゆきで入った。でも投げることは好きだったので」。こうして導かれるように野球の道に進んだ。
4年の4月にはレギュラーを獲った。当時はレフトや内野だったが、次第にほぼサードになり、たまにピッチャーもした。
中学は軟式の野球部に所属した。内野手だったが、3年の春に「人数が足りなくて」はじめてキャッチャーマスクをかぶった。
■高校でキャッチャーのおもしろさを知る

高校は文武両道の東筑高校に進学した。自身は内野をやろうと思っていた。当時は165~6cmの65~6kgで「そんなガッチリした感じでもなかった」そうだが、「がっつりキャッチャーをやってるやつがいなくて、やれと。まさかキャッチャーをやるとは…」。意に沿わなかったが、見込まれたからにはやるしかない。
「キャッチャーは本当に難しいと思いながらやっていた。どんだけやることあるねん、ていうくらいやることや考えることが多い」。
けれどその中に喜びもあった。当時の監督がキャッチャー出身だったことから、配球面をつぶさに教わり、引き出しを増やしていった。「こうしたいなと思ったとおりに相手がハマッてくれたときは楽しかった。性根が悪いのかな(笑)、相手の嫌がることをするようにしていた」。
徐々にキャッチャーとしての醍醐味を味わうことができるようになっていった。

高校卒業時には「なにかしら手に職をつけたい」と体育教師を志望し、福岡教育大学を受けた。「あんま勉強してないから、まさか国立に受かるとは…」。自分でも信じられなかった。
受かると思っていなかったから、滑り止めの私大近くのアパートの内覧に行く予定で飛行機も押さえていた。合格発表の翌日の便だ。当然、喜んでキャンセルした。
■大学4年時にプロ志望届を提出するも、指名漏れ

大学では1年秋から不動のレギュラーキャッチャーとなり、4年春のリーグで打率・385をマークしてベストナインに輝いた。
当時、福岡六大学リーグには九州共立大の大瀬良大地投手(広島東洋カープ)や九州産業大の浜田智博投手(中日ドラゴンズ)ら好投手も多かったが、「ボク、なにげに打ちましたよ(笑)」とドヤ顔で語る。

卒業後は社会人野球へ進むことを希望していたが、高校の先輩がプロの某球団でスカウトをしており、プロ志望届を出すよう勧められた。ここで初めてプロを意識しはじめたという。「それがなかったら、プロは考えもしなかった」。
しかし指名はかからなかった。「悔しいし、いたたまれない。複雑な気持ちだった」そのときを思い出し、こう振り返る。
■野球で後悔したくない

その後、九州三菱自動車から話がきて、入社が決まった。しかし一度点火した炎は簡単には消せない。社会人野球を経てプロを目指すことを心に誓った。当時、親交のあった山本功児氏(故人・元読売ジャイアンツ、ロッテオリオンズなど)からも「お前はプロに行ける」と太鼓判を押してもらったこともあり、プロへの決意を胸に抱いて社会人野球に打ち込んだ。

社会人の場合、社業との関わりは会社によって違う。九州三菱自動車は販売会社で、野球部といえど一般社員と同じノルマを与えられる。大村選手は入社して1年目は車や車関連の小物の販売、車検、JAFの契約など営業全般に奔走した。ちなみに営業成績はあまり振るわなかったそうだ。
2年目は総務でエクセル入力などパソコン業務をこなした。いずれも午前中に野球部の練習を済ませたのち、午後から社業に勤しんでいた。

プロスカウトの目に留まるには、社会人野球の2大大会である都市対抗か日本選手権に出場しないと厳しい。が、在籍していた2年間、本戦出場は叶わなかった。
そうした中で大村選手が抱えていたのは「野球で後悔したくない」という思いだった。「いろんなことに気を遣いすぎて、野球が下手になってる気がした。野球に専念できるところにいきたい」。

そこで知ったのが独立リーグの存在だった。知人のトレーナーが「こういう道もあるよ」と示してくれたのだ。退社し、石川ミリオンスターズに入団が決まった。
だらだらやるつもりはなかった。プロを目指すのは「1年勝負」と決めた。「指名がかからなかったら、燃え尽きるためにあと1年、長くやっても2年」と自ら期限を設定した。
そして念願のプロからドラフト指名された。
■えぐかった藤浪投手のストレート

昨年は前述の右肩痛以外にも左足首の捻挫や左太もも裏の肉離れ、鼻の骨折など、故障をしながらもイースタン・リーグで99試合に出場し、リーグ6位(チームではトップ)となる打率・268を残した。
ただ「前半に比べると後半はヘバッて、スイングにキレがなかった。振る体力が足りないと思った」と省みる。本塁打の5本はすべて前半に記録したもので、後半は1本もサク越えがなかった。「打率も前半は3割近くあった。キャンプでいきなりケガ(左足首の捻挫)したので、振る量が足りなかった」と自己分析する。

“地獄のキャンプ”といわれた秋季キャンプでは「ボクの野球人生の中でもトップクラスの練習量」と自らを追い込んだ。テーマは「強いまっすぐに振り負けない、1軍で通用するスイング」だった。
きっかけはフェニックス・リーグにあった。タイガースの藤浪晋太郎投手との対戦だ。「3番・ファースト」で出場した大村選手は「初回から6者連続三振、トータルで2ケタ三振させられた。ボクも2コしちゃった」と振り返る。(注:2017年10月25日、西都でのS-T。スワローズは先発の藤浪投手に5回で12コの三振を喫している)
「えぐい。速っと思った。別格でした…」。
そこで宮出隆自バッティングコーチに相談した。「速いボールに負けないようにしたい」と。宮出コーチからは「突っ込まず、できるだけ軸足に残すことを意識するように」とアドバイスを受けた。杉村繁、石井琢朗両コーチとも10種類のティーバッティングに取り組んだ。

「コンタクトする技術とか、総合的に成長した」と自身も手応えを得て、今年を迎えた。春季キャンプはファームスタートだったが、「西都でしっかり振り込んで、オープン戦で呼ばれたらいいな」と思っているところに、キャンプ中盤でお呼びがかかった。
すぐに小林さんにLINE(無料通信アプリ)で「やばい。緊張します」と送った。このときも小林さんは「呼ばれるってことは期待してもらってるんだから、応えればいいだけ。気負わなくていいよ。普段どおりにやってれば支配下になれるよ」と優しく返してくれた。
大村選手は「しがみついてやるしかない!」と腹をくくった。
■全ポジション守るくらいの気持ちで

そこからアピールをしまくり、ようやく支配下登録にこぎつけた。しかしその時点で、「支配下になるだけだったら、すぐに切られる。1軍で活躍したい」と、ここがゴールではなく、やっとスタート地点に立てたにすぎないことは、大村選手本人が一番よくわかっていた。
3月22日に一旦、ファームに降格したが、小川監督からも宮本慎也ヘッドコーチからも前向きな言葉をかけてもらっていた。「お前ならすぐチャンスはあるから」と。
そして「内野と外野の練習をしとけ」との指令も授かった。これまでもキャッチャー以外にファースト、サードの経験はある。ファームではセカンド、さらには外野の練習にも取り組み、イースタンで7試合、ライトを守った。
「全部守るくらいの気持ちで!」と意欲的で、来るべき昇格のときに向けて、準備だけはしっかりやってきた。
なによりバッティングが評価されてここまできた。それならばと、自身もさらに打棒に磨きをかけていくつもりだ。「積極的に。率も残して、大事なところで打てるように」。
確実性と勝負強さを携えて、次に狙う“初”はプロ初安打だ。
【大村孟*関連記事】