【戦国こぼれ話】関ヶ原合戦の前年、黒田長政は巧みな戦略で生き残りを図っていたという驚くべき真相
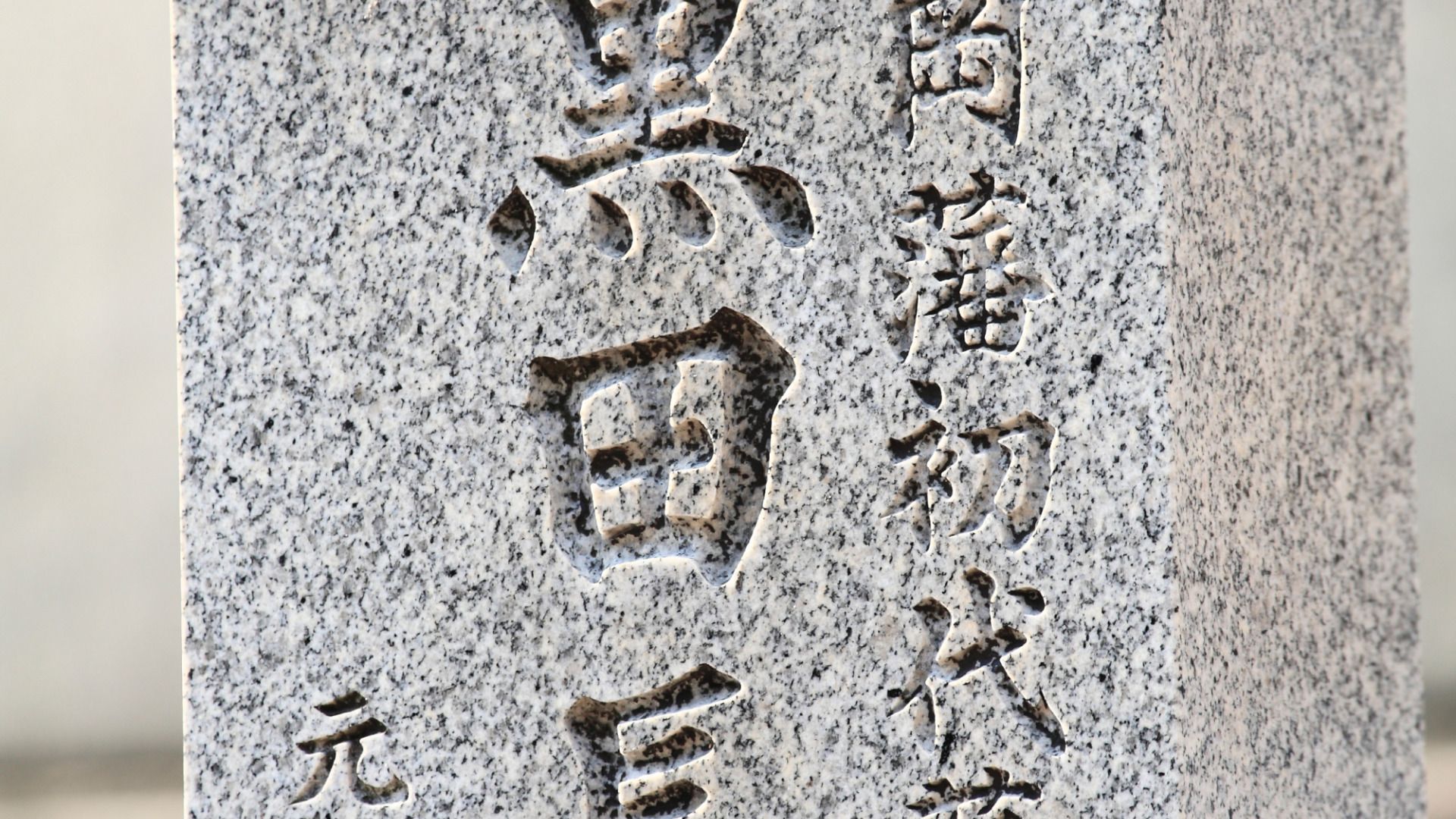
9月15日といえば、関ヶ原合戦が勃発した日だ。前年の慶長4年(1599)閏3月には石田三成が失脚し、徳川家康は豊臣政権内で確固たる地位を築いた。同じ頃、黒田長政は関ヶ原合戦を予感していたかの如く、諸大名との連携を強めていた。その真相とは。
■黒田長政と吉川広家の盟約
慶長4年(1599)閏3月の石田三成の失脚後、徳川家康は諸大名と起請文を交わすことにより、連携を強めることに腐心した。同時に、大名間の連携も急速に進むことになる。
黒田長政も例外なく、諸大名と起請文を交わし、同盟関係の構築に腐心した。同年閏3月、長政は吉川広家に宛てて起請文を差し出した(「吉川家文書」)。その内容は、次の3ヵ条になる。
①公私において問題が生じたときは、とにかく相談すること。
②両者で交わした話の内容は、一切他言してはならないこと。
③何事も相談したとおりに行い、裏切ってはならないこと。
この起請文の末尾の神文は、長政の自筆によるもので、花押に相当する部分には血判が押されている。実は、すでに黒田官兵衛(長政の父)と広家との間で書状が交わされ、2人は親密な関係にあった。
長政も起請文を交わすことにより、いっそう広家と関係を強めたのである。長政が広家と盟約を結んだのには、もちろん理由があった。広家は、毛利輝元を支える存在であり、強固な関係を築くことにメリットがあったからだ。
この間、官兵衛は広家に手紙を送り、「長政を自分(官兵衛)と同様にお願いしたい」と依頼した(「吉川家文書」)。この一連の流れを見ればわかるとおり、長政と広家は切っても切れない関係を結んだのだ。
■2人の強固な関係
長政と広家との関係が密であったことは、ある1つの事件からうかがうことができる。同年7月、広家は五奉行の一人・浅野長政と伏見で喧嘩に及ぶことがあった(「吉川家文書」)。輝元は、ことのほか事件を心配していた。
輝元は自ら仲介役を務め、広家に助言を与えるなど解決に懸命であった。輝元からすれば、豊臣政権の中枢に位置する浅野長政との関係に亀裂が入ることは得策ではない。
しかしながら、実際に問題解決に力を発揮したのは、広家と起請文を交わした黒田長政であった。
同年8月、黒田長政は広家に書状を送り、浅野長政の1件が解決したことを告げた(「吉川家文書」)。いかなる手段によって、和解に持ち込んだかは不明である。
黒田長政は家康と懇意であったので、そのルートを用いて解決に導いた可能性も考えられる。仮にそうであるならば、家康にとって仲介の労を取ることは損にはならない。黒田長政と広家の関係は、さらに強固なものになった。
関ヶ原合戦が近づくと、長政は広家に調略を仕掛け、西軍に属した毛利方を東軍に寝返らせることに成功した。これも、前年からの布石が功を奏したといえるだろう。
■策士だった長政
長政は、肥後の相良頼房とも起請文を交わした(「黒田家文書」)。その1条目は秀頼を守り立てるよう家康から依頼があったので、秀吉の遺言にしたがい、秀頼を粗略にする気持ちがないことを誓約したものである。続けて、家康に対して忠節を尽くすことを誓っている。
こうして、長政と頼房は盟約を結んだ。起請文の秀頼への忠節は名目にすぎず、実際は家康への忠誠を誓うというのが実態だった。豊臣公儀を支える家康への忠誠が、結果として秀頼を守り立てるという巧みなロジックだったのだ。
もちろん長政は「反三成」の急先鋒だったので、最初から西軍に与する気持ちはなかっただろう。家康に急接近し、諸大名と盟約を結ぶことで、自らの立場を有利にしようとしたのである。それはまさしく、父・官兵衛譲りの才覚だったといえよう。










