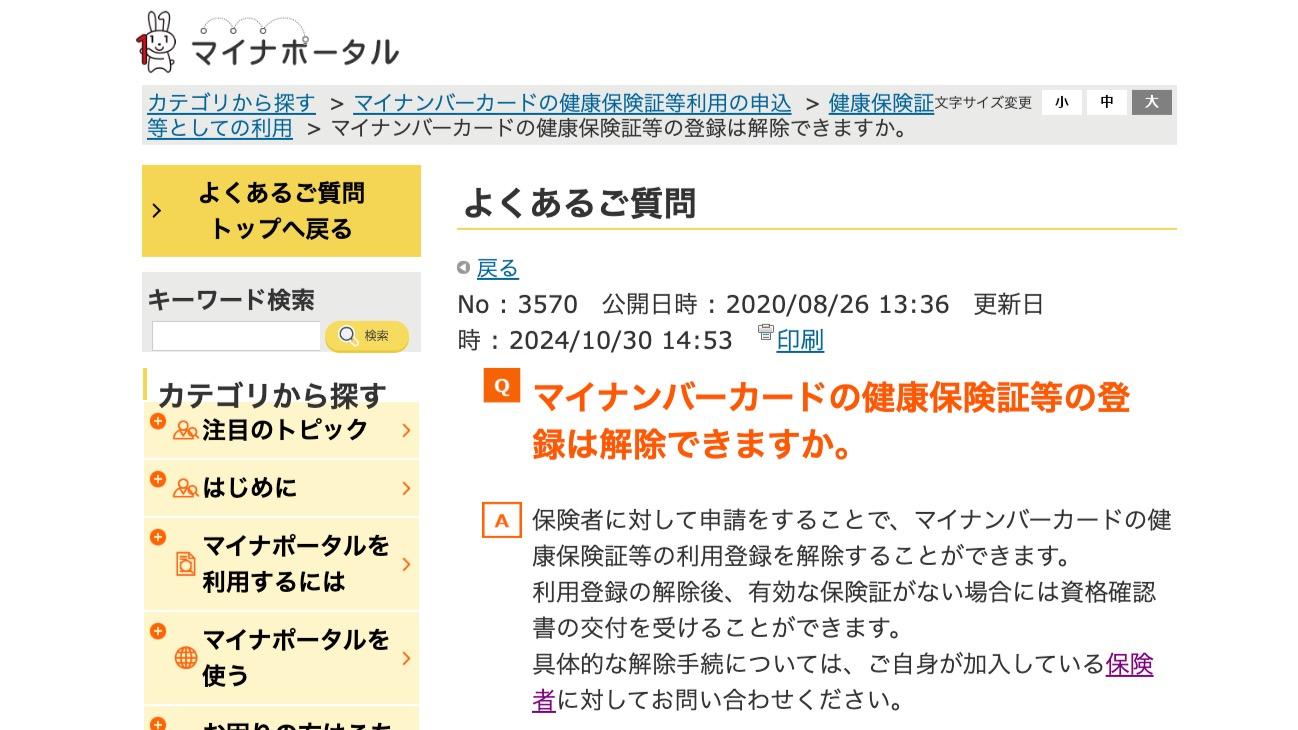鎌倉幕府の軍事制度を支えた、守護と御家人とは

2022年に放映された「鎌倉殿の13人」は、今も人気があると聞いた。源頼朝は鎌倉幕府を開き、平氏に続く武家政権を樹立した。その根本の一つになったのが軍事制度なので、以下、詳しく考えることにしよう。
鎌倉幕府の職制は時代によって変遷はあるが、基本的に将軍を頂点として執権、連署が支え、重要事項は評定衆の合議に委ねられた。後期になると、得宗専制という体制へと移行する。得宗専制とは、得宗(北条氏の家督)個人に集中した政治体制である。
幕府そのものの機関は、侍所、政所、問注所、引付衆が設置され、地方支配は京都守護(のちの六波羅探題)、長門探題、鎮西奉行、奥州総奉行、守護、地頭が担当した。
鎌倉時代の軍事を探るうえで、幕府成立以前の体制を確認する必要がある。治承4年(1180)、源頼朝は打倒平氏の兵を挙げると、惣追捕使という名目で東国に守護を置くようになった。これが基礎となった。
文治元年(1185)、頼朝は後白河から「文治の勅許」を獲得することにより、守護・地頭の設置や兵糧米の徴収を認められた。この時点で、鎌倉幕府の成立とする見解もあるが、いまだに論争は続いている。
守護は各国に置かれ、「大犯三箇条」の権限を行使した。「大犯三箇条」とは、京都内裏・大内裏大番役(内裏と院御所の警固役)の催促、謀叛人および殺害人の逮捕である。当初、大番役の期間は6ヵ月だったが、5代執権の北条時頼によって3ヵ月に短縮された。
つまり、鎌倉時代の守護は、鎌倉幕府の軍事行政官だったといえる。鎌倉時代後期になると、諸国の守護の多くは北条氏が独占するようになった。ただし、室町時代の守護とは異なり、任国の支配権を認められたわけではない点に注意すべきだろう。
実際に軍事の中核を担ったのは、御家人である。御家人は将軍から所領を与えられる代わりに、戦時においては出陣して貢献した。将軍と御家人は御恩と奉公という双務契約を通して、強固な主従関係を結んだのである。御家人を統括するのは、侍所の役割だった。
一般的には、守護が任国内の御家人を戦争時に動員した。ただし、西国の御家人の動員は、六波羅探題の管轄だった。元寇の際、諸国御家人は鎮西探題の指揮命令系統下にあったのである。
なお、元寇における恩賞が不十分だったため、御家人の不満が募ったといわれているが、現在では疑問視する向きもある。