「今残さないと、調理文化が消える」 食研究家たちが支持するレシピ本、危機感から制作

1984年から1993年まで発行され、累計160万冊に達しているロングセラーの全集がある。『日本食生活全集』(農山漁村文化協会)がそれで、47都道府県ごとに1冊ずつ、昭和初期の食事を聞き書きしたもの。庶民の食生活をうかがい知る貴重な資料はこれまで、多くの研究者やジャーナリスト、食文化に興味を持つ人たちに利用されてきた。

その続編の役割を担うシリーズが現在、農文協(農山漁村文化協会)から年4回ムック形式で発行されている。『伝え継ぐ 日本の家庭料理』シリーズがそれで、今回は都道府県ごとではなく、料理のジャンルごとに全16冊出す。2017年11月に刊行が開始され、これまでに「すし」「肉・豆腐・麩のおかず」「小麦・いも・豆のおやつ」「炊きこみご飯・おにぎり」など8冊が出ている。次回は11月に「汁もの」を出す予定だ。
内容は、料理の写真、レシピ、そしてその料理について取材した記事で構成されている。作り方やビジュアルだけでなく、どんなときに作られる料理がどのように受け継がれているのかまで分かる構造になっている。
今、食卓を紹介するテレビ番組やインターネットの情報は、大量にある。人が何を食べているのかを知りたい、あるいは自分が食べたものを伝えたい、という欲求を持つ人がたくさんいるからだ。レシピも大量に流通している。しかし、全国に渡って昔の食卓を伝える二つのシリーズは、貴重と言える。なぜならそれは、私たちの親や祖父母の記憶を記録したものだからだ。
現在のシリーズはどのように生まれ、どんな発見があったのか。発行に携わった農文協の編集者たちと、取材・執筆を行った日本調理科学会の1人で、東京聖栄大学准教授の福留奈美さんにうかがった話を、一問一答形式で紹介する。

「100年先まで伝えたい」シリーズ。なぜ今刊行するのか?
――まず、『日本食生活全集』発行の目的から教えてください。
農文協・遠藤隆士さん(以下、遠藤と表記):構想は1970年代からありました。輸入農産物が自由化され、減反が始まり、高度経済成長で食生活が大きく変わりました。農家や農村に立脚した出版をする農文協としては、日本の農家や農村を守るために、日本の風土に根ざした食文化や暮らし方を記録しないといけないという危機感がありました。
聞き書きする時代を昭和初期に設定したのは、それが地域の風土に根ざした食事が残っていた最後の時代だからです。その後の戦争や高度経済成長で、暮らしが変わっていきますから。そして、その頃に食事をつくっていた世代が、まだご存命でもありました。
――今回のシリーズを、都道府県別ではなく、料理のジャンルごとに設定された理由は?
農文協・中田めぐみさん(以下、中田と表記):最初は47都道府県でやろうという話で、撮影も進めていました。しかし、今の出版状況で47冊出し続けられるか。どういう形が一番届きやすいだろうかと、改めて考えたのです。
遠藤:料理ごとだと、横断的に料理を比較できます。また、全国一斉に本作りを進める結果、地元の料理を伝えようという動きが、全国で盛り上がるのではという考えもありました。
福留奈美さん(以下、福留):昭和30~40年代の食生活をお聞きしました。高度経済成長期に食生活が激変しますので、その前までに定着していたもの。聞き書きしたのは、70代後半から90代初めまでの、当時主婦として台所を切り盛りしていた方々が中心です。
――調査はなぜ日本調理科学会の方が行ったのですか?
福留:私どもでは2001年度から、「調理文化の地域性と調理科学」と題して、「豆・いも類」「魚介類」「行事食」の調査研究を行ってきました。その中で、昔は食べていたけれど食べなくなったものの話が出ており、書き残しておかないと調理文化を喪失してしまうという危機感がありました。
材料が使えなくなり、別のもので代替されている料理もあります。例えばドジョウが豚肉になっていたり、山鳥を獲れなくなったので、今は鶏肉で炊き込みご飯にしているなど。
中田:鯨料理をどうするかも議論になりました。取材を始めた2012年頃は、鯨を食べるとあまり大っぴらに言えない風潮がありましたので。でも、100年後に鯨をどう食べたらいいか分からないと困るから残しましょう、となった。山口など捕鯨地帯ではよく食べられていましたし、東北では塩鯨を食べます。
小学生が作れる料理も。
料理は各県100品ずつ選んだ中から40品まで減らし、さらに掲載する際に27~28品まで絞り込んでいる。基本的に各県の著作委員が「次世代に伝えたいもの」が選ばれている。料理についての発見を聞いた。
遠藤:千葉県の「おぼろずし」は、砂糖がジャリジャリ口に当たるほどで、砂糖の塊を食べているような感じです。でんぶにするアコウダイ150gに対して、砂糖が100gも入ります。それがごちそうなのです。
――掲載された料理は、今も作られているのですか?
遠藤:最近は、家で作らなくなったという話は多いです。
中田:スーパーへ取材へ行ったものもあります。でも、その料理は地元のスーパーで店のお母さんからお嫁さんへ受け継がれて、冬になると必ず仕込むもの。お年寄りがわざわざ買いに来るので、午前中に売り切れてしまう。家庭料理の延長にあるものなので、それはそれでいいとしました。それは「魚のおかず」に載せた茨城県の「ごさい漬け」。塩で下漬けしたぶつ切りサンマを、大根、赤トウガラシ、柚子、塩を加えて本漬けにしたものです。
福留:高知の皿鉢料理はもともと、料理人を呼んで作ってもらっているものを、地域のみんなで協力して覚えていった。もともとプロの技術が入り込んでいた。それを今は、集まって作る地域がなくなったので、今は仕出し屋が引き受けてくれています。
中田:作り手は家庭の主婦とは限らないけれど、誰かが食べたいと思っているものを誰かが引き受ける形で残っています。
――簡単に作れるので驚いた料理もあったそうですね。
中田:小学校3年生の子が、夏休みの自由研究で作った料理があります。「小麦・いも・豆のおやつ」に載っている滋賀県の「幸福豆」です。小麦粉、砂糖、水を混ぜ、それを炒った大豆を加えてさらに混ぜ、フライパンで直径5~6センチの円形に焼くものです。モチモチとした小麦粉の台とコリっとした大豆の食感が面白くていいんですよ。
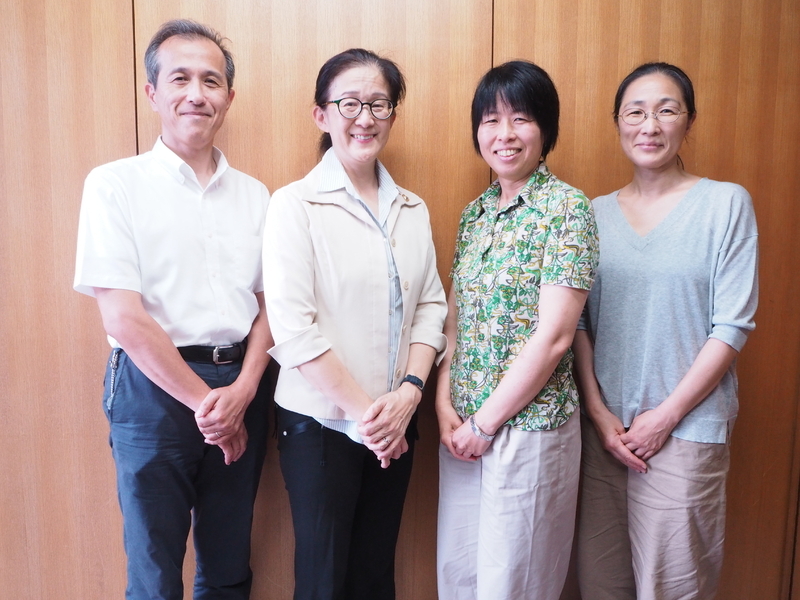
レパートリーが多い魚と豆腐の料理
シリーズ全体を通して読んでみると、今は情報社会の中で見えづらくなっている、日本の食生活の特徴が浮かび上がる。たとえば、魚料理のレパートリーが多いこと。先述の「ごさい漬け」のほかにも、魚をさばいて切り身にしたのち、和え物にする、漬物にする、つみれにして焼くなど、手間をかけた料理が多い。
焼いたり揚げた小魚を、酢醤油や三杯酢に漬けて食べる、香川県の「あじの三杯酢」、岡山県の「焼きままかりの酢醤油漬け」、福岡県の「えつの南蛮漬け」などがある。
つみれ料理としては、青魚をすりつぶして揚げた東京都の「たたき揚げ」、カツオを焼いた徳島県の「かつおの沖なます」、サンマにネギ、ショウガ、味噌、卵を加えて焼いた茨城県の「ぱいた焼き」などが紹介されている。
魚が豊富に獲れたが、電気冷蔵庫があまり普及していなかった時代に、大量の魚を保存し目先を変えて楽しむ知恵が、これらの料理には詰まっている。その知恵は、動物性たんぱく質のほとんどを、魚に頼る歴史から生まれたものだ。

一方で、肉料理は煮物や鍋物が中心。レパートリーの少なさから、肉がそれほど食べられてこなかったことがわかる。
魚も肉も手に入りにくいときに、頼りにされていたたんぱく源は、豆である。「肉・豆腐・麩のおかず」には、豆腐料理もいろいろ紹介されている。寒天で豆腐を寄せた新潟県の「寄せ豆腐」、豆腐を炒って小エビやニンジンなどと和えた山口県の「つしま」、あらかじめ季節の菜っ葉を入れて固めた宮崎県椎葉村の「菜豆腐」などバラエティ豊かである。
豆腐を日持ちさせる工夫もある。和歌山県紀の川市の正月料理「しめ豆腐」は、藁で包んだ豆腐を茹で、出汁と調味料で煮る。似た料理は、岐阜県や鳥取県にもある。
大切にされている、すしともち
異なる地域で同じ名前や同じ発想の料理があるのは、豆腐料理だけではない。
「ばらずし」は、岡山県や広島県、愛媛県、香川県、京都府、宮崎県にある。名前は違うが、東京都の「ちらしずし」、神奈川県の「かて飯」、徳島県の「金時豆入りかき混ぜ」、島根県の「すもじ」、鹿児島県の「さつますもじ」も、野菜を中心にさまざまな具材を混ぜ込んだすしである。
「炊きこみご飯 おにぎり」の巻では、野菜やいも、魚介類などで増量してコメを節約した時代の工夫が見られる。海がない岐阜県の「さんまご飯」は、行商人が運んでくる塩サンマを炊き込んだ料理である。やはり内陸部の兵庫県丹波地方の「焼きさばご飯」は、ほぐした焼きサバ、タケノコ、フキ、ニンジン、干しシイタケ、こんにゃく、油揚げが入った炊き込みご飯で、田植えの際に手伝ってくれた人などに配るごちそうだ。これだけで食事として成立する工夫がされている。

もち料理のバラエティが豊かなのは、寒冷地である。宮城県の一大稲作地帯、登米市では、正月はもちろん、彼岸、盆、法事、結婚式や田植えなど何かあればもちを搗く習慣があった。紹介されているのは、「納豆もち」「ずんだもち」、エゴマを使った「じゅうねんもち」、「えびもち」「しょうがもち」、鶏ひき肉とゴボウ、ショウガなどを煮詰めてかけた「ふすべもち」と、さまざまな具材を絡めて食べる。
秋田県の「バターもち」は、搗きたてのもちに、バターと砂糖、小麦粉、卵黄を加えて、さらに搗いたもの。マタギが猟に出る際などに重宝されたのは、「寒くてもかたくなりにくい」からである。
福島県の豪雪地帯、郡山市湖南町周辺では、「豆腐もち」が作られてきた。搗きたてのもちに、炒めた豆腐を絡めたもの。手間をかけて作るもちに、やはり手間をかけて手作りした豆腐を合わせたこの料理は、特別なごちそうだったのである。
全国の多様な風土の中で生まれ、受け継がれてきた料理は、一つ一つに背景があり、大切にされてきた歴史がある。生活環境が大きく変わった今、家庭では作られなくなった料理も、スーパーや飲食店が受け継ぎ守っている。それがおいしければ残る。今でも大量に作ることで、おいしくなると思われているすしや漬物もある。昔ながらの味つけが愛されている料理がある。
たくさんの料理が日々生まれ、外国からも入ってくる現代において、私たちの根っこがどこにあったのかを伝えてくれる貴重な仕事である。











