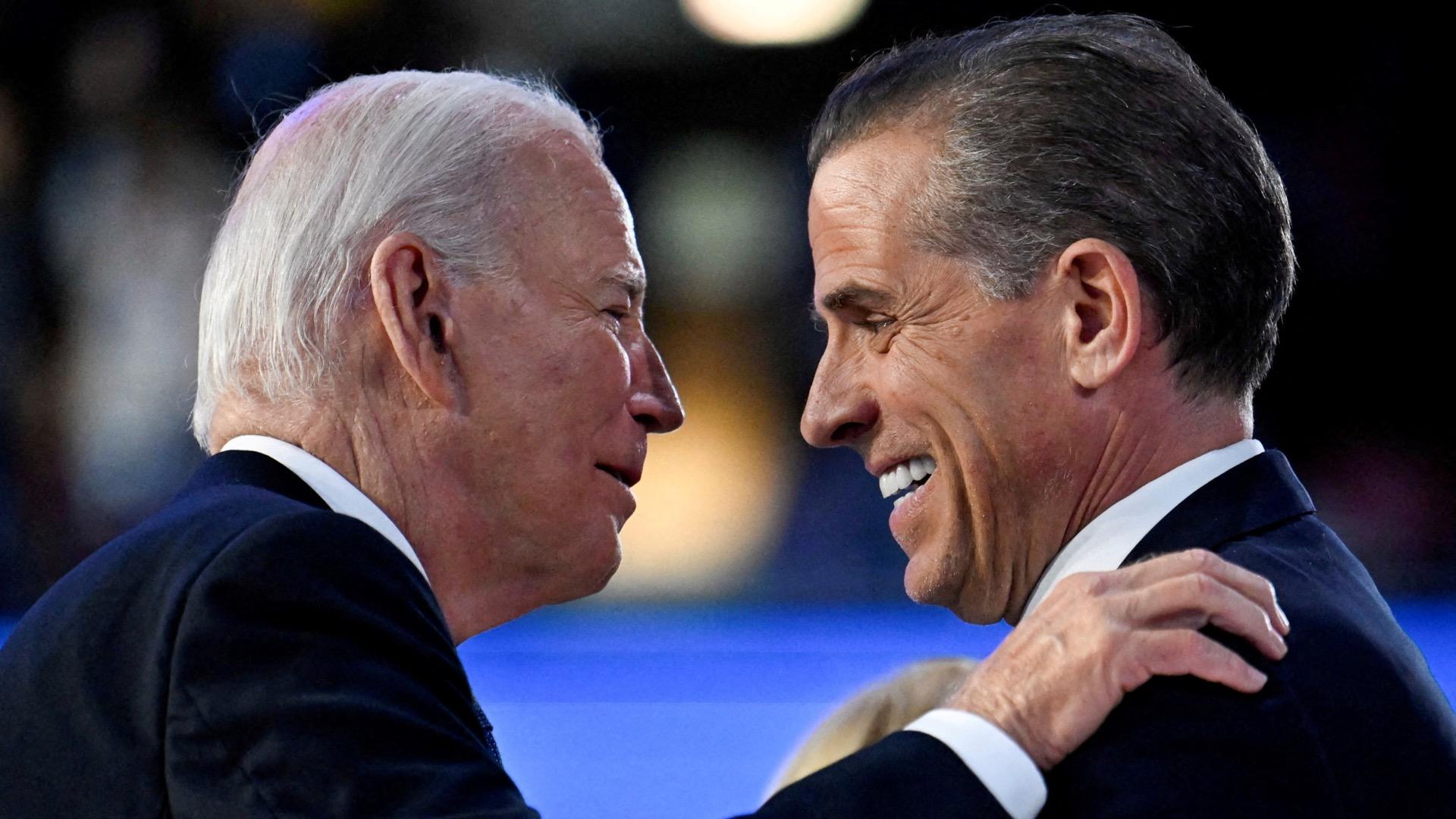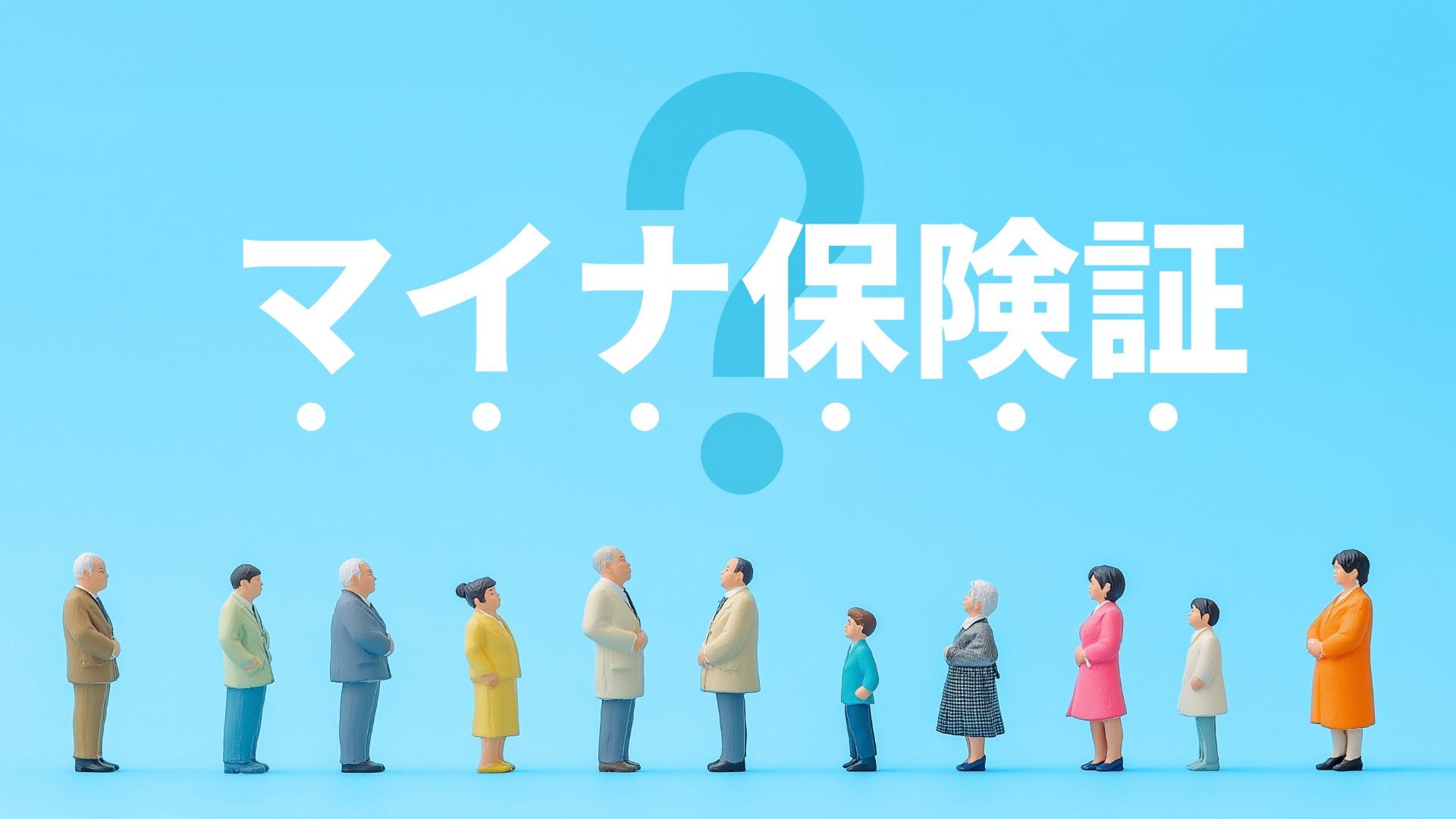話題の『モンテッソーリ教育』ご家庭でもできる9つの取り組みを幼児教育講師が紹介します!

幼児教育講師のTERUです。
日々の子育て本当にお疲れ様です!
今日は『モンテッソーリ教育をご家庭で取り入れる9つの方法』というテーマでお話しします。
この記事ではモンテッソーリ教育って何?といったことはお話ししていません。
あくまで、教育者としての私の経験からモンテッソーリ教育のエッセンスをご家庭で取り入れるならこの9個がオススメというものをご紹介するという内容です。
①子どもが自分で扱えるものを用意する

これは、自分の気持ちが強くなる2歳ぐらいのお子さんから実践できるもので、お子さんの持ち物を選ぶときに「デザイン」ではなく、「機能面」を重視して選ぶように心がけましょう!という取り組みです。
例えば、お子さんの水筒が必要になったときなど、ついつい子どもの好きな模様やキャラクターで選ぶことを優先してしまいがちですが、もしその水筒をお子さんが自分で開けられなかったり、飲めなかったりしたら、その都度親が手を出して手伝ってあげなくてはいけませんよね。
そうなると自分で挑戦する気持ちや自主性を育むチャンスが減ってしまう可能性があります。
それよりも、水筒の大きさや重さ、飲み口の形など、機能面を重視して選ぶことをオススメしています。
その上でその水筒がお子様の好きなデザインであれば、愛着も持てるのでなお良いですね!
②できるだけ本物に触れさせる
子どもは2〜3歳ぐらいから親の使っている物に自然と興味を持ち始めます。
そういったときに危ないからといって使わせないのではなく、子どもに触れさせてあげる機会を作ってあげることが大切です。
本物に触れることで、大人と同じ物が使えるという満足感も感じられますし、なによりたくさんの学びがあります。
例えば、プラスチックのコップを使っていた子が親の使っているガラスのコップに興味を持ったとします。
プラスチックのコップはたしかに軽くて丈夫ですが、子どもの興味の持った重くて割れやすいガラスのコップを渡してあげることによって
・「パパ・ママの使っているコップはちょっと重たいんだ」
・「割れやすいから気をつけよう」
と学んでいきます。
素材は同じものでサイズが小さいものを用意してあげられるとより良いですね。
ただ、これは正直割ってしまうリスクなども考えるとなかなか取り入れるのに負担を感じるご家庭もあると思いますから、ご家庭の状況やお子さんの年齢に合わせて検討してみてください。
③子どもに選択させる

子どもは「自分で選ぶ」という行為を繰り返すことで主体性が育まれ、自分で考える力が身についていきます。
お子さんとお買い物に行って洋服を選ぶときに「〇〇ちゃんはこのお洋服が似合いそうだからこれにするわね!」と勝手に親が決めてしまうのではなく、
2枚の洋服を見せながら
「〇〇ちゃんはこれとこれなら、どっちがいいかな?」
などと聞いて選ばせてあげましょう。
他にも、公園に遊びに行って家に帰りたがらない子も
「時計の長い針が3か4、どっちになったら帰る?」
と聞きながら子どもに選ばせてあげることで、時間になったら納得して家に帰れる子も多いです。
④おもちゃなどの置き場所を決める
子どもは2歳ぐらいから、おもちゃなどの場所を決めておけば自分が欲しいときに自分でそこから持ってきて遊ぶことができます。
さらに、その子専用のおもちゃ箱を用意したり、そこにその子の名前や好きなマークを付けたりしてあげると「自分専用の特別な場所」という認識ができて、「使うときにはそこから取り出す」「使い終わったらそこに片付ける」という習慣が身に付いていきやすくなります。
まだ0〜1歳くらいの年齢であれば、おもちゃが適度に散らばっている方が興味・好奇心に合わせて探究活動ができるので、2歳を過ぎたあたりから意識してみると良いと思います。
⑤自分への配慮ができるコーナーを用意する

これは自分で洋服を着たり、少しずつ身の回りのことができるようになってきたタイミングで作ってみることをオススメする環境の1つです。
どこかに子ども専用の小さな机と鏡、そしてできれば座れる椅子なども用意して、いわば小さな化粧台のようなものを作ってあげます。
そして例えば、
- 鼻水が出てしまったとき
- 髪の毛が乱れているとき
- お出かけの前に洋服をチェックするとき
親が手を出して直してあげたり鼻をかませてあげるのではなく、
「ちょっと鏡を見てみようか!」
と、そのコーナーへ行くことを促していきます。
そうすることで『自分で自分のことに気づく』という練習になっていきます。
そこには鏡だけではなく、ティッシュやゴミ箱などを用意しておくと良いですね。
これだけで身だしなみなどへの意識がグッと上がった子もいるので、良かったらやってみてください。
では、ここからはさらに子どもとの関わり方や具体的な取り組みに近いものをご紹介していきたいと思います!
⑥物の正しい使い方を教える3つのポイント

当たり前ですが、どんなに良いおもちゃや教材があったとしても、子どもがその使い方を知らなければ意味がありませんよね。
最初にどのように使うのか、使い方を子どもが理解できるように説明する必要があります。
例えば、何かをこぼしてしまったときに自分で雑巾で床を拭くことを教えたいとします。
ポイント1『名前と保管場所と使う場所を教える』
初めて雑巾を使うときは、最初に子どもに見せて「これは『雑巾』っていうものなんだよ」ときちんと名前を教えてあげるようにしましょう。
そしてどんな場所やどんな場合に使うのかということやしまう場所もきちんと教えてあげることで、いずれ子どもが使いたいときに自分で出して使えるようになります。
ポイント2『子どもの意思を確認する』
何か子どもに教えたいことがあったり一緒に取り組みたいものがある場合は、親の想いだけで進めるのではなく、子どもを1人の人格として尊重して「一緒にやってみない?」と子どもに声をかけてから行うようにしましょう。
このときにもし「やりたくない」といった場合は無理にやらせる必要はありません。
「そっか。じゃあまた気が向いたらやろうね」と伝え、また別のタイミングで誘ってあげるとどこかのタイミングで「やってみたい」と興味を持つことも多いです。
ポイント3『子どもが観察しやすい位置で見本を見せる』
子どもが「僕もやってみる!」と親の誘いを許可した後は、見本を見せることを大切にしていきましょう。
今回の雑巾であれば、ちゃんと親の手元が見える位置が良いでしょうし、他にもハサミの切り方を見せるなら、子どもの利き手側に座ってやり方を見せましょう。
利き手側で見せることで、子どもが見たときに親の見本が格段に見やすくイメージがしやすいため、模倣しやすくなります。
これは、ご家庭でよく行う「折り紙」などでも同じことが言えます。
どこを折るのか、どんな形に折るのか、正しく見本を観察できるように、子どもが見やすい位置で見せることを心がけましょう。
⑦子どもが伸びる教え方3つのポイント

子どもは3歳頃から、大人の真似をして同じようにできることが増えてきます。
そのため、新しいおもちゃや教材などはすぐに渡すのではなく「まず親がやり方を見せる」ということが大切になってきます。
ポイント1『とにかくゆっくりと見本を見せる』
親が普通のスピードで見せても、子どもにとっては早すぎて目が追い付きません。
ゆっくりと行い、しっかりと観察させてあげることが大切になってきます。
また、やっているときは親は喋らずに行うようにしましょう。
幼児期の子はまだ同時に2つのことをするのが苦手なので、説明をしながら見本を見せるとどちらに集中したら良いのか分からなくなってしまいます。
説明が必要なのであれば、手を止めて説明するようにしましょう。
ポイント2『すぐにやらせない』
見本の途中で子どもが「やりたい!」と言っても「終わるまで待っていてね」と伝えることで、待っている間に「やりたい」という気持ちが大きくなっていきます。
ただ、私個人としてはあまりに待たせすぎるとやる気が反対になくなってしまうので、お子さんの様子を見ながらバランスを取っていくのが良いかなとも思います。
ポイント3『否定しない』
子どもが間違ったやり方をしてしまったときに「違う」「それじゃできないよ」といった否定的な言葉をかけてしまうと、子どものやる気や興味がなくなってしまいます。
そういうときは代わりにもう一度見本を見せてあげましょう。
先ほどの折り紙の例でいうと、子どもがうまく折り紙が折れなくても
「ママがもう一度折るから見ててね」とまた最初から折り、
子どもが間違えたところはさらにゆっくりと丁寧に見せ「やってごらん」と言葉をかける
そうすることで、子どももさらに鮮明なイメージができて「もう一度挑戦してみよう!」という気持ちが湧いてくるかもしれません。
子どもが「もう一回やりたい」と言った場合は成長のチャンスです!
何度もやらせてあげながら、時間の許す限り親はそっと見守ってあげられると良いですね。
⑧お手伝いを通じて成長していく

子どもは特に2歳を過ぎた頃から体も言葉も大きく成長します。
お手伝いにはこの時期の成長に必要な動作が数多く含まれています。
例えば、洗濯のお手伝いでは
・洗濯ばさみを「つまんで留める、外す」
・洗濯物を「畳む、運ぶ」
など、様々な動きを学ぶことができます。
特に洗濯ばさみは指先を使う練習になりますよね。
もしまだお手伝いが難しい年齢であれば、最初は親が家事をしているところを見せるだけでも十分です。
子どもはなんでも大人の真似をしたがるので、時間が経って年齢が大きくなるにつれ、親がやっている家事に興味を持つようになります。
そして、そんなお手伝いで欠かせないものがあります。
それが「踏み台」です。
踏み台があることで親と目線が近づき、一緒に家事をしている気持ちが強くなる上に、自分で手が届くというお手伝いに対する喜びも大きくなるので用意してみることをオススメします。
⑨遊びに文字を取り入れる
子どもは3・4歳頃から文字に興味を持ち始める子も多いです。
しかし、いきなり文字を読み書きするのではなく、2歳頃から指先を多く使うことが大切になってきます。
指は「第2の脳」と呼ばれるほど脳の発達への影響が大きいので、たくさん使っていけるといいですね。
先ほどご紹介した洗濯ばさみもそうですし、
- 小さなものをつまむ
- 紙を破る
など様々な指先の動きをすることで、「いずれ文字を書けるようになる手」が作られていきます。
そして、3・4歳になったら次の2つの遊びが文字習得に繋がります。
1.「五十音ならべ」

まず五十音が書いてある積み木を用意します。
積み木がなければカードでもいいですし、文字を書いた紙でも構いません。
やる事は次の通りです。
- 「あいうえお」の5枚をバラバラに置き、それを正しい順番に並べ替える
- 並べることができたら、それを1つずつ指さしながら「あいうえお」と声に出して読んでみる
こうすることで、ただ耳で覚えただけで「あいうえお」と発音していくのではなく、並べ替える過程を通じて1文字ずつちゃんと認識しながらひらがなを習得していくことができます。
「あいうえお」ができたら「かきくけこ」や「さしすせそ」など五十音すべてが読めるように同じ方法で少しずつ練習していき、それにも慣れてきたら今度は、横に「あかさたな」で読んでいくことで子どもは五十音のどこに何の文字があるのかを把握していくことができます。
これができてくると、その後スムーズに言葉を読んだり書いたりすることに繋がっていきます。
2.「なぞり文字」

これはモンテッソーリでは『砂文字』というザラザラした文字を指でなぞる教具を使うのですが、ご家庭でもまずはいきなり鉛筆などで書き始めるのではなく、指でのなぞり書きを大切にしていきましょう。
- 最初は親が指でゆっくりと文字をなぞる
- 子どもはそれを見ながら真似をしてなぞる
そうすることで、正しい書き順が身に付いていきます。
指で書くのに慣れてきたら、いよいよ筆記用具を使います。
いきなり鉛筆ではなく、はじめは筆圧が弱くても書ける水性のフェルトペンを使い、見本の文字の上にトレーシングペーパーを置いてなぞっていきます。
見本が透けていてそれをなぞりながら書くことができるため、そのトレーシングペーパーにはきれいにかけている字が残ります。
そのため「上手に書けた!」と自信につながり、他の文字にも挑戦したくなることが多いです。
もちろん最初からきれいに書くことを求めてはいけませんからね!
あくまで子どもの成功体験を作るためのサポートです。
それを繰り返していくことで、文字を書くことの楽しさや大きな自信に繋がっていきます。
いかがでしたでしょうか?
モンテッソーリ教育の考え方や取り組みのほんの一部のエッセンスのご紹介ではありましたが、ご興味のある方はできそうなものから無理なく取り組んでみてくださいね。
皆さんの子育てを応援しています!
オススメの関連記事はこちら
動画でより深く学びたい方はこちら