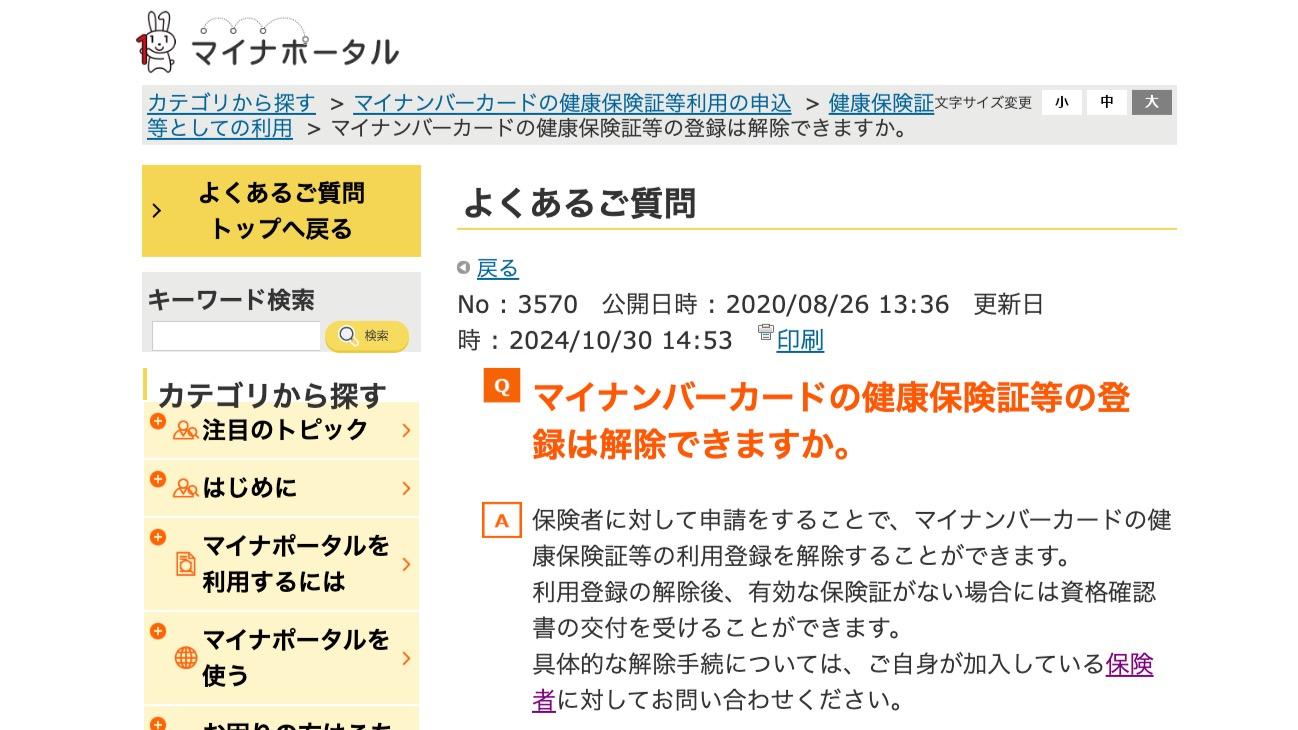ウクライナ情勢が緊張するなか、米国は自らが制空権を握るシリア東部領空でロシア軍機の通過を許す

米国のCNNは、米高官2人の話として、2月15日に米主導の有志連合が制空権を握るシリア東部のユーフラテス川東岸上空にロシア軍3機が進入し、有志連合所属の戦闘機がこれを誘導する対応をとったと伝えた。
進入したのはロシア軍の貨物機1機とこれを護衛していたTu-22超音速爆撃機2機。
有志連合に事前の通知を行わず、イラク上空を経由し、シリア東部の「非紛争地帯」(de-confliction zone)に進入した。
「非紛争地帯」とは?
「非紛争地帯」は、2015年10月に米国とロシアがシリア国内での「テロとの戦い」にかかる航空作戦での偶発的な衝突を回避するためとして、ユーフラテス川東岸地帯に設置され、その領空は有志連合が掌握、ロシア軍、シリア軍による航空作戦は原則禁じられた。
当時、米国はトルコが「分離主義テロリスト」と位置づけるクルド民族主義組織の民主統一党(PYD)の民兵である人民防衛隊(YPG)主体のシリア民主軍とともに、ユーフラテス川東岸でイスラーム国に対する軍事作戦(生来の決意作戦)を行っていた。
一方、ロシアは、シリア政府、「イランの民兵」とともに、ユーフラテス川西岸で、イスラーム国、シャームの民のヌスラ戦線(現シャーム解放機構)が主導する反体制派に対する掃討戦を行っていた。
「非紛争地帯」以外の地域は、ロシア軍とシリア軍が制空権を握っている。だが、イスラエル軍が頻繁に越境爆撃を行い、また米軍も2月2日のイドリブ県アティマ村近郊でのイスラーム国のアブー・イブラーヒーム・クラシー指導者暗殺作戦に代表される軍事作戦を繰り返し、「非紛争地帯」にかかる合意を無視してきた。
関連記事
■米国が、シリアでイスラーム国指導者を殺害 その意味とは(Newsweek日本版)
■イスラエル軍がシリアをミサイル攻撃し民家などに被害、ロシア軍は電子戦システムを作動させ攻撃を妨害

ウクライナ情勢と無関係か?
2月15日のロシア軍機による「非紛争地帯」進入を受け、米国はロシア側に事前通知が不十分だと警告した。だが、ロシア側はそのまま飛行を継続すると返答した。そのため、米空軍のF-16戦闘機などからなる有志連合の航空機が対応し、ロシア軍機が「非紛争地帯」を出るまで並行して飛行、これを誘導したという。
「非紛争地帯」を出たロシア軍機は、シリア駐留ロシア軍司令部が設置されているラタキア県のフマイミーム航空基地に着陸した。
ロシア軍はまた、約6時間後にも同様の行動を繰り返し、別の貨物機と軍用機が同じ空域を通過した。
CNNは、今回の事案に関して、ウクライナ情勢をめぐって米国とロシアの緊張が高まるなかで発生したが、米国は現時点でこれらの問題が関連していると考えていないと強調した。
だが、2月15日にはロシアのセルゲイ・ショイグ国防大臣を代表とする軍事使節団がシリアを訪問し、タルトゥース港(タルトゥース県)沖の地中海東部でのロシア海軍の軍事演習やシリア駐留ロシア軍司令部が設置されているフマイミーム航空基地を視察、バッシャール・アサド大統領とも会談した。また、これと合わせて、ロシア軍はTu-22M中距離爆撃機、MiG-31迎撃戦闘機を地中海東部での軍事演習に参加させるためにフマイミーム航空基地に配備した。
関連記事
■ロシアのショイグ国防大臣がシリアを訪問し、アサド大統領と会談する中、首都ダマスカスなどで爆破テロ発生
こうした動きは、アラブ・メディアでは、ウクライナへのロシア軍の侵攻を抑止するとして、米軍がドイツや東欧に部隊を派遣し、NATO海軍が地中海で軍事演習(ネプチューン・ストライク)を敢行するなか、ロシア軍がこれに対抗するために軍事プレゼンスを誇示していると報じられている。
今回のロシア軍機による「非紛争地帯」通過も、ロシアの対抗措置の一環をなしていると見ることができる。CNNによると、米軍はロシア軍機を誘導したと伝えている。だが、ロシア軍の動きを阻止するには至っておらず、ロシア側は、「威力偵察」とでも言うべき動きを通じて、米国の行動力や決断力(の低さ)を見極めることに成功しているのである。
米国と有志連合のシリア駐留は国際法違反
なお、「非武装地帯」設置の前提となっているシリアでの有志連合による軍事作戦は、シリア政府を含むシリアのいかなる主体の同意を得ておらず、国際法上は違法である。だが、米国はシリア政府の正統性を一方的に否定するとともに、シリア民主軍を「協力部隊」(partner forces)と位置づけ、現在も「テロとの戦い」、油田地域の防衛を口実に、同地とヒムス県南東部のタンフ国境通行所一帯地域(通称55キロ地帯)の27カ所に基地を設置、900人から3,000人と言われる将兵を違法に駐留させている。