【光る君へ】紫式部が予見した、誇り高き清少納言の「風流とは程遠い顛末」とは(家系図/相関図)
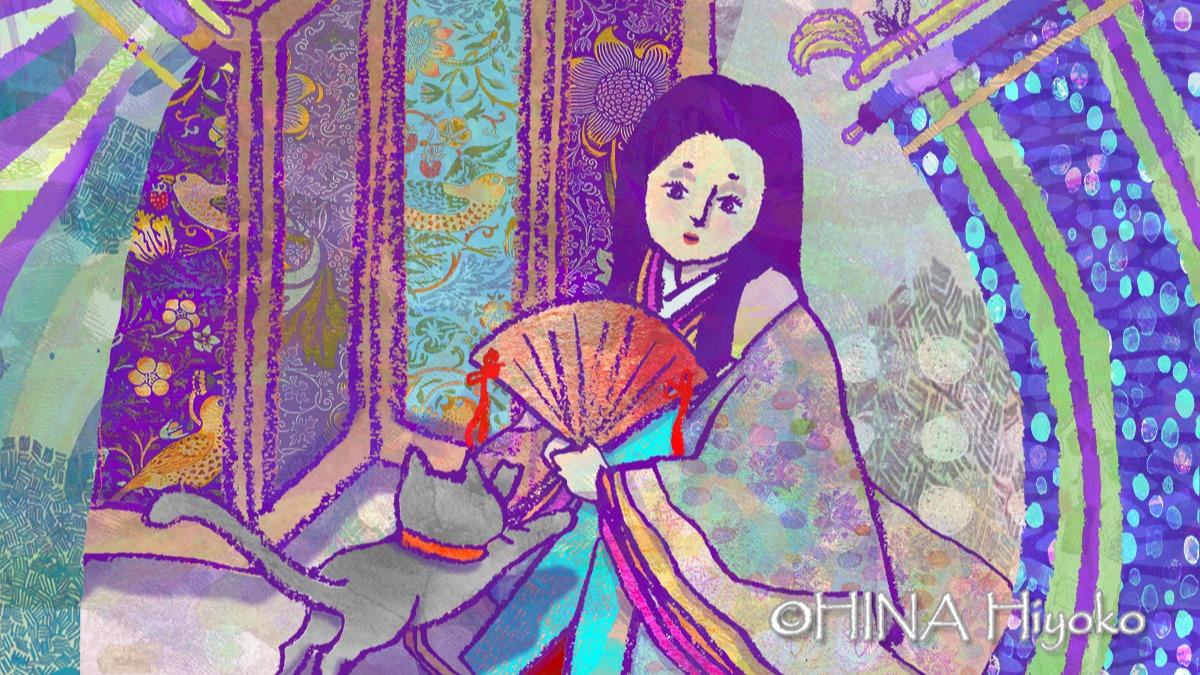
NHK大河ドラマ『光る君へ』。世界最古の小説『源氏物語』の作者・紫式部(演:吉高由里子)と、平安時代に藤原氏全盛を築いた藤原道長(演:柄本佑)とのラブストーリー。
早いもので、今回の大河ドラマもそろそろ折り返し。ついに、まひろ(紫式部)に藤原宣孝(演:佐々木蔵之介)が求婚。
宣孝が越前に行った記録はない、当時の男性はあんなにストレートに求婚しないなどといった声はあるが、それにしても宣孝がカッコいい。これまでのコミックリリーフぶりを忘れるほどだ。
「忘れ得ぬ人がいてもよろしいのですか」と尋ねるまひろに「よい、それもおまえの一部だ」これだけでも胸キュンなのに、そのうえで「おまえを丸ごと受け止められるのはわししかいない」。
大した自信だけど、確かにその通りなのかもしれないと思わせてしまう説得力、さすがだ。
そんな2人の結婚生活についてはコチラの記事に書いている。
(参考記事:【光る君へ】正反対だから惹かれあった?陰キャな紫式部の結婚生活とは?(相関図・家系図)5/19
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/8c13e094f940a0e6c6e1f90f69c0d91019e65944)
◆このドラマで見方が変わったNo.1は道長ではなく清少納言?
◎自慢話・悪口満載の『枕草子』の真実
さて、今回の主役は清少納言(ききょう・演:ファーストサマーウイカ)である。授業で習った清少納言のイメージといえば、「『枕草子』で自慢話と人の悪口ばかり書いている人」と感じていた人が多いのではないだろうか。
確かに彼女は『枕草子』の中で、自分がいかに才気にあふれ中宮定子(演:高畑充希)に認められていたかを綴っている。(香炉峰の雪:第284段)
さらに、身分の低い者や年取った者、容貌の優れない者へは、以下のように手厳しい。
・似合わないもの。下々の家に雪が降る景色、下々の家に月の光が差し込むのもせっかくの月が台なし。年取った妊婦。若い夫がほかの女のもとへ通うのに嫉妬する女。女官のまねをして紅の袴をはく身分の低い女(第42段)
・不器量な女と瘦せこけた貧相な髭面の男が添い寝するのは見苦しい(第105段)
・みすぼらしくつらそうに見えるものは、貧相な牛の引く汚らしい牛車。みすぼらしい身なりをした女が子どもを背負った姿。年取った物乞い(第118段)
しかし、清少納言は『枕草子』を己の自己顕示欲を満足させるために書いたわけではない。自慢話と見せかけて、彼女が本当に書きたかったのは「定子その人の輝き」であった。
そして重要なことは、彼女が『枕草子』を書き始めたとき、すでに定子の後宮はその輝きを失いつつあったということ。この事実を知るとき、清少納言と『枕草子』の見方がガラリと変わるのではないだろうか。
『枕草子』は、父・藤原道隆(演:井浦新)の死去で後ろ盾を失い、没落の一途をたどる定子とその後宮をたたえるために書かれたことは間違いない。ドラマ同様、絶望の淵にあった中宮を慰め、生きる糧となっていた可能性はあるだろう。
◎「女房は天職?」清少納言はどんな家に生まれた?
清少納言とはどのような人物で、どのような人生を送ったのか。
以前にも紫式部と比較しつつ、清少納言の出自や性格についてはコチラに書いたが、簡単におさらいしたい。
(参考記事:【光る君へ】紫式部と清少納言、どちらが偉い?どちらが幸せだった?(家系図/相関図)1/21
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/91bee207d86893e42718492eaee5bc8e569744bf)
さまざまな資料から、清少納言は陽気で、女房が天職のような人だったと推察されている。
出仕後すぐに家に逃げ帰ったと伝わる紫式部ほど、清少納言は女房勤めに対して、苦手意識はなかったようである。それは彼女の性格だけではなく、身分の違いも影響しているかもしれない。
当時は藤原氏全盛。とくに主流となったのが藤原北家。紫式部の家系は傍流ではあるが、れっきとした藤原北家である。

こちらが清少納言の家系図と並べたもの。

元名門出身の紫式部にとって、女房勤めはかなり抵抗のある事だった。姫君がいきなり召使になると考えれば、納得できるかもしれない。
当時の出世コースから、かなり離れた場所にいる清少納言には、もとよりそんなプライドは必要なかったのかもしれない。
◆清少納言の最初の結婚
◎引きこもった清少納言に届いた、定子からの手紙とは
しかし清少納言も、常に強く明るく前向きだったわけではない。
『枕草子』には、清少納言の初出仕の記載がある。定子の顔をまともに見られないほど緊張していたと書かれている。(第179段)
また、清少納言は道長一派である藤原斉信(ただのぶ・演:金田哲)と親しかったせいで、道長側に通じていると噂が立った。
ドラマの中では描かれなかったが、定子が第一子を出産した996年秋頃、噂を気にして長く実家に引きこもったと『枕草子』には書かれている。(第138段)
そんな彼女に定子は山吹の花びらに「言はで思ふぞ(口には出さなくても思っていますよ)」と一言だけ添えた文を送る。
勇気を出して再出仕した清少納言に定子は「あら、そこに見えるのは新しい女房かしら」(もちろん清少納言のこと)とユーモアを忘れない。
定子と清少納言は、ただ一方的に少納言が支えただけではなく、お互いに支え合う関係だったのである。
◎無骨でいい人だけど…夫・橘則光との関係
清少納言の最初の結婚はおそらく981年頃で、彼女は15歳くらいだったと考えられている。夫は花山天皇の乳母の子で、斉信の家司(かせい:執事)を務めた橘則光。子に則長がいる。
夫の則光は武勇にも容貌にも優れ、盗賊を取り押さえたという逸話も残る好男子だが、『枕草子』にはモノのわからない野暮で気弱な人物として描かれている(第80段)。
則光は和歌が苦手で、和歌をよこすなら別れるときにしてくれ、と常々言っていた。そんな夫に清少納言は別れの和歌を送ったが、則光は「また和歌なんてよこして!」と見もしなかったという。
実は則光は、いくつかの和歌集に和歌が収録されている勅撰歌人。人並み以上に和歌は詠めたと考えられる。
また、清少納言は実は和歌にはさほど自信がなく、父・清原元輔の名が重いと書いている(第95段)。
夫婦どちらにとっても歌人の名門・清原の名は重かったのかもしれない。
998年頃、則光が遠江(とおとうみ:現在の静岡県)に赴任したことをきっかけに、2人は別れたとされるが、のちに出てくる説をとれば、ここはつじつまが合わない。
◎伊周の失脚を足掛かりにした出世欲の男…藤原斉信との関係
定子の身内以外で『枕草子』に数多く登場する貴公子が前述の藤原斉信である。
斉信は現在は道長一派であるが、道隆が権勢をふるっていた頃は当然、定子の後宮に足しげく通っていた。
一時期、斉信は清少納言の悪い噂を信じ込み、彼女と絶交状態になっていた。それでも彼女のことが気にはなっていたのだろう。あるとき仲間内で清少納言の噂になり、その場のノリで彼女の実力を試してやろうと歌をよこしたという。
(このあたり、『源氏物語』のホモソーシャルな集い(雨夜の品定め)をほうふつとさせる)
彼女の返歌があまりに見事で、斉信との仲たがいは解消されたようだ(第78段)。
『枕草子』に描かれる清少納言と斉信との関係は、『紫式部日記』の紫式部と道長の関係と比較してもあまり艶っぽくはない。
2人のやり取りを読んで筆者が感じたのは、紫式部と道長とはまったく異なる「対等な関係」である。
本来は受領の娘で後宮に出入りできる身分ではない自分が、当代きっての上流貴族である斉信と対等に渡り合えていることを、清少納言は書き残したかったのだろう、と研究者・赤間恵都子さんも書いている。
定子の兄・伊周が失脚した「長徳の変」の舞台となったのは斉信の屋敷。ことの次第を道長に告げたのもドラマ同様、斉信だといわれている。直後に斉信が参議に昇進したのは当然その功績だろう。
道長が「はめられた」というように、斉信は出世欲の強い抜け目のない人物だったと伝わる。自分の主家の没落を足掛かりに出世する斉信を清少納言はどう感じていたのか。
2人が大河ドラマのような男女の仲だったかどうかは不明だが、個人的には「一度くらい関係を持ったからって、自分の女扱いしないで」と斉信にいうききょうにしびれた。
清少納言なら、これくらいのことは口にしてバッサリと貴族男性をぶった切ってくれそうである。

◎あの有名な和歌のもととなったエピソード…藤原行成との関係
大河ドラマでは「道長大好き」を隠さない藤原行成(演:渡辺大知)だが、実は清少納言ともかなり仲がよかったようである。
清少納言は『枕草子』で行成を「見た目は普通だしデキる感じもしないけど、実は並みの男ではない」と、微妙な表現でほめている。
『小倉百人一首』におさめられた清少納言の和歌
「夜をこめて 鳥の空音(そらね)は 謀(はか)るとも よに逢坂(あふさか)の 関は許(ゆる)さじ」
は、実は行成とのやり取りの中で生まれた。
もとは中国の歴史書『史記』にある故事。鶏の鳴き声を合図に開く関があり、鶏のまねが上手な者が関守をだまして関を開けさせた、という話から。
「鶏のモノマネなどしても逢坂の関は開きませんよ」がこの和歌の意味。
それに対して行成は
「逢坂は 人越えやすき関なれば 鳥鳴かぬにも 開けて待つとか(逢坂の関は超えやすい関なので、鶏が鳴かなくても開けて待つのでは)」
と返している。
これは、「あなたにはなびきませんよ」という清少納言に対して「あなたはきっと待ってくれているはずだ」と行成が返しているともいわれる。
でもこれって、「清少納言はガードが甘い」という意味にもとれる?う~~ん。
ただ清少納言と行成は男女の仲だったわけではなく、和歌の中で大人のお遊びをしていただけ、というのが定説のようである。
◆清少納言の晩年
◎藤原棟世との再婚
清少納言は則光と別れ、父の友人で20歳以上年の離れた藤原棟世と再婚している。2人の間に生まれた上東門院小馬命婦はのちに中宮彰子に出仕しており、その時期から2人の結婚は986年頃だとする説もある。
しかし、となると彼女が定子の女房となった993年にはすでに棟世と再婚していたことになる。996年頃に執筆をはじめた枕草子に前夫則光の記載はあるが、棟世の名がないのは不思議である。
いずれにしても清少納言は、定子の死後は出仕をやめて、棟世の赴任先に同行したと伝わる。棟世は摂津守だったので、京からほど近い現在の大阪北部で暮らした。
清少納言はおそらく35歳前後。国司夫人として子育てをしながら、たまに『枕草子』に加筆したりして優雅に暮らした模様である。
しかし年の離れた夫は数年後に死去。清少納言は京都に戻り、東山月輪の山荘に移り住んだ。ここで亡くなったと伝わるが、正確な没年はわかっていない。
東山月輪がどこであるかは諸説ある。一説によれば、現在の泉涌寺(せんにゅうじ)のあたりだとされる。泉涌寺境内には清少納言の歌碑が建てられている。
泉涌寺は皇室の菩提寺(御寺)であり、定子の墓所・鳥戸野陵にほど近い。
定子の菩提を弔いながら暮らしたと考えるのは自然だが、清少納言の時代には、このあたりは月輪と呼ばれていなかったともいわれる。
◎少しわびしいくらいが風流な女の一人暮らし
清少納言には、晩年の落魄説がいくつも流れている。
その理由の一つが、紫式部が『紫式部日記』において「清少納言のような人の行く末にいいことなどあるはずかない」となかば「呪い」のようなことを書いたせいだともいわれる。
落魄説をいくつかご紹介しよう。
荒れ果てた粗末な清少納言の家の前で若い貴族が「清少納言も落ちぶれたなぁ」と話していた。
すると、彼女は恐ろしい形相で家から飛び出して来て「駿馬の骨を買わないのか」と言い返した(名馬なら骨になっても価値があるという中国の故事から)というが、これはまだいい。
ひどいのはこちら。清少納言が出家後身を寄せた兄・清原致信(むねのぶ)が1017年に襲撃された。
僧形の清少納言も男と間違えられて殺されそうになったが、着物をまくり陰部を見せて女性だと証明したというのだ。
風流と粋を愛した清少納言の行く末とは、にわかには信じられない、信じたくない話である。
冷静に考えれば、彼女は贅沢三昧ではなかったにせよ、落ちぶれてはいなかったはずである。
息子の則長は正五位下・越中守、娘の上東門院小馬命婦も前述のとおり中宮彰子に出仕しているのだから、十分母を支えられただろう。
ドラマの中では親友同士のまひろとききょう。史実において紫式部と清少納言の面識はないといわれているが、2人の娘はともに中宮彰子に仕えている。
紫式部や娘の大弐三位と清少納言の娘との交流については伝わっていないが、大河ドラマでは新しい解釈で描かれることになるかもしれない。
清少納言は『枕草子』の中で「女の一人住まい」について書いている(第173段)。
「女が一人で暮らす場所は、完璧な住まいではなく、少し荒れて寂しげなくらいがちょうどよい」の言葉通り、質素でありながら楽しく暮らしたのではないだろうか。
清少納言なら、質素で少し寂しい住まいの中に「いとおかし(素敵)」なものをたくさん見つけて暮らしたのだと『枕草子』ファンならば信じたいところである。
(イラスト・文 / 陽菜ひよ子)
◆主要参考文献
歴史読み枕草子: 清少納言の挑戦状(赤間恵都子)(三省堂)
枕草子(角川文庫)
フェミニスト紫式部の生活と意見 ~現代用語で読み解く「源氏物語」~(奥山景布子)(集英社)
ワケあり式部とおつかれ道長(奥山景布子)(中央公論新社)
紫式部日記(山本淳子編)(角川文庫)










