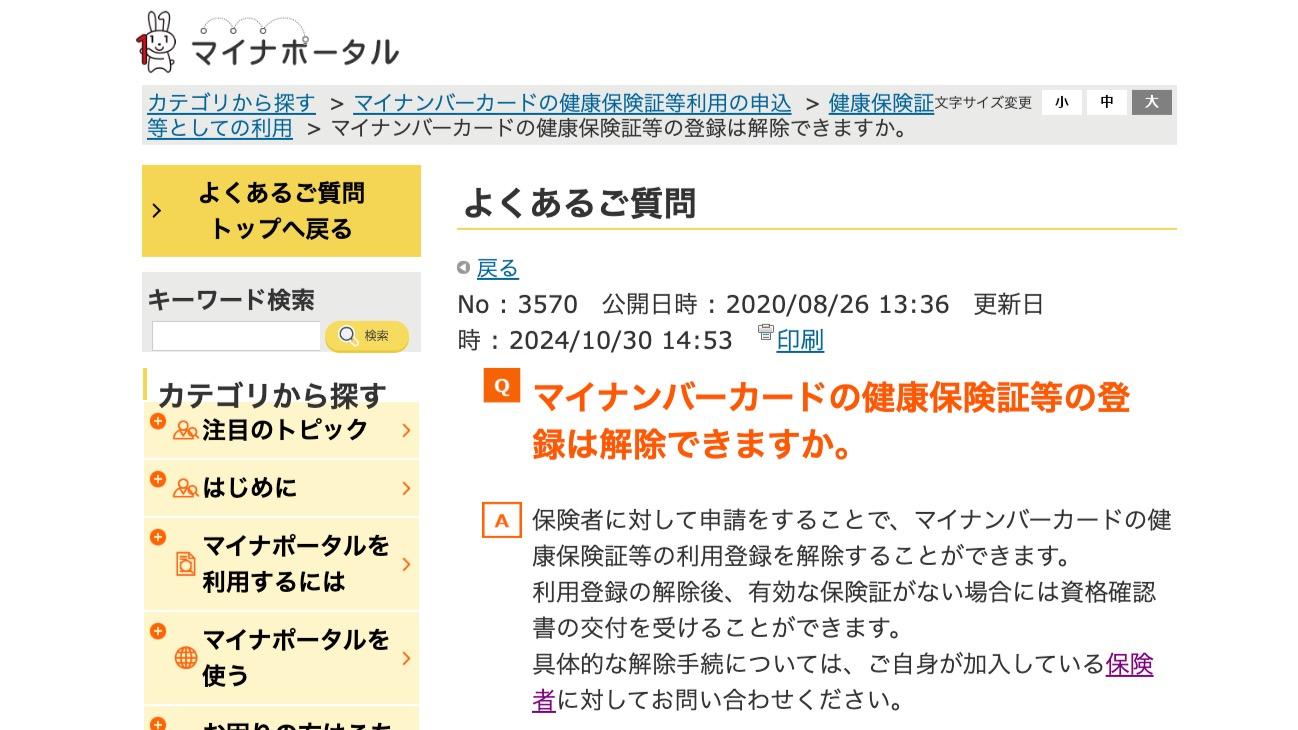【戦国こぼれ話】今村翔吾さんの小説『塞王の楯』に登場する石垣職人「穴太衆」とは

直木賞を受賞した今村翔吾さんの小説『塞王の楯』では、石垣職人「穴太衆」が重要な役割を果たしている。彼らがいったいいかなる集団なのか、深く掘り下げてみよう。
■穴太衆とは
穴太衆は、「あのうしゅう」と読む。その本拠は現在の滋賀県大津市坂本穴太で、比叡山の麓にあった。もともと穴太衆は、古墳を築造していたといわれている。
横穴式石室墳の穴太古墳群は、花崗岩の野面石(自然石)を乱積みしたもので、石の積み方は高句麗や百済でも確認できる。
それゆえ、穴太の横穴石室は、朝鮮半島から伝わった技術であるといわれている。それが、のちの穴太衆によって継承されたと推測される。
その後、穴太衆は天台宗寺院の延暦寺、日吉大社とかかわり、特に延暦寺の末寺の里坊の石垣は彼らが築いたもである。
石の積み方は、自然石を加工しない方法で、今も大津市内では美しい街並みとして残っている。以来、穴太衆は寺院の石工を生業とするようになった。
■戦国時代以降の穴太衆
戦国時代になると、穴太衆の活躍がクローズアップされるようになった。元亀2年(1571)、織田信長は比叡山の焼き討ちを行った。焼き討ち後、信長は比叡山の石垣を崩そうとしたが、びくともしなかった。
石垣のあまりの堅牢さに信長は驚愕した。天正4年(1576)、信長が安土城(滋賀県近江八幡市)を築く際、穴太衆に石垣を築かせた。現在、安土城には石垣の遺構が残っているが、それは穴太衆がすべて築いたものである。
以降、穴太衆の石工としての手腕が高く評価され、各地の築城に動員された。信長以外にも、豊臣秀吉が重用したという。今も、穴太衆の技術は継承されている。
■穴太積みとは
穴太積みとは、先述のとおり加工しない自然石を石垣として積み上げる技法のことである。石の形がバラバラであるが、巧みに配置された石は容易に崩れることがなかった。
なお、穴太積みとは、野面積みとイコールのように思われるが、決してそうではない。江戸後期以降、その独自の積み方を穴太積みと称するようになった。
穴太積みの真髄は、以下の2点に集約されよう。
①使用する石材の声を聞き、その心を知ること。
②使用する石材を適所に配置し、安定感のある積み方をすること。
こうして穴太積みは高く評価され、戦国時代には多くの城の石垣で採用されたのである。
■むすび
石垣の積み方には、このほか「打込み接ぎ」、「切込み接ぎ」といった石を整形した技法もある。城を見学する際には、石垣の積み方にも注目すべきだろう。