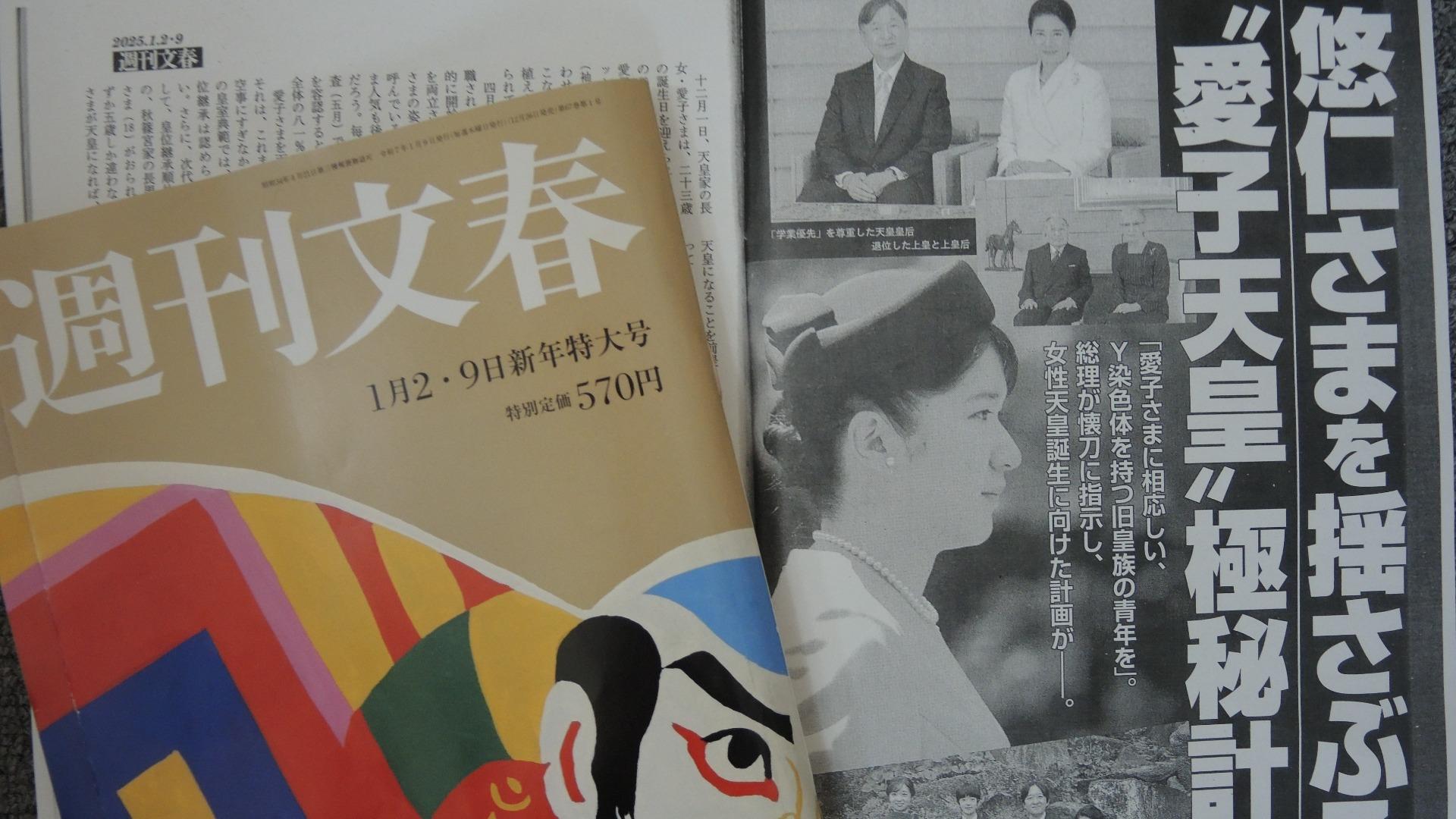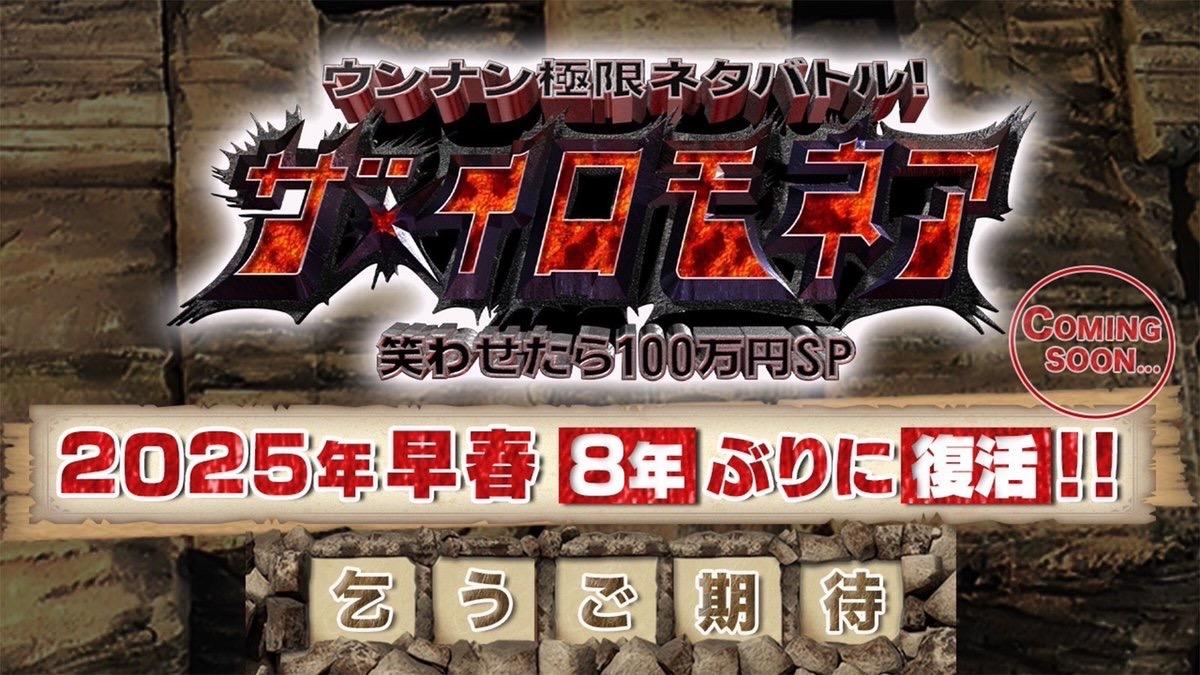「不倫」をしても離婚請求はできるのか(その1)~請求が認められる「3つ」の要件

不倫をした配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか。もし、このようなことが裁判で認められたら不条理なような気がします。では、実際にどのような判決が出されてきたのか見てみることにしましょう。
「有責配偶者」からの離婚請求は認められなかった
夫婦関係が破綻して回復の見込みがない状態にある場合でも、有責配偶者(不倫をしたなどで夫婦関係の破綻の責任がある配偶者)からの離婚請求(民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」の規定に基づく離婚請求)を判例は長く否定する態度をとってきました。
民法770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
有責配偶者からの離婚請求を認めてしまったら、正義に反することですから、ある意味当然と考えられます。
有責配偶者からの離婚請求が緩和
しかし、夫が妻以外の女性と同棲している事実があっても、妻との婚姻関係が完全に破綻した後に生じた場合には、5号による離婚請求を排斥すべき理由はないとする判決(最高裁判決昭和46年5月21日)が出たことで、有責配偶者からの離婚請求を否定する考えが緩和していきました。
よく、著名人の不倫の会見で、配偶者のある者と不倫関係にあった者が、「(不倫)相手の夫婦関係は破綻していた」と釈明することを聞くことがありますが、この判決が影響していると考えられます。
また、以下のような有責配偶者からの離婚請求を、一定の条件の下で、夫婦関係が破綻している事実のみを離婚原因とする判決が出てきました。
・別居生活が相当な長期となり、家庭裁判所の調停により真摯な和合の試みがなされた場合に、特段の事情がない限り離婚請求を容認できる(東京高裁昭和55年5月29日)
・36年間にわたる別居により婚姻関係の破綻している夫婦について、夫の有責性が年月の経過により風化しており、子の福祉を害し、妻が経済的苦境に立つこともないとして有責配偶者である夫の離婚請求を容認した判決(仙台高等裁判所昭和59年12月14日)。
有責配偶者からの離婚請求を認める「3つ」の要件
そして、最高裁判所は、昭和62年(1987年)に前述の民法770条1項5号所定の事由について、「有責配偶者からの離婚請求を認めないという趣旨まで読みとることはできない」として、以下のような従来の判例理論を変更する判決を下しました。
離婚請求が信義則に照らして許されるものであるかどうかを判断すべきであるとして、「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んだこと」(相当期間の別居)、「未成熟子の不存在」、「相手方配偶者が離婚により精神的・社会的にきわめて過酷な状態に置かれることがないこと」(過酷状態の不存在)という3つの要件が満たされる場合に離婚請求が容認される(最高裁判決昭和62年9月2日)。
その後、有責配偶者からの離婚請求については、この最高裁判所が示した、「相当期間の別居」「未成熟子の不存在」そして「過酷状態の不存在」の3つの要件を柱に議論されるようになっています。
このように、有責配偶者からの離婚請求が認められる判決は出ていますが、だからといって、不倫を肯定しているわけでは当然ありませんので念のため。