コロナ禍で気になる「日本茶の研究結果」3選!実はすごいお茶のパワー
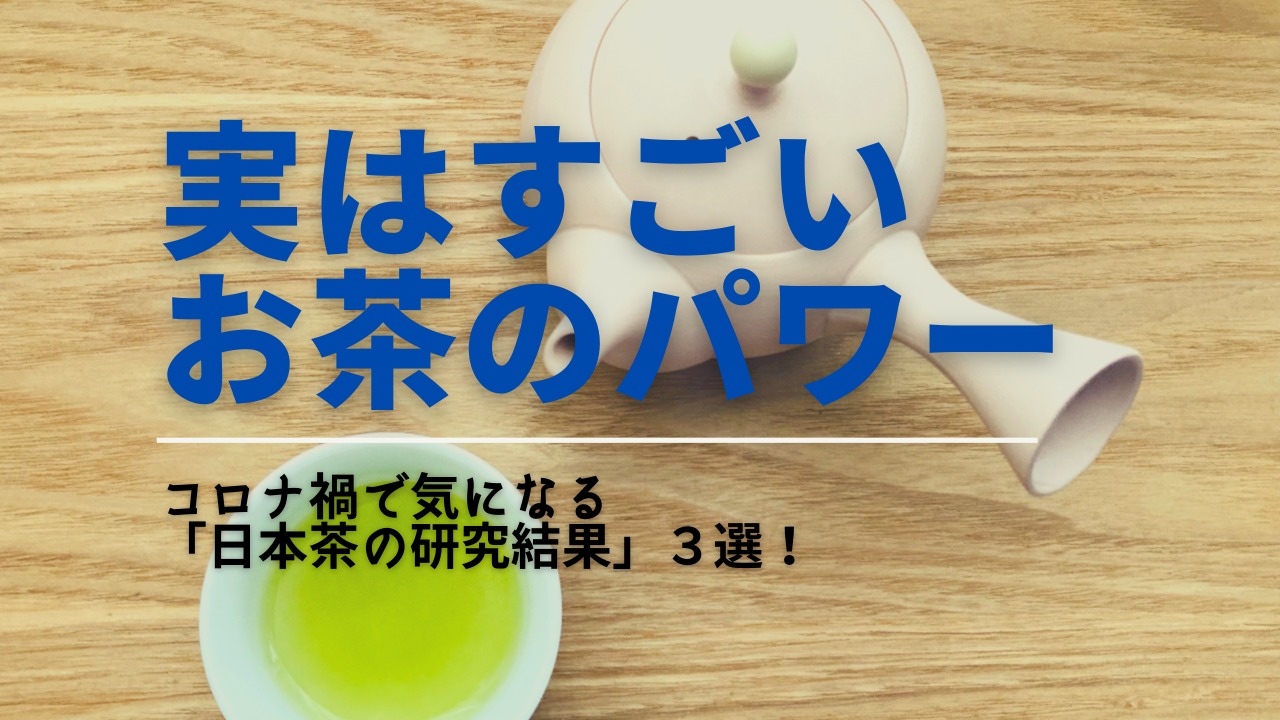
「お茶は体に良い」とか「風邪予防に良い」とかいろいろ聞くけど、実際どうなの?って思っている方、多いのではないでしょうか。
お茶の成分やその効果については長年いろいろな機関で研究が進められていますが、昨年から今年にかけてはコロナ禍におけるお茶の研究が行われ、次々と研究結果が発表されています。
その中から、今私が注目している最新のものを時系列で3つご紹介します。
その1.奈良県立医大の発表「市販のお茶に新型コロナウイルスを不活化(無害化)する効果」
昨年(2020年)の11月下旬、日本茶業界で「ついに!」と話題になったのが、奈良県立医大の発表です。
読売新聞の記事によると、
実験したのは、市販されているペットボトル入りの緑茶2種類、茶葉から入れた紅茶と大和茶の計4種類。ウイルスが入った液体を混合し、作用を調べた。その結果、30分後に紅茶は99・99%、大和茶は99・9%までウイルスが減少。ペットボトルでは緑茶1種類も99%まで減り、別の緑茶はあまり変化がなかった。ボトル入りのお茶や茶葉など数百種類以上から無作為で選んでおり、矢野寿一ひさかず教授(微生物感染症学)は「感染力を失わせる能力が高いお茶とそうではないお茶があった」と説明。不活化する仕組みは不明だが、お茶に含まれるカテキンが関係する可能性を指摘した。
とあります。
ちなみに、記事中の「大和茶」というのは奈良県で生産されたお茶のことです。
茶葉からいれたものは紅茶も緑茶も効果があったとのこと。しかし、試験管での研究結果なので人の体内でどのような働きをするかは未確認のようです。
2020年度は茶葉の市場価格がかなり落ち、生産者など関係者には大打撃となって落ち込んでいた日本茶業界には久しぶりの明るいニュースで、とても嬉しく思ったのですが、それほど大きなニュースになることなくそのまま過ぎ去った感が否めません・・・。
お茶って地味な立ち位置なのでしょうか(泣)。
それはさておき、記事詳細や研究については下記のリンク先にありますので、ご興味ありましたらご覧ください。
読売新聞の2020年11月28日の記事(外部リンク)
奈良県立医科大学のプレスリリース(外部リンク)
その2.京都府立医大と伊藤園の共同研究「茶カテキン類による新型コロナウイルス不活化効果を試験管内の実験で確認」
こちらは今年(2021年)6月に発表されたものです。
茶カテキン類がウイルスのスパイクたんぱくに結合し、細胞への感染能力を低下させる効果などを確認しました。また、試験管内でヒト唾液中に加えたウイルスに対しても、茶カテキン類による迅速かつ効果的な不活化がみとめられました。
とあり、唾液を使ったという点で、上の奈良県立医大の発表より少し進んだ内容になっているようです。
茶カテキン類は、茶類に高濃度に含まれます。しかし茶類を経口摂取しても血液中への移行は少なく、特に重合したカテキン類はほとんど吸収されません。そこでお茶を飲んでも、消化管から吸収されたカテキン類が全身的に作用する効果は期待しにくいと考えられます。一方で、お茶を口中に含んだ時に、口腔内で唾液中のウイルスが茶カテキン類によって不活化される効果は期待できると考えられます。それゆえ、多くの人がお茶を飲めば、唾液中のウイルスが不活化されることによって飛沫感染が減少し、人集団全体としてはウイルスの感染拡大を減弱させられる可能性は考えられます。たとえば飲食店などで、マスクを外したら会話する前にまずお茶を含み飲みする(10秒間程度口腔内全体にお茶を行き渡らせてから飲む)、といった行動を多くの人がとれば、症状のない感染者から周りの人への感染が減らせるかもしれません。つまり、お互いに他人のためにお茶を飲むという、「公衆衛生的な」使い方は有効な可能性があります。
お茶を口に入れて少し置いてから飲む「含み飲み」がおすすめ、とあります。
外出時などはいつも自分で淹れたお茶をボトルにいれて持ち歩いていますが(うっかり忘れたらペットボトル)、ちょっと意識してみたいと思います。
もちろん、インフルエンザ予防でよく聞く「お茶でうがい」も良いとされていますし、お茶の香りですっきりするので気分転換にもなると思います(あくまで個人の感覚です)。
ただし、こちらの研究も試験管内での研究となり、まだまだ今後も研究が続けられるようです。
京都府立医科大のホームページ(外部リンク)と伊藤園中央研究所主催の「伊藤園健康フォーラム」のサイト(外部リンク)より詳細が見られます。
後者は前回の健康フォーラムのアーカイブも見られ、さらに次回9/3配信の健康フォーラムのお知らせもあります(8/29現在)。
その3.静岡県環境衛生科学研の発表「緑茶成分にコロナ不活化効果 ウイルスの細胞感染力を抑制」
最新の研究発表はこちら、つい最近、今年(2021年)8月10日に発表され、静岡新聞に掲載されたものです。
試験管レベルで緑茶成分のエピガロカテキンガレート(EGCG)に、ウイルスが細胞に感染する力を抑制する効果が認められた。
とあり、まだこれから研究内容の査読が行われるとのことなので、今後改めて発表があるのではと思います。記事は静岡新聞サイト(外部リンク)をご参照ください。
エピガロカテキンガレート(EGCG)はいくつかあるカテキンのの中で緑茶を熱いお湯で淹れたときによく出る成分の1つで、強い苦味と渋味の成分で、抗炎症作用があると言われています。

水出し緑茶の場合はエピガロカテキンガレート(EGCG)は出にくいのですが、水出しは免疫力アップに関わると言われるエピガロカテキン(EGC)が摂取できると別の機関で研究されています(参照:外部リンク農研機構ホームページ)。
今後も様々な研究結果が明らかになりそうで、ワクワクします。
お茶は薬ではなく嗜好品
1000年以上前に中国から薬として伝わったお茶。今は日常を豊かに楽しむ嗜好品です。
ここまでお茶に関する様々な研究結果をご紹介しましたが、お茶は薬ではありませんので、そのおいしさや香りを楽しむ飲み物として「飲んでいてもし何か健康面で良いことがあったらラッキー!」くらいのスタンスで生活に取り入れるのが良いのではと個人的に思います。
また、お茶に含まれるカフェインは摂りすぎには注意が必要な成分です。体に良いと言われるカテキンに対しても稀にアレルギーを持つ方がいたり、鉄剤を飲んでいる方の場合は鉄分の吸収を阻害するためお茶と一緒に飲まないようにお医者さんから言われたりもします(私も以前そう言われお茶を飲むのを控えていた時期があります)。
それを踏まえた上で、適量を楽しむ。この「楽しむこと」なしに義務のように飲むのはおすすめしません。自分の味覚に合うものでないと楽しめないので、味覚に合わないものを無理に飲むのは良くないと思います。
飲んでリラックスしたりリフレッシュできる、それが一番ではないでしょうか(お茶に限らず)。
急須で淹れるのが大変なら、ティーバッグやペットボトルのお茶も良いと思います(もちろん時間と余裕と道具がある方は急須で淹れた時のお茶の味と香りは格別なのでぜひ!)。
このお茶の味が気に入っているから飲む、ちょっと出がらしのお茶でうがいしてみようかな、など気軽な気持ちで日本茶を楽しんでいただけたらと思います。

最後に、お茶の効能について初心者の方向けにわかりやすくまとめてあるページをご紹介します。
Japan Tea Action「お茶の効能」(外部リンク)
お茶の淹れ方のヒントなどもありますのでぜひご覧ください。お茶の見方が変わるかもしれませんよ。










