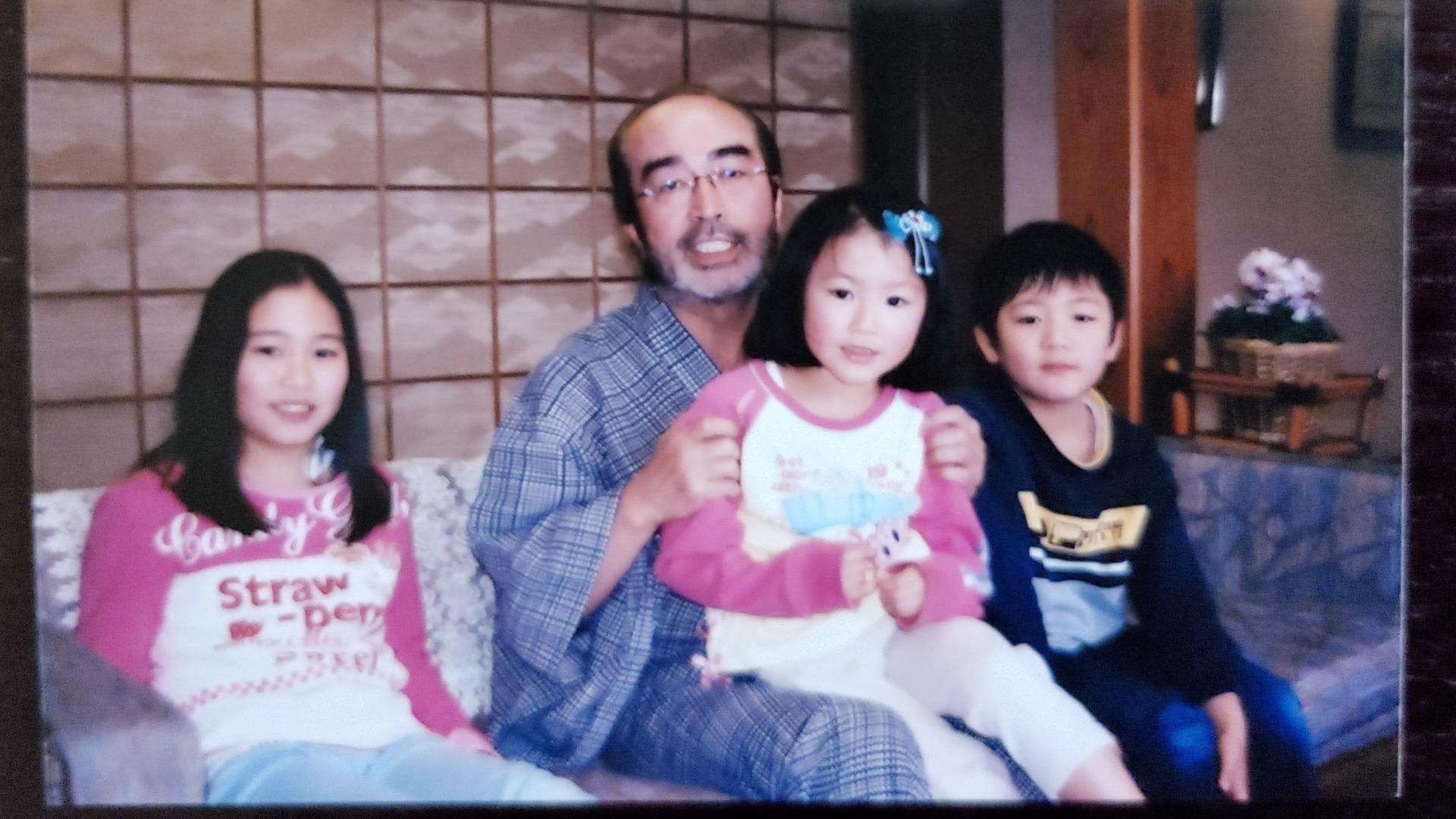GW映画のラインナップにマンガ市場の構造的変化を痛感せざるをえない
それにしてもこのゴールデンウイークの映画のラインナップはすごい。劇場アニメとマンガ原作の実写映画が目白押しなのだ。「ドラえもん」「クレヨンしんちゃん」「名探偵コナン」などは言うに及ばないが、実写映画でも「暗殺教室」「ちはやふる」「テラフォーマーズ」「アイアムアヒーロー」等々…。それに「僕だけがいない街」も予想を超えるロングランになっている。
その中でも「暗殺教室」と「ちはやふる」の闘いは象徴的だ。原作はそれぞれ集英社と講談社のマンガだが、製作がフジテレビと日本テレビ。マンガの原作は出版社が版権を管理しているのだが、映像化作品の権利についてはテレビ局が獲得し、しかもそれが以前とは比較にならないほど大きなビジネスになっている。フジテレビも日本テレビも実写映画とアニメの権利を獲得し、映画部門とアニメ部門と局をまたいで大展開している。
「暗殺教室」は実写映画公開にあわせて1月から6月までアニメを放送。しかもそれは同作品の『週刊少年ジャンプ』での連載終了というタイミングにも合わせたもので、大きな盛り上がりを見せている。フジテレビは「暗殺教室」について1年前にも実写映画とアニメで大成功を収めており、特にアニメについては、中国を始め、海外配信が予想を超える大きなビジネスになっている。
http://www.ansatsu-movie.com/index.html
一方の日本テレビも、「ちはやふる」二部作の実写映画にあわせて以前放送したアニメの素材を使ってスペシャル番組を放送するなど(来る5月2日にも放送予定)、局をあげたクロスメディア戦略を展開している。今年はこの後、秋に「デスノート2016(仮)」の映画公開もあるのだが、アニメと実写映画を連動させてコンテンツビジネスを展開するというやり方を戦略的に推進している。
http://www.chihayafuru-movie.com/
マンガは大手出版社において、デジタル化とライツビジネスをめぐって新たな展開に至っているのだが、そこにIT企業やテレビ局が関わり、コンテンツビジネスとして大きな市場を形成しつつある。月刊『創』最新号(5・6月合併号)の特集「マンガ市場の変貌」の取材で春から出版社やテレビ局の取材を相当行ったが、マンガをめぐるビジネスが今、大きな構造的変化を遂げようとしつつあることを実感した。
『創』では1990年代半ばからほぼ毎年、この時期にマンガ特集を掲載してきたのだが、戦後のマンガをめぐる歴史のうち現在のこの時期を第3期と呼んでいる。1950年代末から週刊漫画誌が登場して新たな市場を形成しストーリー漫画が大きく花開く時期が第1期。60年代末から青年誌という新たなジャンルが生まれることでマンガ市場がほぼ倍増、大手出版社がバブルともいうべき多大な利益をあげたのが第2期。そしてマンガがデジタル化とライツビジネスの拡大によって新たな飛躍を遂げつつある現在が第3期というわけだ。出版だけをとってみれば、マンガ雑誌が軒並み赤字に転落し、出版社がそれをまとめた単行本を映像化などの仕掛けも活用してヒット商品に押し上げるというビジネスモデルに転嫁していった時期だ。
例えばマンガ市場を分析する時に活用する出版科学研究所の統計データが、今年からマンガのデータに雑誌とコミックスだけでなくデジタルの数字を加えることになった。これは大きな変化で、つまりマンガを紙媒体だけで考えると市場が行き詰まっているという結論になってしまうのだが、デジタルや映像をめぐる売り上げを含めると話は全く違って逆に市場は拡大しているという結論になる。ただ現状においては、出版社はデジタルコミックのデータを公表していないし、映像化や関連商品を含めた市場規模のデータとなると実態の把握はほとんどなされていないのが実情だ。ただ業界の実感として、その部分は急速に拡大しており、いまやマンガ市場を考えるのに、出版だけを考えてはいけない時代になったのは明らかだ。特にこの1~2年の配信ビジネスの急拡大は特筆すべきものと言える。
映像化や配信事業は、日本のマンガを一気に海外へ拡散しつつある。そのマンガの配信ビジネスに積極的に関わろうとしているのが講談社だが、昨年、そのライツ部門に異動した吉田昌平デジタル国際・ビジネス局次長兼ライツ・メディアビジネス局次長(前「ヤンマガ」編集長)に聞いて驚いたのは、「進撃の巨人」や「FAIRY TAIL」が海外で受け入れられているのは当然として、例えば「聲の形」といった作品がアメリカでよく売れているという。日本のマンガは予想を超える規模で海外に市場性を獲得しつつあるのだ。ちなみに吉田さんとはかなり前からの知り合いだが、前述したようにやたら長い肩書になったのは、これまで別々だった国際ライツと国内ライツ(テレビ化映画化)を連動させるために両方を兼務させたためだ。つまり講談社としては、ライツ関連のいろいろな事業を密に連動させて大きなビジネスを展開しようという方向に舵を切っているのだ。
「週刊少年ジャンプ」の元編集長として知られる鳥嶋和彦さんが昨年、突然、集英社専務から子会社の白泉社の社長に移ったことが業界で話題になったが、その鳥嶋さんにこの3月に会って話を聞いた。白泉社は今年、人気マンガ「3月のライオン」がNHK総合でアニメ化され、来年春には実写映画も控えているとあって、大きな期待が寄せられている。
現在もコミックスが初版60~70万部というヒットマンガなのだが、映像化によってそれが100万の大台に乗るだろうと言われている。白泉社にとっても勝負どころと言えよう。ただ鳥嶋社長は「それはもちろんうれしいことですが」と言った後で、「それだけではだめなんです」とこう語った。
「デジタルとライツをきちっと回して、ヒット作が出ない年でも収益が上がるようにしないといけない。そのために権利をきちんととっていかないといけないんです」
そういうコンテンツビジネスをしっかりとやっていけるかどうかが、出版社のマンガをめぐるビジネスの将来の明暗を分けるだろうというのだ。その意味では、集英社・講談社・小学館の大手3社だって将来にわたって安泰かどうか予断を許さないという。
デジタルコミックをめぐっては出版社以外のITなどの会社がどんどん参入しているし、ゲームやアニメと連動させてキャラクターを展開させるというビジネスでは、ゲーム会社はもちろん、テレビ局も本腰を入れて取り組みつつある。フジテレビは今年、人気ゲーム「モンスターハンター」のアニメ製作に取り組むことを既に発表している。
本当に今、日本のマンガとアニメをめぐる状況は、大きく変わりつつある。出版界とかテレビ界といった垣根を超えて、そのコンテンツビジネスは大きな市場規模になろうとしつつあると言える。
2月から3月にかけて出版社やテレビ局をまわってマンガ・アニメに関する取材をしてみて、その構造的変化を実感した。それがどういう実情になっているかについては、ぜひ発売中の『創』の特集をご覧いただきたい。