乾癬患者の血中に増加するTfh細胞とTph細胞 - 病態への関与と治療標的としての可能性
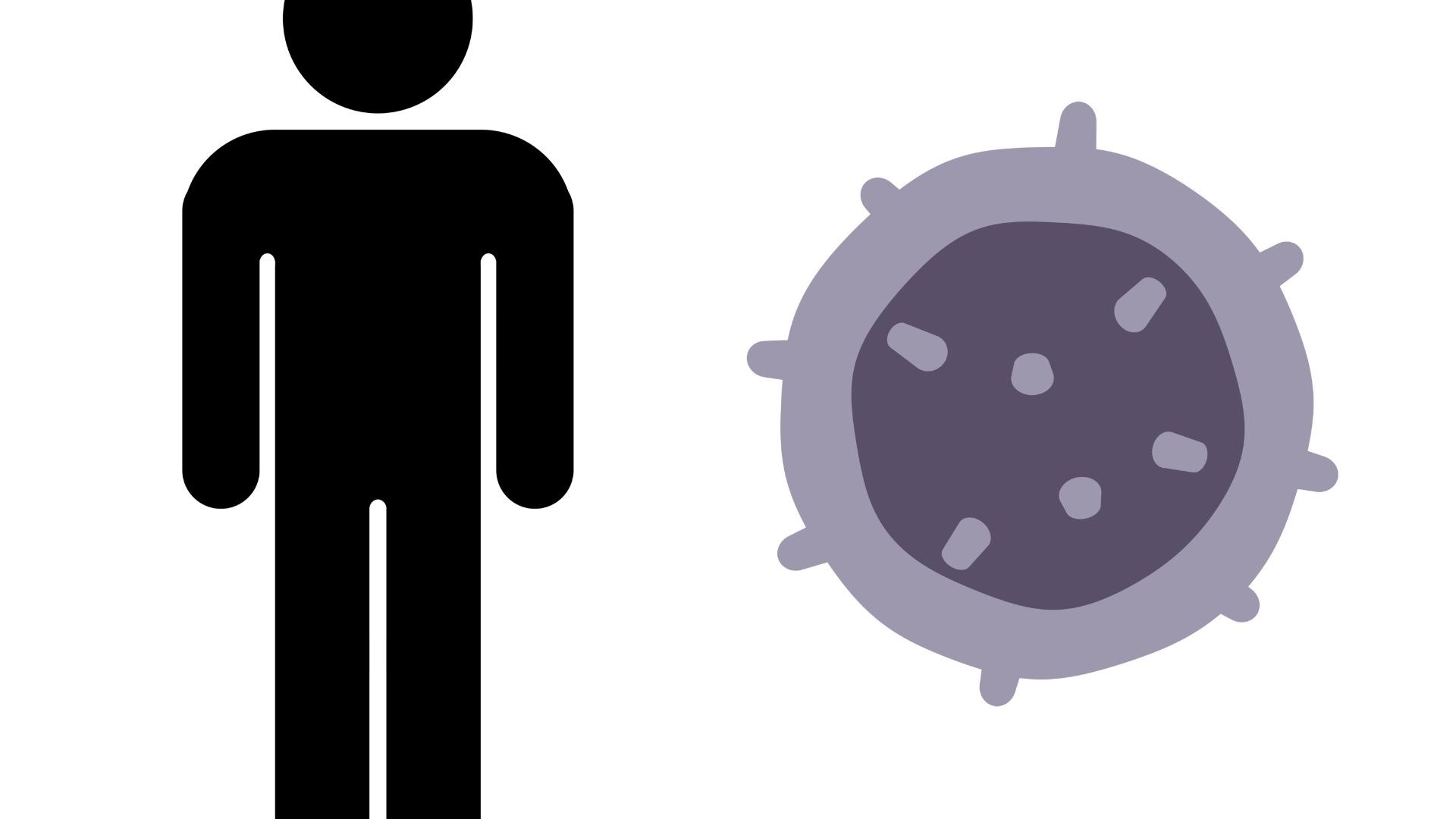
【乾癬治療の新たな選択肢 - IL-17を標的とした生物学的製剤】
乾癬は、皮膚に炎症性の発疹が生じる慢性の皮膚疾患です。近年、乾癬の病態にIL-17(インターロイキン17)という炎症性サイトカインが深く関与していることが明らかになってきました。IL-17は、免疫担当細胞の一種であるTh17細胞から産生され、炎症反応を促進する働きを持っています。
この研究成果を受けて、IL-17を標的とした生物学的製剤(バイオ医薬品)が乾癬治療に用いられるようになりました。具体的には、セクキヌマブやブロダルマブといった抗IL-17抗体製剤です。これらの薬剤は、IL-17の働きを直接的に阻害することで、乾癬に伴う皮膚の炎症を抑えることができます。
【Tfh細胞とTph細胞 - 乾癬病態への関与】
Tfh細胞(T follicular helper cell)とTph細胞(T peripheral helper cell)は、ともにCD4陽性Tリンパ球に属する細胞集団です。Tfh細胞は、B細胞の活性化や抗体産生を助ける役割を担っており、自己免疫疾患との関連が指摘されています。一方、Tph細胞は非リンパ組織においてB細胞を支持する機能を持つと考えられています。
今回の研究では、乾癬患者の末梢血中におけるTfh細胞とTph細胞の割合が健常人と比べて有意に増加していることが示されました。特にTfh細胞では、ICOS(共刺激分子の一種)やPD-1(免疫チェックポイント分子の一種)の発現が亢進した活性化状態の細胞が増えていたとのことです。これらの結果から、Tfh細胞とTph細胞が乾癬の病態形成に何らかの形で関与している可能性が示唆されました。
【IL-17標的療法がTfh細胞とTph細胞に与える影響】
研究チームは次に、IL-17を標的とした生物学的製剤の投与が、Tfh細胞やTph細胞の分画に与える影響について検討しました。その結果、セクキヌマブやブロダルマブによる治療を3ヶ月間受けた乾癬患者では、Tfh細胞の割合が有意に減少することが明らかになりました。さらに、ICOS陽性やICOS・PD-1共陽性といった活性化状態のTfh細胞も減少が認められたそうです。Tph細胞についても同様の傾向が観察されました。
以上の結果から、IL-17を標的とした生物学的製剤は、Tfh細胞やTph細胞の分画を減少させることで乾癬の病勢を改善している可能性が示されました。IL-17とTfh細胞、Tph細胞の相互作用が乾癬の病態に関与しているとすれば、これらを標的とした新たな治療戦略の開発にもつながるかもしれません。
乾癬は、患者のQOL(生活の質)を大きく損なう難治性の皮膚疾患です。IL-17を標的とした生物学的製剤の登場により、乾癬患者の治療選択肢が広がったことは喜ばしい限りです。また、Tfh細胞やTph細胞といった新たな治療標的の可能性が示されたことで、乾癬のさらなる病態解明と革新的治療法の開発が期待されます。
参考文献:
Tsiogkas SG, Mavropoulos A, Dardiotis E, Zafiriou E, Bogdanos DP. Biologics targeting IL-17 sharply reduce circulating T follicular helper and T peripheral helper cell sub-populations in psoriasis. Front Immunol. 2024;15:1325356. doi:10.3389/fimmu.2024.1325356










