【深読み「鎌倉殿の13人」】激闘!倶利伽羅峠の戦い!木曽義仲が平家に圧勝した秘密
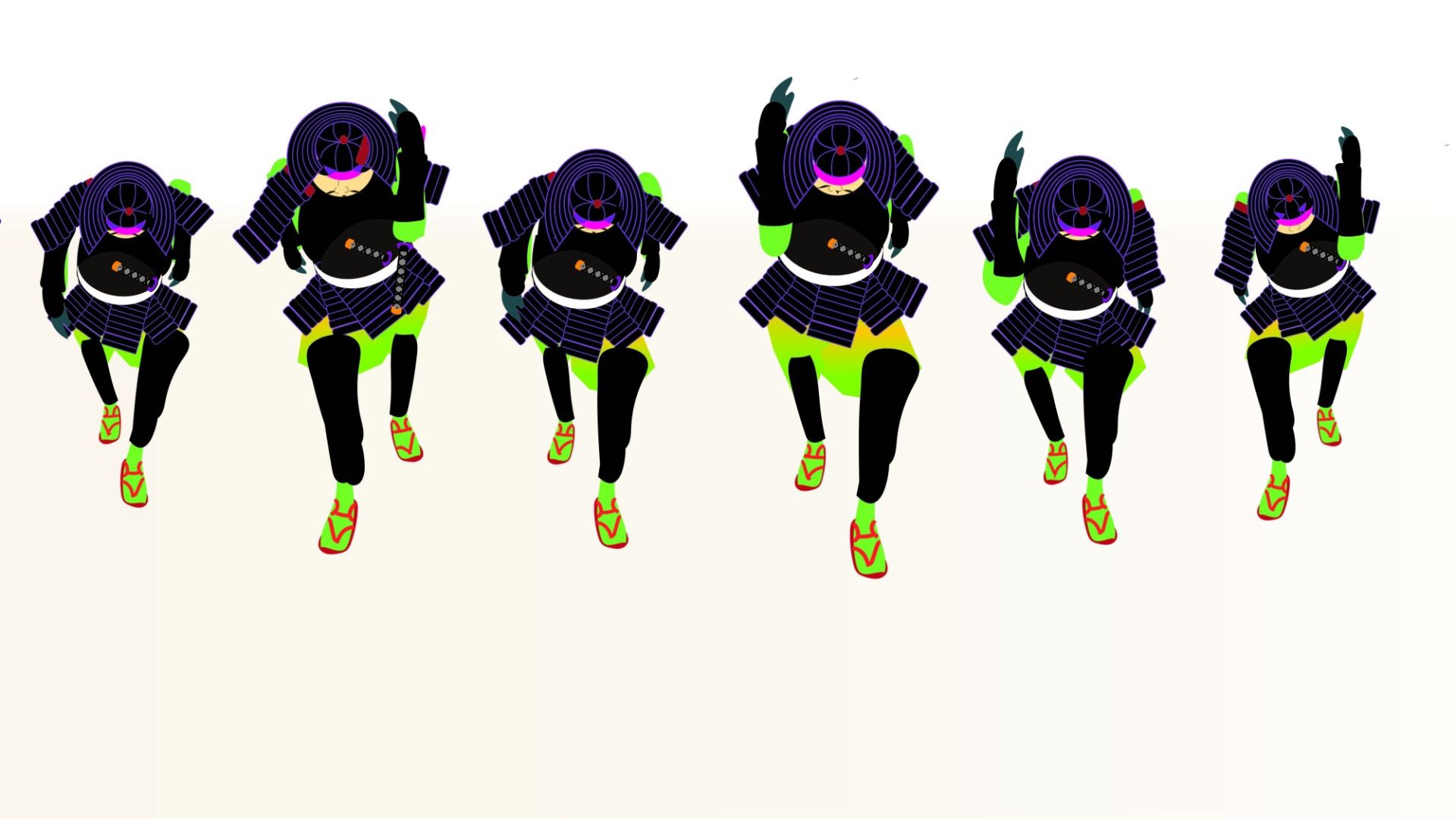
大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の第14回では、木曽義仲が倶利伽羅峠の戦いで圧勝し、入京を果たした。義仲はどうやって戦いを制したのか、その理由を深く掘り下げてみよう。
■平家軍の北陸出陣
治承5年(1181)を境として、飢饉に伴う兵粮不足が懸念され、源平は一戦を交えることがなかった。その間隙を縫って、木曽義仲は着々と北陸方面に権力基盤を築いた。
寿永元年(1182)3月、焦る平家は院宣を盾にして、諸国の荘園から兵粮米を徴収した(『玉葉』)。あまりの過酷な取り立てぶりに、荘園を保持する公家らの心は、平家から離れていったという。
しばらく戦いは停滞したが、寿永2年(1183)4月になって、ようやく合戦の機運が盛り上がってきた。平家は平維盛以下、通盛、知盛、行盛、経正など、一門の精鋭を選りすぐり、10万といわれる軍勢で義仲追討軍を編成したのである。もはや義仲を放置できなかった。
同年4月26日、平家の大軍は越前国に入国すると、敵方の火打城(燧ケ城址:福井県南越前町)を攻囲した。同城は川を堰き止めた、人工的な湖に囲まれており、容易に攻めることができなかった。
しかし、城内に籠城していた平泉寺(福井県勝山市)の長吏斉明が平氏に内通し、湖を破壊する方法を伝えたという。平家方は教えどおりに湖を破壊し、そのまま城に攻め込むと、落とすことに成功した。平家は幸先の良いスタートを切り、そのまま加賀国へ進んだのである。
■倶利伽羅峠の戦い
同年5月9日、平盛俊は般若野(富山県高岡市・砺波市)に陣を置いていた。義仲配下の今井兼平は、休んでいる盛俊の陣営の奇襲に成功した。これにより盛俊が率いる軍勢は、いったん撤退を余儀なくされた。しかし、これは平家の決定的な敗北ではなかった。
その後、平通盛、知度らが率いる約3万の軍勢は志雄山(石川県宝達志水町)に、平維盛、行盛、忠度らが率いる約7万の軍勢は砺波山(石川県津幡町・富山県小矢部市)にそれぞれ着陣した。二手に分かれて、義仲を挟撃する作戦だった。
一方の義仲が率いる軍勢は砺波山に向かい、叔父の源行家らの軍勢を志雄山に向かわせた。同時に、平家軍の背後には、配下の樋口兼光を向かわせるという周到な作戦を立てていた。その軍勢は7万といわれている。義仲は地の利を知り尽くしており、それは大きなアドバンテージだった。
5月11日未明、義仲は松明を400~500頭もの牛の角に付け、平家に夜襲を仕掛けた。平家の軍勢は慌てて逃亡を企てるが、すでに背後を樋口兼光に押さえられていた。もう逃げ場はなかったのだ。
退路を断たれた平家軍は、たちまち大混乱に陥って逃げ出そうとするが、唯一の逃亡経路だったのが倶利伽羅峠である。将兵は闇の中だったので先がないことに気付かず、次々と谷に落ちて落命した。こうして平家の10万という軍勢は壊滅し、維盛らは命からがら京都に逃げ帰ったのである。
勢いを得た義仲軍は快進撃を続け、7月に念願の入洛を果たした。その直前、平家一門は安徳天皇を伴い、無念にも都落ちしたのである。その点は、改めて取り上げることにしよう。
■むすび
倶利伽羅峠の戦いの経緯については、疑問がないわけでもない。まず、平家方の軍勢が10万、義仲の軍勢が7万というのは多すぎる。この10分の1でも多いように感じる。
義仲軍が松明を400~500頭もの牛の角に付け、平家に夜襲を仕掛けたというのも、荒唐無稽に過ぎるだろう。義仲軍は地の利があったのだから、それを生かして奇襲戦を仕掛けたという程度ではないだろうか。
いずれにしても、平家の軍勢は地理に不案内な場所で、戦巧者の義仲の巧みな戦いぶりに敗れ去ったということになろう。










