高齢者の負担は増やさなければならないの?
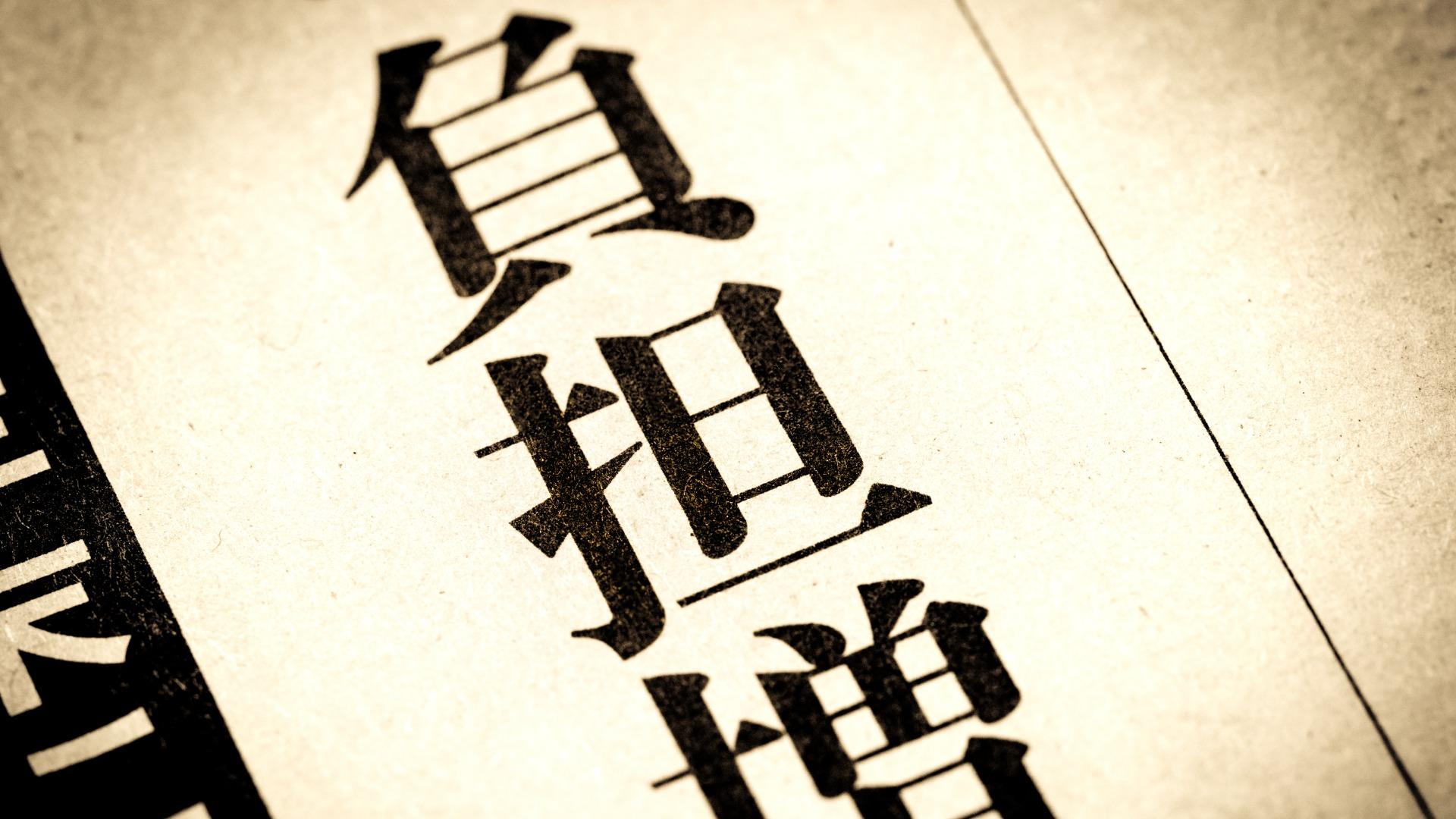
昨日3月24日、橋下徹さんがレギュラーコメンテーターを務めるフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」を見ていたら、社会保障の持続性を担保し、世代間格差を是正するために、高齢者も資産保有額に応じた応分の負担が必要との意見で一致していた。
高齢者の負担も増やすという方向性は全世代型社会保障の構築に邁進する政府の主張とピタリと符合するのは興味深い。


こうした主張の背後にあるのは、全世代型社会保障で肥大化する一方の社会保障の財源を工面するのが、現状の現役世代中心ではもう持たないという認識だろう。
少々古い試算ながら、控えめな政府の見通しでも、2040年には社会保障負担は185.9兆円から212.5兆円と2023年(当初予算ベース)130.7兆円の+42%増から+63%増となる一方で、現役世代人口は▼15%減少するため、所得が増えない限り、現状の社会保障を維持するためだけでも現役世代一人当たりの負担は+68%から+92%増加することになる。これまでGDPは政府の見込み通りには伸びてはこなかったが、社会保障給付費はなぜかほぼ政府の見込み通りに伸びてきている現状に照らせば、大袈裟な話でもないだろう。さすがにこれでは現役世代の暮らしがままならなくなるのは確実なので、現役世代の負担を少しでも軽減するには高齢者にも負担を求めなければならないという理屈だ。



こうした肥大化する一方の社会保障給付を支えるために負担を増やさなければならないというのは、明治以降現在に至るまでの日本の財政観である「量出制入」を反映した考え方でもある。よく高齢化で社会保障給付費が増える有様を社会保障の「自然増」と呼ぶが、これも支出増を前提とした考え方に他ならない。筆者などは負担する現役世代が減るのだから社会保障の「自然減」が必要だと思うのだが、そうした考え方はないようだ。
日本の社会保障134.3兆円(2023年度当初予算ベース)のうち全体の86%、115.2兆円を社会保険が占めている。
社会保険は民間保険と同じく何らかのリスクに備えた仕組みだが、民間保険は必要性に応じて加入の是非は個人の判断に委ねられている一方、社会保険は強制的に加入させられる点で区別される。
日本の社会保険は基本的には老後を支えるものとして整備されてきており、その結果、保険としてあるべきリスクに応じた負担ではなく、現役世代から高齢世代への所得移転となっていて、要するに国営のネズミ講である。私たちは少子化、高齢化が進行するなか国営のネズミ講に強制加入させられているのだ。
だからこそ、少子化、高齢化が進むことで、国営のネズミ講の親が増える一方で負担する側の子や孫が減れば、子や孫だけでなく親であるはずの高齢者の負担も増やさなければならない事態がやってきているのだと言える。
先に挙げたフジテレビの番組で「現役世代に比べて税・社会保障の高齢者負担」についての視聴者アンケートで、「妥当だ24%、優遇されすぎだ37%、重すぎる39%」との結果になった。
実際、高齢者の負担率は1996年の9.2%を底として2023年には14.2%と5ポイント上昇しているのは確かなのだが、2023年現在で他の世代の負担割合と比較すると低いことが分かる。


税・社会保障負担に関する世代間の認識のギャップがうかがい知れて大変興味深い。だからこそ、社会保障改革が一向に進まないともいえるだろう。
年齢別の資産保有額を見ると、平均的な日本の世帯では、死ぬ直前の世代で最高となっている。つまり、結果的には老後のリスクに直面しなかったのと同様になっている。

本来であれば、まずは自分で自分の老後に備えて蓄積したはずの自分の資産を取り崩しつつ足りない部分を社会保障で埋めるべきところ、老後の資産には手をつけなくてもよい状況となっている。
これは過大な世代間所得移転を政府が行っているということを意味する。
現役世代の「自然減」に合わせて、社会保障給付を削減すればよいので、過大な世代間所得移転を維持するため更なる負担を現役世代はもとより高齢世代に求める必要は全くない。
日本の財政観を「量出制入」から「量入制出」という本来の財政観に戻せばよい。
そして、過大な社会保障を効率化しスリム化すればよいだけだ。高齢者の資産に手を付ける必要もない。
社会保障の効率化には窓口負担の一律3割化や乳幼児、児童・生徒の医療費無償化(税負担化)の廃止などが考えられる。価格メカニズムに従えば、割引があるところ超過需要が生まれるし、価格が上昇すれば(負担が増えれば)需要が減ることになるからだ。
社会保障の効率化を行うことなく負担を増やすということは、日頃から健康に気を使っている高齢者の努力も無にすることになる。
さらに、窓口負担一律3割化による高齢者医療需要の削減は、オーバーワークが指摘される医師の働き方改革にも資することになるので一石二鳥だと思うがいかがだろう?
最後に蛇足ではあるが、政府の規模が大きくなればなるほど、私たちの所得や財産から政府に収納される割合が増えていくので、確実に日本の社会主義化が進んでいることも指摘しておきたい。










