あまりに謎多き石田三成の出自。7つの説から考えてみる
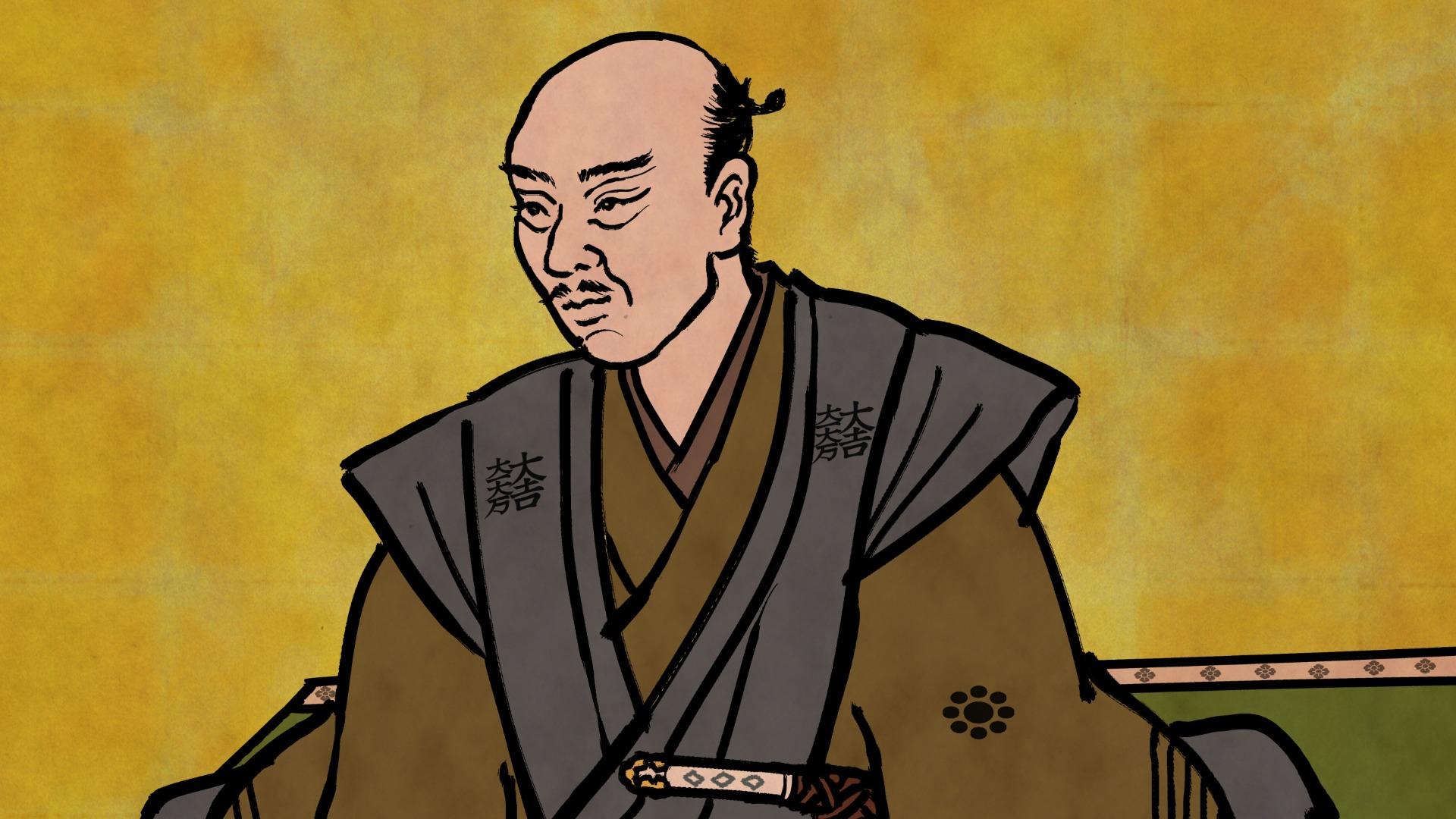
現代においても、素性のよくわからない人がいるが、戦国時代は実に多かった。石田三成もその1人であり、その素性は神秘のベールに包まれているので、7つの説から考えてみよう。
①妙心寺寿聖院(京都市右京区)に伝わる過去帳『霊牌日鑑』による説
石田正継(三成の父)の父は前陸奥入道清心、祖父は前蔵人入道祐快であり、寿永3年(1184)に木曽義仲を討ち取った石田為久が先祖であるという。為久は、相模国大住郡糟屋庄石田郷(神奈川県伊勢原市)出身の武将である。
②極楽寺(和歌山県有田市)に伝わる系図による説
正継の父は北面の武士の下毛野氏の流れを汲み、正継は母方の石田の名字を名乗ったと書かれている。
③讃岐丸亀家に伝わる『京極家譜』による説
石田氏は近江京極家に仕える家臣だったというが、この石田氏の本拠は長浜市の石田ではなく、梓河内(滋賀県米原市)のことである。石田氏は、その近くの京極方の猪ノ鼻城を守備しており、関を設けて関銭を徴収していたという。
④常福寺(滋賀県米原市)に伝わる過去帳による説
この過去帳には、至徳元年(1384)以降の石田家の系図が詳しく書かれており、室町時代初期頃に正継の曽祖父に当たる人物が石田村(滋賀県長浜市)に移ったと記す。
⑤『江州佐々木南北諸士帳』による説
石田刑部左衛門と浅井家の祐筆を務めた石田長楽庵は、書に優れた人物であり、浅井氏の右筆を担当した。2人は、三成の先祖と何らかの関係があったと推測されている。
⑥『伊吹社奉加帳』による説
天文5年(1536)にあらわれる石田七郎左衛門、同新左衛門尉は、三成の先祖だったのではないかと指摘されている。
⑦最新の説
近年では、「大原観音寺文書(滋賀県米原市)」に15世紀以降、「石田東殿」「石田景俊」の名が見え、彼らは三成の先祖ではないかと指摘されている。石田氏の初見は、応永26年(1419)の『本堂造作日記帳』である。
「大原観音寺文書」の関連史料を検討した結果、三成の先祖は荘園(山室保)の経営を現地で行う代官だった可能性が高いとされ、しかも同寺は石田氏の檀那寺だったので、この説は有力視されている。
石田氏は石田村(滋賀県長浜市)を本拠とし、山室保(滋賀県長浜市)の荘園代官を務めていた。その後、京極氏や浅井氏に仕えたと推測され、三成の代に至って秀吉に仕えるようになったのである。
主要参考文献
太田浩司『近江が生んだ知将 石田三成』(サンライズ出版、2009年)










