MERYが本当に復活するために注目すべき3つのハードル
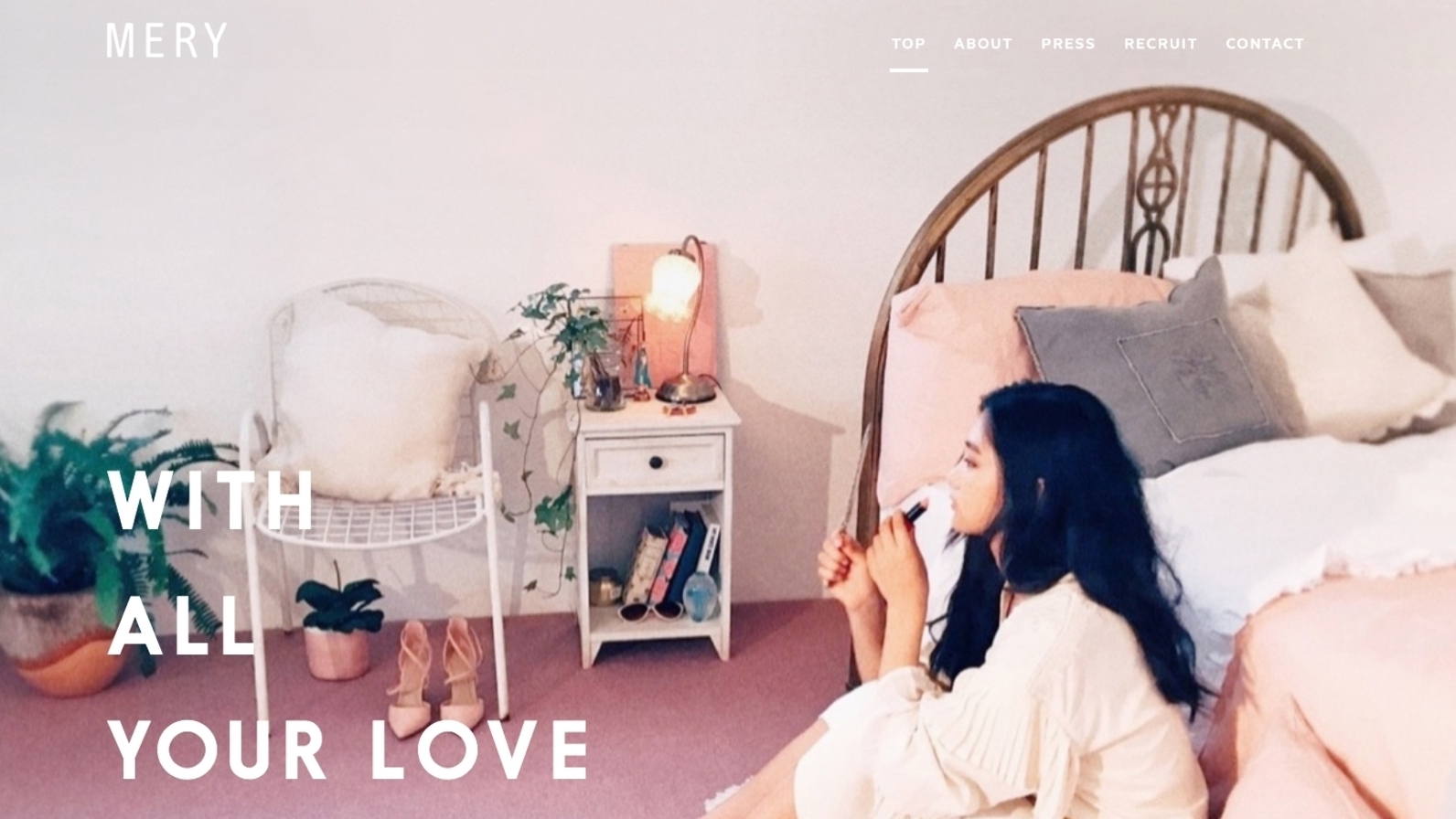
11月21日にMERYの運営が再開し、一週間がたちました。
MERYといえば、昨年のWELQ騒動を起点にした一連のDeNAのキュレーションプラットフォーム騒動の影響を受け、全記事非公開に追い込まれたことが記憶に新しい方も多いでしょう。
MERYの全記事非公開になったのが2017年の12月5日でしたから、今回の復活まで実にほぼ1年間がかかったことになります。
参考:DeNAが「MERY」全記事の非公開化を発表「厳正かつ公正な調査」のため
MERYのファンからの歓迎の声がある一方で、著作権違反への対応が全て終わっていないことに対する不満の声も少なからずあるようで、今回のMERY復活に対しては人によってかなり見方が異なるようです。
個人的にもYahoo!ニュースでDeNAメディア騒動についてのまとめ記事を書いたこともありますし、メディアミートアップというイベントで、WELQ騒動についての振り返りをした背景もあるので、今回のMERY復活に対する考えをまとめておきたいと思います。
参考:DeNAコピペメディア騒動の背景にある5つの病の連鎖を考える
参考:MERYとWELQ、何がダメだったのか?BuzzFeed古田氏×ヨッピー氏×徳力氏が語るメディアの存在意義
MERYの復活の可否は、日本のネットメディアの未来を占う
まず、結論から最初に書いておくと、私自身はMERY復活は歓迎している人間です。
ある意味、MERYのように象徴的に業界の悪役としてバッシングされた企業が、二度目のチャレンジとして正しいやり方を学んで復活できるかどうかというのは、業界にとっても非常に重要なことだと感じているからです。
もちろん、MERYの副社長に、個人的にもワールドマーケティングサミットのアンバサダー等いろんなところでご一緒している江端さんが就任されているので、より期待感が強いというのはありますが、それ以上にMERYの復活には非常に象徴的な意味があると考えています。
一番の不良だった生徒が改心してチームをリードすることで、学校全体の雰囲気が変わるというインパクトの大きさは、スクールウォーズ世代の方には、きっと分かっていただけるはず。(分からない方々すいません)
個人的にも、去年のWELQ騒動に影響され、メディアミートアップというイベントを主催しているのは、同じような間違いを自分達がどうすれば避けられるのかというのを自分自身悩んでいるからなのですが。
ある意味、著作権問題を軽視した運営で、ライター界隈や既存メディア業界から嫌われている面も強かったMERYが、今回の復活でネットメディアにおける模範的な存在になれるかどうかは、ネットメディア業界全体にとっても非常に重要なことだと思います。
特に今回の新体制のMERYにおいては、運営のメインを小学館が担当し、量ではなく質を重視するとはっきり明言されています。
参考:再始動するMERYは「量より質」 山岸社長が目指す学生ライターと編集部の融合
もし「量より質」を重視する方針でMERYが再び成功することができれば、ネットメディア業界においても量より質を重視して成功できることが明確になることになります。
逆に、ある意味、今回のMERYの再チャレンジが失敗したら、多くのネットメディア関係者が「やはりMERYが成功したのはコピペでコストを下げてたからだ」とか「とにかく量を重視した方がやっぱり儲かるんだ」と思われてしまう可能性があるわけで。
ただでも、WELQ騒動後にもコピペ運営を続けているメディアが残ってしまっている現状をさらに悪化させてしまう要因にもなりかねません。
そういう意味では、言い方を変えると個人的には、新生MERYには成功してもらわないと困る、とすら感じているのが正直なところです。
ただ、MERY復活のためには大きなハードルがいくつもあります。
個人的に注目しているポイントは下記の3点です。
■MERY読者は1年のブランクを気にせず戻ってくるのか
■広告主は再びMERYに広告を出稿するようになるのか
■質を重視するMERYの新体制で利益を出すことはできるか
一つずつ見てみましょう。
■MERY読者は1年のブランクを気にせず戻ってくるのか
最初で最大のハードルは、1年という長いブランクによる読者離れでしょう。
MERYが運営を休止したときにはMERYロスという言葉が話題になるほど、MERYにはたくさんのファンがいたことが明らかになりました。
また、復活した日のツイッターの投稿やインスタグラムのコメント欄を見ると、MERYの根強いファンの人達がMERY復活を喜んでいる様子が伝わってきます。

ただ、さすがに1年という月日は長いです。
さすがの多くのMERYファンもこの1年間MERYの復活を待っているわけもなく、他の媒体を代わりの情報源にしていたはず。
1年間の間に当然ライバルメディアも、力をつけています。
Yahoo!のグループ企業であるTRILLは月間1500万人のユーザーに利用されているとのことですし。

LOCARIは、オトナ女子のNo1アプリというキャッチコピーのCMを、MERYの再開の日に公開してきました。
それぞれターゲットの違いはあるようですが、当然ながら読者を取りあうライバル関係として、お互いを意識しているのは間違いないでしょう。
現在の復活後一週間経過したMERYのサイトを見ると、記事のView数は数百~数千のものが中心で多いもので2万程度のようですので、月間2000万ユニークユーザーで、なんと4億PVを超えていたと言われる休止前に比べると当然ながらスロースタートの印象はあります。
ただ、いわゆるお気に入りのハートマークの数はライバルメディアと比べても遜色ない印象もありますので、このあたりは今後のMERY社によるアクセス数の発表に注目されるところです。
■広告主は再びMERYに広告を出稿するようになるのか
読者が戻ってくるかどうかと並んでMERYにとって重要なのが、広告主が戻ってくるかどうか、になります。
現時点では、MERYには記事広告の出稿はまだされていないように見受けられますが、当然メディアとして運営して行くには広告収入が非常に重要。
MERYは休止前には若い女性にリーチするために非常に有効なメディアだったと言われており、他の媒体に比べても抜きんでて効果が高かったと聞いています。
何しろ昨年のadtech東京2016の筆頭スポンサーがMERYだったわけで。
実際、MERYが休止したときに広告主の担当者が、代わりの広告をどこに出せば良いんだと嘆いているのを聞き、驚いた記憶があります。
また、DeNAのキュレーションメディアを全て一旦休止すると守安さんが判断したときに、MERYだけは継続する判断をした背景には、当時MERYには億を超える広告が出稿されていたため、休止することによる広告契約のペナルティを気にしたのではないかという推測をされている人もいたほど。
一般的に言えば、広告主からすると一度騒動があったメディアに広告を出稿することにはリスクがありますが、当然ながらMERYに再び多くの読者が帰ってくれば、広告主としても有力な広告出稿先としてMERYを選択肢に入れる流れにはなるでしょう。
現在のところ、MERY復活に対して、まだ旧MERYにおける著作権対応が終わってないという不満の声は一部で見られるものの、広告を出している企業に対して不買運動をしかけたり、広告主にクレームをしたりというレベルの批判は少なそうです。
そういう意味では、広告掲載が復活して最初に広告を掲載した企業が批判されなかったことが確認されれば、他の広告主も安心して広告を掲載できると思うはずで、この点については比較的スムーズにいく気もします。
どちらかというと、読者が戻ってくるかどうかの方が重要でしょう。
■質を重視するMERYの新体制で利益を出すことはできるか
個人的に一番注目しているのが、この3番目のポイントです。
冒頭に書いたように、バズフィードのインタビューに対して、MERYの山岸社長は明確に量より質を重視する運営をすることを明言しています。
旧MERYに対する新MERY体制の違いを気がついた範囲だけでも簡単に書き出してみると、こんな感じ。
・編集のチェックがなかったのを、校閲と編集で二重チェック体制に
・量のノルマ制で大量に記事を書かせていたのを、時給契約で質重視に
・画像は勝手にコピペしていたものを、購入が必要なものは購入
・インスタグラムやツイッターのエンベッドも、投稿した本人に許諾確認
旧MERY時代のやり方に比べると、真逆と言って良いほど手間とコストをかける体制に変わっているのが分かります。
当然ながら騒動になったMERYの看板を維持して復活するわけですから、前のやり方を変えるのは当然ですが、ポイントになるのは「それで儲かるのか」という点です。
雑誌などの既存メディア時代に比べると、ネットメディアにおけるバナー広告の単価が安いために、多くの既存メディアがネットに進出しても昔ほど儲からないと嘆いている現状に対して、1本の記事作成にコストをかければ当然利益が出ないリスクはあがります。
山岸社長はインタビューで、しばらくは赤字でもいい前提でやるという趣旨の発言をされていますが、当然ながら企業において永遠に赤字で慈善事業をやるわけにはいきませんから、MERY継続のためには黒字化のめどがつくことが必須でしょう。
ただ、実は前述したように旧MERYが休止するタイミングで、億を超える広告が出稿されていたという噂もありますので、実は旧MERYの段階で、MERYは質にエネルギーを投じても利益が出るだけの広告収入を得られていたという説もあります。
だからこそ、ここまで山岸社長も江端副社長も、はっきりと質を重視する方向を宣言できるのではないかなと、期待を込めて見ています。
いずれにしても、やはりMERY復活のための最重要のポイントは、新MERYが読者に再び喜んでもらうコンテンツを提供し、多くの読者に再び読まれるMERYとなることができるかどうか、ということにつきるかと思います。
App Annieのデータを見る限り、再開初日ダウンロードは、全体で25位、ショッピングで2位まで行っていたようです。

その後は下がってきているようですが、この初日からアプリをダウンロードして復活を喜んでくれた人達が、再びMERYを楽しんでくれているかどうかが、まずは最大の注目点といえるかもしれません。
失敗から学ぶからこそ進化があるはず
まだまだ一部にはMERYの著作権違反を許せていない方もいるようですが、実は記者会見で公式に謝罪をし、著作権違反に対しての罰金の支払いにも対応しているDeNAグループは、他の企業に比べると相当しっかりした対応をしている企業といえます。
世の中には、未だにコピペメディア的な運営スタイルを続けている企業があるのも残念ながら現実のようですし、コピペ運営をしていたことに対してヨッピーさんに糾弾されていたSpotlightが、気がついたら特に目立った謝罪も無いままR25に統合されてしまっていたこととかを踏まえると、DeNAグループ対応の真面目さは逆に際立っているように思います。
もちろん、私自身もDeNAグループに対する感情的な批判記事を書いていた人間ですし、偉そうなことを言える側では無いですが。
やはり、人間は失敗から学ぶからこそ進化できる生き物のはずで、一度失敗した人を、その罪を元に永遠にバッシングし続けるのは間違っているように思います。
個人的には、旧MERYの運営会社ペロリの創業者である中川さんに、復活や汚名挽回のチャンスが与えられなかったのは残念だと思ってしまう側の人間です。
参考:「社長退任のあいさつで皆泣いた」 WELQに端を発したキュレーション騒動、MERYから見た実情
そういう意味では、どの広告主が、MERYに二度目の挑戦への応援としての広告出稿を最初に実施するのかが気になるところではありますし。
はたしてMERYが、昨年の騒動からどこまでの行為がNGで、どこまでは許容範囲だという判断をしたのかというのも非常に気になるところなのですが。
そのあたりはメディアミートアップ参加者の方々と議論した内容をまた報告させて頂くとして。
また記事が無駄に長くなりましたので、今日のところはこの辺で。
くどいようですが、株式会社MERYの方々には、スクールウォーズの大木大助ばりの見事な更正劇を見せて頂くことを楽しみにしております。










