【深掘り「鎌倉殿の13人」】変後、一族もろとも悲惨な最期を遂げた梶原景時
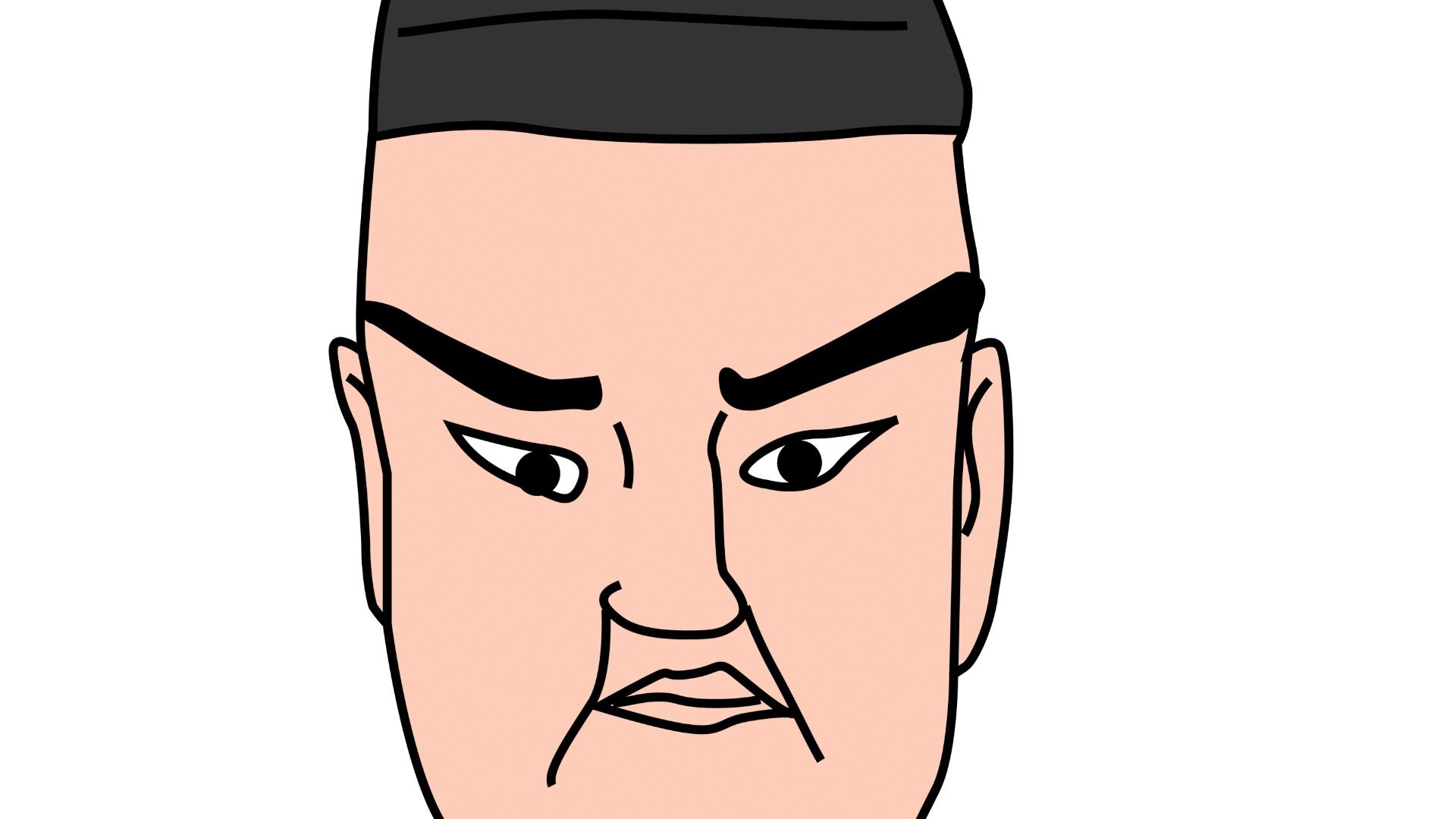
大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の28回目では、梶原景時の変が取り上げられた。今回は、変の経緯について、詳しく掘り下げてみよう。
■変の引き金
正治元年(1199)10月から翌年1月にかけて続いた梶原景時の変は、頼朝死後の最初の大事件だった。すでに御家人間では景時に対する怒りが渦巻いており、それが表面化したものなのである。
有力な御家人は「打倒景時」で一致して弾劾し、ついに景時と梶原一族を滅亡に追いやったのだ。以下、その経緯について確認しておこう。
正治元年(1199)10月、朝光は亡き頼朝の思い出を語り、「忠臣は二君に仕えずというのだから、出家すべき」だったと述べ、世情が穏やかではない旨の発言をした。これは考えようによっては「頼家には仕えたくない」とも取れる発言なので問題視された。
朝光の発言を問題視したのが、景時だった。景時の意図は不明であるが、さすがに御家人たちは黙っていなかった。焦った朝光が三浦義村に相談すると、景時討伐の気運が大いに高まったのである。
同年10月、千葉常胤・三浦義澄・千葉胤正・三浦義村・畠山重忠・小山朝政・結城朝光・足立遠元・和田義盛・比企能員ら御家人66名は、鶴岡八幡宮(神奈川県鎌倉市)に結集した。
景時に恨みを持っていた中原仲業が景時の弾劾状を作成すると、66名の御家人はそれに署名した。そして、弾劾状を大江広元に託し、頼家に差し出したのである。
■景時の対応
しかし、広元はただちに頼家に弾劾状を提出せず、和解する方法を考えていた。広元は無用な混乱を避けたかったのだろう。こうして広元は弾劾状を預かっていたが、義盛に催促されたので、頼朝に差し出さざるを得なくなった。
同年11月、頼家は景時の弁明にした。というのも、景時は頼朝から頼家の傅役を任され、「一の郎党」と称された人物である。互いに持ちつ持たれつの関係だった。頼家が景時に同情的になるのもうなずける。
景時討伐の背後には、北条時政の策略があったのは疑いない。頼家与党だった景時を討つことにより、時政が幕府運営の主導権を握るのは明らかだった。
結局、景時は讒言の件について、十分な弁明ができなかった。同年12月、景時は鎌倉を追放され、相模国へ一族郎党とともに下向したのである。景時の保持していた播磨国守護は小山朝政に、美作国守護は和田義盛にそれぞれ与えられた。
■景時の最期
翌年1月、景時は相模国に城を構え、鎌倉幕府に謀反の意を示した。そして、西国の武士を味方にするため上洛したが、駿河国狐崎(静岡市清水区)近くで幕府方と交戦となった。
景時以下の一族は奮戦したが、無念にも討ち死にした。しょせんは多勢に無勢である。梶原一族の首は探し出され、路上に晒されたという。こうして梶原一族は滅亡し、時政の威勢が高まることになったのだ。










